システムをクラウド化するメリット・デメリットや注意点を解説
2025-03-18
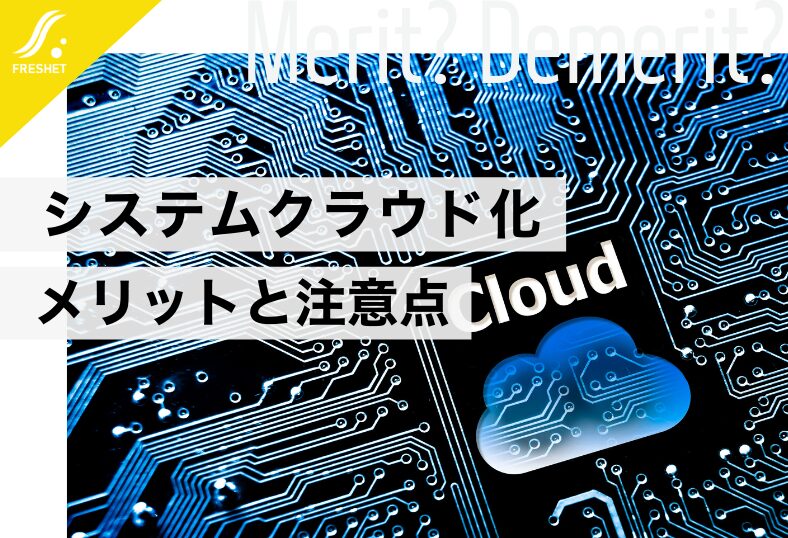
既存システムのクラウド化は、企業の担当者にとって悩みのタネです。システム移行におけるコストの計算や事業者の選定、計画の立案などを考えると、途方に暮れてしまうのも無理はありません。
しかし、クラウド化によるメリットは多く、コスト削減や業務効率化、強固なセキュリティの実現など、企業の成長には欠かせない要素が含まれています。本格的なデジタル時代に向けて、今から移行を考えることは賢い選択肢といえるでしょう。
本コラムでは、クラウド化の基本やクラウドサービスの種類、オンプレミスとの違いなどをわかりやすく解説。さらに、クラウド化のメリットやデメリット、移行時のスケジュールや注意点、失敗しないコツなども解説していきます。既存システムのクラウド化を検討中の方は、本コラムを参考にして、最初の一歩を踏み出してください。
目次
システムのクラウド化とは?
システムのクラウド化とは、従来のオンプレミス環境(自社内のサーバーなど)で運用していたシステムを、インターネットを通じて利用できるクラウド環境にシステムを移行させることを指します。クラウド化により、物理的なサーバーを保有することなくシステムを利用できるようになるのです。
近年は、ビジネス環境の変化に迅速に対応する手段としてクラウド化の重要性が高まっており、多くの企業がクラウドサービスの導入を進めています。
システムのクラウド化が必要な理由
システムのクラウド化は、企業の成長に欠かせない選択肢のひとつですが、近年、企業のクラウド化が求められている背景として、政府の方針や働き方の変化、 DX推進などが挙げられます。
2018年6月に政府が公開した「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」では、『クラウド・バイ・デフォルト原則』と呼ばれる、”クラウドを第一候補として検討する”という原則が打ち出されました。それ以降、政府情報システムのクラウド化が進んだことで、民間企業にもクラウド化の流れが広がっています。
参考:「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」
また、コロナ禍におけるテレワークの増加も、クラウド化を後押しする要因のひとつです。
オンプレミス(社内システム)では、社外からのアクセスが難しいといった課題がありましたが、クラウドなら場所を選ばずに柔軟な働き方を実現できます。
さらに、「DX(デジタルトランスフォーメーション)推進」により、クラウドを活用した業務効率化が脚光を浴びています。経済産業省は過去のレポートで「2025年の崖」と表現し、国内のIT化が進んでいない現状を明らかにしました。既存システムのクラウド化は、まさにこうした危機を乗り越えるための大切な一歩といえます。
参考:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」
主なクラウドサービスの種類
主なクラウドサービスは、SaaS、PaaS、IaaSの3種類です。
SaaSから順に自由度が高いクラウドサービスとなりますが、それぞれには特徴があるため、まとめて覚えておきましょう。
SaaS:Software as a Service
「SaaS(読み:サース)」は、私たちの生活に最も身近なクラウドサービスです。
パッケージ版ソフトウェアの「ウェブ版」と考えるとわかりやすく、ユーザーはクラウド事業者のアプリケーションやサービスを、インターネット経由ですぐに利用できます。主な利用者は企業よりも個人が多く、特にコロナ禍以降、ZoomをはじめとするSaaSの利用者が急増しました。
【代表例】
・オンラインストレージ:Google Drive、Dropbox
・会議ツール:Google Meet、Zoom
・グループウェア:Google Workspace、Microsoft 365
PaaS:Platform as a Service
「PaaS(読み:パース)」は、アプリケーションを開発・実行するための環境を提供するクラウドサービスです。
ユーザーは、インターネットを通じて開発に集中できるメリットがあり、その際はインフラをはじめとする細かい設定は必要ありません。迅速なアプリケーションの開発や構築を目的とする企業に適しています。
【代表例】
・Google App Engine
・Microsoft Azure App Service
・AWS(Amazon Web Services)Elastic Beanstalk
IaaS:Infrastructure as a Service
「IaaS(読み:イアース)」は、インフラそのものを提供するクラウドサービスです。
ユーザーは、OSや開発環境、ミドルウェアなどを細かく設定する必要があるため、難易度が高いです。その代わり、クラウドサービスの中ではとりわけ自由度が高く、オンプレミスに近い構成を持っています。社内に詳しい担当者やチームを配置して運用するのが一般的でしょう。
【代表例】
・Google Compute Engine
・Microsoft Azure Virtual Machines
・Amazon EC2
オンプレミスとクラウドの違い
両者の違いを身近なもので例えると、オンプレミスは持ち家、クラウドは賃貸のようなイメージです。
実際は、主にコスト面や運用面、カスタマイズ性などに違いがあるため、ここではオンプレミスとクラウドの違いを確認していきます。
| クラウド | オンプレミス | |
|---|---|---|
| コスト | 低→高 | 高→低 |
| 運用 | 簡単 | 難しい |
| カスタマイズ | 低い(種類による) | 高い |
コスト面
クラウドは、クラウド事業者からサーバーが提供されるため、最初にまとまった費用がかかりません。少ないコストですぐに利用を始められる点が最大のメリットです。その代わり、従量課金制によるランニングコストが発生するため、長い目で見ると費用が増える可能性があります。
一方でオンプレミスは、サーバーの設置や構築など、最初にこそ費用はかかりますが、将来的なコストは抑えられます。特に、負荷のかかるシステムの場合、クラウドよりもオンプレミスの方が将来的に安くなるケースが多いです。
運用面
SaaSやPaaSでは、クラウド事業者がインフラ管理を行うため、運用面での負担が減ります。(ただし、IaaSの場合は、自社に専門的な知識を持った担当者が必要です。)
一方でオンプレミスでは、自社でサーバーやネットワーク、セキュリティを管理・運用するため、専任の担当者やチームが必要となります。大企業では、適した人材を確保できますが、中小企業の場合、人材不足などにより運用が厳しくなる可能性があります。
カスタマイズ性
クラウドサービスの種類によっては、カスタマイズ性が低い恐れがあります。特にSaaSは、サービスの機能が限定されているためカスタマイズ性が乏しいです。カスタマイズ性を求める場合は、自由度の高いIaaSがおすすめです。
一方でオンプレミスでは、自社の環境に適したカスタマイズが可能です。一般的な業種だけでなく、特殊なニーズのある業種の場合でも、オンプレミスであれば対応が可能です。しかしその分、システム設計の難易度は上がり、開発コストや運用保守の負担は増えるでしょう。
システムクラウド化のメリット
システムのクラウド化には多くのメリットがありますが、ここでは代表的な3つのメリットについてご紹介します。
初期コストの削減
クラウドサービスの魅力は、初期コストが少ないことです。サーバーを買ったり構築したりする必要がないため、設備投資用の初期コストがかかりません。クラウドサービスは主に従量課金制を採用しており、使った分だけのコストが発生する仕組みであるため、初期コストの削減は、中小企業にとって大きなメリットとなります。
運用保守の負担を軽減
オンプレミスでは、自社で管理する範囲が広く、担当者に負担が集中しがちです。一方で、クラウドサービスであれば事業者がインフラやセキュリティの管理をするため、運用保守の負担を軽減できます。その結果、空いた分のリソースを別の業務に充てることが可能です。
>>運用保守とは?それぞれの違いや外部に依頼する際の注意点についても解説
強固なセキュリティの実現
近年、ハッキングや情報漏洩のニュースを耳にするようになりました。クラウド化に悩む企業の中には、インターネットの脆弱性が理由で導入を見送っているケースも存在します。とはいえ、オンプレミスで万全のセキュリティ対策を施すのは難しいです。
その点、クラウドサービスは、常に最新のセキュリティ対策を導入しているため、オンプレミスよりも比較的安全に利用できます。
システムクラウド化のデメリット
システムのクラウド化にはメリットがある一方で、一部注意すべきデメリットもあります。メリットとデメリットどちらが大きく感じられるかは、企業のニーズによって異なるため、欠点を正しく理解しておくことも大切です。
ここでは、代表的な3つのデメリットについて、詳細を確認していきましょう。
長期的なコスト
メリットでは初期コストの削減を挙げましたが、これはあくまで最初のみの恩恵です。今後、長い間運用する場合や大量のリソースが必要となる事業を展開する場合は、オンプレミスの方がコストを抑えられる可能性があります。自社の目指す方向性によっては、クラウドサービスのランニングコストがデメリットになる可能性もあるため、状況によっては、オンプレミスの継続利用を考えましょう。
>>システムのランニングコストの相場はいくら?コスト削減方法についても解説
多様なリスク
クラウドサービスのパフォーマンスは、外部要因に大きく左右されます。インターネットの接続が不安定になった場合や、サイバー攻撃でサービスが一時的に停止した場合、業務に影響が出る可能性が高くなります。特定のクラウドサービスのみで運用していると、大きな被害を受けやすいため、重要なシステムはクラウドサービスではなく、オンプレミスを利用するとよいでしょう。
クラウド事業者への依存
近年、世界情勢や物価上昇の煽りを受け、クラウドサービスの値上げが増えています。その際、特定のクラウド事業者へ依存してしまうと、料金の改定はもちろん、プライバシーポリシーの変更などで影響を受けることがあります。こうした依存を避けるためにも、複数のクラウドサービスを利用して、リスクを分散することも検討してください。
システムクラウド化の進め方
既存システムのクラウド化に失敗するケースは、計画不足の一点に尽きます。では、具体的にどのような手順で進めればよいか、移行の進め方について解説していきます。
1.現状分析
既存システムのクラウド化でもっとも大切なことは現状分析です。まずは、なぜ既存システムをクラウド化したいのか?その目的を明確にしましょう。コスト削減や運用保守の負担軽減、拡張性の向上、企業によって目的は異なるはずです。この時点で明確な目的を定めておくことで、計画をスムーズに進められます。
2.クラウド事業者の選定
基本的には、大手クラウド事業者(GoogleやMicrosoft、Amazonなど)から自社の目的に合うサービスを選ぶとよいでしょう。現状分析にて、自社の状況を洗い出し、その内容をもとに、各クラウド事業者の特徴を比較しながら決めてください。なお、独自システムを運用している場合は、大手クラウド事業者以外の選択肢も検討するとよいです。
3.スケジュールの確定
現状分析やクラウド事業者の選定後にスケジュールを確定します。システムの規模にもよりますが、通常、数ヶ月から半年、長くても数年程度が一般的です。できるだけ、トラブルが起きないように綿密に移行のスケジュールを立てましょう。
>>システム開発の期間の目安は? 作業工程から短縮方法までわかりやすく解説
4.移行テスト
クラウド化の前に、テスト環境で移行テストを行ってください。多くのクラウド事業者が無料トライアルを提供しているため、こうしたキャンペーンを活用して、システムの動作確認を行うことをおすすめします。その際も忘れずにバックアップをとり、万が一に備えましょう。
5.運用保守・最適化
クラウド化の完了後は、クラウド環境の最適化と運用保守体制の整備を行います。クラウドサービスの多くは従量課金制のため、常に見直しを行い、コストの最適化を意識してください。また今後に備えて、クラウドサービスに適した運用保守体制の整備も行うと良いでしょう。
システム移行時の注意点
既存システムのクラウド化には、移行前と移行中、移行後、それぞれのタイミングに注意点があります。ここでは、各フェーズの具体的な注意点を解説していきます。
クラウド移行前には、目的の明確化、クラウドサービスの選定、クラウド事業者の比較が大切です。コスト削減やパフォーマンス向上などの目的を明確にし、適切なクラウドサービス(SaaS・PaaS・IaaS)を選びましょう。また、クラウド事業者の料金プランやサポート体制を比較し、長期的な視点で計画を立てることが重要です。
続いて、移行中のトラブルも想定しておきます。データ移行の失敗やシステム障害の発生など、事前にリスクを想定し対策しておきましょう。バックアップ取得後は、段階的に移行を実施するのが望ましいです。また、予期せぬトラブルに対応するために、クラウド事業者のサポート窓口などを確認しておきましょう。
移行後は、コスト管理やシステム監視を強化し、安定した運用を目指していきます。クラウドは基本的に従量課金制のため、常に最適化を行い、コストを管理していきましょう。また必要に応じて、担当者のトレーニングも実施し、長期的な運用に支障が出ないようにすることも大切です。
失敗しないシステムクラウド化のコツ
既存システムのクラウド化に失敗する多くのケースは、事前の準備不足です。少なくとも、ここで紹介する3つのコツを抑えておくことで失敗するリスクを減らすことができます。いずれも事前にできることのため、しっかりと確認しておきましょう。
どのシステムをクラウド化するか考える
既存システムのクラウド化を考える際、多くの方がすべてのシステムを一気に移行しようと考えます。しかし個人情報や機密情報など、移行対象によってはオンプレミスが適していることもあるため、慎重に考えなければいけません。
最近では、クラウドサービスとオンプレミスを組み合わせた「ハイブリッドクラウド」を導入している企業もあります。既存の概念にとらわれない柔軟な発想で、システムのクラウド化を考えましょう。
独自システムの場合は移行に注意する
企業によっては、その業界独自のシステムを運用しているケースがあります。この場合、一般的なクラウドサービスへの移行は難しいかもしれません。
クラウド事業者を選ぶ際は、そもそも自社のシステムが独自のものかどうかを確認してください。もし、独自システムを採用している場合は、外部への委託を考えることをおすすめします。
システムのクラウド化が難しい場合は委託する
単純なシステムのクラウド化であれば自社でも対応できますが、複雑になればなるほど移行は難しくなります。その際は自社でクラウド化するのではなく、システム開発会社などに依頼することもひとつの手です。
クラウド化にかかる工数や時間を考えると、結果的に費用がかかったとしても費用対効果は高いです。クラウド化の失敗を回避するためにも、積極的に外部委託を検討してみましょう。
システムのクラウド化でよくある質問
最後に、システムのクラウド化でよくある質問を紹介していきます。多くの人が持つ疑問を解消して、既存システムのクラウド化を実現してください。
Q.クラウド化に向いている「クラウドサービス」は?
laaSです。
IaaSはオンプレミスに近い構成のため、既存システムのクラウド化に向いています。自社の状況によっては、最小限の変更で既存システムをクラウド化できるかもしれません。
PaaSはアプリケーション開発に特化しているクラウドサービスのため、企業の目的によっては向いている可能性があります。また、SaaSは決められたアプリケーションとサービスを利用するため、既存システムのクラウド化には向いていないでしょう。ただし、メールやチャットなど、一部システムのクラウド化には向いています。
Q.クラウド化には「どのくらい時間」がかかる?
システムの複雑さや移行方法、クラウド化の知識の有無などで異なります。
一部の小規模なシステムをSaaSに移行する程度であれば、数日から一週間程度で完了しますが、大規模なシステムの場合、スケジュールから実行までに数ヶ月から数年程度かかるケースもあります。
主に、システムの複雑さや移行方法、クラウド化の知識の有無などで、目安となる時間は変動するため、余裕を持った計画が大切です。もし、迅速に既存システムのクラウド化を実現したい場合は、システム開発会社などに移行を依頼するのが得策です。
Q.クラウド化後は「どのくらいコスト」がかかる?
クラウド事業者の料金形態や利用時間によって異なります。
クラウドサービスは、基本的に従量課金制(SaaSはサブスクリプション型が多い)を採用しています。企業によって利用時間が異なるため、一概にどれくらいのコストがかかるかは判断しづらいです。
自社のこれまでの状況を確認した上で、ランニングコストを想定しておきましょう。特に、今後システムの負荷が増える見込みがある場合は、より詳細なコストシミュレーションが重要となります。
まとめ
本コラムでは、既存システムのクラウド化に関する基本的な情報から、メリット・デメリット、移行時のスケジュールや注意点、失敗しないコツなどを解説してきました。
既存システムのクラウド化と聞くと、多くの方が大変で難しそうというイメージを持ちますが、適切な手順を踏むことで、スムーズに進めることが可能です。
フレシット株式会社では、既存システムのクラウド化はもちろん、クラウド化後の機能追加や運用保守まで一貫して提供しております。
もし、既存システムのクラウド化に課題をお持ちのお客さまがいらっしゃいましたら、まずは、下記よりお問い合わせをいただければと思います。
監修者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田 順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

