「仕様凍結=開発の終わり」ではない! 変更管理と成功するシステム開発の秘訣
ビジネスは変化する。だからこそ “仕様凍結” と “変更管理” のバランスが重要!
2025-03-23
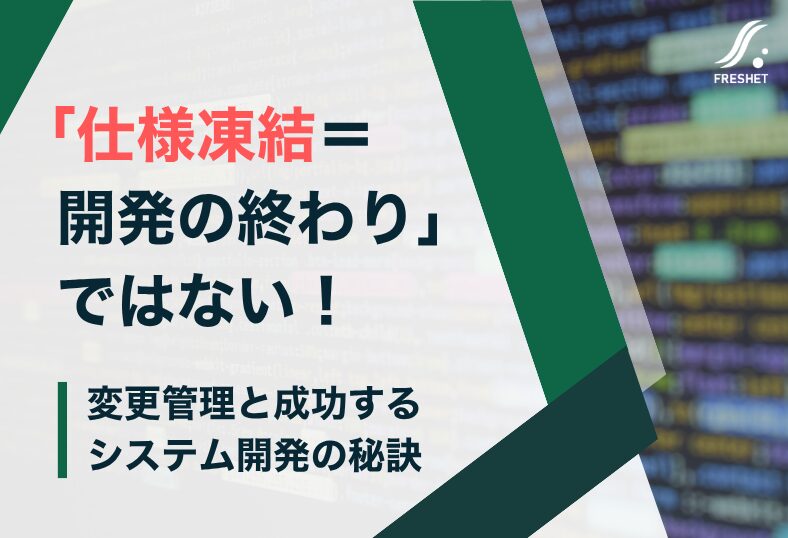
システム開発において「仕様凍結」は重要なプロセスですが、それは開発の終わりを意味するものではありません。仕様を凍結することでプロジェクトの方向性を明確にし、スケジュールやコストを安定させることができますが、ビジネス環境の変化や新たな要件が発生した場合には仕様の見直しが必要になることもあります。
つまり、仕様凍結と変更管理を両立させることが、成功するシステム開発の鍵となるのです。本コラムでは、その具体的な方法を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
【関連記事】
システム開発の依頼の流れは?失敗しないためのシステム開発会社の選び方についても解説
目次
【記事要約】旭川医大とNTT東の裁判、仕様凍結後の追加開発要望が争点に
電子カルテを含む病院情報管理システムの開発失敗を巡る訴訟で、札幌高裁は一審判決を覆し、旭川医科大学に全責任があると判断した。プロジェクト開始後、医大側は大量の追加開発を要求。NTT東は625項目を受け入れた後、仕様凍結に合意したが、その後も171項目の要望が続いた。高裁は、仕様凍結の合意が開発要望の拒否に相当すると認定し、NTT東のプロジェクトマネジメント義務違反を否定。契約解除時点でシステムはほぼ完成していたとし、旭川医大に約14億円の賠償を命じた。ユーザー企業には、開発ベンダーの説明を受け、プロジェクトを適切に管理する責任があることが改めて示された。
出典:日経コンピュータ「失敗の全責任はユーザー側に、旭川医大とNTT東の裁判で逆転判決」2017年9月29日
【記事要約】旭川医大とNTT東、仕様凍結後の追加開発が訴訟に発展
旭川医科大学とNTT東日本の病院情報管理システム開発は、仕様の追加・変更が続いたことで開発遅延に陥り、最終的に契約解除と訴訟に発展した。当初2009年9月の稼働予定だったが、仕様変更が相次ぎ、2009年7月に仕様凍結を決定。しかし、その後も171項目の追加要望があり、NTT東は136項目を受け入れたが、開発はさらに遅延した。2010年4月、旭川医大は契約を解除し、NTT東は23億円の損害賠償を請求。裁判では、仕様凍結後の追加開発が争点となり、旭川医大の協力義務違反が指摘された。ユーザー企業には、仕様を適切に管理し、開発ベンダーと協力する責任があることが改めて示された。
出典:日経コンピュータ「システム開発の失敗を巡り裁判に至るまで、旭川医大とNTT東の2010年」2010年10月13日号
ポイントをひとことで
仕様凍結は開発の安定化を図る手段であり、変更管理と両立することが成功のカギです。
本コラムが指摘するように、仕様凍結はプロジェクトの混乱を防ぎ、スケジュールやコストを適切に管理するために不可欠ですが、ビジネス環境の変化や業務プロセスの見直しにより、変更が必要になることもあります。重要なのは、変更管理のルールを明確にし、影響分析を徹底することです。無計画な仕様変更は開発の混乱を招きますが、適切な変更管理を行えば、仕様凍結後でも柔軟かつ安定した開発を継続できます。事業会社は、仕様確定後も変化に対応できる開発体制を整えることが求められます。
仕様凍結の目的とは?
仕様凍結とは、システムの要件や設計を確定し、原則としてそれ以降の変更を制限することを指します。これにより、以下のようなメリットがあります。
- プロジェクトの混乱を防ぐ
仕様が確定していないと、開発途中での追加要件が発生し、方向性がぶれる可能性があります。仕様凍結を行うことで、開発を安定して進めることができます。 - スケジュールとコストの管理がしやすくなる
仕様変更が頻繁に発生すると、追加の工数やコストがかかり、納期の遅延につながります。仕様を固定することで、計画通りの開発が可能になります。 - システムの品質を確保できる
仕様が変わるたびに修正が加わると、バグが発生するリスクが高まります。仕様凍結により、品質を維持しやすくなります。
仕様凍結後に変更が必要になる理由
仕様を凍結した後でも、開発中に以下のような理由で変更が必要になる場合があります。
- 市場環境の変化:競争環境や法律の改正により、新たな機能が必要になる。
- 業務プロセスの変更:社内の業務フローが変わり、当初の仕様では対応できなくなる。
- ユーザーの新たなニーズの発見:テスト段階で、より良いユーザーエクスペリエンスのために調整が必要になる。
- 技術的制約の発生:開発途中で技術的に実現不可能なことが判明し、仕様を変更する必要がある。
仕様凍結と変更管理を両立させる方法
- 変更管理プロセスを明確にする
仕様変更が発生した場合の手続きを事前に決めておくことが重要です。例えば、変更要請は書面で提出し、影響を分析した上で承認する仕組みを整えます。 - 変更の影響分析を徹底する
仕様変更が開発スケジュールやコスト、品質にどのような影響を与えるのかを慎重に検討し、適用可否を判断する必要があります。 - 段階的なリリースを活用する
仕様変更が頻発する場合、全機能を一度にリリースするのではなく、段階的に開発・導入することで、リスクを最小限に抑えられます。 - 関係者全員で合意を得る
仕様変更が必要になった場合、開発チームだけでなく、事業会社の関係者も含めて合意を取ることが重要です。これにより、後のトラブルを防ぐことができます。 - 変更を最小限に抑える努力をする
すべての仕様変更を受け入れるのではなく、本当に必要なものかを精査し、不要な変更を避けることで、開発の安定性を確保します。
まとめ
仕様凍結は開発の安定化に不可欠ですが、変更が一切許されないというわけではありません。市場環境や業務要件の変化に柔軟に対応しながらも、適切な変更管理を行うことで、プロジェクトの成功率を高めることができます。
フルスクラッチ開発を進める際には、仕様凍結と変更管理のバランスを意識し、計画的にプロジェクトを進めることが重要です。
仕様凍結と変更管理、その両立がシステム開発成功のカギです。
フレシット株式会社は、フルスクラッチ開発において仕様凍結の徹底と、必要な変更への柔軟な対応を両立することで、事業会社の皆さまが求める理想のシステムを実現します。
当社の強みは、要件定義の段階からお客様の業務を深く理解し、適切な仕様管理とスムーズな変更対応の仕組みを構築することです。市場環境や業務フローの変化にも迅速に対応できる体制を整え、開発の安定性を維持しながらも、ビジネスの進化に適応できるシステムを提供します。
「変化に強く、ビジネスの成長を支えるシステムを構築したい」とお考えなら、ぜひフレシット株式会社にご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

