DX推進の落とし穴?「標準化」と「個別最適」のベストバランスとは
「効率化」と「競争力」、DX成功のためのバランス設計
2025-03-25
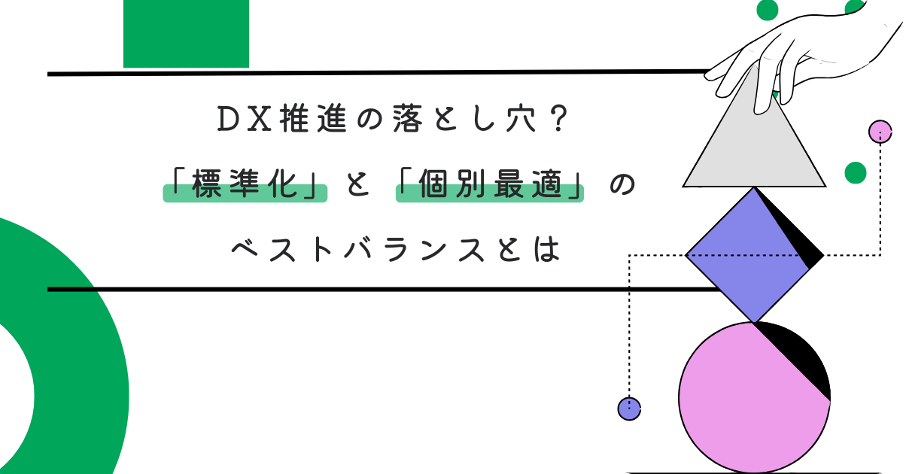
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進において、多くの企業が「標準化」と「個別最適」のバランスに悩んでいます。行政システムの標準化が進められる中、企業においても業務のデジタル化を進める際に、どこまで標準化すべきか、どの部分を独自の業務フローに最適化すべきかが重要なポイントとなります。
本コラムでは、その最適なバランスについて考えていきます。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
【関連記事】
DXを推進するためのシステム開発についてプロが解説
目次
【記事要約】行政のDX推進、文字基準統一でシステム効率化
デジタル庁は、自治体の基幹業務システムにおける文字基準を統一し、2026年度を目標に「行政事務標準文字」として7万字を策定する。従来、自治体ごとに異なる「外字」のルールがシステムの障害となり、職員負担やベンダーロックインの原因となっていた。統一基準により、行政のデジタル化を加速し、効率向上を図る。住民の理解を得るための周知活動も強化される予定。
出典:日本経済新聞「行政で使う文字、70万→7万字に 微妙に違う漢字統一 デジタル庁、システムの効率向上」2025年1月7日付朝刊
ポイントをひとことで
DXを推進する上で、「標準化」と「個別最適」のバランスは極めて重要です。標準化によってコスト削減や業務効率化が可能になる一方、過度に標準化すると独自性が失われ、競争優位性を損なうリスクがあります。一方で、個別最適を重視しすぎると、システム開発コストの増加や運用負担の増大につながります。本コラムでは、この二者のバランスを取るための具体的なアプローチとして、コア業務の個別最適化、APIやマイクロサービスの活用、システム開発会社の選定ポイントを提示しています。DXの本質は、自社のビジネスモデルに適した形でデジタル化を推進することです。システム導入の際は、目先のコストや短期的な効率化だけでなく、長期的な競争力を見据えた意思決定が求められます。
標準化のメリットとリスク
標準化とは、特定の業界や組織内で統一されたルールや仕様を採用することです。これにより、以下のようなメリットが得られます。
- コスト削減
統一されたシステムを導入することで、開発や保守にかかる費用を削減できます。 - 業務の効率化
異なる部署やグループ間でのデータ連携がスムーズになり、業務の無駄が減ります。 - システム開発会社の変更が容易
共通の仕様に基づいて開発されているため、特定のシステム開発会社に依存せず、柔軟にパートナーを変更できます。
一方で、標準化には以下のようなリスクもあります。
- 業務の柔軟性が低下
業界標準やパッケージシステムの仕様に業務を合わせる必要があり、独自の強みを生かしにくくなります。 - イノベーションの阻害
標準化されたシステムに縛られることで、新しいアイデアや技術導入の自由度が制限される可能性があります。
個別最適のメリットとリスク
個別最適とは、企業の業務に最も適した形でシステムをカスタマイズすることを指します。このアプローチには、以下のようなメリットがあります。
- 業務にフィットしたシステム構築
企業独自の強みや業務フローに合わせた最適なシステムを構築できます。 - 競争優位性の確保
独自の業務プロセスをデジタル化することで、競争力を高めることが可能です。 - 柔軟な拡張性
自社の成長や市場の変化に応じて、システムを柔軟に拡張・変更できます。
しかし、個別最適にも以下のリスクがあります。
- 開発・運用コストの増加
フルスクラッチ開発の場合、初期投資が高くなり、運用コストも増加する可能性があります。 - システム開発会社への依存
特定のシステム開発会社の技術やノウハウに依存しやすく、他社への移行が難しくなる場合があります。 - 統合の難しさ
標準化されたシステムとの連携が難しくなり、データの整合性が取れないこともあります。
標準化と個別最適のベストバランスとは?
では、企業はどのように標準化と個別最適のバランスを取るべきでしょうか?
コア業務は個別最適、非コア業務は標準化
競争優位性を生む業務(例:製造プロセス、顧客管理)は、個別最適化を進める。
一方、一般的な業務(例:会計、人事管理)は、標準化されたシステムを活用する。
APIやマイクロサービスの活用
標準化されたシステムと個別最適化されたシステムを柔軟に連携させるために、APIやマイクロサービスを活用する。
長期的な視点でシステム開発会社を選定する
フルスクラッチ開発を行う場合、将来的なサポートや技術進化に対応できる開発会社を選ぶ。
特定の開発会社に依存しすぎないよう、システムの設計段階から移行可能性を考慮する。
まとめ
DXを推進する上で、標準化と個別最適のどちらを選択するかは、企業のビジネスモデルや業務の特性によります。コア業務には柔軟な個別最適を、非コア業務にはコスト削減と効率向上を目的とした標準化を導入することで、バランスの取れたDXを実現できます。企業ごとに最適な戦略を見極めながら、DXの推進を進めていくことが重要です。
フレシット株式会社では、企業のDX推進における「標準化」と「個別最適」の最適なバランスを見極め、フルスクラッチ開発によるオーダーメイドのシステム構築を支援しています。
お客様の業務プロセスに深く寄り添い、競争優位性を高めるシステムを設計するとともに、将来的な拡張性や他システムとの連携も考慮した柔軟な開発を実現します。
長期的な視点でビジネスの成長を支えるシステムを構築したい企業様は、ぜひフレシット株式会社にご相談ください。あなたのビジネスに最適なDXソリューションを、共に創り上げていきましょう。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

