DX推進に潜む仕様変更リスクとその対策——持続可能な開発のために
中長期プロジェクトに求められる、設計と対応の余白
2025-04-07
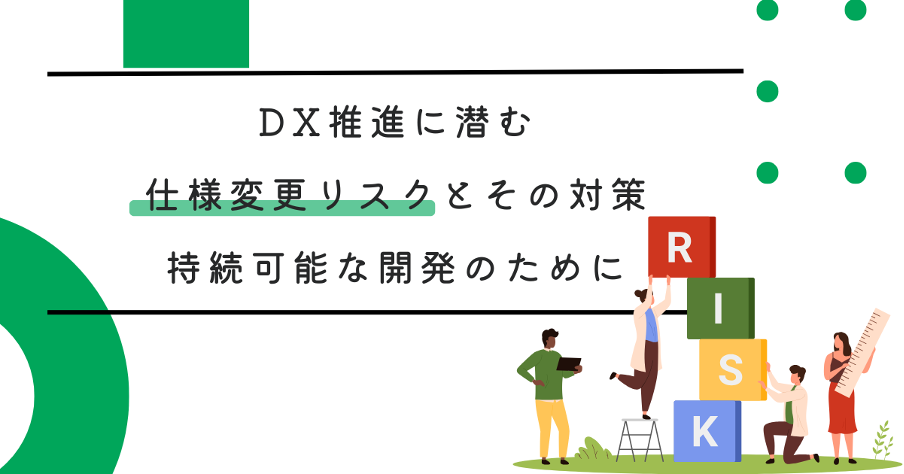
DXプロジェクトを進める中で、当初の想定から徐々に仕様が膨らみ、気づけば「計画とまったく違うものができてしまった」「いつまで経っても終わらない」といった状態に陥るケースが少なくありません。
本コラムでは、DX推進における「仕様変更のリスク」に焦点を当てながら、長期開発や不確定要素の多いプロジェクトにおける“失敗パターン”を整理し、それを回避するために有効なフルスクラッチ開発の柔軟性について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】文化シヤッター訴訟にみるDXの落とし穴、PaaS活用失敗で日本IBMに賠償命令
文化シヤッターの販売管理システム刷新において、日本IBMはPaaS「Salesforce1 Platform」での開発を請け負ったが、カスタム開発が想定の20%から95%に膨張し、開発は頓挫。東京地裁は、同社がPaaSの技術的制約を軽視しプロジェクト管理義務を怠ったと認定し、19.8億円の賠償を命じた。DX推進には、標準機能の活用と業務プロセス改革の両立が不可欠である。
出典:日経コンピュータ、2022年8月4日号 pp.104-106「販売管理システムの開発が頓挫 日本IBMに19.8億円の賠償命令」
【記事要約】文化シヤッター訴訟確定、DX失敗の責任問われ日本IBMに約20億円の賠償命令
文化シヤッターのDX推進の一環で始まった販売管理システム刷新が頓挫し、日本IBMに約20億円の賠償が確定した。最高裁は2025年1月、双方の上告を棄却。PaaS「Salesforce1 Platform」の制約やカスタム開発の過剰による構築失敗が主因とされ、プロジェクト管理の不備がDX失敗に直結した。本件は、クラウド活用における適切な設計と標準機能重視の重要性を浮き彫りにしている。
出典:日経クロステック「文化シヤッターのシステム開発訴訟の判決が確定、日本IBMに20億円の賠償命じる」2025年1月15日
ポイントをひとことで
このコラムは、DX推進プロジェクトにおいて見過ごされがちな「仕様変更リスク」に焦点を当て、特に中長期で進行する開発案件で陥りやすい“迷走パターン”を明確に描いています。DXは変化を前提とした取り組みである以上、当初の要件に固執するのではなく、仕様の変化を受け入れ、柔軟に対応できる設計と体制が不可欠です。特にフルスクラッチ開発は、こうした不確実性を前提に柔軟性と拡張性を持たせられる点で、プロジェクトを“止めない”大きな武器になります。
なぜDXプロジェクトは仕様変更で“迷走”するのか
DXは単なるシステム導入ではなく、業務やビジネスモデルそのものを見直す取り組みです。そのため、プロジェクトを進める中で以下のような変化や発見が頻繁に発生します。
- 業務の課題が深掘りされ、新たな要件が浮かび上がる
- 関係者の視点の違いによって優先順位が変わる
- 市場環境や経営方針の変化に伴い、機能の方向性がずれる
こうした変化に柔軟に対応できなければ、次第に「仕様変更の連鎖」に巻き込まれ、開発の遅延・コストの増加・品質の低下といった問題が顕在化していきます。
ありがちな“失敗コース”とは?
DXプロジェクトにおいて特に陥りがちな「失敗コース」は以下の通りです。
コース1:とにかくスピード重視でスタートし、設計が甘くなる
→ 結果、後から仕様変更が頻発し、開発が迷走。
コース2:パッケージやPaaSに業務を押し込もうとする
→ カスタマイズが膨らみ、プラットフォーム制約に苦しむ。
コース3:システム開発会社任せで、自社内の意思決定が曖昧
→ 要件定義がぶれ続け、プロジェクトが長期化。
これらはすべて、仕様の変化に柔軟に対応できない体制や技術的な制約によって起こるパターンです。
仕様変更は悪ではない。問題は「対応力」
仕様変更は、必ずしもネガティブなものではありません。むしろ、プロジェクトが前向きに進んでいるからこそ、新しい気づきや改善点が生まれるのです。
問題は、その変化に耐えられるかどうかです。
- 柔軟なアーキテクチャになっているか
- 業務要件と開発仕様が噛み合っているか
- 開発体制が機敏に対応できる設計になっているか
このような“対応力”が欠けていると、仕様変更が「プロジェクトの価値を高める機会」ではなく、「迷走の引き金」になってしまいます。
フルスクラッチ開発が持つ“対応力の強さ”
フルスクラッチ開発は、既存のプラットフォームやパッケージに依存しないため、設計段階から柔軟性を前提とした構築が可能です。これにより、以下のような強みが発揮されます。
- 要件の変更にも段階的・柔軟に対応できる設計
- 不要な機能を削ぎ落とし、必要なものに絞った構成ができる
- 業務フローや組織体制の変化を見越した拡張性が確保できる
さらに、フルスクラッチなら、開発のパートナーであるシステム開発会社と密な対話・共創の体制が取りやすく、変更内容の背景や目的を共有しながら進行できるというメリットもあります。
まとめ:DXは“柔軟に進化できるプロジェクト設計”が成否を分ける
DX推進において最も怖いのは、「当初の想定に固執して、変化に対応できないこと」です。
そのリスクは、計画段階では見えづらく、進行中に“ジワジワ”と深刻化していくのが特徴です。
だからこそ、初期の設計や開発手法の選定においては、「変化を前提とした柔軟性」があるかどうかを必ず見極めるべきです。
仕様変更は避けられません。問題なのは、それを受け止めるだけの“設計の自由度”と“開発の対応力”があるかどうかなのです。
フルスクラッチ開発は、その最適な答えのひとつです。
DXを「止まらないプロジェクト」にしないために、今一度、選択肢を見直してみませんか?
こうした“変化に強い”プロジェクト設計こそが、DXを止めず、成長につなげる鍵になります。
フレシット株式会社は、完全オーダーメイド型のフルスクラッチ開発を通じて、貴社の業務や構想の変化に柔軟に対応できるシステムを一緒に設計・開発いたします。
要件が固まっていない段階からの相談にも対応し、対話を重ねながら、仕様の揺れや変更を前提にした拡張性のある設計をご提案可能です。
中長期で見ても“路線変更に強い開発体制”をお探しの方は、ぜひ一度フレシットにご相談ください。
貴社のDXを、進化し続けるプロジェクトとして共に育てていきます。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

