“完成しないプロダクト”が競争力を生む──継続的改善を前提にしたDXシステム設計とは?
「完成」は終わりではない。DX時代のシステムは“育てる”もの
2025-04-08
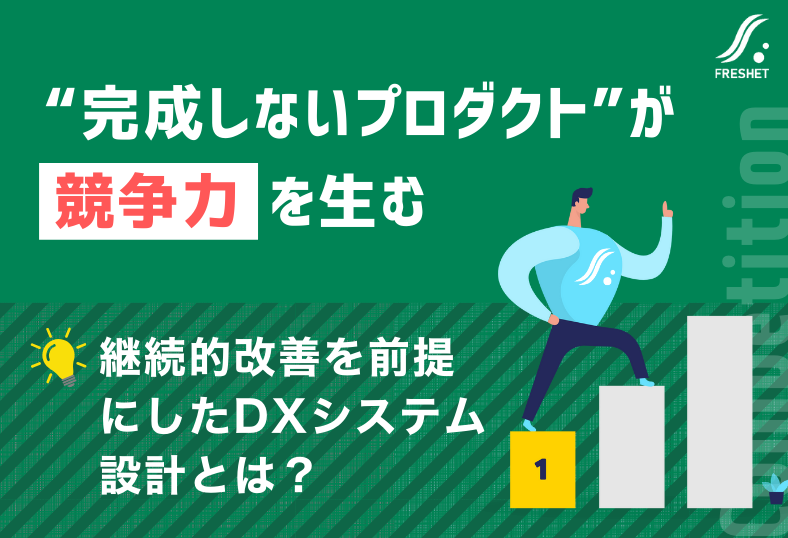
DXを推進するうえで、多くの企業が見落としがちな視点があります。それは、「完成」をゴールにしないという考え方です。
今、求められているのは、導入して終わりのシステムではなく、使いながら現場に合わせて進化し続ける“未完成のプロダクト”です。製造現場での取り組みから、その本質を考えてみましょう。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】今治造船、DX視点で「人への投資」実現 作業服にデータ連携と現場最適化を導入
今治造船は、従来の「綿100%」にとらわれず、防護性と通気性を両立した新作業服を開発。高温環境や火花が飛ぶ現場でも快適かつ安全に作業できるよう、素材から独自に設計した。加えて、作業服にバーコードを付けて使用状況をデータ化し、弱点分析や改良に生かす構想も進行中。これは現場データを活用して業務改善を図るDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環であり、「人への投資」を体現する取り組みである。
出典:日本経済新聞「今治造船、作業服『綿100%』常識破る 新素材で防護・通気を両立」2025年4月2日付朝刊
ポイントをひとことで
今治造船の作業服開発は、単なるユニフォーム刷新ではなく、現場データを起点にした継続的改善=DXの本質を体現する好例です。バーコードによる使用履歴の可視化は、業務改善に向けた「気づき」をデータとして蓄積し、次の改善につなげる仕組みを意図しています。これは業務システムにも通じる考え方であり、「完成を前提としない設計思想」が、変化の激しい時代において柔軟性と競争力を維持するための鍵となります。システムは作って終わりではなく、使いながら進化させるべきです。
作業服に“改善の種”を仕込む、今治造船の着眼点
今治造船が開発した新作業服は、防護性と通気性を両立したオリジナル素材を使い、社員の安全性と快適性を高めるために設計されました。しかし本当に注目すべきなのは、その後に見据えている「改善を前提とした仕組み」です。
作業服には一着ずつバーコードが付けられており、誰が・どの現場で・どんな作業をしたかというデータを蓄積できるようになっています。たとえば、穴が開いた場所やタイミングを分析することで、設計の弱点を特定し、次回の改良に活かす計画があるといいます。
このように「現場データを集め、改善に活かす」サイクルは、まさにDXの本質といえるでしょう。
システムにも求められる「進化前提」の設計思想
これはシステム開発においても同じです。
一度開発して終わりではなく、業務の変化や現場のフィードバックを反映しながら、使い続けるうちに“育っていく”システムこそが、DXの時代に適応したシステムです。
しかし、こうした柔軟性を確保するには、業務プロセスにきちんとフィットする設計が不可欠です。既製品やパッケージソフトでは、思い通りの改善を加えることが難しく、結果的に業務にツギハギの運用が発生してしまいます。
その点、フルスクラッチのシステム開発であれば、自社の業務に最適化した仕様で設計できるため、「継続的な改善」を前提としたシステム構築が可能です。
まとめ:“未完成”を前提にすることが、未来の完成形につながる
DXとは、一度きりの変革ではなく、継続的に業務をアップデートし続ける仕組みづくりです。
そのためには、「完成=終わり」と考えず、現場から得られるデータを取り込みながら改善を重ねていく姿勢が重要です。
私たちフレシット株式会社は、現場の声や業務の実態にしっかりと耳を傾けながら、「使いながら育てていく」システムの設計・開発をフルスクラッチでご支援しています。
業務に深くフィットし、将来の変化にも柔軟に対応できるシステムを一緒に作り上げていくことが、私たちの強みです。
「パッケージでは自社の業務に合わない」「改善したいが、どこから手をつければいいかわからない」といったお悩みをお持ちでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
フレシットが、貴社のDXの“次の一手”を共に考えます。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

