【ETC障害に学ぶ】本番リリースの“万が一”に備える──切り戻し可能なシステム設計がDX成功を支える
切り戻し可能な構成がもたらす、安心と継続性
2025-04-20
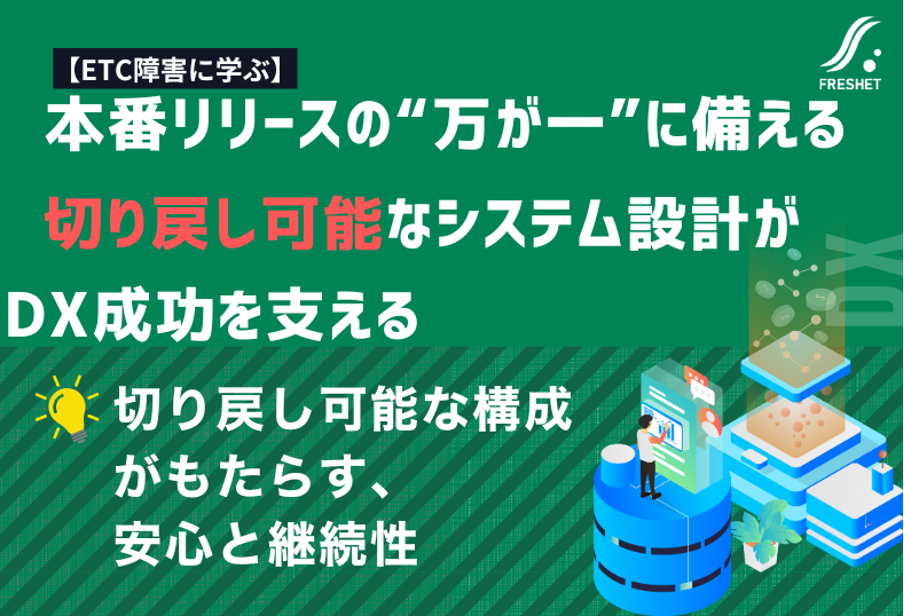
2025年4月に発生したETCシステムの障害は、東京や愛知など広範囲に影響を及ぼし、大きな混乱を招きました。今回の障害は、新たな割引制度の導入に伴うシステム改修中に発生したもので、「切り戻し」に時間がかかったことも被害拡大の要因とされています。
こうした事例からわかるのは、障害は避けられないという前提のもとで、いかに迅速に“戻せる”仕組みを用意できるかが、DX時代の成功を左右するということです。
本コラムでは、切り戻し可能なシステム設計の考え方と、なぜそれがDXにおいて不可欠なのかを解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】ETC障害が浮き彫りにしたDXの課題──複雑化する基幹システムと「2025年の崖」
中日本高速道路のETC障害は、継ぎはぎ的なシステム改修による複雑化が主因で、DX推進の遅れが浮き彫りとなった。基幹システムの老朽化と技術者不足が重なる「2025年の崖」が迫る中、多くの企業がブラックボックス化したシステムを抱え、改修のたびに障害リスクが高まっている。DXを進めるには、抜本的な再設計と障害時に備えた「切り戻し」体制の整備が不可欠である。
出典:日本経済新聞「ETC障害、システム複雑化が弱点 応急復旧で再開」2025年4月8日付朝刊
ポイントをひとことで
このコラムは、DXを推進するうえで見落とされがちな「切り戻し可能な設計」の重要性に焦点を当てています。システム障害は完全には防げない以上、事業継続の観点からは“いかに早く元の状態に戻せるか”が鍵となります。多くの企業が抱える「戻れない構成」「テスト環境との乖離」「段階導入が難しい設計」は、障害時に深刻なリスクを招きます。こうした課題を未然に防ぐには、初期設計段階から「停止を想定し、止めない工夫を施す」ことが不可欠です。まさに設計力と運用力が問われる時代です。
障害は起きる前提で設計する時代へ
現代のシステムは、複雑化と多機能化が進んでおり、障害が起こるリスクを完全に排除することは不可能に近くなっています。とりわけ、基幹業務やインフラを支えるシステムでは、一度の障害が業務停止や顧客離脱につながるリスクをはらんでいます。
そのため、「障害は必ず起こるもの」として捉え、発生時に迅速に前の状態に戻せる“切り戻し体制”を持つことが、今後のシステム設計において不可欠な視点となっています。
なぜ「戻せない設計」がDXの足かせになるのか
DXの推進はスピードが命ですが、その一方でシステムの安定稼働も担保しなければなりません。しかし、従来のシステム構築では「常に前進すること」が優先され、“戻る”という考え方が設計から抜け落ちているケースも少なくありません。
この状態で万が一トラブルが発生した場合、復旧には多くの工数と時間を要し、場合によっては運用停止や顧客対応の混乱につながります。DXにおける俊敏性と安定性の両立には、「切り戻し可能な設計思想」が極めて重要なのです。
切り戻しを実現するためのシステム構成のポイント
切り戻しを可能にするには、初期設計の段階で以下のような構成や仕組みを取り入れることが推奨されます。
- 段階的リリース(カナリアリリースなど):
一部のユーザーや環境に限定して新機能を提供し、問題があればすぐにロールバック可能。 - バージョン管理と環境分離:
本番環境・検証環境・開発環境を明確に分離し、検証結果をもとに安全なリリース判断が可能。 - 自動バックアップ・復元機構:
リリース前の状態をスナップショットなどで保持し、即座に復旧できる体制を用意。
これらを可能にするには、汎用的なシステム改修ではなく、自社業務に最適化されたフルスクラッチ開発が有効です。
フルスクラッチ開発で“止めないシステム”を実現
既製のパッケージや改修ベースの開発では、柔軟な構成設計や切り戻し機能の実装に限界がある場合もあります。一方、フルスクラッチであれば、事業特性や将来の運用体制を見据えた設計が可能です。障害時の影響範囲を抑え、スピーディに復旧できる構造を、設計段階から組み込めるのは大きな強みです。
DXの推進にあたり、“とにかく進める”のではなく、“止めない”仕組みを組み込むことが、これからの開発には求められています。
まとめ
本番リリースはDX推進の重要な一歩ですが、その裏側では「戻る」準備がなされていなければなりません。システム障害は完全には避けられないものだからこそ、切り戻し可能な構成設計こそが、ビジネス継続とDX成功の要となります。
フルスクラッチ開発を通じて、障害にも強く、将来的な拡張にも対応できる柔軟なシステム基盤を構築することが、今まさに求められています。システム開発会社を選ぶ際は、「戻せる設計」を前提とした開発実績や設計思想を持つパートナーと組むことが、今後のリスクに備える最良の判断となるでしょう。
こうした「止めないための仕組み」を開発段階から丁寧に組み込むには、業務理解と柔軟な設計力を兼ね備えた開発パートナーの存在が欠かせません。
フルスクラッチ開発を専門とするフレシット株式会社では、初期設計から運用フェーズまでを見据えたシステム構築を強みとし、切り戻しや段階リリースといったリスク対策も実装可能です。もし、貴社の業務に本当にフィットする“止めないシステム”をご検討であれば、ぜひ一度ご相談ください。課題に寄り添い、未来につながるシステムをご提案いたします。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

