【ETC障害から考える】システムを止める決断が未来を守る──大規模更新時の“戦略的オフライン”という選択肢
計画的停止が支える、持続可能なシステム運用
2025-04-22
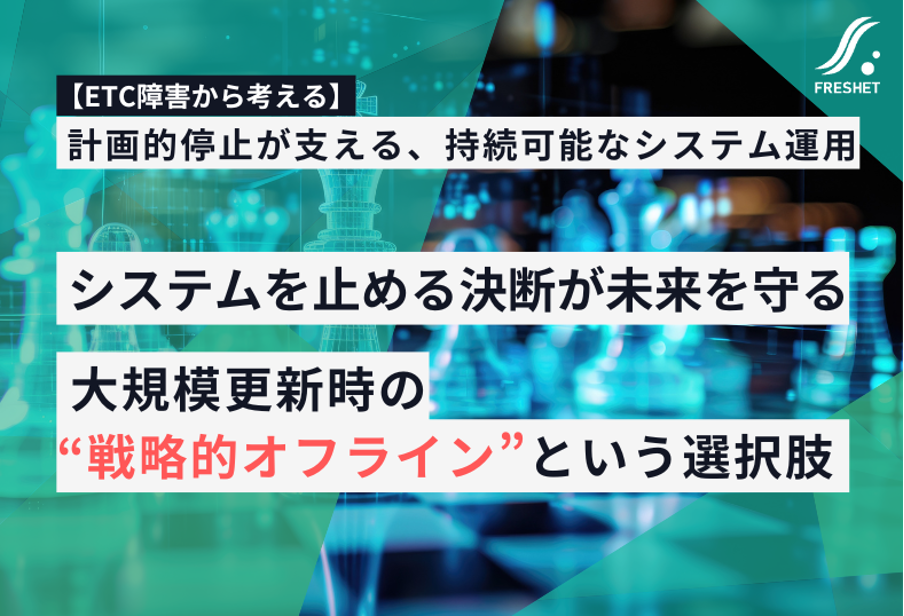
2025年4月に発生したETCシステム障害は、広範なエリアに影響を及ぼし、社会インフラにおける“止まらないことのリスク”を浮き彫りにしました。更新作業中の不具合により、カードが読み取れず通行ができない状況が相次ぎ、最終的にはレーンの開放という緊急措置が取られる事態に。今回注目すべきは、あえて“止める”という判断を取れていれば、影響範囲を最小限にとどめられた可能性がある点です。
本コラムでは、すべてをノーダウンタイムで対応しようとする姿勢の危険性と、“戦略的オフライン”という選択肢の価値について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】ETC障害が浮き彫りにしたDXの課題──複雑化する基幹システムと「2025年の崖」
中日本高速道路のETC障害は、継ぎはぎ的なシステム改修による複雑化が主因で、DX推進の遅れが浮き彫りとなった。基幹システムの老朽化と技術者不足が重なる「2025年の崖」が迫る中、多くの企業がブラックボックス化したシステムを抱え、改修のたびに障害リスクが高まっている。DXを進めるには、抜本的な再設計と障害時に備えた「切り戻し」体制の整備が不可欠である。
出典:日本経済新聞「ETC障害、システム複雑化が弱点 応急復旧で再開」2025年4月8日付朝刊
ポイントをひとことで
このコラムは、「止めないこと」こそが正義とされがちなシステム運用の常識に一石を投じています。すべてをノーダウンタイムで進めようとする姿勢は一見理想的ですが、障害発生時にはかえって被害を広げるリスクがあります。特に大規模なシステム更新時には、“あえて止める”という戦略的判断が、結果的に事業の信頼性やユーザー体験を守る選択になり得るのです。DXが加速する今こそ、設計段階から「止める前提」の柔軟性を組み込む視点が求められています。
「止めない」を最優先することの落とし穴
現代のシステム運用では、“止めないこと”が当たり前とされてきました。ECサイトや決済サービスなど、システムが止まれば即売上や信用に直結する業種では、ノーダウンタイムが大前提です。
しかし、今回のETC障害のように、一見止まっていないように見えても、内部ではエラーが蓄積され、ユーザー体験が損なわれていくという“静かなる障害”が起こるリスクもあります。何が起きても止めずに進行させる方針は、かえってリスクを拡大させてしまう可能性があるのです。
“あえて止める”という選択肢
そこで注目すべきなのが、“戦略的オフライン”という考え方です。たとえば、大規模なデータベース移行や基幹系システムの再構築、インフラの切り替えなど、不可逆的な作業が伴う更新時には、あえて短期間のサービス停止を設ける方が、結果的に安全かつ効率的な場合も多くあります。
サービスを止めるという判断は、ビジネスにとって痛みを伴う決断ではありますが、長期的には大きなトラブルを防ぎ、運用コストを抑える効果もあります。
停止に踏み切る判断に必要な視点
“止める”判断をするためには、以下のような視点と準備が求められます:
- 影響範囲の洗い出しと周知体制の整備:
ユーザーや関係者に事前周知を行い、サービス停止の理解を得る体制が不可欠です。 - メンテナンスウィンドウの明確化:
アクセスが少ない深夜帯や休日など、影響を最小限にするタイミングを選定します。 - 切り戻しとバックアップの体制:
万が一の不具合に備えて、迅速に旧環境に戻せる構成と自動バックアップ体制を設けておくことが前提です。
これらの判断と実行には、業務への深い理解と、柔軟な設計・開発が可能なシステム開発会社との連携が欠かせません。
フルスクラッチ開発だからこそできる「戦略的オフライン」設計
フルスクラッチ(オーダーメイド)でのシステム開発であれば、将来的な停止を前提とした運用設計や、切り戻し可能な構成、段階的な切替え計画なども最初から組み込むことが可能です。これは、パッケージソフトや改修ベースでは対応が難しい柔軟性です。
事業継続性と安全性を両立するためには、リリース後だけでなく「リリースの瞬間」にこそ、綿密な設計と判断力が求められます。その鍵を握るのが“止める勇気”なのです。
まとめ
あらゆる業種において、DXの加速とともにシステム更新の重要性は増しています。しかし、その過程において「絶対に止めない」という姿勢だけが正解とは限りません。あえて止める“戦略的オフライン”という判断が、長期的に見て事業の安定運用と信頼性を守る場合もあるのです。
更新作業を成功させるためには、業務フローやリスクを深く理解したうえで、システム構成・移行計画・周知体制を一貫して支援できるパートナーが必要です。フルスクラッチ開発を検討する際には、こうした“止める設計”も視野に入れた構築ができるかどうかが、成功の分かれ道となります。
このように、「止める」という決断を前提にした設計こそが、長期的な信頼性と安全性を支える鍵となります。
フレシット株式会社では、こうした“戦略的オフライン”を含むリスク設計や運用設計を初期段階から丁寧に織り込んだフルスクラッチ開発を強みとしています。単なる要件通りの構築にとどまらず、事業継続・将来拡張・運用現場のリアルまで見据えたご提案が可能です。大規模な更新や基幹システムの再構築を検討されているご担当者さまは、ぜひ一度お気軽にご相談ください。貴社にとって最適な“止めないための設計”をご提案いたします。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

