【ETC障害が映す企業システムの実態】ブラックボックス化した基幹システムが会社を止める日──技術者がいなくなる前にやるべきこと
ブラックボックス、それは静かに進行するリスク。
2025-04-26
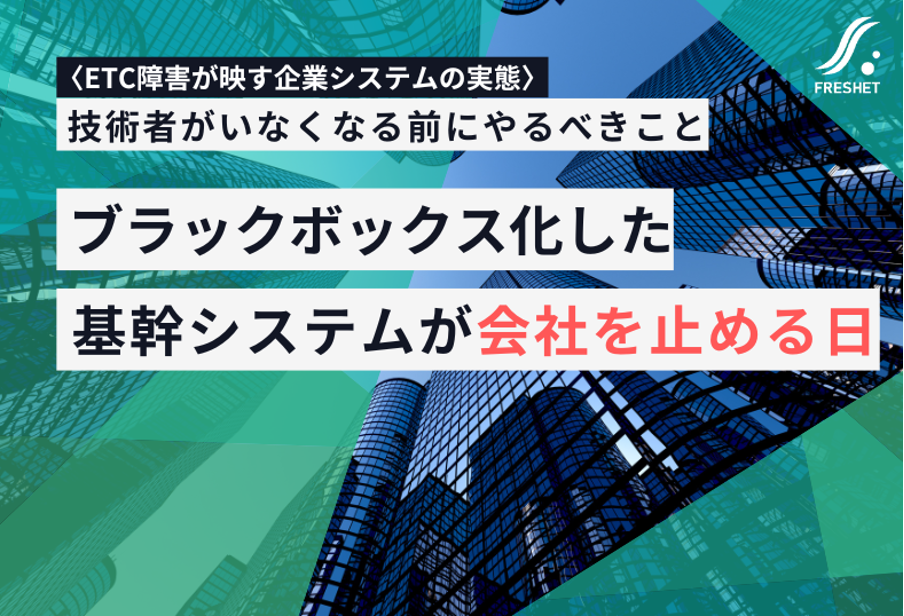
2025年4月に発生したETCシステムの大規模障害は、単なるシステム不具合ではなく、企業や組織における基幹システムの「ブラックボックス化」がもたらす構造的リスクを浮き彫りにしました。長年にわたり改修を繰り返した結果、システムの全貌を理解しているのは一部の担当者だけ。技術者の退職や異動によって、その知識が失われれば、致命的な停止や再構築困難という深刻な事態に直面します。
本コラムでは、こうしたリスクを未然に防ぐために、企業が今取り組むべき現実的なアプローチについて解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】ETC障害が浮き彫りにしたDXの課題──複雑化する基幹システムと「2025年の崖」
中日本高速道路のETC障害は、継ぎはぎ的なシステム改修による複雑化が主因で、DX推進の遅れが浮き彫りとなった。基幹システムの老朽化と技術者不足が重なる「2025年の崖」が迫る中、多くの企業がブラックボックス化したシステムを抱え、改修のたびに障害リスクが高まっている。DXを進めるには、抜本的な再設計と障害時に備えた「切り戻し」体制の整備が不可欠である。
出典:日本経済新聞「ETC障害、システム複雑化が弱点 応急復旧で再開」2025年4月8日付朝刊
ポイントをひとことで
このコラムは、属人化とブラックボックス化が進行した基幹システムが、企業にとっていかに深刻なリスクをもたらすかを明快に示しています。技術者の退職や異動によって“誰も中身を把握していないシステム”が残された場合、障害対応はもちろん、機能追加やDX推進すらままならなくなります。企業が持続的に成長するためには、システムの可視化と段階的な再設計が不可欠であり、それを実現するためのパートナー選定が成功の鍵となるでしょう。
“中の人しかわからないシステム”が招くリスクとは
多くの企業が運用している基幹システムは、長年にわたってその時々の要件に応じて改修が繰り返されてきました。その結果、設計当初の構造は失われ、改修内容も個々の担当者に依存したものとなり、ドキュメントや仕様書が十分に残されていない状態で運用されているケースが非常に多いのが実態です。
このような“属人化”したシステムは、特定の技術者がいなければ手を加えることも、障害時に迅速な対応を取ることもできません。もし、その担当者が退職や異動をすれば、業務全体が機能不全に陥るリスクすらあります。
ブラックボックス化がDXの障害にもなる
属人化された基幹システムは、単に運用リスクが高まるだけでなく、DX推進の足かせにもなります。クラウド移行や外部システムとの連携を進めようとしても、既存のコードやデータ構造が理解できず、変更に対して極めて慎重にならざるを得ない状況に陥ります。
さらに、過去の改修が連鎖的に影響し合っている状態では、何かを変更すればどこで不具合が起きるかわからないという不透明性が障害対応の迅速化を妨げ、業務停止のリスクを増大させます。
今すぐ着手すべき「可視化」と「段階的再構築」
ブラックボックス化への対応には、以下の2ステップが効果的です。
- 現行システムの棚卸しと可視化
機能一覧、データフロー、画面・バッチ処理の関係性を明文化し、どこが属人化しているのかを特定します。既存の担当者が健在なうちに、その知識を言語化・図式化することが急務です。 - 段階的な再構築(モジュール単位の再設計)
全体を一気に置き換えるのではなく、リスクの少ない領域から段階的に再構築するアプローチが現実的です。フルスクラッチでのモジュール単位再設計により、機能ごとの独立性を高め、将来的な変更にも耐えうる柔軟な構造にすることが可能です。
このような段階的な取り組みは、長期的には保守コスト削減や障害対応の迅速化にもつながります。
信頼できるパートナーと取り組むべき理由
属人化を解消し、持続可能なシステムへと転換するには、単なる開発の受託ではなく、業務理解と構造設計を伴走できるシステム開発会社の存在が重要です。
現状の課題抽出から設計思想の見直し、将来の拡張性を見据えたアーキテクチャまで、トータルで支援できるパートナーと組むことで、リスクを最小限に抑えた再構築が可能になります。
まとめ
企業の基幹システムが“ブラックボックス化”することで、システム障害やDX推進の遅れといったリスクは避けられなくなります。特定の技術者に依存し続ける運用体制は、企業の持続的成長を大きく妨げる要因です。
その前に、可視化と段階的再構築を通じて、健全で育てていけるシステム基盤へと移行することが求められています。システムが会社を止める前に──いまこそ、“誰でも運用・保守ができる状態”を前提とした、構造的な変革に取り組む時です。
こうした構造的な課題に向き合い、将来を見据えた基幹システムへの転換を実現するには、単なる開発作業にとどまらず、業務の本質を理解しながら設計段階から伴走できるパートナーが必要です。
フルスクラッチ開発を専門とするフレシット株式会社は、属人化のリスクを解消し、モジュール単位で“育てられる”システムをゼロから構築することで、企業の中長期的な成長を支援しています。今の仕組みに不安や限界を感じているご担当者さまは、ぜひ一度ご相談ください。持続可能で、変化に強いシステムづくりをご一緒いたします。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

