【ETC障害の事例から考える】「絶対に止めない」が招く危機──更新作業における“割り切り”の重要性とは
リスクは「止まること」ではなく、「止まれないこと」。
2025-05-04
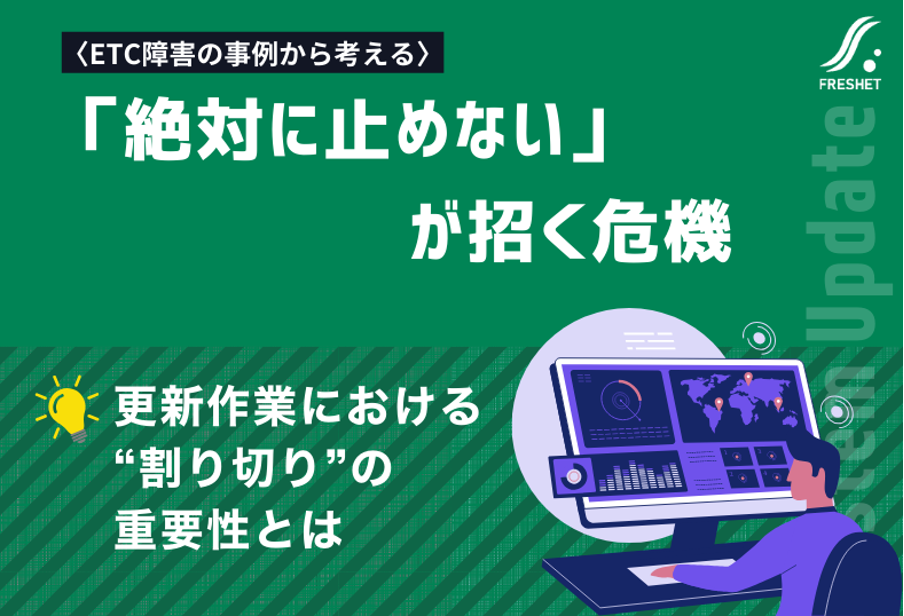
2025年4月に発生したETCシステムの障害では、100カ所以上の料金所でETCが利用不能となり、社会インフラの根幹が揺らぎました。この障害は、更新作業中に想定外の不具合が発生したことが原因ですが、特に注目すべきは「止めずに更新しようとしたこと」による影響の大きさです。
本コラムでは、「絶対に止めない」という運用方針がかえってリスクを増幅させる理由と、“止めるべきときに止める”という判断を可能にする開発・運用設計のあり方について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】ETC障害が浮き彫りにしたDXの課題──複雑化する基幹システムと「2025年の崖」
中日本高速道路のETC障害は、継ぎはぎ的なシステム改修による複雑化が主因で、DX推進の遅れが浮き彫りとなった。基幹システムの老朽化と技術者不足が重なる「2025年の崖」が迫る中、多くの企業がブラックボックス化したシステムを抱え、改修のたびに障害リスクが高まっている。DXを進めるには、抜本的な再設計と障害時に備えた「切り戻し」体制の整備が不可欠である。
出典:日本経済新聞「ETC障害、システム複雑化が弱点 応急復旧で再開」2025年4月8日付朝刊
ポイントをひとことで
このコラムは、「絶対に止めない」という姿勢が、かえって深刻なシステムリスクを招くという本質的な問題を突いています。無停止での更新を目指すあまり、障害発生時の初動が遅れ、結果的に影響範囲が拡大してしまうケースは少なくありません。だからこそ、止めるべき時に“計画的に止められる”設計と体制の構築が、真の事業継続性を支えます。これは単なる運用上の工夫ではなく、初期設計からの意思と構造に基づくべき戦略的な選択です。
「止めずに進める」が最良とは限らない
システム運用において「サービスを止めないこと」は、確かに重要な価値です。特に金融、物流、公共インフラなどでは、サービス停止が直接的な損失や混乱につながるため、“ノーダウンタイムでの更新”が理想とされてきました。
しかし、すべての更新作業を無停止で完遂するには、高度な設計・運用体制と十分なリスク評価が前提です。それを超えて「とにかく止めてはならない」という思想が優先されると、問題が発覚した際の切り戻しや緊急停止の判断が遅れ、結果として被害が拡大するケースもあります。
ETC障害の例では、想定していなかったシステム階層での不具合が広範囲に影響を及ぼし、復旧までに多大な時間とコストがかかりました。ここにあるのは、「止めるべきときに止められない」ことの危うさです。
「止めても安心」を設計に組み込む
安全な更新作業を支えるためには、“止めても大丈夫な体制”をあらかじめ設計しておくことが重要です。これは、単にバックアップを取るという意味ではなく、止めることでデータ不整合や業務停止が最小限で済むよう、構造的に備えるという考え方です。
以下のような準備・設計がそれを支えます。
- 業務への影響範囲を定義した事前シミュレーション
- 切り戻し可能なリリースプロセスとロールバック設計
- 停止中の業務継続策(バッチ遅延処理や代替入力機能など)の用意
- ユーザーや関係者への周知を含めた計画的な停止スケジュール
“止めても安心”な状態が確保されていれば、「無理に止めない」ことが最善ではないと判断できる柔軟性を持てるのです。
フルスクラッチ開発だからこそ実現できる柔軟性
これらの設計は、画一的なパッケージや既存システムの制約下では、実装が難しいケースもあります。フルスクラッチ開発であれば、業務ごとの特性やリスク許容度に応じた細やかな運用設計が可能です。
停止時の影響分析、段階的な更新構成、代替手段の提供など、止めることを前提にした“割り切りある設計”を最初から組み込めるのは、オーダーメイド開発ならではの強みです。
また、開発段階から業務部門とシステム開発会社が連携することで、単なる技術的実装にとどまらず、業務継続性を重視したシステム運用の仕組みそのものを共に設計することができます。
まとめ
DXの進展とともに、システム更新の頻度やスピードが増す中、「絶対に止めない」という運用方針は、かえってリスクを高めることがあります。
重要なのは、“止めるべきときに止められる設計”を用意し、止める判断ができる体制をつくっておくことです。
そのためには、業務理解に基づいた柔軟な設計力と、長期的な運用までを見据えた構築戦略が必要です。止めずに走り続けるためには、止まれる余白を設計に持つこと──それがこれからのシステム運用の基準となるでしょう。
こうした「止めるべき時に止められる」システムを実現するには、業務と運用に深く根ざした設計思想と、柔軟な開発体制が不可欠です。
フレシット株式会社では、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発を通じて、お客さまの業務特性や将来構想に合わせた運用設計を初期段階から構築します。更新時の安全性や業務継続性まで見据えた、長期的に“育てられる”システムづくりをご希望の企業さまは、ぜひ一度ご相談ください。貴社にとって最適な選択肢をご提案いたします。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

