働きがいを高める社内DXとは?大阪ガスの社内報刷新に学ぶ、従業員エンゲージメントを支える仕組みづくり
社員の心に届く、DX時代の社内コミュニケーション術。
2025-05-16
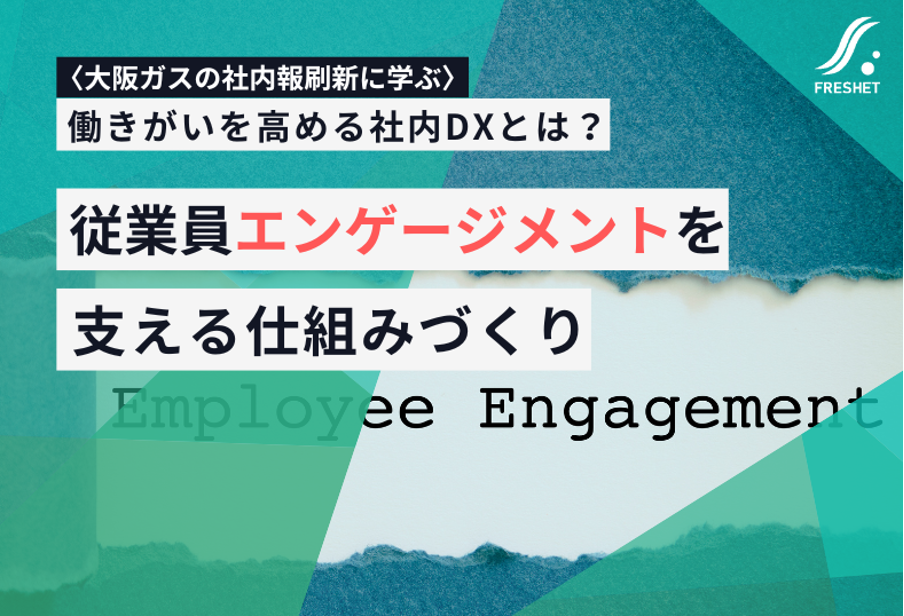
近年、人的資本経営の観点から、従業員エンゲージメントの向上が企業経営において重視されています。中でも注目を集めているのが、「社内報」のデジタル化や機能強化による情報共有の高度化です。大阪ガスが実践した“社内報×DX”の取り組みは、多くの企業にとって参考になる好例といえるでしょう。
本コラムでは、社内報のDX化がどのように従業員の心を動かし、エンゲージメントを高めるのかを解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】大阪ガス、DXで社内報を進化 従業員エンゲージメント向上へ
大阪ガスは、従業員の働きがい向上を目的に、社内報「がす燈」をDXの観点から大幅に刷新。SNS風の投稿機能「GASスタグラム」やハッシュタグ検索、記事ランキングなどを導入し、閲覧率を従来の「3割の壁」を超える約45.5%に向上させた。今後は閲覧データとエンゲージメントスコアの連携により、従業員の関心に即したコンテンツ配信を進め、次世代型社内報の実現を目指す。
出典:日本経済新聞「働きがい向上へ社内報進化 大ガス、閲覧率5割近くに」2025年5月13日付朝刊
ポイントをひとことで
社内報の刷新にDXを取り入れた大阪ガスの取り組みは、情報発信に「双方向性」と「データ活用」を加えることで、従業員エンゲージメントを定量的かつ継続的に高める好例といえます。特に注目すべきは、閲覧行動の可視化とエンゲージメントスコアの紐づけにより、コンテンツ改善をPDCAで回せる体制を構築している点です。こうした仕組みは、単なる社内広報にとどまらず、経営戦略と現場の橋渡し役として機能し得る重要な情報資産となります。
社内報は「読まれない」が当たり前?
社内報は長年にわたり企業内の情報共有手段として活用されてきましたが、「なかなか読まれない」「届けたい情報が届かない」といった課題を抱える企業は少なくありません。いわゆる「3割の壁」と呼ばれるように、従業員の閲覧率が30%を超えることは難しいとされています。
しかし、近年のDX推進の流れの中で、従業員目線の設計と機能性を取り入れることで、社内報の価値を再定義する企業が現れています。
大阪ガスの取り組みに見る“読まれる社内報”の工夫
大阪ガスでは2024年夏に社内報のシステムを刷新し、SNS風の投稿機能「GASスタグラム」やハッシュタグ検索機能、アクセスランキング表示など、従業員が使いたくなる仕組みを取り入れました。その結果、閲覧率は約45.5%に達し、「3割の壁」を大きく突破しました。
このような改善の裏には、「閲覧データの取得・活用」があります。従業員ごとの閲覧状況をデータ化し、どのコンテンツが関心を集めているか、誰がどの情報に触れているかを可視化することで、社内報の内容を継続的に最適化できるようになったのです。
フルスクラッチで作る“社内報システム”の可能性
大阪ガスの事例に限らず、社内報のDXには業務や組織文化に応じたカスタマイズが不可欠です。テンプレート型の既製ツールでは対応が難しい場合、フルスクラッチによる社内報システムの開発が有効な選択肢となります。
たとえば以下のような機能を自社に合わせて設計・実装することが可能です。
- 従業員参加型の投稿機能
- タグ・検索・お気に入りなどの利便性機能
- 閲覧履歴やリアクションのデータ取得
- 経営層からの発信とフィードバックの可視化
- エンゲージメントスコアとの連携分析
これらの要素を組み合わせることで、単なる情報発信ツールを超えた、「従業員と組織をつなぐプラットフォーム」としての役割を担うようになります。
【関連記事】
システム開発の依頼の流れは?失敗しないためのシステム開発会社の選び方についても解説
システム開発の費用相場は?費用を抑えるコツや依頼先選びのポイントについても解説
まとめ
社内報のDXは、従業員の関心を可視化し、エンゲージメントを高めるための有力な手段です。大阪ガスのように、使いやすさや参加しやすさを重視した設計と、継続的なデータ活用によって“読まれる社内報”を実現した事例は、多くの企業にとって学びの多いものといえるでしょう。業務や社風に最適化されたフルスクラッチ開発によって、より強固な組織づくりが可能になります。
こうした取り組みを自社で実現するには、自社の文化や業務プロセスに最適化されたシステムの構築が重要です。フルスクラッチ開発を専門とするフレシット株式会社では、貴社の課題や目的に応じて一から設計することで、汎用ツールでは実現できない“伝わる”社内ツールの開発を支援しています。使いやすさとデータ活用を両立した仕組みづくりにご興味がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

