【新基幹システム開発の訴訟から学ぶ】なぜマッピング作業は止まるのか?発注側と開発側、すれ違いの本質と乗り越え方
2025-07-26
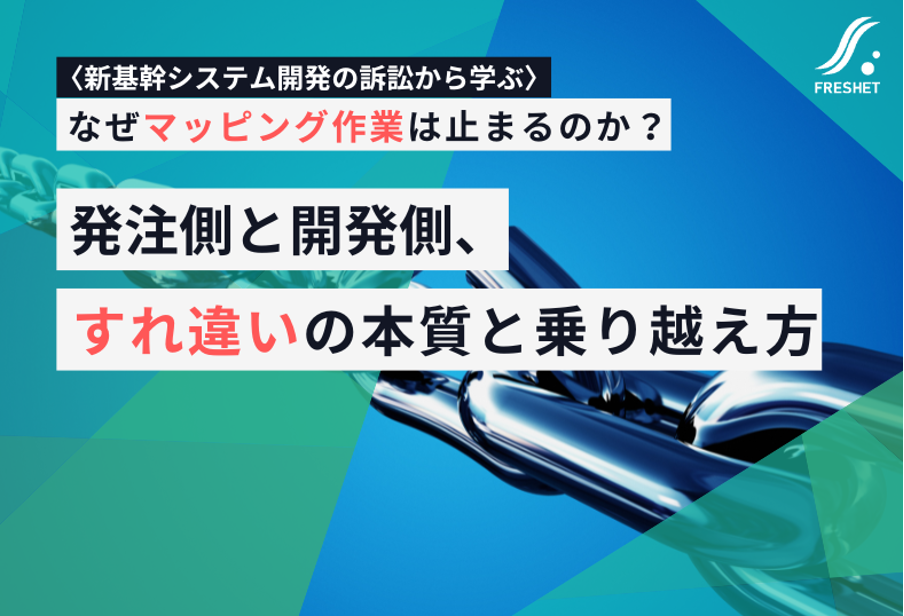
基幹システムの刷新プロジェクトが開発途中で頓挫し、システム開発会社を相手取った訴訟にまで発展したというニュースがありました。中でも注目すべきは、データ連携における“マッピング作業”が大きな障害となった点です。多くの企業にとって、複数システム間の連携は避けて通れない課題であり、マッピング作業の停滞は業務全体に深刻な影響を及ぼします。
本コラムでは、マッピング作業が止まる本質的な理由を、発注側と開発側双方の視点から整理し、その乗り越え方を考察します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】新基幹システム開発を巡る訴訟、マルヨシセンターがソフテックに2.3億円の賠償請求
マルヨシセンターは、老朽化した基幹システムの刷新を目的にソフテックへ開発を委託したが、作業の遅延や仕様不備により稼働に至らず、やむなく別のITベンダーへ委託。これを受けて、支払い済み金額や追加発注費用など計2億2990万円の損害賠償を求めてソフテックを提訴した。争点は、データ連携ツール「ASTERIA」の導入認識の食い違いや、マッピング作業遅延の責任所在。両社は高松地裁で争う見通し。
出典:日経コンピュータ「新基幹システムの開発が頓挫 ベンダーに2億2990万円の賠償請求」2025年5月12日
ポイントをひとことで
マッピング作業の遅延は単なる技術的課題ではなく、業務理解・情報整理・設計思想の不一致が引き起こす構造的問題です。特に、発注側が旧システムや業務の仕様を十分に言語化できていない場合や、開発側が業務文脈を読み解かずに仕様を構築する場合、両者のすれ違いは避けられません。フルスクラッチ開発においては、ツール導入ありきではなく、「何を、なぜ繋ぐのか」という目的起点の設計こそが、マッピング精度と連携の実効性を高める鍵となります。
マッピング作業はなぜ「止まる」のか
データ連携のマッピング作業とは、異なるシステム間でやり取りされるデータを整合させるための設計業務です。構造の異なるデータ同士をどのように変換し、どのような条件でやり取りするかを定義するこの工程は、単なる“作業”ではなく、システム全体の成否を左右する設計フェーズといえます。
しかし実際の現場では、このマッピング作業が予定通りに進まず、プロジェクト全体の遅延につながることが少なくありません。その要因は、開発会社の技術的な遅れや、発注側の準備不足といった単純なものではなく、両者の認識のずれや設計の前提条件の食い違いが複雑に絡み合っていることが多いのです。
発注側にありがちな構造的な課題
発注側に多く見られるのは、旧システムの仕様が担当者の属人的なノウハウに依存しており、明文化されていないケースです。結果として、「何のデータを、どのように連携するのか」といった前提情報が整理されないまま、マッピング設計が進められてしまうのです。
さらに、プロジェクト初期の要件定義で“データ連携の目的”まで踏み込まず、「とにかく繋がればいい」という感覚でツール導入が先行する場面もあります。このような状態では、マッピング作業に入った段階で初めて仕様のズレやデータの不整合が発覚し、手戻りや調整が発生してしまいます。
開発会社側の対応力にも差が出る
一方で、開発会社側にも課題はあります。業務全体を十分に理解しないまま、提供された資料をもとにマッピングを進めようとしたり、ツールの仕様ありきで進行した結果、実業務と乖離した設計になってしまうことがあります。
また、要件定義の初期段階で「何を、なぜ、どのように連携すべきか」という全体像を発注側と丁寧にすり合わせるプロセスを軽視してしまうと、後工程での混乱に繋がりやすくなります。ツールの導入は手段にすぎず、それを機能させるための構造や文脈を開発会社側が積極的に整理・提案していくことが重要です。
【関連記事】
システム開発の依頼の流れは?失敗しないためのシステム開発会社の選び方についても解説
システム開発の費用相場は?費用を抑えるコツや依頼先選びのポイントについても解説
「どこで詰まるか」ではなく、「なぜ詰まるのか」を見極める
マッピング作業が止まると、表面上は「連携できない」「フォーマットが合わない」といった技術的な問題に見えますが、根本には“目的や前提の共有不足”があります。
連携すべきデータが何で、どう活用されるべきものか。それが業務上のどの位置にあるのか。そうした情報を整理しないまま連携設計を進めても、必ずどこかで齟齬が発生します。
システム連携は、単なる技術課題ではなく“業務の流れを再設計する作業”でもあります。発注側と開発会社の双方が「業務」と「データ」の両方に目を向け、設計をすり合わせることが、マッピング作業の停滞を防ぐ鍵となります。
まとめ
マッピング作業が止まる理由は、単なる作業遅延やミスではありません。発注側の業務やデータ構造の棚卸し不足、開発側の設計理解の浅さ、そして双方の前提共有の不足が絡み合って生じる構造的な問題です。
「なぜ止まるのか」を正しく理解し、目的から逆算してマッピング設計を進めることが、システム連携の成功につながります。発注側・開発側が対等な立場で協働しながら進めることが、安定したシステム構築の鍵となるでしょう。
こうしたマッピング作業の停滞を防ぐには、「何を、なぜ、どう繋ぐのか」を業務視点で丁寧に紐解き、技術と業務の両面から設計を進める姿勢が欠かせません。フレシット株式会社では、初期段階から業務フローに深く入り込み、発注側とともに目的を共有しながら、ゼロベースで連携設計を構築します。仕様に業務を合わせるのではなく、業務に最適化した仕組みを一緒につくり上げたい企業さまは、ぜひ一度ご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

