【“システム納品後に想定外の不具合”を防ぐには】QAコストを“納得感あるもの”にするために――想定外をカバーするアドホックテストという選択
限られた予算で現実的な品質保証を実現する方法
2025-07-15
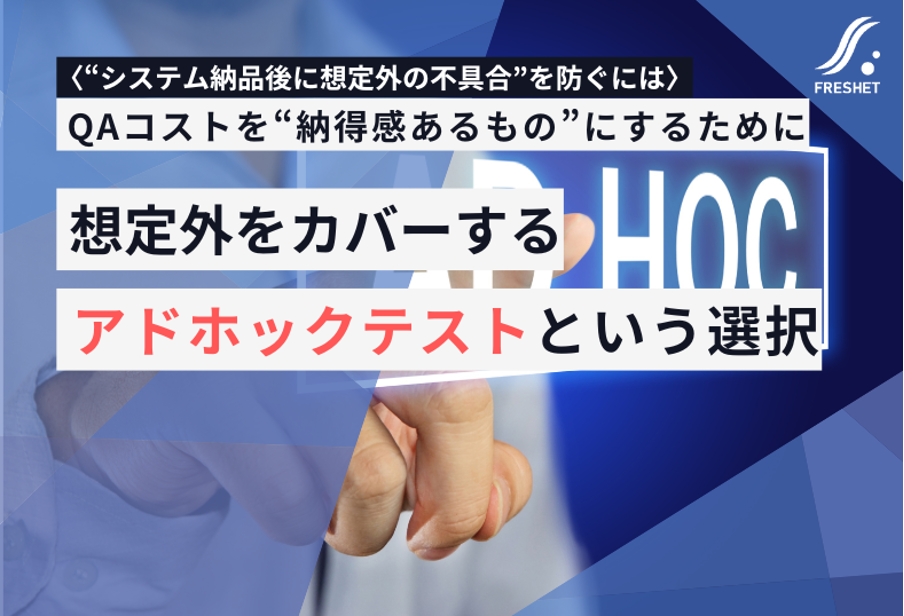
システム開発における品質保証(QA)には、一定のコストが伴います。しかし、「それ、本当に必要なテストですか?」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。とくに、実際の運用ではまず発生しないような操作に対して、工数をかけて検証が行われていると、コストに対する納得感が揺らぐ場面もあります。
本コラムでは、そうした現場の声をふまえながら、リアルなユーザー行動に即したQAのアプローチとして「アドホックテスト」の活用について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】ソフトウェア開発における失敗率が依然高水準、品質保証が成功の鍵に
2023年の調査によると、ソフトウェア開発プロジェクトの約3割が完了前に中止され、予算超過やスケジュール遅延も頻発している。原因には要件定義の不備やコミュニケーション不足、品質保証(QA)の軽視などが挙げられる。成功率を高めるには、開発初期からのQA体制構築と継続的な改善が不可欠であり、プロジェクトの品質と信頼性を支える重要な要素とされている。
ポイントをひとことで
QAにかかるコストは「無駄な保険」と見なされがちですが、本来は“想定外”を減らすための投資です。特にアドホックテストは、定型テストでは拾いきれない現場目線の不具合を見つけるために有効で、限られた予算内でも高い効果を発揮します。すべてのパターンを網羅するのではなく、実際の使われ方に即したテストにリソースを振り向けることで、発注側の納得感と実効性の両立が可能になります。QAの設計にも“使われ方”の解像度が求められます。
テスト工数とコストへの“違和感”
システムの品質を担保するにはテストが欠かせませんが、テスト項目が増えるほどコストも比例して増加します。発注側からすると、「どう考えてもユーザーがやらない操作」のために時間と予算が割かれているのを見ると、違和感や不満を覚えることがあります。
本来、テストの目的は「現実の利用環境で問題なく動くこと」の確認であり、過度に理想化されたケースではなく、実態に即した検証が求められるべきです。
アドホックテストとは何か
アドホックテストとは、仕様書通りの動作確認を行う定型テストとは異なり、テスターの経験や直感に基づいて、実際のユーザーがとり得る操作を想定して行う自由度の高いテストです。
業務フローにそった動作確認や、説明書を読まずに触るユーザーを想定した“気づきのテスト”としても活用されます。ドキュメント化されていない“盲点”を見つけることができ、限られたリソースの中でも現実的かつ実践的な品質保証が可能になります。
“やらない操作”より“ありがちな誤操作”を重視する
ユーザーが絶対にやらない操作のテストに工数をかけるより、現場でよく起こる誤操作や、マニュアルを見ずに使われる場面を想定した検証にリソースを振り分ける方が、現実的なリスク回避につながります。
アドホックテストは、まさにそのような「ありがちな落とし穴」を見つけ出すことに強みがあり、「実際に起こるかもしれない不具合」を発見することにフォーカスしています。こうしたテストへの予算配分であれば、発注者側にも納得感が生まれやすくなります。
テスト設計に“ユーザー目線”を取り戻す
すべてのパターンを網羅的に検証することは現実的ではありません。だからこそ、「どう使われるか」に寄り添ったテスト設計が重要になります。
アドホックテストをうまく取り入れることで、実際の操作感に即した検証ができ、「使ってみたら不便だった」「気づかずに入力ミスが起こっていた」といった、よくある“納品後の困りごと”を未然に防ぐことが可能になります。
まとめ
システムの品質保証は、単なる“抜け漏れチェック”ではなく、実際の運用現場を見据えた設計とテストであるべきです。
「やらない操作」への過剰な対応よりも、「ありがちな使い方」に焦点を当てたアドホックテストの導入は、限られた予算の中でも納得感あるQAを実現する選択肢となります。品質とコストのバランスをとりながら、現場で本当に役立つシステムを届けるために、テストの在り方を今一度見直してみてはいかがでしょうか。
こうした現場に即した品質保証の考え方は、発注先の開発姿勢にも直結します。フレシット株式会社では、仕様書通りに作るだけでなく、実際の業務フローや利用シーンを深く理解したうえで、アドホックテストを含む柔軟なQA設計を行っています。机上の理屈だけではなく、使い勝手や運用負荷まで見据えたフルスクラッチ開発を通じて、「納得感のあるシステム」をご提供します。仕様のその先まで、ともに考えていきましょう。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。
公式Xアカウントはこちら

