〈スタートアップ成長戦略〉MVPで始める業務システム開発──無駄な機能を省き成果を最速で出す方法
最小スタートで最速ゴール──MVPで変わる開発戦略
2025-08-12
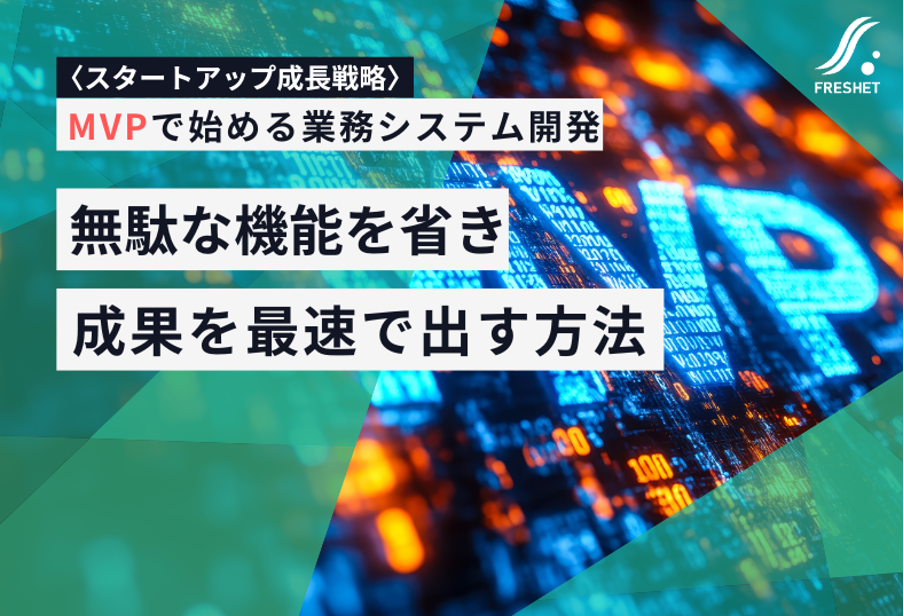
業務システム開発では、「必要だと思っていた機能がほとんど使われない」「現場が求める仕様と完成物がズレている」といった失敗例が後を絶ちません。その多くは、最初から全機能を一度に作り込む“全部入り開発”に起因します。
そこで有効なのが、MVP(ミニマム・バイアブル・プロダクト)のアプローチです。必要最小限の機能でシステムを短期間でリリースし、実運用から得られるデータやフィードバックをもとに改良を重ねることで、本当に使われるシステムを効率的に完成させられます。
本コラムでは、MVPの基礎から、業務システム開発で活用する際の具体的な手順や成功事例まで解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】スタートアップの成長を左右する「プロトタイプ開発」の進め方
スタートアップは創業後、顧客課題を深掘りし、試作品(プロトタイプ)で市場適合性を検証する段階に入る。重要なのは資金制約下でも顧客が購買を決める最小限の機能=MVPを特定すること。スマートバンクは150件のインタビューや海外調査を経て、カードとアプリ連動の家計管理サービス「B/43」を開発。半年継続率は98%に達した。シェアダインは半年間で20回以上試験利用を行い、利用者の食の悩みと料理人のスキルを可視化する機能を搭載。明確な差別化により投資家の評価も獲得した。
出典:日本経済新聞「〈The Startup Life〉ステージ(2)プロトタイプ開発 顧客射止める機能探れ インタビューで深掘り」2025年8月7日付朝刊
ポイントをひとことで
MVP開発は、業務システム構築におけるリスク低減と投資効率向上の有効なアプローチです。最初から全機能を作り込む従来型では、納期の遅延や不要機能の増加が起こりやすく、運用現場の実態と乖離することも少なくありません。MVPは必要最小限の機能で早期に運用を開始し、現場からのフィードバックを基に改善を重ねるため、現実的な業務フローに適合したシステムを構築できます。特に将来的な拡張を前提とするフルスクラッチ開発と相性が良い手法です。
MVPとは何か──概念と目的
MVPは「顧客が価値を感じるために必要な最小限の機能」を備えた製品やサービスのことです。元々はスタートアップの新規事業開発で使われる考え方ですが、業務システムにも適用可能です。
目的は、“最小の投資で最大の学びを得る”こと。完成度100%を目指して開発を長期化させるのではなく、動く状態を早期にリリースし、そこから得られる現場の反応や利用データを基に改良を重ねます。
なぜ業務システム開発でMVPが有効なのか
業務システム開発では、部署や役職ごとに異なる要望が集まり、当初計画より仕様が膨れがちです。結果、納期が遅れたり、実際には使われない機能が混在したりする事態が発生します。
MVP開発は以下のメリットをもたらします。
- 短期間で運用開始:業務改善効果を早期に得られ、投資回収のスピードが速まる。
- 仕様のズレ防止:机上の要件定義では見えない課題を、実運用で明確化できる。
- 無駄な機能の削減:利用頻度や重要度の低い機能を初期段階で見極められる。
- 柔軟な方向転換:事業環境や業務フローの変化に合わせて仕様を調整できる。
実運用で得られるフィードバックの価値
開発段階で想定した“理想の業務フロー”は、現場で使うと意外な障害に直面することがあります。例えば、
- 入力画面の項目順が作業手順と合わず、入力効率が下がる
- 自動化機能が一部の例外処理に対応できない
- スマホやタブレットでの表示が現場の利用シーンに合わない
こうした課題は、実際に使ってみなければわからないことが多いのです。MVPなら、運用初期からこうしたフィードバックを吸い上げ、素早く改修できます。
他の開発アプローチとの比較
- ウォーターフォール型:要件定義から本番リリースまでの期間が長く、仕様変更が難しい。
- パッケージ導入:初期機能は豊富だが、自社独自業務との適合性や柔軟な機能追加に限界がある。
- MVP+フルスクラッチ:初期は最小機能で構築し、必要に応じて自由に拡張可能。運用に沿った進化が可能。
この比較からもわかる通り、フルスクラッチ開発はMVPの思想と非常に相性が良く、将来的な拡張性や他システムとの連携も柔軟に対応できます。
成功するMVP開発の進め方
1. 機能の優先順位を明確化
すべての要望を同時に実装するのではなく、業務インパクトが大きく、ROIが高い機能から着手します。
2. 検証指標を設定
MVP段階での目的は「利用価値の検証」です。利用率、作業時間の削減率、エラー件数の減少など、効果を定量化する指標を決めましょう。
3. 改善サイクルの確立
フィードバックを短期間で反映できる体制が必要です。特に現場担当者との密なコミュニケーションが不可欠です。
4. 将来の拡張性を設計段階で確保
初期は小規模でも、将来的な機能追加や外部システムとの連携を見据えた設計を行うことで、MVPからスムーズに本番システムへ移行できます。
>>MVP開発の成功事例4選!成功のポイントについても徹底解説
事例から学ぶMVPの効果
例えば、飲食チェーンの発注管理システム開発において、最初から全店舗分の機能を作るのではなく、数店舗限定で発注・在庫管理のコア機能だけを実装。1か月間の運用で、入力画面の改善点や自動計算ロジックの修正点が洗い出されました。このフィードバックを反映した上で全店舗に展開し、結果として開発期間は当初計画より20%短縮、追加機能の無駄も削減できました。
まとめ
MVPによる業務システム開発は、短期間で実運用を開始しながら、現場の声を反映してシステムを磨き上げる実践的なアプローチです。全機能を一度に作り込むリスクを避け、最小限の投資で最大限の効果を得ることができます。特にフルスクラッチ開発では、MVP段階から将来の拡張性や独自要件に柔軟に対応できるため、ビジネスの成長に合わせたシステム進化が可能になります。
フレシット株式会社では、このMVPの考え方を軸に、初期段階から無駄を省いたフルスクラッチ開発を行っています。お客様ごとの業務フローや将来の拡張構想を丁寧にヒアリングし、必要最小限の機能で早期リリース。その後の運用で得られた知見をもとに、柔軟かつスピーディにシステムを進化させます。既製パッケージでは実現できない“自社仕様に最適化された業務システム”を、確かな技術力と伴走型の開発体制で実現します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

