【生成AI活用の進化から考える】“最後は人が使う”システム設計の重要性
生成AIを業務成果に変える、人中心のシステム設計
2025-08-14
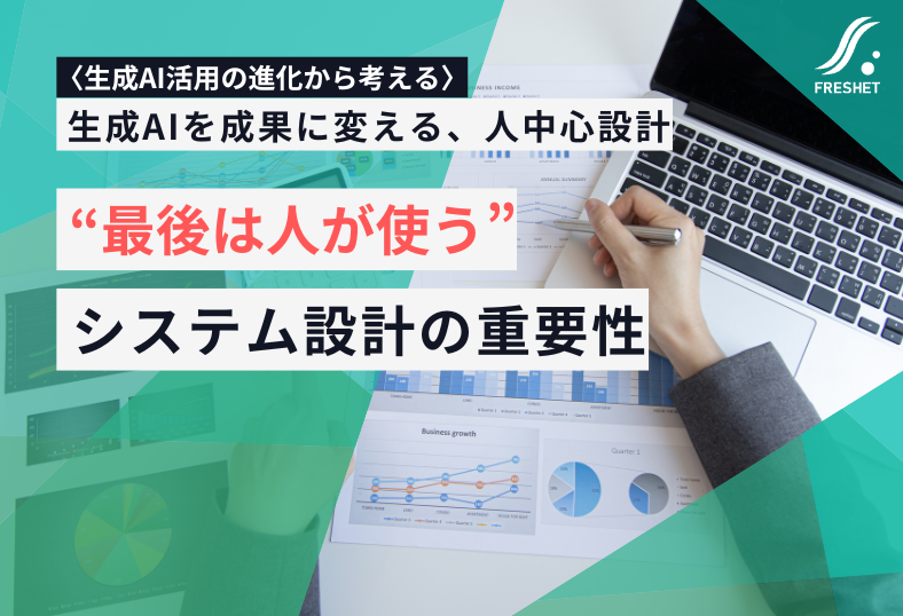
生成AIは、膨大なデータを瞬時に解析し、複雑な判断材料を短時間で提示できるまでに進化しています。しかし、その出力がどれほど高精度でも、現場の担当者が理解できず、適切な行動につなげられなければ意味がありません。実務で成果を生むには、「AIの結果をどう見せるか」「どう行動に結びつけるか」という、人を起点にした設計が不可欠です。
本コラムでは、AIの解析力を業務価値へ変えるための表示設計と操作フロー構築のポイントを解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】生成AIで揺れる法テック業界、差別化の決め手は「使い勝手」
生成AIの急速な進化により、契約管理や法務調査を担うリーガルテック分野では、一般的な生成AIでも一定の成果が得られるようになった。これにより、専用サービスの普及が進む一方、差異化の必要性も高まっている。各社は契約レビューの細部まで自動確認できる機能や、業務に即した操作性の改善など「使い勝手」の向上に注力。弁護士監修や専門データの活用で精度を高め、誤回答リスクへの対応も進める。覇権サービスがない中、実務に根差した利便性の確保が競争力の鍵となる。
出典:日本経済新聞「生成AI、法テック揺さぶる 契約管理や法務調査 実用レベルに 各社が差異化を模索」2025年8月4日付朝刊
ポイントをひとことで
生成AIは膨大な情報処理や解析を得意としますが、その出力が業務価値につながるかは「人が使える形」に変換できるかで決まります。現場で即座に理解できる表示設計や、判断から次のアクションまで迷わず進める操作フローは不可欠です。特に契約レビューや承認業務では、重要項目の可視化や関連情報への容易なアクセスが、判断精度とスピードを大きく左右します。AIの力を成果に変えるには、人を起点としたシステム設計が核心となります。
AIの出力は「そのまま」では現場に届かない
生成AIの出力は、多くの場合、汎用的な形で返ってきます。例えば契約書レビューでは、AIが条文の変更点を抽出しても、現場にとって重要な支払条件や責任範囲の変更がどこに含まれているのか、一目で分からないケースがあります。
また、解析結果が長文や専門用語で埋め尽くされていると、確認作業に時間がかかり、判断スピードが落ちます。結局のところ、AIの能力を業務成果に変えるには、そのままの出力ではなく、現場目線に翻訳した「業務で使える形」に加工する仕組みが必要です。
現場が理解しやすい表示設計
効果的な表示設計は、情報の視覚化と優先順位付けから始まります。
- 色分け:重要度や変更の種類に応じて色を使い分ける(例:追加=青、削除=赤、修正=黄)
- タグ付け:変更箇所に「支払条件」「納期」「責任範囲」などのタグを自動付与
- 多層ビュー:全文表示と差分強調表示の切り替え、概要表示と詳細表示の選択を可能にする
これらを組み合わせることで、ユーザーは数百ページの契約書でも、最も重要なポイントに短時間でたどり着けます。さらに、変更理由や関連資料へのリンクを埋め込み、確認作業から検証作業への移行もスムーズにします。
判断を支える操作フロー設計
解析結果を見せるだけでは、業務は前に進みません。重要なのは、その場で次の行動へ移れる導線を設計することです。
例えば契約レビューシステムでは、差分表示画面から直接「修正依頼」「承認」「差し戻し」の操作が可能であれば、画面遷移による手間や情報の見落としを防げます。また、AIが示した変更案をワンクリックで修正文案に反映し、人が最終チェックする流れを組み込めば、効率と精度の両立が実現します。
さらに、業務フローに合わせて画面遷移を最小化することも重要です。法務、経理、営業など部門ごとの作業順序を分析し、それぞれに最適な操作動線を提供することで、システムは現場に自然と馴染みます。
AIと人の「得意」を組み合わせる
生成AIは膨大な情報処理やパターン分析を得意としますが、最終的な判断や責任は人に委ねられます。そのため、システムはAIの計算結果を「人が即座に理解できる形」に変換し、判断材料として提示する役割を担います。
逆に、人が判断する部分をAIが補助しやすいように、入力フォームや確認項目を最適化することも有効です。こうした相互補完の設計こそが、生成AI時代のシステムに求められる本質的な価値です。
まとめ
生成AIの解析力は年々進化していますが、その価値を引き出すかどうかは「最後に使う人」にかかっています。理解しやすい表示、業務に沿った操作フロー、そしてAIと人の役割分担を意識した設計は、単なるツールを「業務を前進させる武器」へと変えます。AI時代だからこそ、人を起点としたシステム設計が欠かせません。
フレシット株式会社では、現場での実務に沿ったUI/UX設計と、業務フローに最適化された操作性をゼロから作り込むフルスクラッチ開発を強みとしています。生成AIの解析力を最大限に活かしつつ、出力を業務で使える形に変換し、判断や行動につながる仕組みを構築します。既製システムでは埋めきれない細部まで反映し、貴社の業務に真にフィットするシステムをご提供します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

