需要を見極めた新サービスを成長させる──仕様変更に強いオーダーメイドでの開発について
市場変化を先取りする柔軟なシステム開発
2025-08-19
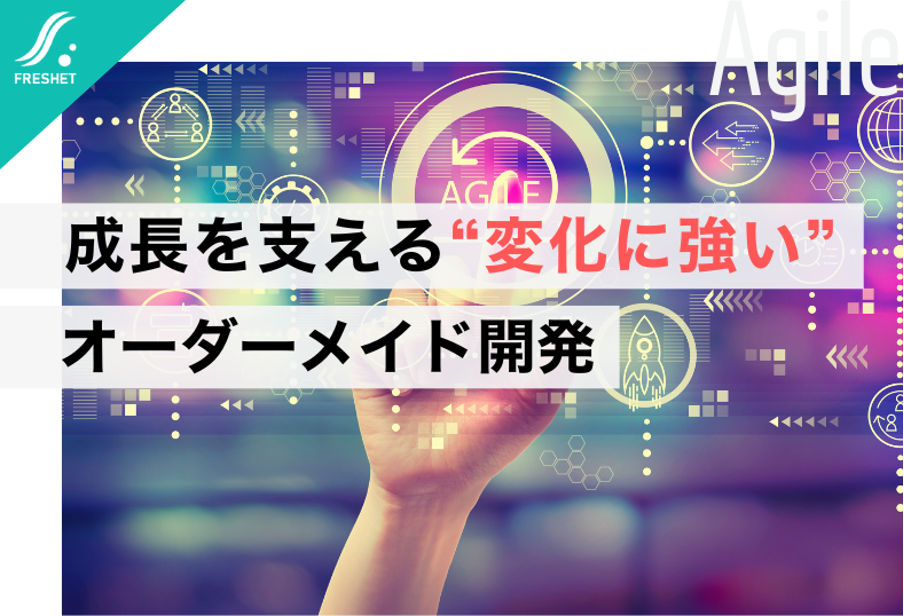
新サービスの立ち上げはゴールではなく、むしろ本当のスタートです。リリース後には、ユーザーの利用状況や市場の変化に応じて、仕様の見直しや機能の追加が頻繁に求められます。これらの変化に柔軟かつ迅速に対応できるかどうかが、サービスが成長するか停滞するかを左右します。
本コラムでは、仕様変更に強いシステムを構築するための設計思想と、改善サイクルを継続的に回すための開発体制の重要性について、フルスクラッチ開発の観点から解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】需要の見極めと新サービスの磨きこみが成長を左右──ピボット成功の条件
スタートアップは創業事業が必ずしも成功するとは限らず、需要を見極めた上でのピボットが成長の鍵となる。10Xは献立アプリ「タベリー」からネットスーパー立ち上げ支援サービス「ステイラー」へ転換。利便性課題を改善し、大手小売のニーズを捉え、品質向上で黒字化事例を実現、21億円の資金調達に成功した。Azitも外出需要減で配車事業を撤退し、技術を応用した新サービスを展開。資金余力があるうちの決断と自社適性の見極めが成長の決め手となる。
出典:日本経済新聞「〈The Startup Life〉ステージ(3)資金調達 祖業からの転換、成長導く 資金余力あるうちに決断」2025年8月8日付朝刊
ポイントをひとことで
新サービスはリリース後に必ず改善の機会が訪れますが、そのスピードと質は初期設計で大きく左右されます。特に仕様変更への適応力は、事業継続と成長の分水嶺となります。フルスクラッチ開発は、事業固有の要件や将来の変化を見越した柔軟な構造設計が可能であり、改善サイクルを高速で回す基盤を築けます。短期的な改修効率だけでなく、長期的な拡張性と保守性を両立する設計思想と運用体制こそが、競争優位を維持する鍵といえます。
新サービスが直面する改善の現実
新サービスは、開発初期の構想どおりに進むとは限りません。実際の運用に入ると、ユーザーからのフィードバックやデータ分析から、新たな課題や改善ポイントが次々と浮かび上がります。
例えば、想定していなかった利用パターンが発生したり、競合他社が革新的な機能を追加したり、法改正や業界標準の変更があったりします。これらの変化に後手で対応してしまうと、サービスの魅力はすぐに薄れ、ユーザー離れを招きます。
だからこそ、立ち上げ時点から「改善前提」のシステム構築を行うことが重要です。
仕様変更に強いフルスクラッチ開発の優位性
パッケージや既存の汎用システムは導入が早い反面、仕様変更の自由度が限られるケースが多く、大幅な機能追加や仕様変更には時間もコストもかかります。
一方、フルスクラッチ開発は、要件定義の段階から自社の事業特性・業務フロー・将来の拡張性までを見据えて設計できるため、後からの仕様変更にも柔軟に対応できます。
また、既存の構造や制約に縛られないため、UI/UXの改善やビジネスモデルの変化にも素早く追随でき、改善サイクルを短期間で回せる点が大きな強みです。
改善サイクルを支える開発体制のポイント
いくら仕様変更しやすい設計をしても、それを活かせる開発体制がなければ機能しません。重要なのは、システム開発会社と発注企業の間に密なコミュニケーションがあり、開発者が事業背景や顧客の利用環境を深く理解していることです。
さらに、以下のような体制が改善サイクルの質とスピードを高めます。
- 小規模な改修を継続的に行えるスプリント型の進行
- 改修前に影響範囲を素早く確認できるテスト環境の整備
- ユーザーデータやアクセス解析を活用した改善の優先順位づけ
- 仕様変更時の影響を最小限に抑えるモジュール化設計
これらを仕組みとして日常的に回すことで、改善のための意思決定が速くなり、競合との差別化にも直結します。
長期的な視点での設計と運用
サービスの寿命を延ばすためには、短期的な改善だけでなく、長期的な拡張性と保守性も確保する必要があります。初期段階から、将来的な負荷増加や機能追加を見越したスケーラビリティ設計を行い、コード品質やドキュメントの整備を怠らないことが重要です。
>>基幹システムの寿命はどれくらい?使い続けるリスクや入れ替えの進め方も解説
また、運用フェーズではモニタリング体制を確立し、障害予兆やパフォーマンス低下を早期に察知できる仕組みを組み込みます。これにより、改善のタイミングを逃さず、安定稼働と成長の両立を図ることができます。
まとめ
新サービスを成長軌道に乗せるには、リリース後の改善サイクルを支える「仕様変更への適応力」が不可欠です。フルスクラッチ開発は、変化を前提とした柔軟な設計を可能にし、改善のスピードと精度を高めます。事業の進化とともに変化し続けるシステムを作ることこそが、長期的な競争優位を築く鍵になります。
フレシット株式会社は、事業特性や将来の拡張性まで見据えたフルスクラッチ開発を強みとしています。要件定義の段階から丁寧に伴走し、仕様変更や機能追加にも柔軟に対応できる設計思想を持ったシステムを構築します。変化の激しい市場環境でも、改善サイクルを止めずに事業を成長させたいとお考えであれば、ぜひ私たちにご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

