〈投資判断の観点〉“作らない選択”も成果のひとつ──プロトタイプで見極める投資対効果
開発に踏み出す前に「撤退」を選ぶ価値
2025-08-24
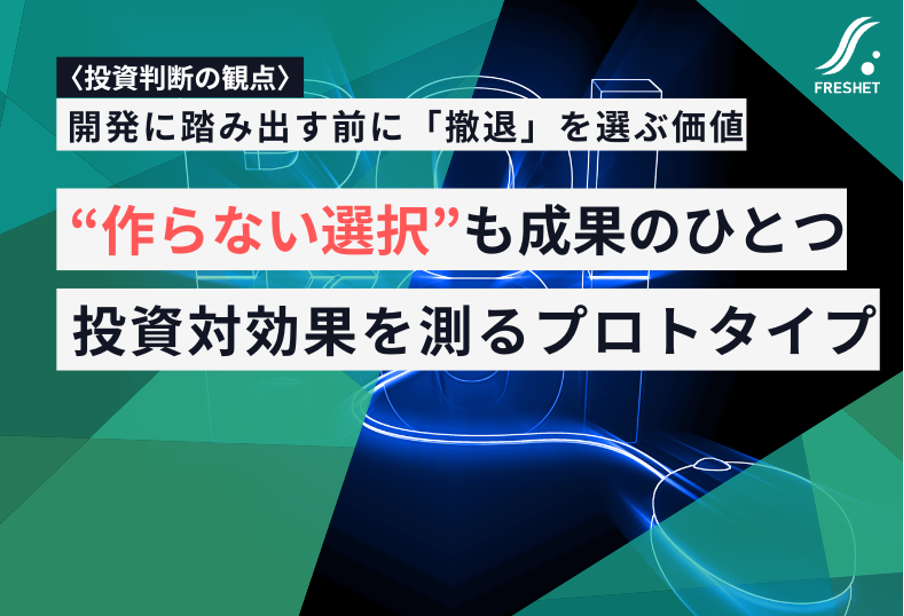
DXや新規システム開発の現場では、「作る」と決めてから本格的に着手するケースが多いですが、その結果として大きな手戻りや投資の無駄が発生することも少なくありません。重要なのは、開発を進めること自体を成果とするのではなく、「やるべきではない」と判断することもまた成果である、という視点です。プロトタイプ(試作品)は、その判断を早期に下すための強力なツールです。
本コラムでは、“作らない選択”を企業にとって前向きな成果と捉え、投資対効果を最大化する方法を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】スタートアップの成長を左右する「プロトタイプ開発」の進め方
スタートアップは創業後、顧客課題を深掘りし、試作品(プロトタイプ)で市場適合性を検証する段階に入る。重要なのは資金制約下でも顧客が購買を決める最小限の機能=MVPを特定すること。スマートバンクは150件のインタビューや海外調査を経て、カードとアプリ連動の家計管理サービス「B/43」を開発。半年継続率は98%に達した。シェアダインは半年間で20回以上試験利用を行い、利用者の食の悩みと料理人のスキルを可視化する機能を搭載。明確な差別化により投資家の評価も獲得した。
出典:日本経済新聞「〈The Startup Life〉ステージ(2)プロトタイプ開発 顧客射止める機能探れ インタビューで深掘り」2025年8月7日付朝刊
ポイントをひとことで
プロトタイプを通じて「やるか・やらないか」を判断することは、単に開発の効率化に留まらず、経営資源の最適配分に直結する重要なプロセスです。システム開発では、完成させること自体が目的化しがちですが、本来は投資対効果を最大化するための手段であるべきです。限られた時間とコストを有効に活用するためには、初期段階での検証を通じて「撤退」も選択肢として捉える柔軟さが求められます。開発を進める勇気と同じくらい、やめる判断を下す覚悟が企業の持続的成長を支えるのです。
プロトタイプが持つ「進める」と「やめる」の両面の価値
多くの企業がプロトタイプを「完成に近づくステップ」と捉えています。しかし、本質的な価値は「進める根拠」と「やめる根拠」の両方を与えてくれることにあります。試作品を実際に操作してみることで、ユーザーが想定通りの価値を感じられるかどうか、業務効率が改善するかどうかを検証できます。もし効果が限定的だと判明すれば、やめる判断を正当化できる材料になります。これは単なる中止ではなく、リソースを有効活用するための成果と言えます。
“作らない判断”が成果となる理由
システム開発において最も避けるべきは「不要な投資を長期間続けること」です。数千万円規模の開発が進んだ後に「使われない」「期待した成果が出ない」と分かれば、損失は取り返しがつきません。プロトタイプを用いて早期に「やらない」判断を下すことは、損失を最小限に抑え、他の有望な施策に経営資源を回せるという意味で成果そのものです。つまり、“作らない”ことは失敗ではなく、戦略的な成功への一歩なのです。
投資対効果を見極める具体的なステップ
プロトタイプを活用して投資判断を下すには、以下のプロセスが効果的です。
- 課題を明確化する:顧客インタビューや業務観察を通じて、解決すべき本質的な課題を把握する。
- 必要最小限で試作する:解決に直結する機能に絞り込み、短期間で試作品を構築する。
- 実運用に近い環境で検証する:現場担当者に使ってもらい、業務改善効果や利用価値を確認する。
- 継続か撤退かを判断する:得られたデータをもとに、「続ける」「軌道修正する」「やめる」を早期に決定する。
この流れを踏むことで、投資対効果を定量的かつ納得感をもって見極められます。
軌道修正や仕様変更の判断にも有効
プロトタイプは「やめるか進めるか」だけでなく、軌道修正や仕様変更の判断にも有効です。実際に使ってみると、「ユーザーの操作が直感的ではない」「想定外の業務パターンに対応できない」といった課題が明らかになります。こうした改善点を早期に洗い出し、仕様に反映させることで、完成後に大きな手戻りをするリスクを減らせます。つまり、プロトタイプは進行判断だけでなく、品質と適合性を高めるための重要な判断材料にもなるのです。
システム開発会社と連携するメリット
短期間で効果的なプロトタイプを構築するには、経験豊富なシステム開発会社の支援が不可欠です。業務課題のヒアリングから要件整理、迅速な試作品構築までを一貫して行える体制があれば、検証の精度もスピードも格段に高まります。その結果、やめるべきプロジェクトを早期に止める判断や、修正すべき仕様を適切に見極めることができ、経営資源を無駄なく活用できます。
まとめ
プロトタイプは、単なる試作ではなく「投資対効果を見極めるための判断ツール」です。作ることを前提とせず、やめる・修正するという判断を含めて早期に決定できるからこそ、企業は大きな損失を回避できます。“作らない選択”を成果と捉える視点は、システム開発やDX投資を成功に導くための重要な考え方です。開発を進めること以上に、やらない判断を適切に下すことが、結果的に企業の成長を加速させるのです。
プロトタイプによって「続ける」か「やめる」かを見極める姿勢は、システム開発において欠かせない投資判断の軸となります。しかし、こうした見極めを正しく行うためには、事業特性や業務フローに沿った柔軟な設計が前提となります。フレシット株式会社は、既製の枠にとらわれないフルスクラッチ開発を強みとし、企業ごとに最適な判断材料を提供できるシステム構築を支援しています。単なる機能実装にとどまらず、経営課題を踏まえたシステム設計にこだわることで、プロトタイプの効果を最大限に引き出し、企業の意思決定に確かな根拠を与える開発を実現します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

