【メルカリのAI基盤整備に学ぶ】「バラバラのシステム」ではAIは育たない──フルスクラッチ開発で実現する学習可能な統合環境
部門を超えたデータ統合が生み出す、生成AIの真価
2025-08-22
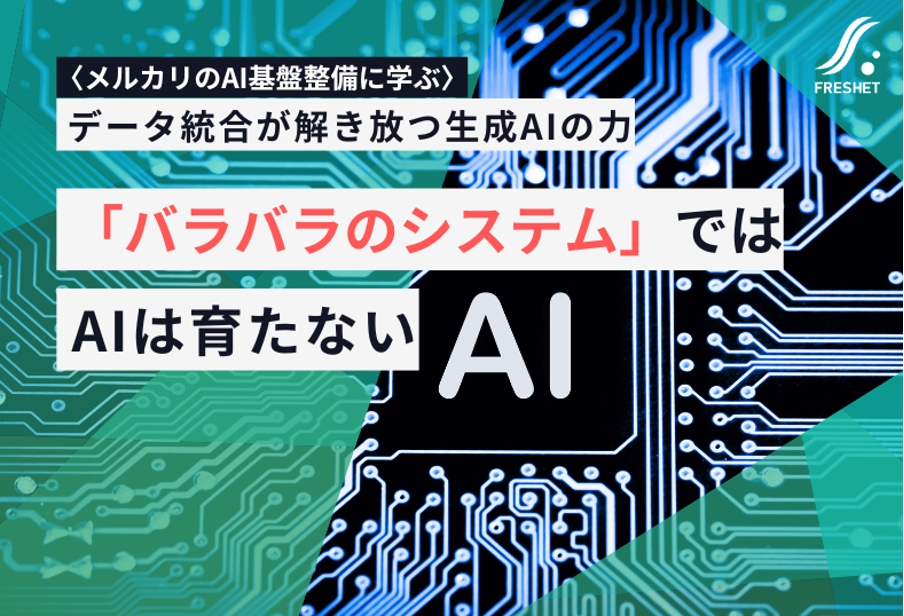
生成AIを業務や経営に活用する動きが広がる中、多くの企業が直面しているのが「データの分断」という課題です。人事や経理、営業、カスタマーサポートといった各部門が独立してシステムを運用している結果、企業全体のデータがサイロ化し、AIが学習できる情報が限られてしまいます。こうした環境では、AIのアウトプットは一部の断片的な知見にとどまり、実務に直結する効果を得ることは困難です。
本コラムでは、部門横断でデータを統合し、AIが継続的に学習できる基盤を整備するための実務的アプローチについて、フルスクラッチ開発の観点から解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】メルカリ、社内データ統合で生成AI活用を加速
メルカリは年内をめどに、人事・経理など社内業務システムに分散するデータを統合し、生成AIを経営基盤として本格活用する。MCP(モデル・コンテキスト・プロトコル)やAPIを用いた連携で、重複業務を削減し迅速な意思決定を可能にする狙いだ。統合データは部門横断的に検索・参照でき、利益相反の確認や経営情報の共有にも活用される。人員削減ではなく社員の再教育による生産性向上を重視し、米国事業の立て直しにも生成AIを導入する方針である。
出典:日本経済新聞「メルカリ、AI基盤整備 人事や経理のデータ統合 年内めど 意思決定速く」2025年8月21日付朝刊
ポイントをひとことで
企業が生成AIを実務に活かすには、まず「正しく十分に学習できる環境」を整えることが重要です。部門ごとに独立したシステムのままではAIは断片的な情報しか扱えず、経営や業務改善に直結する力を発揮できません。フルスクラッチ開発によるデータ統合は、業務プロセスに即した柔軟な設計を可能にし、AIが全社的な文脈で継続的に学習する基盤を築きます。これにより、経営と現場が共有知をもとに迅速かつ精度の高い意思決定を行える体制が実現します。
サイロ化がもたらす“AIの壁”
企業にはさまざまな業務システムが存在します。人事は勤怠・スキル情報を管理し、経理は予算や支出を管理し、営業は顧客接点をCRMに蓄積し、カスタマーサポートは問い合わせ履歴を持っています。これらのシステムが連携していない場合、AIはそれぞれの部門データを個別にしか学習できません。結果として「営業効率化には役立つが、経営全体の改善にはつながらない」といった部分最適に陥りがちです。
AIはデータが分断されるほど“視野狭窄”になり、誤った結論を導き出すリスクもあります。サイロ化を解消することは、AIを経営の武器に変えるための前提条件といえるでしょう。
データ統合が描き出す新たな価値
データを部門横断で統合すると、これまで見えなかった関係性やパターンが明らかになります。
- 人事と経理のデータを掛け合わせることで、採用コストと売上貢献度を評価できる
- 営業とサポートのデータを統合すれば、顧客対応の品質がリピート率にどう影響するかを把握できる
- 経営管理データと現場オペレーションを結びつけることで、全社的なボトルネックを特定できる
このように、統合データを背景にAIが学習することで、経営層の意思決定から現場改善までを一気通貫でサポートできるようになります。
なぜフルスクラッチ開発が有効なのか
市販のパッケージ製品やクラウドサービスは便利ですが、データモデルや連携方式に制約があり、自社の独自業務に完全にフィットさせるのは難しいのが現実です。特に、AI活用を前提としたデータ統合では以下の課題が顕著です。
- APIが限定されており、必要な粒度でのデータ取得ができない
- 異なるベンダー製システム間での整合性が取れない
- 将来の業務変更に柔軟に対応できない
フルスクラッチ開発であれば、業務フローを起点にデータモデルを設計し、統合アーキテクチャを柔軟に構築できます。さらに、拡張性を見据えたAPI設計により、新規事業や追加システムが発生しても容易に統合基盤に組み込むことができます。AIが長期的に“育つ”環境を整えるには、この柔軟性が欠かせません。
学習可能な環境を維持するための運用設計
統合基盤を作っただけでは不十分です。AIが常に価値あるアウトプットを出し続けるには、最新データを継続的に取り込み、再学習の仕組みを運用に組み込む必要があります。
- データ更新を自動化し、遅延なくAIに反映する
- データの品質を保つため、クレンジングや正規化の仕組みを組み込む
- 部門追加や新しい業務プロセスが発生した際に、スムーズに基盤へ拡張できる設計にしておく
このような運用設計により、AIは企業の“現在進行形”を学習し続けることができ、経営や現場に即した提案を出せるようになります。
経営と現場をつなぐ「共有知」の創出
データ統合のゴールは、単なる一元化ではありません。部門を超えて情報を共有することで、経営層は現場の動きを把握し、現場は経営判断の背景を理解できるようになります。生成AIは、この「共有知」を媒介として、双方を結びつける役割を果たします。結果として、全社的に共通認識を持ち、戦略と実務が一体となった意思決定が可能になります。
将来展望:生成AIとデータ統合の進化
今後は、AIが単にデータを分析するだけでなく、自律的に業務を遂行する「AIエージェント」として機能する時代が訪れます。そのためには、AIがアクセスするデータが正確で一貫性を持ち、組織全体をカバーしていることが前提になります。データ統合の質が、AIの実力を左右する時代になるのです。
まとめ
生成AIを真に活用するためには、「AIツールを導入する」だけでは不十分です。サイロ化したシステムを解消し、部門横断でデータを統合する基盤を整えることこそが、AIを“育て”、継続的に成果を出し続けるための条件です。フルスクラッチ開発による柔軟かつ拡張可能なアーキテクチャは、企業の成長や変化に合わせてAIを進化させ続ける力を持っています。経営と現場をつなぐ「共有知」を創出し、組織全体で学習を続けられる環境づくりが、これからの競争力の核心となるでしょう。
生成AIを活用した学習可能な統合環境を構築するには、業務の実態に即した柔軟な設計が欠かせません。フレシット株式会社では、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発を強みとし、部門横断で活用できるデータ統合基盤の構築を得意としています。既存のパッケージやクラウドサービスでは埋めきれない“すき間”を埋め、企業ごとの独自要件に最適化したシステムをゼロから設計することで、継続的に学習し成長するAI環境を実現します。組織全体の知をつなぎ、持続的な競争力へと変える基盤づくりを、私たちがご支援いたします。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

