転記作業をゼロに──フルスクラッチ開発で重複入力を自動化し、業務効率と正確性を両立する
重複入力をなくし、効率と正確性を両立する統合基盤
2025-08-26
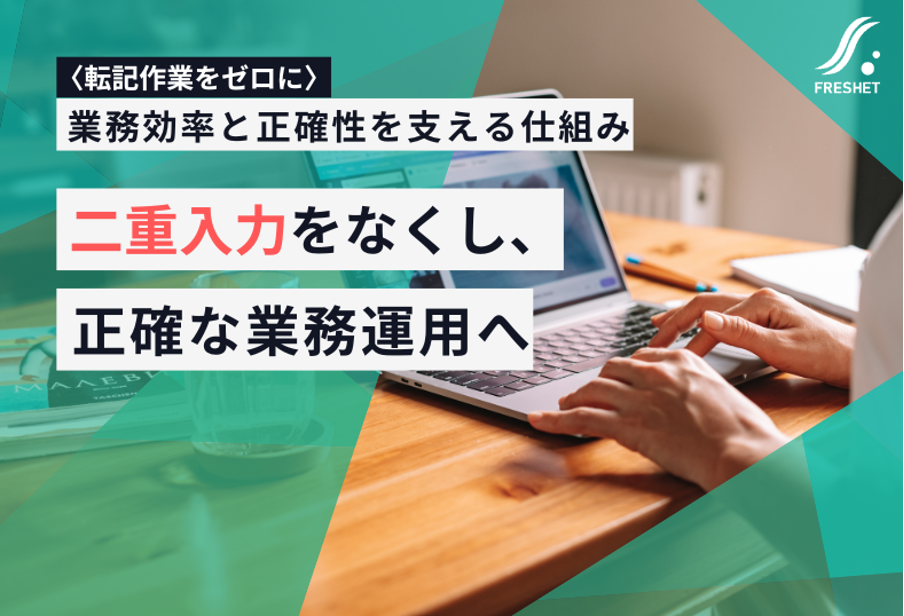
多くの企業が抱える課題の一つが「同じ情報を複数のシステムに入力しなければならない」という重複作業です。顧客情報や人事データ、経理情報などを部門ごとに異なるシステムで扱うため、転記や二重入力が日常化しています。この繰り返し作業は担当者の負担を増やし、入力ミスによる経営リスクも拡大させます。
本コラムでは、こうした非効率を解消するために、フルスクラッチ開発を用いてシステム間連携を自動化し、業務効率と正確性を両立させる実務的アプローチを紹介します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】メルカリ、社内データ統合で生成AI活用を加速
メルカリは年内をめどに、人事・経理など社内業務システムに分散するデータを統合し、生成AIを経営基盤として本格活用する。MCP(モデル・コンテキスト・プロトコル)やAPIを用いた連携で、重複業務を削減し迅速な意思決定を可能にする狙いだ。統合データは部門横断的に検索・参照でき、利益相反の確認や経営情報の共有にも活用される。人員削減ではなく社員の再教育による生産性向上を重視し、米国事業の立て直しにも生成AIを導入する方針である。
出典:日本経済新聞「メルカリ、AI基盤整備 人事や経理のデータ統合 年内めど 意思決定速く」2025年8月21日付朝刊
ポイントをひとことで
転記作業や二重入力は、一見すると小さな非効率に見えますが、企業全体で積み重なると大きなコストとリスクを生み出します。特にデータの誤入力や不整合は、経営判断の誤りや顧客対応の品質低下につながる重大な要因です。フルスクラッチ開発による統合基盤の構築は、単なる自動化以上に「業務プロセスに即したデータの流れ」を実現できる点に価値があります。人手に依存しない仕組みを作ることで、組織全体が正確で信頼できるデータを基盤に動ける体制を整えることが可能になります。
重複入力が生む「見えないコスト」
転記や二重入力は、一見すると些細な作業のように思えるかもしれません。しかし、企業全体で見ると膨大な時間とコストを消費しています。例えば、1回の転記に数分かかる業務を1人の担当者が1日10回繰り返した場合、年間では数十時間規模の工数になります。これが複数の部門で同時に発生すれば、数百時間単位の無駄な作業が積み上がることになります。
さらに深刻なのは、ヒューマンエラーによるリスクです。請求額の誤入力や支払い情報の重複登録は、企業の信用を揺るがす問題につながりかねません。特に金融や製造など正確性が重要な業界では、一度の入力ミスが取引先との関係に大きな影響を与える可能性があります。
転記依存から脱却できない理由
多くの企業では、既存のパッケージシステムやSaaSを導入しています。しかし、それぞれのシステムは独立して設計されており、必ずしもシームレスに連携できるわけではありません。APIが用意されていない場合や、CSVによるインポート/エクスポートに依存している場合、どうしても人手を介した転記作業が残ってしまいます。
また、既存のシステム間連携ツールを導入したとしても、自社の業務フローに完全に適合するわけではなく、「部分的には便利になったが、結局どこかで人の手が必要」という状態に陥るケースが多いのが現実です。
自動化で実現する「ゼロ転記」環境
転記作業をなくすためには、システム間のデータ連携を徹底的に自動化することが不可欠です。
- API連携:各システムのAPIを活用し、顧客や取引データをリアルタイムで同期。入力の二重化を防ぐ。
- CSV連携の自動化:APIが用意されていないシステムの場合でも、定期的なCSV出力をトリガーにし、自動変換・自動インポートを行う仕組みを構築。
- ワークフローの統合:業務プロセスの起点を整理し、「一度の入力で全システムに反映される」流れを設計。
これらを組み合わせることで、人が関与する余地を極小化し、転記や二重入力を“ゼロ”に近づけることが可能になります。
フルスクラッチ開発が果たす役割
市販の統合ツールや既存パッケージの機能だけでは、自社の業務に合わせた柔軟なデータ連携は難しいのが実情です。例えば、経理システムの勘定科目コードと販売管理システムの商品コードの粒度が一致していなければ、そのままではデータを結びつけられません。
フルスクラッチ開発では、このようなギャップを埋めるための変換ロジックやマスタ整備を業務に合わせて設計できます。また、事業成長に応じて新しいSaaSやパッケージを導入しても、既存の統合基盤に柔軟に組み込めるよう拡張性を確保できるのも強みです。これにより「使えるデータ環境」を長期的に維持できます。
正確性を担保するための設計ポイント
単にデータを自動でつなぐだけでは、正確性は担保されません。実務的な視点からは、以下のポイントが重要です。
- データ正規化:入力ルールを統一し、同一の顧客がシステムごとに別名で登録される重複を防ぐ。
- クレンジング機能:異常値や不完全データを自動検知・修正する仕組みを組み込む。
- 監査ログ:自動処理の過程を記録し、エラーや不整合があった際に迅速に追跡可能にする。
- 拡張設計:新規部門や追加システムが生じた際にも、最小限の改修で統合に組み込めるようにする。
こうした仕組みが整うことで、正確で信頼性の高いデータが全社的に共有でき、経営判断の質を高めることにつながります。
成功事例に見る効果
ある小売企業では、販売システムと在庫管理システムが連携しておらず、商品入荷データを手作業で二重登録していました。フルスクラッチで統合基盤を構築し、APIとCSVを組み合わせて自動反映する仕組みを整備した結果、担当者の月間作業時間は50時間以上削減されました。さらに、入力ミスによる在庫差異が大幅に減少し、欠品や過剰在庫のリスクを抑えることに成功しました。
別のサービス企業では、人事システムと経理システムの間で給与データの転記が必要でしたが、これを自動化することで、年次決算時のエラー修正にかかる負担を大幅に削減しました。こうした取り組みは、単なる効率化にとどまらず、社員がより付加価値の高い業務に時間を割ける環境を生み出しています。
【関連記事】
在庫管理システム開発 完全ガイド|開発費用や成功のポイントなどを解説
まとめ
重複入力や手作業による転記は、企業にとって大きな隠れコストであり、精度の低下やリスクの要因にもなります。APIやCSVを駆使した自動化と、それを業務実態に即して設計できるフルスクラッチ開発は、転記ゼロを実現するための最も有効な手段です。効率化と正確性を同時に実現する統合基盤を整えることで、企業は社員の時間をより価値ある業務に振り向け、持続的な成長につなげることができます。
転記作業をなくし、業務全体の効率化とデータの正確性を両立するには、自社の業務プロセスに合わせた柔軟なシステム設計が欠かせません。フレシット株式会社は、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発を強みとし、APIやCSVを駆使した自動連携や、複数システムをつなぐハブとなる統合基盤の構築を得意としています。既存のパッケージやSaaSでは埋めきれない“すき間”を補い、現場の手間を削減しながら経営判断に活かせる正確なデータ環境を実現します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

