業務データを可視化するだけで終わらせない行動変容の仕組み
見せるだけの管理から、動かす仕組みへ
2025-09-08
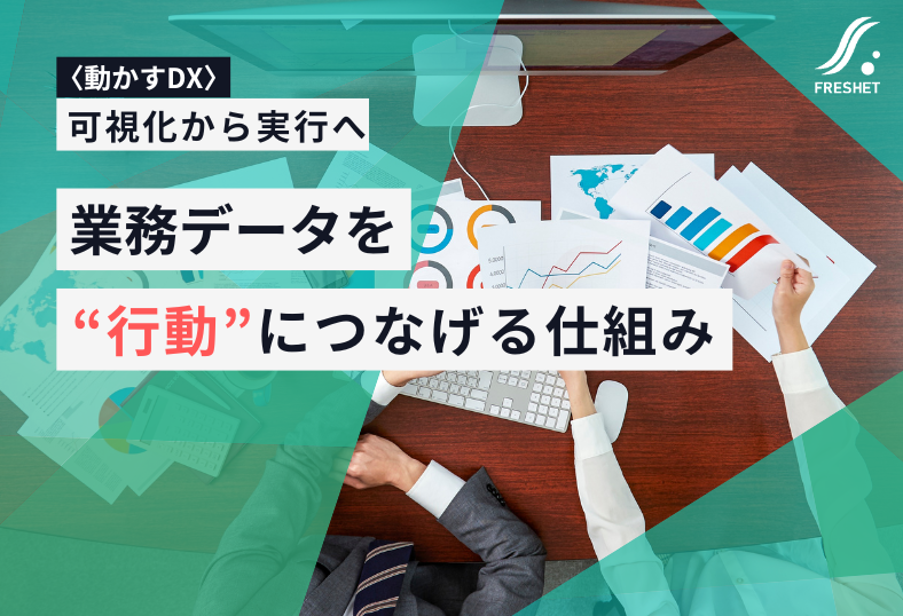
東京都が都立高校で試行している学習管理システム(LMS)では、生徒の学習履歴を記録・可視化する取り組みが進んでいます。ある生徒は「記録が見えることで勉強のモチベーションになる」と話しました。このエピソードは教育現場にとどまらず、企業のDX推進にも通じます。
業務データを可視化することは第一歩にすぎません。本当に価値が生まれるのは、データが気づきを促し、その気づきが従業員や組織全体の行動を変えていくときです。
本コラムでは「可視化→気づき→行動改善」という循環をどのように設計すべきかを掘り下げます。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
【関連記事】
おすすめの生徒管理システム10選を徹底比較!【2025年最新】
目次
【記事要約】都立高校、DXで学びを刷新──LMS導入で主体性を育む教育へ転換
東京都は都立高校の教育を「一斉指導型」から脱却し、デジタルとリアルを組み合わせた学びへ転換する。2025年度は生成AIを活用した教材開発や学習管理システム(LMS)の試行導入を進め、生徒が進度や学習履歴を自ら管理できる仕組みを整備。これにより主体性を育成し、教員も個々の学習状況に応じた指導が可能となる。LMSは通信制校で効果を確認済みだが、全日制での導入には教員の働き方への影響もあり慎重な検討が必要とされる。東京都はこうしたDXを通じ、変化の速い社会に対応できる人材育成を目指す。
出典:日本経済新聞「都立高、一斉指導を転換へ 生徒が学習管理システムで進度計画全日制でも導入視野 主体性生む環境整備」2025年8月26日付朝刊
ポイントをひとことで
業務データの可視化はDXの第一歩に過ぎず、その先にある「気づき」と「行動改善」まで結びつけてこそ真の価値を発揮します。単なるダッシュボードや数値の羅列では従業員は動かず、仕組みが形骸化してしまいます。大切なのはデータに文脈を与え、現場が次に何をすべきかを理解できる仕掛けを組み込むことです。これにより従業員は指示待ちから主体的な行動へと転換し、組織文化の変革が進みます。DXとは効率化ではなく行動を変える力そのものだといえます。
可視化の限界と落とし穴
近年、多くの企業がBIツールやダッシュボードを導入し、売上や生産性をグラフ化しています。しかし「数字を並べただけ」で終わってしまっている例も少なくありません。情報は表示されていても、現場の従業員が何を読み取り、どう活かせばよいのかが分からないため、せっかくの仕組みが“使われないシステム”になってしまうのです。
さらに、指標が多すぎることで逆に混乱を招き、「何を優先すべきか分からない」という状態に陥ることもあります。可視化自体が目的化してしまうと、組織は改善どころか停滞してしまうリスクすらあるのです。
データに“文脈”を与える設計
教育の学習管理で効果を発揮するのは、学習履歴の単なる羅列ではありません。「目標に対していま自分がどこにいるのか」がわかるように設計されているからこそ、生徒の主体性を引き出せます。
同じことが業務データにもいえます。売上や稼働率を可視化するだけでは不十分で、「基準値や目標との比較」「改善余地の見える化」といった文脈を持たせる必要があります。そうすることで従業員は数字をただ眺めるのではなく、「このままでは達成できない」「次はここを改善しよう」といった具体的な気づきを得られるのです。
行動変容を促す仕掛け
気づきが生まれたとしても、それが日常業務に結びつかなければ意味がありません。重要なのは、可視化を行動改善に直結させる仕掛けです。
例えば営業部門であれば、案件ごとの進捗を可視化するだけでなく「次に取るべきアクション(商談化すべき顧客リストや優先順位)」まで導き出す仕組みを設計することで、数字が行動に直結します。製造現場では、不良率の推移を表示するだけではなく「どの工程で不具合が多発しているか」「改善すべき作業手順は何か」といった具体的な改善策を提示することで、現場の動きが変わります。
つまり、可視化の出口に「行動を促すナビゲーション」が組み込まれているかどうかが、成否を分けるポイントになります。
DXと組織文化の変革
「可視化→気づき→行動改善」の循環が定着すると、組織文化そのものが変わっていきます。上司からの指示に依存するのではなく、従業員が自ら課題を発見し、改善に取り組む自律的なスタイルが育まれます。
これにより、管理型の組織から主体性を重んじる組織へと変革が進み、エンゲージメント向上や離職率低下といった副次的効果も期待できます。DXとは単なるシステム更新ではなく、こうした行動変容と文化変革をもたらす仕組みづくりにこそ真価があります。
フルスクラッチ開発の価値
既存のパッケージシステムや汎用的なBIツールでは、企業固有の業務に完全に適合させることは困難です。「自社にとってどのデータが重要か」「どのタイミングで提示すべきか」は企業ごとに異なり、既成の仕組みに合わせるだけでは行動改善につながらないことが多いのです。
その点、フルスクラッチ開発であれば、自社の業務フローや文化に沿って“気づき”と“行動”をつなぐ仕組みを柔軟に設計できます。結果として、可視化が単なる管理ツールではなく、組織を変えるエンジンとして機能するようになります。
まとめ
業務データの可視化はゴールではなく出発点です。重要なのは、そこから生まれる気づきをどう行動につなげるか、そしてその循環を組織に根付かせることです。汎用的な仕組みではなく、自社の業務特性に合わせた設計こそが、DXを組織変革の力に変える鍵となります。可視化を「見せるだけ」で終わらせず、組織の行動を変える仕組みへと昇華させることが求められています。
可視化から気づきを生み、行動改善へとつなげるには、自社の業務に合わせた柔軟なシステム設計が欠かせません。フレシット株式会社は、フルスクラッチによるオーダーメイド開発を強みとし、企業ごとの業務プロセスや文化に最適化した仕組みを構築してきました。既製のツールでは実現しにくい「データが行動を変える設計」を実現することで、DXを単なる可視化で終わらせず、組織変革につなげたいとお考えのご担当者さまを強力に支援します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

