通販サイトの“誤誘導デザイン”問題から考える──ユーザーセントリックはコスト削減につながるUI/UX設計
DX投資を無駄にしない、プロトタイピングとUI/UX最適化の実践
2025-09-15
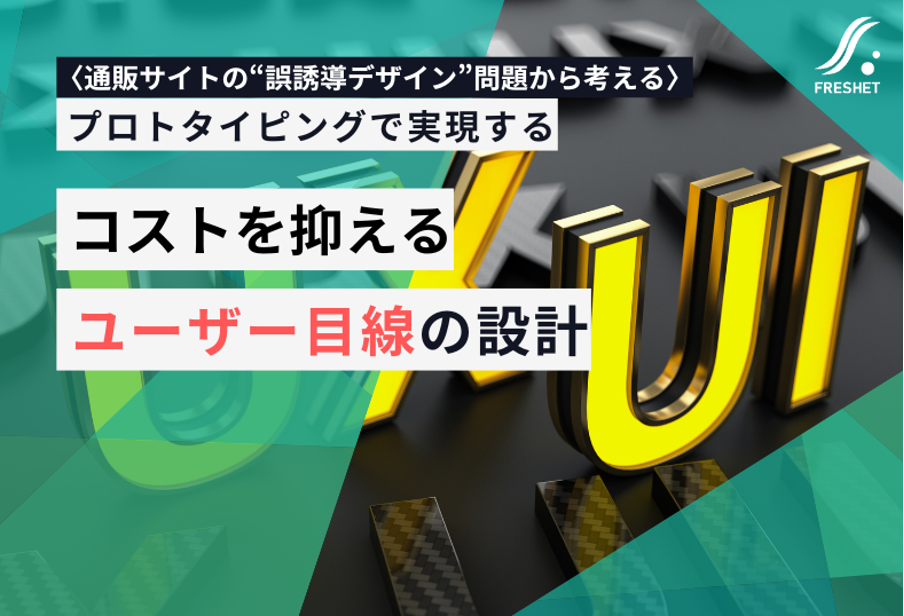
通販サイトで「ダークパターン」と呼ばれる誤誘導デザインが広く使われていることが話題になっています。利用者にとって不利益な選択肢を気付かないうちに押し付けるこうした設計は、短期的には売上を押し上げても、長期的には信頼を失い、修正対応や解約対応のコストを増大させます。
この事例は、企業システムの開発にも大きな示唆を与えます。業務システムやサービス基盤においても「利用者が使いにくい」と感じれば、不満や追加要望が積み重なり、開発後に手戻りが発生します。本コラムでは、ユーザーセントリックな設計思想がどのように手戻りを防ぎ、結果としてコスト削減につながるのかを解説し、プロトタイピングやフルスクラッチ開発の具体的な強みも紹介します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】通販サイトに蔓延するダークパターン、DX時代の透明性確保が急務
国内主要通販サイトの7割で、定期購入が初期選択されるなどの「ダークパターン」が確認された。これらは景品表示法や独禁法に抵触する恐れがあり、消費者保護の観点からルール整備が求められている。デジタル化に伴いオンライン取引が日常化する中、UI/UX設計は単なるマーケティング手法を超えて、企業のDX推進における信頼性確保の核心的課題となっている。公正かつ分かりやすい設計が、利用者の安心と競争環境の健全化につながる。
出典:日本経済新聞「通販サイト7割ダークパターン 顧客惑わすデザイン勝手に定期購入・メルマガ登録に印 消費者保護ルール重要」2025年8月5日付朝刊
ポイントをひとことで
システム開発で最も大きな無駄は、完成後に利用者からの不満や修正依頼が相次ぎ、設計をやり直す「手戻り」です。その多くは初期段階でユーザー視点を十分に取り入れられなかったことに起因します。ユーザーセントリックな設計は、現場の業務や利用者の行動を出発点にすることで、このリスクを最小化します。さらにプロトタイピングで操作感を確認し、フルスクラッチ開発の柔軟性を活かすことで、無駄なコストを防ぎながら本当に使われるシステムを実現できます。
手戻りが生じる典型的なシナリオ
システム開発において手戻りが発生する場面は少なくありません。たとえば、発注者が作成した要件定義書をそのまま基に開発を進め、リリース後に「現場で想定通りに使えない」と指摘されるケースです。ユーザーの業務フローや操作感が十分に反映されていないと、修正依頼や追加開発が相次ぎ、当初想定した予算や納期は大きく崩れてしまいます。
また、導入後に「入力項目が多すぎて処理が遅い」「解約や登録変更の操作が複雑」といった声が寄せられる場合もあります。これらは仕様段階で気付ければ容易に修正できますが、開発後の改修は設計全体の見直しを伴うためコストが跳ね上がります。
ユーザーセントリック設計がもたらす効果
ユーザーセントリック設計とは、利用者を中心に据え、実際の利用状況や心理的負担を考慮して設計を行うアプローチです。これは単なる「見やすいデザイン」を意味するものではなく、以下のような効果をもたらします。
- 業務効率化:無駄な操作や画面遷移を減らすことで作業時間を短縮する
- 定着率向上:ユーザーが直感的に使えるため、利用習慣が根付きやすい
- 教育コスト削減:複雑なマニュアルを用意しなくても操作が理解できる
- クレームやサポート対応減少:わかりやすい設計により、問い合わせの発生が抑制される
結果として、開発後の不満や修正依頼を減らし、システムの安定稼働とコスト削減につながります。
プロトタイピングで可視化と合意形成
ユーザーセントリックを実践する具体的な手段として、プロトタイピングがあります。画面遷移や操作フローを試作段階で可視化し、ユーザーに実際に触れてもらうことで「イメージと違う」「操作がわかりにくい」といった認識のズレを早期に発見できます。
例えば、入力フォームの設計において、利用者が業務上どの項目を頻繁に扱うのかを試作段階で確認できれば、最小限の項目に絞り込み、ストレスのない画面構成に調整できます。こうした段階的な確認は、仕様書だけでは不十分な部分を補完し、後の大きな修正を防ぐ強力な手段となります。
フルスクラッチ開発の柔軟性と適応力
既存パッケージやSaaSは、スピード導入や標準機能の活用には向いていますが、ユーザーセントリックな視点から見れば限界があります。あらかじめ決められた画面構成やフローを利用者が強いられることで、「自社の業務に合わない」という不満が生まれるのです。
一方、フルスクラッチ開発では、業務プロセスや顧客特性に即してゼロから設計できるため、ユーザー目線を徹底的に反映できます。入力導線や画面遷移、通知の仕組みに至るまで細かく調整でき、まさに「利用者が自然に使えるシステム」を実現可能です。この柔軟性が、利用者の満足度を高めると同時に、手戻りリスクを抑える強みとなります。
コスト削減と価値創出を両立するアプローチ
ユーザーセントリックな設計は単なるコスト削減手段ではありません。開発後の修正を減らすことで開発費用や運用コストを下げる一方で、ユーザーに誠実な体験を提供することで企業の信頼を高め、長期的な価値を創出します。
「コスト削減」と「顧客体験の向上」は一見相反するように見えますが、ユーザーセントリックなUI/UX設計は両立可能であり、持続的なDX推進の基盤となるのです。
まとめ
システム開発における最大のコストは「完成後の修正」によって発生します。その原因の多くは、初期段階でユーザーの声を十分に取り入れられなかったことにあります。ユーザーセントリックな設計は、この手戻りを防ぐ最良の方法です。プロトタイピングを通じた合意形成やフルスクラッチ開発の柔軟性を活用することで、利用者に寄り添ったシステムを実現でき、結果として大幅なコスト削減と企業成長の両立が可能になります。誠実で使いやすいシステムこそが、真のDX成功の鍵といえるでしょう。
フレシット株式会社では、ユーザーセントリックな設計思想を起点に、業務フローや利用者の特性を丁寧に反映したフルスクラッチ開発を行っています。既存の枠に依存しないオーダーメイドの設計だからこそ、手戻りを防ぎながら使いやすさと効率を両立するシステムを実現できます。利用者目線を重視したDXを推進したい企業さまにとって、フレシットは確かな選択肢となります。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

