セールスフォースの導入から学ぶ──なぜ多くの企業がつまずくのか
フルスクラッチ開発による現実的な解決策
2025-09-13
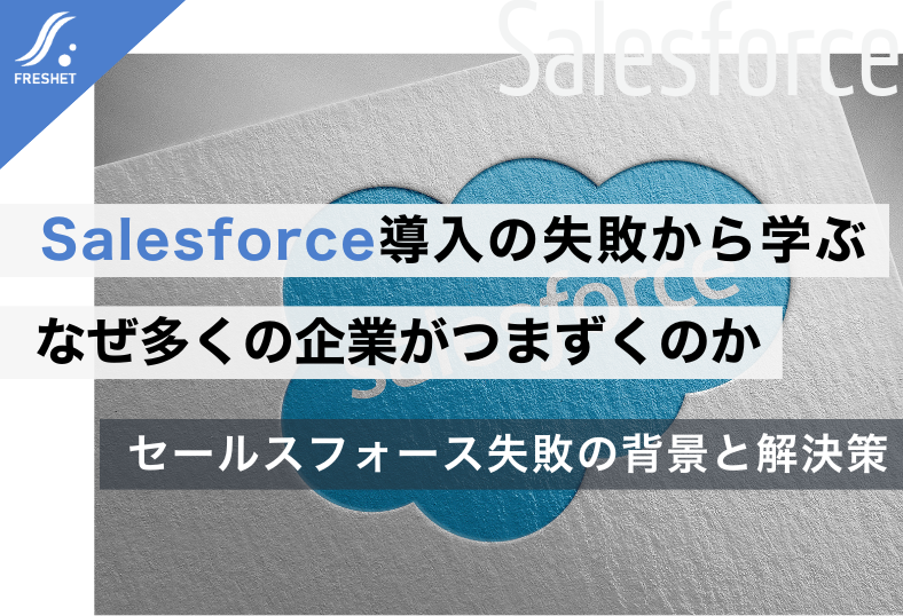
顧客管理や営業支援の定番として広く導入されているセールスフォース。世界的に評価の高いプラットフォームですが、日本企業においては「導入したものの使いこなせない」「思った以上にコストがかかり、結局現場では利用されていない」といった話も少なくありません。
導入がうまくいかない背景には、ツールそのものの特性だけでなく、企業側のリテラシーや運用体制の問題が複雑に絡んでいます。今回は、ある事業会社の代表取締役・Kさまに、当社代表の増田がインタビューを行い、セールスフォース導入で直面した課題やうまくいかなかった要因、そしてフルスクラッチ開発による現実的な解決策について深掘りしました。
>>Salesforceの導入が失敗する理由とその対策について詳細はこちら
目次
セールスフォースとは何か──多機能ゆえの強みと課題
セールスフォースは世界的に利用されるクラウド型のCRM(顧客関係管理)システムで、営業支援からマーケティング、顧客サポートまで幅広い機能を提供します。拡張性やカスタマイズ性に優れており、大企業では基幹システムとして活用される事例も多い一方、多機能ゆえにUIが複雑で直感的に操作しにくいという課題もあります。運用にはデータベースの理解や専門知識が求められ、導入後に思った成果を得られない企業も少なくありません。
ポイントをひとことで
セールスフォースは高機能で拡張性に優れたツールですが、一般の社員が使いこなすには高度なITリテラシーや管理体制が必要であり、結果的に導入後に思った成果を得られないと感じる企業も少なくありません。UIの複雑さやオーバースペック問題は、コストと運用負担を増大させる要因です。重要なのは、自社に本当に必要な機能を見極め、現場に即した仕組みを選択することです。フルスクラッチ開発は、その課題を解消し企業に最適な基盤を提供できる現実的な選択肢です。
加えて、導入における具体的な問題点としては、以下が挙げられます。
- 直感的でないUIと古い画面設計による操作性の低さ
- データベース構造への理解を前提とした高い学習コスト
- 作り込みすぎることで複雑化し、修正や運用に追加コストが発生する点
- 1ユーザーあたりの高額なライセンス費用によるランニングコストの負担
- 現場業務では性能を持て余すオーバースペック問題
UIの難しさ──直感的に使えない画面設計
増田:セールスフォースについて、一般の社員の方が使いにくいと感じる理由は何でしょうか。
Kさま:一番大きいのはUIです。画面が直感的でなく、古い印象があります。単純なCRMツールならすぐに操作できますが、多機能な分、ボタンやドリルダウンが多すぎて迷いやすい。現場の社員にとっては「どこを押せば良いのか分からない」状態になりがちです。
増田:なるほど。UIが古臭く直感的でないということですね。
Kさま:そうです。入力だけなら簡単ですが、レポート画面を作る、データを組み合わせて活用する、といった操作は難しい。社員のITリテラシーが低いと余計に使いこなせません。以前はアドミン資格を社員に取得させないと、まともに活用できないほどでした。
ITリテラシーが求められる現場
増田:自由度が高い分、データベースに関する理解が必要ということですね。
Kさま:その通りです。データベースの概念を理解していないと、うまく使いこなすことができません。kintoneのようなノーコードツールと違い、拡張性がある反面、知識がないと逆に扱いづらい。大企業なら専任の管理部隊を置けますが、中小企業では負担が大きいと思います。
【関連記事】
kintoneをやめた理由とその後の選択肢について解説
作り込みすぎると逆に複雑化する
増田:カスタマイズを進めるとどうなりますか。
Kさま:作り込めば作り込むほど画面が複雑になり、誰も触れなくなってしまうことがあります。直したいと思っても外部に依頼せざるを得ず、その度に費用が発生する。しかも1ユーザーあたりの単価が高いため、社員数が多い企業ではランニングコストが膨らみます。結果として「導入したけれどうまくいかなかった」と感じてしまう企業は少なくないと思います。
オーバースペック問題──フェラーリを乗りこなせない
増田:具体的にはどのような課題感でしょうか。
Kさま:私はよく「免許取り立てでフェラーリを買うようなもの」と例えています。セールスフォースは600馬力のエンジンを積んだ車のように高性能ですが、日常業務でそこまでの性能を必要とする場面はほとんどない。多くの社員にとっては60kmで走れれば十分なので、オーバースペックなんです。
増田:確かに、現場の社員が本業を抱えながら超高性能ツールを使いこなすのは現実的ではありませんね。
Kさま:そうなんです。結局外部に頼らざるを得なくなり、コストもさらに増える。セールスフォースは確かに優れたツールですが、誰もが使いやすいわけではありません。
フルスクラッチ開発の利点──自社に最適なサイズ感
増田:では、代替案としてはどのような方法が考えられますか。
Kさま:現場に必要な部分は既存の安価なSaaSを導入し、それらをAPIでつなげる。一方で、基幹となる管理システムはフルスクラッチで構築する。これが最も現実的で、費用対効果も高いと思います。例えば、名刺データのOCR入力やスマホアプリからの簡易入力は既存サービスに任せて、統合管理システムはオーダーメイドで作る。そういう分担が望ましいと考えています。
増田:つまり「現場は使いやすいツール」「統合はフルスクラッチ」というハイブリッド型の発想ですね。
Kさま:その方が社員にとっても負担が少なく、結果的にシステム全体が活きると思います。
ノーコード・AIの幻想と現実
増田:最近は「ローコードやAIで誰でもアプリが作れる」と言われますが、どう思われますか。
Kさま:データベースの概念が理解できていない人がシステムを作るのは難しいと思います。もしそれが理解できるなら、セールスフォースを最初から十分に使いこなせるはずです。だから結局、現場任せにするよりも、専門的に設計された自社専用の仕組みを構築する方が現実的です。
増田:まさにその通りですね。
まとめ──次につなげるシステム選び
セールスフォースは世界的に評価の高いプラットフォームであり、確かに大企業や専門部隊を持つ組織にとっては強力な武器となります。しかし、多くの中堅・中小企業にとっては「複雑すぎて使いこなせない」「コストばかりかかる」という事例が後を絶ちません。
重要なのは「自社にとって本当に必要な機能は何か」を見極め、それを最適な形でシステム化することです。全てを一つの巨大なツールに任せるのではなく、現場はシンプルなツールで、統合や基幹部分はフルスクラッチで作る。その柔軟な発想こそが、同じ過ちを繰り返さないための鍵になります。
フルスクラッチ開発は単なるシステム構築ではなく、企業ごとの業務特性や現場の運用実態を丁寧に反映させることができます。フレシット株式会社では、要件定義から設計、開発、運用に至るまで一貫して伴走し、既存のSaaSやパッケージの弱点を補いながら長期的に安心して活用できる基盤を提供します。セールスフォース導入で思うような成果が得られなかったご担当者さまも、当社のフルスクラッチ(オーダーメイド)開発によって、自社に本当に合ったシステムを構築する一歩を踏み出してみませんか。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

