運搬ロボットの挑戦から考える──競争から共創へ、強みをSaaSに変えて業界全体を支える仕組みづくり
自社の強みを再定義し、SaaSとして事業化する戦略
2025-09-21
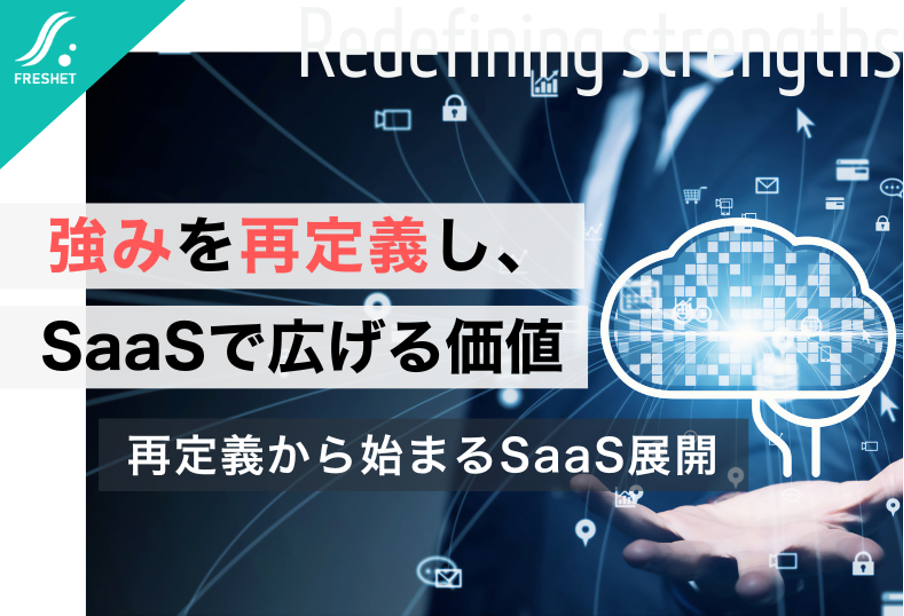
自社の強みを「社内に閉じた効率化」に使うだけでは、時代の変化に耐えることはできません。強みを抽象化して再定義し、新しい事業領域へと踏み出す企業が増えています。そして、その成果をSaaSとして業界全体に提供することは、単なる自社の利益を超え、持続可能な市場形成につながります。
本コラムでは、競争から共創へと発想を転換し、強みをSaaS化して事業モデルを変革する道筋を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】ソミック、車依存から脱却し不整地向け運搬ロボットに挑む
ソミックグループは自動車部品で培った足回り技術を活かし、悪路に強い四輪運搬ロボット「SUPPOT」を開発・販売しています。砂利道や段差をものともせず最大100キログラムを運搬可能で、工事現場や被災地、インフラ点検など幅広い用途を見込む製品です。背景には自動車業界の競争激化と下請け構造の限界があり、同社は「悪路でこそ我々の技術が生きる」と車依存からの脱却を図ります。国内外市場の拡大が期待され、持続可能な成長戦略の試金石となります。
出典:日本経済新聞「運搬ロボ、難路に挑む 砂利道や段差をものともせず ソミック、下請け技術結集」2025年9月3日付朝刊
ポイントをひとことで
自社の強みを抽象化し再定義してSaaS化する流れは、単なる効率化にとどまらず「事業そのものを刷新する」発想です。強みを囲い込むのではなく、業界全体に共有することで共創型の成長モデルを築けます。ただし、抽象化からSaaS事業化へのプロセスには、自社の独自性を損なわない柔軟な設計が不可欠です。システム開発会社と初期段階から協働し、経営戦略とシステム設計を結びつけることが成功の鍵となります。
自社の強みを抽象化するという戦略的思考
企業は必ずしも「新しい技術」を持っていなくても、長年の事業活動で培った知見や仕組みを強みとして保有しています。例えばソミックグループは、自動車部品に閉じた「ボールジョイント」という強みを「悪路での安定走行」という抽象的な価値に再定義し、工事現場向けの運搬ロボット事業へとつなげました。このように、強みを抽象化することで、既存業界の枠を超えた新しい市場を発見できるのです。
抽象化のプロセスはシンプルです。
- 自社の強みを「技術」「業務ノウハウ」「組織文化」といった要素に分解する
- 特定の用途から切り離し、抽象度を上げて再定義する
- 再定義した強みを、他業界や新市場に応用できる形に展開する
このプロセスこそ、既存市場が飽和する時代に成長を続けるための出発点となります。
SaaS化が生み出す新しい収益モデル
強みを事業化する際にSaaSが注目されるのは、「スケーラビリティ」と「標準化」を両立できるからです。社内向けに構築した仕組みをそのままでは外販できませんが、SaaSに変換することで多くの企業が利用可能な形になります。
例えば、社内の業務効率化ツールをSaaSとして公開すれば、同じ課題を抱える他社にも利用してもらえます。利用者が増えることでデータやフィードバックも蓄積され、サービス自体がさらに強化されるという循環が生まれます。これは一括導入型のシステムにはない特徴であり、継続的な利用料による収益モデルも確立できます。
さらに、SaaSは業界課題を共通基盤で解決するための手段となります。自社だけでなく業界全体が共通の仕組みを利用すれば、コスト削減や標準化が進み、市場の信頼性向上にもつながります。
競争から共創へ──業界全体を支える発想
従来の競争戦略では、強みは「自社だけの武器」として保持するものでした。しかし業界の変化スピードが加速する今、独占的に保持するだけでは成長が頭打ちになります。むしろ、強みを共創の基盤として開放することが、中長期的な競争力を高める鍵となります。
SaaSとして提供することで、他社は課題解決の恩恵を受け、自社はサービス改善や拡張によって新たな収益機会を得ます。業界全体の効率化や競争力強化に寄与することで、自社のSaaSは“業界標準”としての地位を築く可能性もあります。つまり、競争に勝ち残る発想から、共創で市場全体を成長させる発想への転換が求められているのです。
システム開発会社との協働が成功の鍵
自社の強みをSaaSに落とし込むには、汎用的なSaaSパッケージでは対応できない要件が数多く出てきます。ここで重要になるのが、システム開発会社との協働です。
特にフルスクラッチ開発は、事業の再定義とSaaS化の橋渡しに有効です。既存の業務フローや強みをシステムに正確に反映させ、さらに将来的な拡張性も考慮した設計が可能だからです。要件定義段階から経営戦略とシステム設計を結びつけることで、「単なるツール開発」ではなく「事業を支える基盤づくり」が実現します。
新事業をSaaSで育てるという未来像
SaaS事業化は単なる技術論ではなく、企業の未来像を描く手段でもあります。自社の強みを抽象化し、新たな市場に投入することで、競合と戦うのではなく、業界全体の持続可能性を高める方向へ進めます。
自社のSaaSが「業界の共通基盤」となれば、その企業は新しいエコシステムの中心に立つことができます。
まとめ
自社に閉じた強みを抽象化して再定義し、それをSaaSとして事業化することは、競争から共創への大きな転換を意味します。自社だけでなく業界全体を支える仕組みを提供することで、新しい収益モデルと持続可能な市場を同時に実現できます。いま必要なのは、強みを囲い込むのではなく、業界と共に育てる発想です。
自社の強みを抽象化し、再定義してSaaSとして事業化するには、柔軟かつ将来を見据えたシステム設計が欠かせません。フレシット株式会社は、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発を通じて企業ごとの独自性を最大限に反映し、業界全体を支える基盤づくりを後押ししてきました。既存のパッケージやSaaSでは対応できない要件にも応え、事業戦略に直結するシステムをゼロから設計できるのが私たちの強みです。新たな価値を生み出すSaaS事業への挑戦をお考えの際は、ぜひフレシットにご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

