自社の強みをアルゴリズムに落とし込む──フルスクラッチでしか実現できない差別化戦略
アルゴリズムを資産化し、持続的成長を支える
2025-09-26
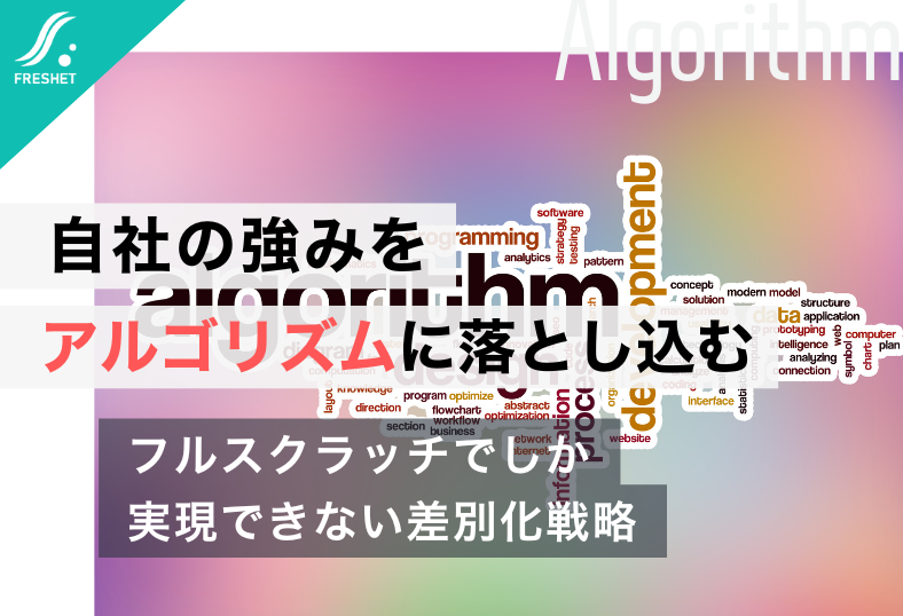
企業の競争力を左右する要素のひとつに「独自アルゴリズム」の存在があります。需要予測や商品改良、顧客行動の分析など、データを起点とした意思決定はビジネスの現場で欠かせないものとなりました。しかし、既存のパッケージソフトや汎用的なSaaSでは、自社の強みを十分に活かしきれないケースも少なくありません。そこで注目されるのが、フルスクラッチで構築する独自アルゴリズムです。
本コラムでは、なぜ独自アルゴリズムが重要なのか、どのように構築すべきか、そして実際の活用事例と今後の展望について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】ユニクロ、データ活用で需要を的確予測し在庫最適化
ファーストリテイリングは23年に「経営コックピット」を導入し、商品レビューや顧客の声3000万件超を収集。販売動向や在庫をリアルタイムで把握し、独自アルゴリズムで需要を予測、工場の生産計画と連動させた。結果として必要な商品を迅速に供給し、販売までの期間を短縮。売れ残りを防ぎつつ商品改良や新素材開発にも反映し、国内ユニクロの売上高はアパレル業界で初めて1兆円を突破した。
出典:日本経済新聞「ユニクロ売上高、国内1兆円超え 前期アパレル企業で初 データ使い需給的確予測」2025年9月14日付朝刊
ポイントをひとことで
独自アルゴリズムは単なる技術要素ではなく、自社の強みを市場優位に変換するための戦略資産です。汎用パッケージでは差別化が難しい中、フルスクラッチ開発は強みを忠実にシステムへ落とし込み、他社に真似できない仕組みを構築できます。ただし成功には、経営戦略とアルゴリズム設計を結びつける視点が欠かせません。システム開発会社と初期から連携し、改善を前提にした仕組みづくりを進めることで、持続的な競争力を維持できます。
独自アルゴリズムが企業競争力を左右する理由
近年、AIやデータサイエンスの進化により、膨大なデータから未来を予測したり、効率的な意思決定を行うことが可能になりました。たとえば小売業であれば「次の季節にどの商品が売れるか」、製造業であれば「どの部品が故障しやすいか」を予測することが経営上の重要な要素になります。
こうした意思決定の核となるのがアルゴリズムです。アルゴリズムは「データをどう扱い、どのようなロジックで結論を導くか」を規定します。つまりアルゴリズムそのものが「企業の頭脳」といえる存在です。もし競合が同じアルゴリズムや汎用サービスを利用しているのであれば、結論や施策は似通ってしまい、差別化は困難になります。逆に自社の業務フローや市場特性に最適化された独自アルゴリズムを持てば、競合に先駆けた意思決定が可能となり、結果として競争力につながります。
パッケージソフトの限界と“差別化できない現実”
多くの企業が導入しているパッケージソフトや汎用的なSaaSは、確かに導入の手軽さやコスト面でメリットがあります。しかし、標準化された機能は「誰でも同じように使える」ことを前提としているため、差別化という観点では不利になります。
例えば、需要予測を行う汎用サービスでは「過去の販売データと季節性」を基準にしたモデルが一般的です。ところが、ある企業にとっては「地域特性」や「天候」「イベント要因」など、より複雑な要素が売上を左右しているかもしれません。標準機能ではそれらを考慮できず、結果として予測の精度が低下し、現場で活用されなくなるケースも多いのです。
つまり、パッケージソフトは一定の業務改善には役立ちますが、「自社の強みを活かした仕組み」にはなりにくいという限界があります。
フルスクラッチだからこそ実現できる独自アルゴリズム
フルスクラッチ開発は、ゼロからシステムを設計するため、自社の強みやノウハウをアルゴリズムに直接落とし込むことが可能です。これはパッケージにはない最大のメリットです。
例えば、小売業における需要予測システムを考えてみましょう。一般的なアルゴリズムでは過去の売上データが中心になりますが、フルスクラッチであれば「特定地域の購買習慣」「SNSでの話題量」「競合店舗のキャンペーン情報」などを独自のデータとして組み込むことができます。その結果、他社には真似できない予測モデルが完成し、在庫の最適化や販売機会の最大化につながります。
同様に、製造業であれば「機械の稼働データ」「現場作業員の経験則」「メンテナンス履歴」を組み合わせたアルゴリズムを構築することで、故障予兆を高い精度で捉えることが可能になります。
自社の強みを抽象化してアルゴリズムに落とし込む
独自アルゴリズムを設計する上で重要なのは「自社の強みを抽象化する」というプロセスです。強みは必ずしも目に見える技術だけではありません。長年の経験で培ったノウハウや、特定業界に特化した業務プロセス、顧客との関係性なども強みに含まれます。
例えば、食品メーカーであれば「賞味期限が短い商品の供給管理」に関する知見は強みです。これをアルゴリズム化すれば、他の業界では再現できない独自の在庫管理システムが生まれます。重要なのは、属人的に散らばっている知識を「データ化」し、アルゴリズムという形で再現可能にすることです。これにより、組織全体で強みを共有し、持続可能な競争力に変えることができます。
【関連記事】
在庫管理システム開発 完全ガイド|開発費用や成功のポイントなどを解説
業界ごとの活用シーン業
・小売業
小売業では「需要予測」が最大のテーマです。フルスクラッチで開発したアルゴリズムは、地域特性やトレンドを即座に反映し、在庫の過不足を防ぎます。結果として、廃棄ロスの削減と販売機会の最大化が実現します。
・製造業
製造業では「予兆保全」が注目されています。独自アルゴリズムにより、機械の稼働データや振動・温度の変化から故障リスクを早期に検知し、計画的なメンテナンスを可能にします。突発的なライン停止を防ぎ、生産効率を高めることができます。
・サービス業
サービス業では「顧客体験の最適化」に活用できます。例えば、顧客の行動ログやアンケート結果をアルゴリズムに組み込み、個々の顧客に合わせたレコメンドやサービス改善を実現します。既存のCRMツールでは拾いきれない独自要素を反映できるのがフルスクラッチの強みです。
システム開発会社との協働で実現する仕組みづくり
独自アルゴリズムをフルスクラッチで構築するには、システム開発会社との協働が欠かせません。重要なのは「システムを作ること」ではなく「事業の強みを仕組みに変えること」です。要件定義の段階で経営戦略や業務の特性を丁寧に整理し、それをアルゴリズムとして設計・実装することが成功の鍵となります。
システム開発会社は単なる技術提供者ではなく、事業戦略を共に考えるパートナーとしての役割を担います。開発の現場では、アルゴリズムを継続的に改善するためのPDCAサイクルをどう仕組みに組み込むかも重要になります。
今後の展望──独自アルゴリズムが業界標準になる可能性
独自アルゴリズムは当初「自社の差別化要素」として設計されますが、その精度や有用性が高まると、やがて「業界標準」として広がる可能性もあります。SaaSとして展開すれば、業界全体の効率化を支える共通基盤となり、同時に新しい収益モデルの柱となります。
このように、独自アルゴリズムは単なる社内効率化のツールではなく、事業そのものを成長させる戦略資産として位置づけることができます。
まとめ
需要予測や商品改良を支える独自アルゴリズムは、企業にとって競争力の源泉です。パッケージソフトや汎用SaaSでは実現できない独自性を、フルスクラッチで開発することで形にできます。そのためには、自社の強みを抽象化し、アルゴリズムに落とし込み、システム開発会社と協働して仕組み化することが欠かせません。独自アルゴリズムを持つ企業は、競争から一歩抜け出し、持続可能な成長へと向かうことができるのです。
独自アルゴリズムを競争力の源泉として活かすためには、柔軟で拡張性のあるシステム設計が不可欠です。フレシット株式会社はフルスクラッチ(オーダーメイド)開発を強みとし、企業ごとの業務特性や強みを忠実にシステムへ反映させることで、他社にはない差別化を実現してきました。既存のパッケージでは対応できない要件にも応え、戦略に直結するシステムをゼロから設計できることが私たちの価値です。競争優位を築く独自の仕組みをお考えの際は、ぜひご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

