複雑化した業務システムをどう整理する?──トヨタの部品管理から学ぶ全体最適化の視点
複雑化した業務を整理するフルスクラッチ開発の強み
2025-09-24
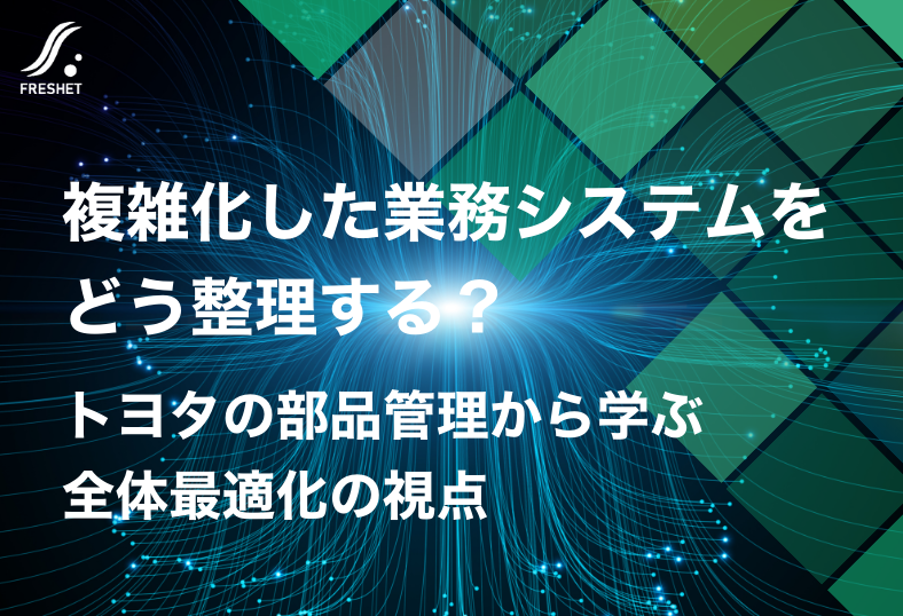
自動車1台にはおよそ3万点の部品が使われているといわれます。巨大なサプライチェーンを抱えるトヨタは、部品の重複や使われない在庫を「俯瞰」する仕組みを導入し、最大8割の削減に成功しました。この考え方は、自動車業界に限らず、複雑化した業務システムにもそのまま当てはまります。日々追加される機能やサービスは、知らぬ間に重複やムダを生み、全体像が見えなくなる原因となります。
本コラムでは、部品管理の発想をヒントに、フルスクラッチ開発で業務システムを最適化するアプローチを詳しく解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】トヨタ、俯瞰的な視点で部品の重複を排除し生産効率を向上
トヨタ自動車は「AREA35」と呼ぶ取り組みを通じ、部品の種類を最大8割削減し、工場内に平均35%の余剰スペースを創出した。従来は車種ごとに個別の改善を進めていたが、開発・生産・販売を一体で俯瞰することで、重複や不必要な部品が浮き彫りとなり、効率化や働きやすさ向上につながった。今後は国内外18工場に展開し、電動化や自動運転で競争軸が変化する中でも、持続的なカイゼンで競争力維持を目指す。
出典:日本経済新聞「トヨタ、部品を最大8割減世界18工場で『カイゼン』 重複回避、種類絞り込み」2025年9月13日付朝刊
ポイントをひとことで
企業の業務システムは成長とともに複雑化し、機能の重複やデータの散在が避けられません。本コラムは自動車の部品管理を例に、俯瞰して全体を把握する視点の重要性を説いています。現場単位では正しい判断であっても、全体最適を阻害する要因となることは多いものです。フルスクラッチ開発は、こうした問題を根本から整理し、自社固有の業務構造に即した最適化を実現できる有効な手段であると再認識させてくれます。
システムはなぜ複雑化するのか
企業の業務システムは、成長とともに規模と機能を拡大していきます。新しい部署が追加され、業務プロセスが細分化されるたびに新システムが導入される。さらに顧客ニーズに対応するための追加開発や、市販サービスの寄せ集めが繰り返されます。その結果、全体像を把握できないほど複雑化し、類似機能や重複データが蓄積していきます。これは、自動車の生産現場で仕様がほぼ同じ部品が乱立し、在庫スペースを圧迫していた状況とよく似ています。
部品管理の発想をシステムへ応用する
トヨタが行った「部品の俯瞰管理」は、全体像を整理し、不要な部品や低稼働の部材を削減するものでした。業務システムも同じです。例えば、顧客情報を管理する仕組みが部門ごとに分かれていると、同じ顧客が複数のデータベースに存在し、更新の不一致や重複登録が生じます。また、承認フローや帳票出力機能なども、部門単位で作られた仕組みが乱立するケースがあります。部品管理と同様に「似て非なるもの」を見つけ、統合・整理する視点が欠かせません。
フルスクラッチ開発だからこそできる全体設計
既存のパッケージソフトやクラウドサービスは便利ですが、基本的には部分最適を目的に設計されています。そのため「全体を俯瞰して整理する」ことは得意ではありません。フルスクラッチ開発なら、企業固有の業務フローやデータ構造を反映させながら、最初から全体最適を意識したシステムを設計できます。複数部門の業務を統合する仕組みや、重複する機能を横断的に管理する仕組みを組み込むことで、システム全体を軽量化し、長期的に運用コストを抑えることが可能になります。
重複とムダを削減するための機能例
全体を俯瞰できるシステムを構築するには、具体的な機能が必要です。例えば以下のような仕組みが挙げられます。
- 業務フローマッピング機能:各部門の業務を横断的に可視化し、重複プロセスを特定。
- データ統合・重複検知機能:顧客や商品データを一元管理し、類似データを自動的に抽出。
- 利用頻度分析機能:使用されていない機能や低稼働のサービスを特定。
- 部門横断ダッシュボード:経営層が全体像を俯瞰し、戦略的に意思決定できる仕組み。
これらの機能は単なる利便性ではなく、組織の「ムダを削減するための基盤」として大きな役割を果たします。
全体最適がもたらす効果
フルスクラッチ開発による全体最適化には、具体的な効果があります。
- 在庫削減:不要なデータや機能を排除し、管理コストを削減
- 業務効率向上:重複するプロセスを整理し、従業員の負担を軽減
- 意思決定の迅速化:経営層が全体像を俯瞰することで、判断のスピードと精度が向上
- 長期的な競争力強化:無駄を省いたシステムは、拡張性やメンテナンス性に優れ、変化する市場に柔軟に対応可能
これはトヨタが工場のスペースを確保し、生産性を向上させたのと同じ構造です。システムにおいても、無駄を削減した分だけ新たな価値創出の余地が広がります。
部門横断で取り組む重要性
システム最適化は、情報システム部門だけの課題ではありません。販売、生産、開発、経理など、全社的な視点が求められます。部門ごとに個別の判断で進めると、結局また部分最適に陥ってしまいます。フルスクラッチ開発を行うシステム開発会社は、複数部門からの要件を整理し、全体像を俯瞰した上で設計を行うため、各部門のバランスを保ちながらシステムを構築できます。
システムの「資産化」を意識する
システムを単なる道具ではなく「資産」として捉えることも重要です。部品管理の改善が工場スペースの有効活用や従業員の働きやすさに直結したように、システムの最適化も企業全体のパフォーマンスを底上げします。特にフルスクラッチ開発は、自社固有のノウハウや業務フローをシステムに落とし込むことができ、長期的に企業価値を高める資産となります。
まとめ
自動車の部品管理と同じように、企業の業務システムも複雑化すればするほど重複やムダが生まれます。現場単位では気づけない非効率を浮き彫りにするには、全体を俯瞰できる仕組みが欠かせません。フルスクラッチ開発は、この俯瞰視点を最初から組み込み、重複を整理し、全体最適を実現できる手段です。システムを資産としてとらえ、無駄を削減して新しい価値を創出する姿勢こそが、これからの企業に求められるアプローチといえるでしょう。
業務システムを部品管理の発想で整理するには、全体像を俯瞰できる仕組みと、自社固有の業務に即した設計が不可欠です。フレシット株式会社は、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発を通じて、企業ごとに異なる複雑な業務構造を丁寧に整理し、重複やムダを排除したシステムを構築します。部分最適では見えない非効率を浮き彫りにし、全体最適を前提としたシステムを資産として残すことができるのが私たちの強みです。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

