複雑化する業務データをどう扱うか──点ではなく面で管理するフルスクラッチシステムの価値
ムダと重複を消すのは“全体を見渡す仕組み
2025-09-28
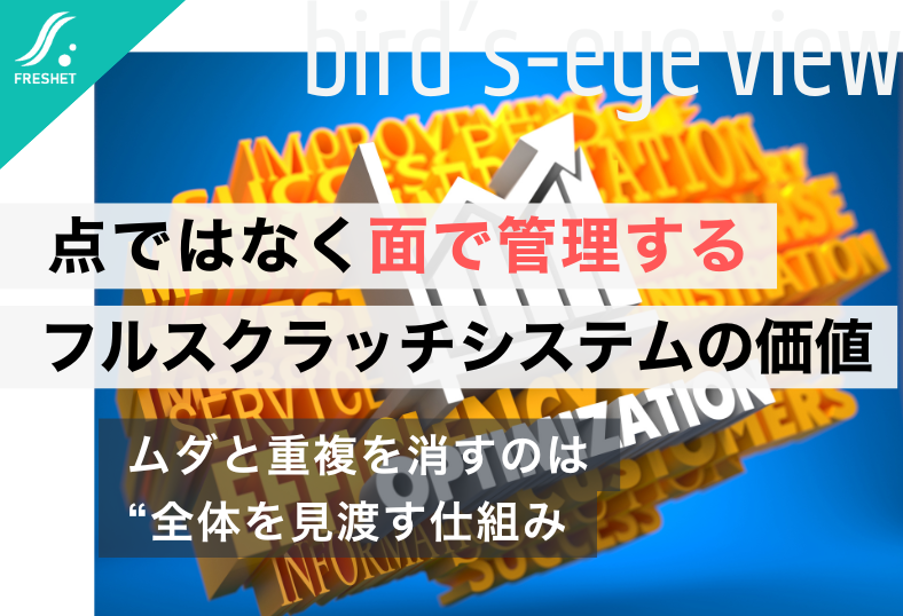
企業活動は多様化し、日々生み出されるデータ量は膨大です。営業部門はExcelで顧客リストを管理し、経理部門は会計SaaSを利用し、マーケティング部門はクラウドの分析ツールを駆使する──このように部門ごとにシステムや管理方法がバラバラになっている企業は少なくありません。しかし部分的に最適化された“点”の管理では、全社的な意思決定に必要な全体像を把握することは難しくなります。
本コラムでは、経営から現場までを横断的に俯瞰できる基盤の重要性と、フルスクラッチ開発がもたらす価値について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】トヨタ、俯瞰的な視点で部品の重複を排除し生産効率を向上
トヨタ自動車は「AREA35」と呼ぶ取り組みを通じ、部品の種類を最大8割削減し、工場内に平均35%の余剰スペースを創出した。従来は車種ごとに個別の改善を進めていたが、開発・生産・販売を一体で俯瞰することで、重複や不必要な部品が浮き彫りとなり、効率化や働きやすさ向上につながった。今後は国内外18工場に展開し、電動化や自動運転で競争軸が変化する中でも、持続的なカイゼンで競争力維持を目指す。
出典:日本経済新聞「トヨタ、部品を最大8割減世界18工場で『カイゼン』 重複回避、種類絞り込み」2025年9月13日付朝刊
ポイントをひとことで
業務システムが部門ごとに最適化されると、情報は点在し、全体像を把握することが難しくなります。本コラムは、Excelや既存SaaSによる部分最適ではなく、全体を俯瞰する基盤を整える重要性を示しています。点ではなく面で管理する仕組みを持つことで、データが有機的につながり、経営判断の精度が高まります。フルスクラッチ開発は、自社固有の業務構造を前提に全体最適を意識した設計が可能であり、長期的な資産価値を生む点で有効です。
部分最適の限界とそのリスク
企業が成長する過程で、多くの部門は自部門の課題解決に適したツールを導入します。Excelは柔軟で低コスト、SaaSはスピーディに導入できるといった利点があります。
しかし、その結果として情報が点在し、重複や齟齬が発生しやすくなります。営業が持つ顧客情報とマーケティングが扱うリード情報が一致しない、在庫データが販売計画と連動していない、会計情報と実際の取引情報に差異がある──こうした状況は現場に混乱を招くだけでなく、経営層が全体の状況を正しく把握できない大きなリスクとなります。
点での管理から面での管理へ
部分最適のツールは“点”での管理に強みがあります。しかし経営が必要とするのは、個別の点ではなく、それらをつなぎ合わせた“面”の情報です。例えば、顧客データ、在庫データ、売上データ、コストデータが一元的に紐づいていれば、商品ごとの収益性や在庫回転率を瞬時に把握でき、的確な投資判断が可能になります。点ではなく面で管理することは、現場の業務効率化だけでなく、経営戦略そのものに直結するのです。
既存SaaSとExcelが抱える課題
ExcelやSaaSは、単体での管理には有効ですが、横断的なデータ活用には限界があります。Excelは属人化しやすく、更新ミスやバージョンの乱立を招きます。SaaSは提供範囲がサービスごとに限定され、他システムとの連携に制約が生じがちです。
さらに、複数SaaSを組み合わせた場合、仕様変更やAPI制限が起きると連携が崩れるリスクもあります。結果的に「情報の壁」が生まれ、部門をまたいだ全体最適化は難しくなります。
【関連記事】
Excel管理に限界を感じていませんか?脱Excelの方法を解説します。
フルスクラッチ開発で実現する横断的な俯瞰
フルスクラッチ開発は、こうした点在する情報を統合し、横断的に俯瞰できる仕組みをゼロから構築できます。業務フローに沿ったデータ構造を設計し、部門ごとの業務を一つの基盤でつなげることが可能です。例えば営業活動から受注、在庫引き当て、出荷、請求、入金までを一気通貫で管理すれば、ボトルネックがどこにあるのかをリアルタイムで把握できます。これは部分最適の仕組みでは決して実現できない強みです。
全体を俯瞰するための具体機能
全社的な俯瞰を可能にするためには、以下のような機能が重要になります。
- 統合データベース:部門ごとに分散するデータを一元管理。
- 重複検知機能:類似データや不整合を自動的に抽出し、データ品質を担保。
- リアルタイムダッシュボード:経営層が全体のKPIを瞬時に把握できる可視化機能。
- 横断的なワークフロー設計:部門をまたぐ業務プロセスを統合し、連携ミスを防止。
- シナリオシミュレーション:在庫削減やサービス統合など、経営判断の影響を事前に試算。
これらの機能が「点ではなく面で管理する」仕組みを支えます。
部門横断で進める全体最適化
システムの全体最適化を進める上で欠かせないのは、部門横断の視点です。販売部門は顧客の声を重視し、生産部門は効率を優先し、経理部門は数値精度を求める──それぞれ正しい判断であっても、部門最適にとどまれば全体最適から外れてしまいます。フルスクラッチ開発を担うシステム開発会社は、各部門の要件を整理し、全社的に調和した仕組みを設計できる点で大きな価値があります。
フルスクラッチシステムの資産価値
部分的に導入されたシステムは、数年後には仕様変更や連携崩壊に直面するリスクがあります。対して、フルスクラッチで設計された基盤は、自社の業務構造に合わせて拡張性を持たせられるため、長期的に資産となります。経営が変化するたびにその都度刷新するのではなく、全体を俯瞰した基盤を育てることが、持続的な成長を支える道筋です。
まとめ
Excelや既存SaaSに依存した部分最適の管理では、全社的な視点での意思決定に必要な情報は得られません。重要なのは、点ではなく面で管理する仕組みを持ち、全体を俯瞰できる基盤を整えることです。フルスクラッチ開発は、自社固有の業務構造を反映した全体最適のシステムを構築し、複雑化する業務を整理する力を持っています。部分最適から脱却し、全体最適を前提としたシステムを資産として育てていくことこそ、これからの企業に求められる取り組みといえるでしょう。
点ではなく面で管理する仕組みを構築するには、既存のツールを組み合わせるだけでは限界があります。フレシット株式会社は、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発を通じて、部門横断で業務やデータを統合し、経営から現場まで一貫して俯瞰できる基盤を設計します。部分最適にとどまらず全体最適を実現するシステムを資産として育てたいとお考えの企業さまにこそ、私たちの強みが生きます。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

