数字の裏に隠れた“兆し”を見逃さない仕組みづくり
目に見えないサインを可視化する──データが語る危険信号を捉える
2025-10-02
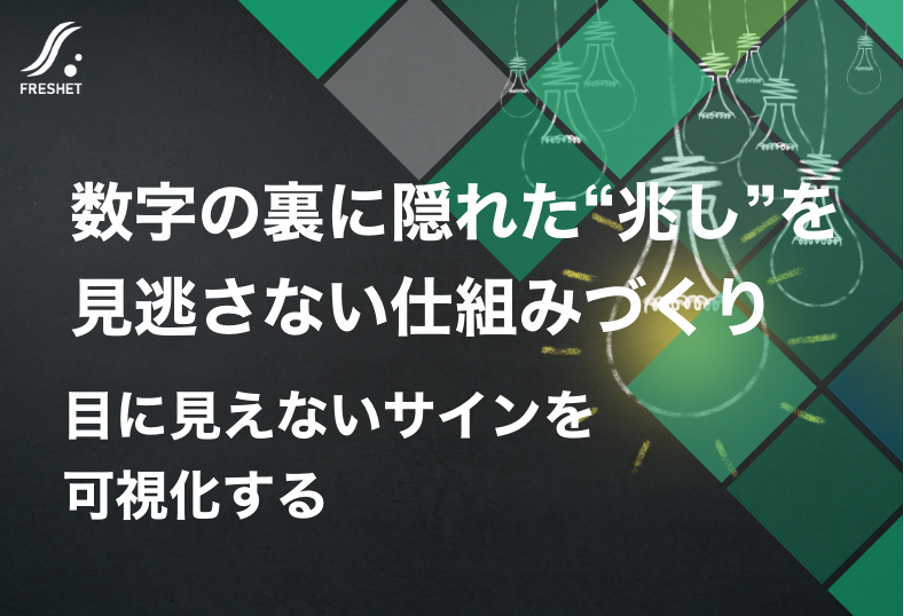
近年、財務データや業務データの異常値をシステムで自動的に検出し、リスクを早期に把握する取り組みが進んでいます。証券取引等監視委員会が不正会計の疑いを抽出するシステムを導入したことは象徴的な例です。この仕組みは財務情報の特徴的な動きを検出し、過去の不正事例をもとにリスクの高い企業を抽出します。こうした異常検知の仕組みは、売上、在庫、顧客行動ログなど、企業が保有するあらゆるデータにも応用できます。
本コラムでは、数字の裏に潜む“兆し”を見逃さないための異常値検出の考え方と仕組みづくりについて解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】証券監視委、不正会計を分析システムで早期検知へ
証券取引等監視委員会は、不正会計の疑いがある企業を自動抽出する新システムを導入した。過去の課徴金勧告事例を基に、有価証券報告書の財務情報を解析し、急激な数値変動や「継続企業の前提に関する注記」の有無を検知。不正リスクの高い企業を一覧化する。従来は職員が目視で選定していたが、今後はシステムで効率化し、違反の早期発見と迅速処分を目指す。最終判断は人が行うが、精度向上を図りつつ改善を重ねる方針である。
出典:日本経済新聞「不正会計の企業、システムで検知監視委導入、過去事例からリスク分析 早期発見・迅速な処分狙う」2025年9月25日付朝刊
ポイントをひとことで
異常値検出の仕組みは、単に不正やエラーを見つけるだけでなく、企業が持つ膨大なデータの中から「未来のリスクや機会」を示すサインを拾い上げる役割を持ちます。重要なのは、システムを万能と捉えず、人の判断と組み合わせて活用することです。システムは膨大な情報を効率的に整理し、特徴的な動きを浮き彫りにしますが、それをどう意味づけ、どのような意思決定につなげるかは人に委ねられます。両者を補完的に組み合わせることが、健全な経営の前提になります。
データに潜むリスクをいかに捉えるか
企業が日々扱うデータは膨大です。売上の推移、在庫の回転率、顧客の購買履歴やアクセスログなど、業務活動を支える数字は多岐にわたります。こうしたデータの中には、一見すると小さな変化に見えても、将来的に大きなリスクや不正の芽につながる“兆し”が隠れていることがあります。
従来は人の経験や勘に頼って異常を察知していましたが、データ量の増加に伴い、人の目だけで把握するのは困難です。ここで必要となるのが、システムによる異常値の自動検出です。機械的にパターンを分析し、通常とは異なる動きをいち早く示すことによって、担当者が迅速に対応できる環境を整えられます。
財務データに見る異常値検出の具体例
財務データは異常値検出の代表的な対象です。例えば、純資産や収益の急激な増減、売上と利益の乖離、短期間での業績の急回復などは、通常の業務活動では説明が難しいケースが多く見られます。
証券取引等監視委員会が導入した新システムは、有価証券報告書の数十項目を分析し、過去に不正が指摘された事案から共通するパターンを学習しています。これにより、表面的な数値の増減だけでなく、異常な動きを示す傾向を精度高く検出できる仕組みが構築されています。
企業においても同様の考え方を応用すれば、早期に異常な傾向を発見し、会計上のリスクや内部統制上の課題を明確化することが可能になります。
売上データに潜むシグナル
売上データもまた異常検知に適した領域です。例えば、特定地域や特定商品だけが突発的に売上増を示した場合、それが自然な需要の変化によるものなのか、不正や誤入力によるものなのかを見極める必要があります。
また、売上の増減が顧客の購買傾向や市場動向と合致しない場合も注意が必要です。異常値検出の仕組みを導入すれば、日次や週次単位での売上推移を自動的にチェックし、過去のパターンから外れた変化を可視化できます。これにより、営業活動の精度向上や不正防止につなげられます。
在庫データの異常をどう捉えるか
在庫データの管理は、企業活動において非常に重要です。過剰在庫や欠品は収益に直結するため、異常の早期発見が求められます。
例えば、仕入量と販売量が不自然に乖離している場合や、特定の商品だけが異常に滞留している場合は、システムが自動的にアラートを発し、担当者が原因を調査できるようにすることが理想です。
また、過去の季節変動や販売キャンペーンのデータを学習させることで、本来予測される変動と実際の在庫推移を比較し、異常を検出する仕組みも構築できます。
顧客行動ログに潜む“兆し”
顧客行動ログは、オンラインサービスやECサイトにとって重要なデータです。アクセスの急増や離脱率の急上昇といった異常は、システム障害や不正アクセス、あるいは顧客満足度の低下といったリスクを示す可能性があります。
異常検知の仕組みを導入することで、通常とは異なる行動パターンを素早く認識し、システム障害やセキュリティ上の脅威に早期対応できます。また、顧客の購買傾向や利用傾向の変化を把握することは、マーケティング戦略の改善にもつながります。
異常値検出を支える仕組み設計のポイント
異常値検出システムを導入するにあたり、重要なのは「どのデータを対象にするのか」「どのような特徴的な動きを異常と定義するのか」を明確にすることです。
単純に数値が一定範囲を超えたからといって異常と判断すると、誤検知や過剰なアラートが多発し、担当者が疲弊する恐れがあります。そのため、過去の実績や業務特性を反映したルール設計が不可欠です。
人とシステムの役割分担
システムが自動的に異常を検出する一方で、最終的な判断は人が行う必要があります。なぜなら、数字の背後には市場環境や顧客心理といった定量化しづらい要素が影響している場合があるからです。
システムが示す異常値はあくまで“兆し”に過ぎず、それをどう解釈し、どのような対応策を講じるかは人の判断が欠かせません。システムと人の役割分担を明確にすることで、効率と信頼性の両立を実現できます。
異常検知の応用領域
異常値検出の仕組みは財務や会計領域だけでなく、幅広い業務に応用できます。
例えば、製造業では機械の稼働データから異常振動や温度変化を検出し、故障を未然に防ぐ「予知保全」に活用できます。物流業では配送時間の遅延や輸送コストの急増を検知し、業務改善に活かせます。このように、異常値検出はリスク回避だけでなく、生産性の向上や顧客満足度の改善にも貢献します。
まとめ
異常値検出の仕組みは、膨大な業務データに潜むリスクや兆候を見逃さず、早期に対応を可能にする強力な手段です。財務データにおける不正会計の検知に限らず、売上や在庫、顧客行動ログなど、あらゆる業務領域で応用可能です。重要なのは、システムが自動的に異常を示し、人がそれを解釈して意思決定につなげるという役割分担を前提に仕組みを構築することです。
数字の裏に隠れた“兆し”をいち早くつかむことは、企業の健全な成長と持続的な競争力の確保に直結します。
数字の裏に潜む兆しを正しく捉えるには、単なるパッケージの導入ではなく、自社の業務特性やデータ構造に最適化された仕組みが不可欠です。フレシット株式会社はフルスクラッチ(オーダーメイド)開発を強みとし、財務データや売上、在庫、顧客ログなど多様な情報を横断的に扱えるシステムを一から設計します。既製の枠に縛られず、“人とシステムの役割分担”を前提にした柔軟な仕組みづくりを実現することで、企業ごとに異なる兆しを見逃さない体制を構築できます。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

