不正会計を防ぐ仕組みから考える──既存パッケージでは拾えない“自社特有のサイン”を捉える方法
自社固有のKPIを起点に、業務特性を反映した異常値検出の仕組みを構築する
2025-10-05
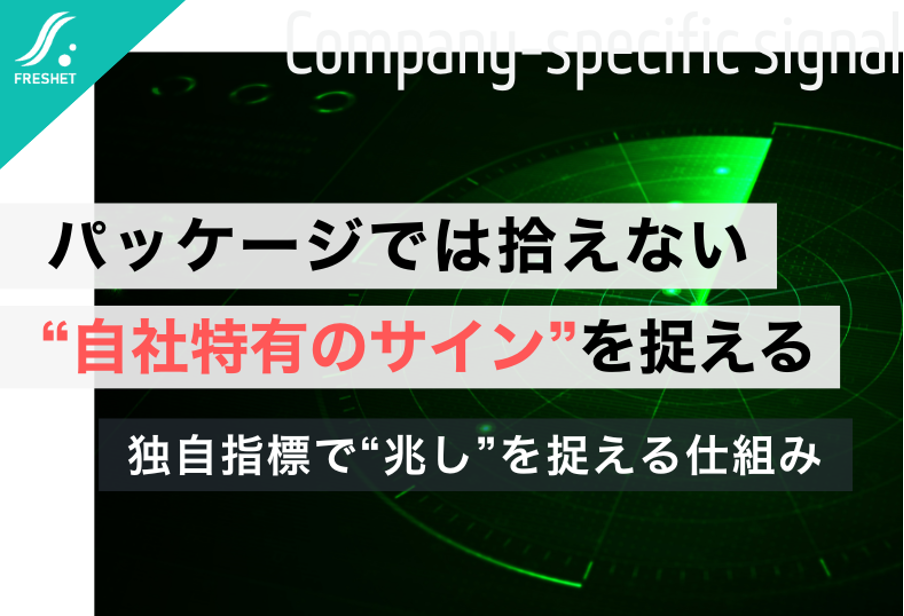
財務データの異常をシステムで検出する取り組みが進んでいますが、既存の市販ツールは一般的な指標に基づいた分析が中心です。しかし、企業の業務特性や自社固有のKPIに目を向けると、標準化された仕組みだけでは見落としてしまう“サイン”が数多く存在します。例えば、ある業界特有の取引慣習や季節変動、特定商品に依存する収益構造などは、一般的な異常検知アルゴリズムでは適切に扱えないことがあります。
本コラムでは、自社特有のサインを捉えるためのパターン分析の考え方と、フルスクラッチでシステムを構築する意義について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】証券監視委、不正会計を分析システムで早期検知へ
証券取引等監視委員会は、不正会計の疑いがある企業を自動抽出する新システムを導入した。過去の課徴金勧告事例を基に、有価証券報告書の財務情報を解析し、急激な数値変動や「継続企業の前提に関する注記」の有無を検知。不正リスクの高い企業を一覧化する。従来は職員が目視で選定していたが、今後はシステムで効率化し、違反の早期発見と迅速処分を目指す。最終判断は人が行うが、精度向上を図りつつ改善を重ねる方針である。
出典:日本経済新聞「不正会計の企業、システムで検知監視委導入、過去事例からリスク分析 早期発見・迅速な処分狙う」2025年9月25日付朝刊
ポイントをひとことで
既存のパッケージツールは幅広い企業に対応する汎用性が強みですが、その一方で自社特有のKPIや業務プロセスを十分に反映できないという限界があります。異常検知やパターン分析は、企業ごとに「正常」とされる基準が異なるため、標準的な指標だけでは本質的な兆候を捉えきれません。フルスクラッチ開発によって、自社のデータ特性に基づいた分析基盤を構築すれば、表面的な数値ではなく、真に重要なサインを浮き彫りにできる点に大きな価値があります。
既存パッケージの限界
市販されている業務システムや分析ツールは、多くの企業に利用されることを前提として設計されています。そのため、異常値検出やパフォーマンス分析も「平均的な企業」に合わせた汎用的な指標が中心です。
確かに基本的な傾向や一般的なリスクを把握するには有効ですが、個々の企業が抱える固有の課題やビジネスモデルに即した“兆し”は見逃されがちです。例えば、製造業では「特定ラインの停止頻度」や「原材料ロットごとの品質差」が重要ですが、既存パッケージにその視点は組み込まれていないケースも少なくありません。
自社特有のKPIを捉える重要性
企業ごとに事業環境や業務プロセスは異なります。売上高や利益率といった共通指標だけでなく、「問い合わせから受注までの平均リードタイム」や「在庫回転率の季節変動」といった自社ならではのKPIを把握することが、実際の経営改善に直結します。
特に、異常値検出の観点では、自社固有の指標における“通常の範囲”を定義できることが大きな強みになります。標準化された分析では異常と判定されない数値でも、自社にとっては危険信号である場合があるからです。
業務特性を反映したパターン分析
自社固有のサインを捉えるには、過去のデータに基づいて「自社にとっての正常なパターン」を定義することが不可欠です。
例えば、小売業であれば曜日や時間帯ごとの売上変動、ECサイトであればキャンペーン実施時のアクセス急増が“通常”として扱われる一方、それ以外の場面で同様の変化があれば“異常”とみなすことができます。
こうした業務特性を反映したパターン分析は、市販ツールには備わっていない柔軟性が求められます。フルスクラッチ開発であれば、業界特性や自社独自の業務プロセスに合わせた仕組みを設計できます。
データの解釈を支援する仕組み
異常値を検出するだけでは、業務改善にはつながりません。検出結果を「なぜ異常と判断したのか」「どの業務に影響を与えるのか」という文脈で解釈できる仕組みが必要です。
例えば、売上の急減少を検出した場合、その背景に「特定顧客の離脱」「システム障害」「在庫不足」といった要因があるかもしれません。これを人が判断しやすい形で提示することで、システムは単なるアラート機能に留まらず、意思決定を支える役割を果たせます。
フルスクラッチ開発では、この“解釈のしやすさ”を前提にUIやダッシュボードを設計することが可能です。
フルスクラッチ開発の意義
フルスクラッチでのシステム構築は、初期コストや開発期間が課題とされがちです。しかし、自社特有のサインを逃さず捉える仕組みを整えることで、中長期的には大きな価値を生み出します。
第一に、汎用的な仕組みに依存しないことで、業務に最適化された分析が可能になります。第二に、自社にしかないKPIを軸にした仕組みを構築することで、競合他社との差別化を図れます。第三に、将来的な業務変化に合わせて柔軟に改修できる拡張性を備えられる点も重要です。
「自社にしか現れない兆し」を見逃さない仕組みを持つことは、リスク管理と成長戦略の両面において大きな武器になります。
具体的な応用例
- 製造業:特定ラインごとの不良率、稼働停止時間、原材料のロット差
- 小売業:店舗ごとの販売傾向、仕入れと販売の乖離、季節変動パターン
- サービス業:顧客問い合わせ対応の遅延率、サービス利用ログの異常な集中
- IT業:システムアクセスログの異常増減、セキュリティリスクの早期兆候
これらの指標は、市販ツールで標準的にカバーされないことが多く、フルスクラッチでの分析基盤が有効に機能します。
人とシステムの役割分担
自社特有のサインをシステムが捉えても、それをどう解釈し、どのような行動につなげるかは最終的に人が判断します。重要なのは、システムと人の役割分担を前提に設計することです。システムは兆しを可視化し、人はその背景を理解して意思決定を行う。この補完関係を強化することで、システムは経営における強力な支援ツールになります。
まとめ
既存パッケージが提供する一般的な指標では、自社固有のKPIや業務特性に基づく“兆し”を捉えきれないケースが多く存在します。企業の成長やリスク管理においては、自社にしかないデータの動きを理解し、それを的確に検出する仕組みが不可欠です。
フルスクラッチ開発によるシステム構築は、コストや工数以上に、自社に最適化された分析環境と将来にわたる競争力をもたらします。数字の裏に隠れたサインを見逃さないために、既存ツールでは得られない柔軟で独自性のある仕組みづくりが求められます。
自社特有のサインを見逃さない仕組みを持つためには、既製ツールに依存するのではなく、自社のKPIや業務特性に合わせて柔軟に設計されたシステムが欠かせません。フレシット株式会社は、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発を通じて、企業ごとの固有のデータ構造や業務フローに最適化した仕組みをゼロから構築します。一般的なパッケージでは拾えない“兆し”を捉え、意思決定を支える独自のシステムを実現できることが、私たちの強みです。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

