大量データから価値を見極める──“抽出→精査”モデルを業務システムに応用する方法
抽出と精査を分離することで実現する、業務データの最適活用
2025-10-06
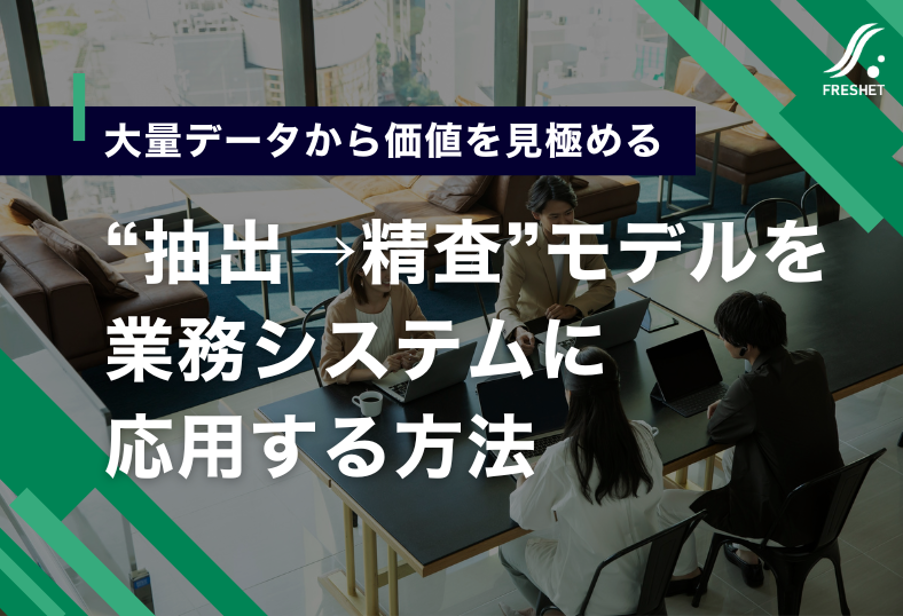
理系学生の採用支援サイトを活用し、人事部が抽出した候補リストを現場社員が精査する──そんなスカウト型採用の事例があります。ここで注目すべきは「候補者リストを一次抽出し、その後の現場による精査を経て適材適所につなげる」という構造です。この仕組みは、採用領域だけにとどまりません。営業リードの選別、仕入先の評価、顧客サポートの優先順位付けなど、幅広い業務プロセスに応用できる考え方です。
本コラムでは、“抽出→精査”という二段階の仕組みを軸に、業務データを活かすフィルタリングと評価フローの具体的な活用方法を考察します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
【関連記事】
システム開発は外注 or 内製?担当者が知るべきメリットやデメリット、外注先の選び方を解説
目次
【記事要約】オムロン、LabBase活用で現場社員が学生を精査しスカウト
理系人材の獲得競争が激化する中、オムロンはLabBaseのサービスを活用し、新卒採用で「待つだけ」から脱却。人事部がキーワード検索で抽出した学生リストを、開発や研究の現場社員が直接精査する仕組みを導入した。これにより、専門性の高い学生とのマッチングを実現し、相互理解を深めるカジュアル面談やインターンシップにつなげている。従来は出会いにくかったCAE分野の人材採用にも成功しており、ニッチ領域の人材確保に有効性が示された。
出典:日本経済新聞「〈就活・採用最前線〉理系新卒採用『第3の手法』オムロンやマツダ、脱『待つだけ』 現場社員がスカウト」2025年9月25日付朝刊
ポイントをひとことで
業務データの活用は「大量の情報をいかに整理し、価値のある対象を見極めるか」に尽きます。本コラムで示された“抽出→精査”の流れは、営業や調達、サポートといった多様な業務で再現性を持つ普遍的なモデルです。重要なのは、システムで一次抽出を自動化しつつ、最終判断は現場の知見に委ねるという役割分担です。属人的な判断を補い、透明性と効率を両立させる仕組みを整えることが、データドリブン経営を実現するための鍵となります。
【関連記事】
マッチングアプリの作り方とは?開発費用や外注時の注意点についても徹底解説!
候補リストを精査するという構造
人材採用におけるスカウト型アプローチでは、まず人事部がキーワード検索や条件設定によって候補者のリストを抽出します。その後、開発や研究の現場社員がリストを確認し、専門性や研究分野の適合性を基準にして精査を行います。この流れは、システム化されたフィルタリングと人間による判断を組み合わせたモデルといえます。
重要なのは「大量データを自動的に絞り込み、その中から本当に価値のある対象を人が見極める」という二段構えの仕組みです。この構造は、多くの業務に共通する普遍的な考え方として転用できます。
営業リード管理におけるフィルタリングと精査
営業活動では、名刺情報、展示会での接点、Webフォームからの問い合わせなど、膨大なリード(見込み顧客)が日々蓄積されます。しかし、すべてのリードに均等なリソースを割くことは非効率です。
ここで有効なのが「候補リストの精査」の仕組みです。
まずはシステム上で属性や行動データに基づき、自動で一次抽出を行います。例えば「過去30日以内に資料請求をした企業」「購買決定権を持つ役職の人物」「自社の主要商材と親和性の高い業種」などを条件に抽出できます。そのうえで、営業担当者が実際に企業の状況や潜在ニーズを精査し、優先度を判断するのです。
この二段階のアプローチにより、営業リソースを高確度な顧客に集中でき、無駄なアプローチを減らすことができます。
仕入先評価における候補抽出と現場判断
製造業や小売業においては、仕入先の選定が事業競争力を大きく左右します。コストや納期だけでなく、品質保証体制や供給の安定性、さらには将来の技術的な対応力も考慮する必要があります。
ここでも「抽出→精査」の構造が有効です。まずは購買部門が基本的な条件で候補をリストアップします。次に、実際に部品や素材を扱う現場や技術部門が候補リストを精査し、実運用に耐えうるかどうかを判断します。
この仕組みをシステム化することで、仕入先候補の一次抽出条件を柔軟に設定でき、評価フローを透明化できます。単なる「価格比較」から脱却し、総合的な視点で仕入先を選定できるようになるのです。
顧客サポートにおける優先度付け
カスタマーサポートの現場では、日々大量の問い合わせが寄せられます。そのすべてに即時対応することは難しいため、優先度付けの仕組みが求められます。
このときも「候補リストを精査する」という発想が役立ちます。
まずはシステムが自動的に問い合わせを分類し、緊急度や契約ランクに基づいて一次抽出します。その後、サポート担当者が内容を確認し、優先度を再評価して対応順序を決定します。
これにより、対応の遅れが致命的となる重要顧客や障害対応を優先し、効率と満足度の両立を図ることが可能となります。
抽出と精査を支えるシステム設計の要点
抽出と精査のプロセスをシステムに落とし込む際には、いくつかの重要なポイントがあります。
- 抽出条件の柔軟性
業務ごとに必要な条件は異なります。ユーザー自身が抽出条件を変更・追加できる仕組みが重要です。 - 精査プロセスの可視化
人による判断がブラックボックス化すると、後からの検証が困難になります。誰がどの基準で判断したのかを記録し、透明性を確保する必要があります。 - データと人間の役割分担
システムは大量データの絞り込みに強みを持ち、人は最終的な適合性や将来性を見極める力に優れています。この役割分担を前提とした設計が不可欠です。 - 継続的な評価指標の見直し
市場や顧客の変化に応じて、抽出条件や精査基準を定期的にアップデートする仕組みを備えるべきです。
抽出→精査モデルの本質
「候補リストを抽出し、現場が精査する」という二段階の構造は、一見すると当たり前のようですが、システムとして正しく実装されているケースは多くありません。抽出が機械的すぎると適切な候補を逃し、精査が属人的すぎると再現性が失われます。両者のバランスをとり、プロセス全体を仕組み化することこそが、業務効率化と成果最大化の鍵といえるでしょう。
まとめ
理系人材採用のスカウト事例に見る「候補リストを精査する」仕組みは、営業、調達、サポートなど多様な業務に共通する普遍的なモデルです。抽出と精査の役割を分け、それぞれに最適な仕組みを与えることで、業務データは単なる蓄積物から意思決定を支える資産へと変わります。組織が持つデータをどう活かすかは、システム設計の工夫次第です。効率と精度を両立させるために、この「抽出→精査」モデルを自社業務にどう応用できるかを考えてみてはいかがでしょうか。
抽出と精査という二段階の仕組みを実際の業務に落とし込むには、現場の特性や判断基準をきちんと反映させる柔軟なシステム設計が欠かせません。既存のパッケージでは拾いきれない自社特有の条件や評価プロセスをシステムに組み込みたいと考えるのであれば、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発が有効です。フレシット株式会社では、お客様の業務に即した要件整理から伴走し、複雑な業務データを活かせるシステムを一から設計します。自社の強みを最大限に発揮できる仕組みをお探しの際は、ぜひ当社にご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

