現場の価値を活かすシステム要件定義の考え方
現場・経営・開発をつなぐ“翻訳力”が、DXを動かす
2025-10-08
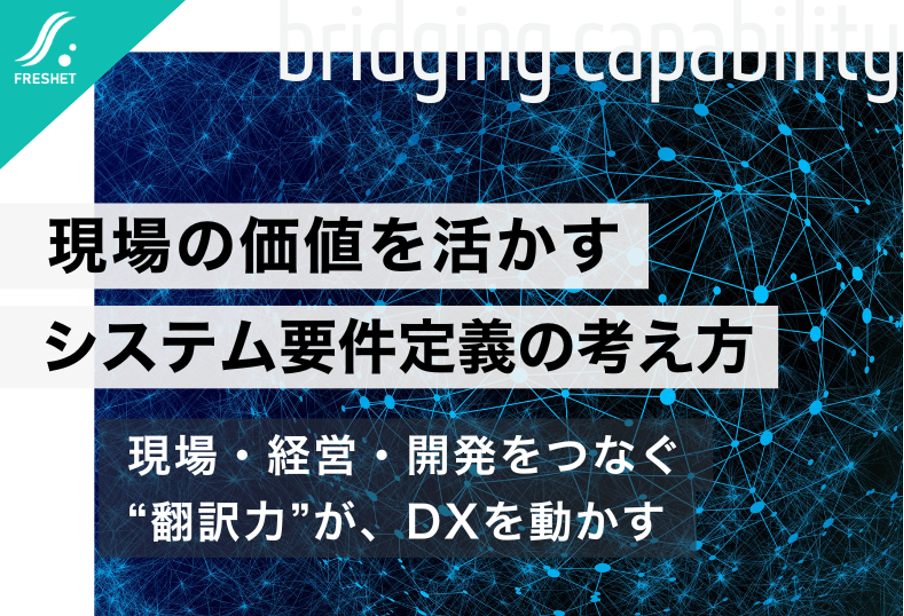
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が進む中で、多くの企業が新システムの導入や業務のデジタル化に踏み出しています。しかしその一方で、「期待したほど成果が出ない」「現場に定着しない」といった声も少なくありません。その多くは、技術力やツール選定の問題ではなく、“現場の価値の拾い上げ方”に課題があります。
本コラムでは、現場の知見や人的資産を正しく反映し、DXを“もったいない”結果にしないためのシステム要件定義の考え方を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】日本居住経験ベトナム人の再雇用にみる、人材循環の新たな課題と可能性
日本での就労や留学経験を持つベトナム人材を、帰国後に日系企業へ再びつなぐパソナグループの求人アプリ「おかえりジョブ」が注目されている。日本の商習慣や礼儀を理解する人材を確保したい企業と、帰国後のキャリア形成に悩む人材を結びつける仕組みだ。一方で、現地に2,000社以上ある日系企業の多くが、こうした“即戦力”を十分に活用できていなかったことが背景にある。悪質な仲介業者を排除するJICAの公式求人アプリの整備も進む中、課題は「送り出し」から「帰還」までの循環をいかに持続的に設計するかに移っている。
出典:日本経済新聞「日本居住経験のベトナム人、帰国後も日系企業で活躍 礼儀・商慣習に精通 パソナ系が求人アプリ」2025年9月19日付朝刊
ポイントをひとことで
DXの多くが形骸化する背景には、「技術導入=変革」と誤解してしまう構造的な問題があります。真の課題は、どの業務をどう変えるかが定義されていないことです。現場には、業務を回すための判断や工夫といった“暗黙知”が数多く存在します。それを可視化し、仕組みに落とし込むのが要件定義の本質です。技術ではなく思考の精度が、DXの成果を左右します。つまり、成功するDXとは「現場の知恵を設計に翻訳するプロジェクト」と言い換えられるでしょう。
DXの“失敗”は、技術ではなく設計思想にある
DXが進まない原因を「現場がITに弱い」「古いシステムが足を引っ張っている」と捉えるケースは少なくありません。しかし本質的な問題はそこではなく、「何を目的に変えるのか」「誰の課題を解決するのか」という根本的な定義が曖昧なままプロジェクトが進む点にあります。
特に多いのが、“ツール導入ありき”でプロジェクトが動くケースです。
「〇〇システムを入れれば自動化できる」「このSaaSが流行っている」といった発想から始まると、現場の実態や目的との整合が取れず、結果として“使われないシステム”になってしまいます。
DXの本質は「業務や組織構造の変革」にあり、技術はそのための手段にすぎません。要件定義の段階で“現場の価値”をどう理解し、設計思想に反映できるかが成功の分かれ目です。
現場の“価値”とは何か──業務フローに潜む暗黙知を見つける
要件定義を進める上で、最も重要なのは「現場の業務を正確に理解すること」です。
ところが、多くの企業では「現場ヒアリング=操作手順の聞き取り」程度で終わってしまうことがあります。これでは表面的な作業しか見えず、現場が日々行っている判断や工夫、経験値に基づく対応といった“暗黙知”が抜け落ちてしまいます。
たとえば、受発注システムの設計において「この条件のときだけ承認を飛ばす」「在庫が不確定なときは仮登録にとどめる」などの運用ルールは、マニュアルに明記されていないことが多いものです。こうした細かな現場判断こそ、業務の品質やスピードを支える“価値”であり、それをシステムに反映できるかが重要になります。
現場の価値を見つけ出すには、ヒアリングだけでなく「観察」と「共体験」が欠かせません。実際に現場で作業を見学し、担当者がなぜその判断をしているのかを質問することで、単なる業務プロセスではなく“思考プロセス”まで理解できます。
問題意識を共有する──“要件定義の前”にすべきこと
要件定義の前に行うべき最初のプロセスは、「問題意識の共有」です。
ここでの目的は、現場・経営層・システム開発会社の三者が、同じ課題構造を見ている状態をつくることです。
たとえば、経営層は「コスト削減」を目的に掲げていても、現場は「手戻りの多さ」に課題を感じているかもしれません。これらは表面的には別の課題ですが、根底に「情報の非対称性」や「フローの不整合」といった共通原因がある場合も多いのです。
問題意識を共有する際は、次の3つの質問を整理すると効果的です。
- なぜ今、変える必要があるのか?(目的)
- 何が現場を苦しめているのか?(課題)
- それが解消されると、どんな状態になるのか?(理想像)
この3点を明文化して初めて、技術的な検討に進む土台が整います。要件定義の成功率は、この「課題の共通理解」の精度に比例します。
要件定義は“翻訳作業”である──現場の言葉をシステムの言葉に
要件定義とは、経営・現場・技術の三者が異なる言語で話している状況を、“同じ構造”に翻訳する作業です。
現場の担当者は「入力が面倒」「ミスが多い」と話し、経営層は「生産性を上げたい」と言い、開発側は「機能追加が必要」と捉える──。それぞれの言葉が指している本質を整理し、構造的に結びつけることがシステム企画の要です。
ここで有効なのが、プロセスを「データの流れ」と「意思決定の流れ」に分けて整理する手法です。
たとえば、「受注データが登録される→在庫確認→出荷指示」というフローを、単なる業務ステップとして捉えるのではなく、
- どの情報を誰が入力し、どの判断材料に使っているのか
- どのデータがどこで止まり、どこで重複しているのか
という観点で分解することで、属人化やムダな手戻りを見つけ出せます。
翻訳作業を経て、現場の言葉が“機能仕様”へと落とし込まれたとき、システムは初めて「使われるもの」になります。
“変えること”に目的を置かない──持続可能なDXへの設計思想
DXを目的化してしまうと、プロジェクトは一時的な「導入イベント」で終わってしまいます。
本来の目的は、「変えたあとに継続的に改善できる仕組み」を持つことです。
持続的なDXを実現するためには、次の2つの要素が重要です。
- 変更に強いシステム構造:業務や組織が変わっても、設定や設計変更で柔軟に対応できるアーキテクチャ。
- データの一貫性と見える化:現場の改善活動に必要な情報が、即座に把握できる状態。
これらを実現するには、“現場が自ら改善できるシステム”を設計することが鍵です。つまり、完成した瞬間が終わりではなく、「改善の起点」となるような設計思想を持つことが求められます。
DXを成功させる「3つの視点」
DXを“もったいない”結果にしないためには、以下の3つの視点を持って要件定義に臨むことが重要です。
- 現場の納得感
現場が自分たちの課題として捉えられる言葉で要件が整理されているか。
「やらされ感」ではなく「自分たちが使いやすくするための仕組みだ」と感じてもらうことが大切です。 - 経営との整合性
経営目標とシステム機能がどのように結びつくのかを明確にする。
単なるコスト削減ではなく、「戦略的価値創出」を意識した要件定義が求められます。 - 継続的改善の設計
システム導入後に発生する課題を、自社で改善できる構造をあらかじめ設計に組み込む。
“完成”ではなく“進化”を前提とする発想が重要です。
まとめ
DXの本質は、新しいツールを導入することではなく、「現場の価値を構造化し、仕組みで支えること」にあります。
システム開発会社に任せきりにするのではなく、自社の課題を正確に定義し、現場の知恵を反映した要件定義を行うことで、初めて“もったいないDX”から脱却できます。
技術よりも、現場の価値の拾い上げ方にこそ、成功のカギがあるのです。
DXを成果につなげるためには、「課題をどう定義し、どんな仕組みで解決するか」を一緒に考えられる開発パートナーの存在が欠かせません。
フレシット株式会社では、画一的なパッケージ導入ではなく、企業ごとの現場特性や業務構造を丁寧に可視化し、課題の本質から設計を行うフルスクラッチ(オーダーメイド)開発を行っています。
要件定義の段階から経営・現場・システムの三者を橋渡しし、使われ続ける仕組みを共に構築します。自社の強みや現場の知見を最大限に活かしたDXを実現したいとお考えの方は、ぜひフレシットへご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

