“作りたいサービス”ではなく、“解決したい課題”から──成功するWEBサービス企画の出発点
「何を作るか」ではなく「なぜ作るのか」から始めるシステム開発
2025-10-11
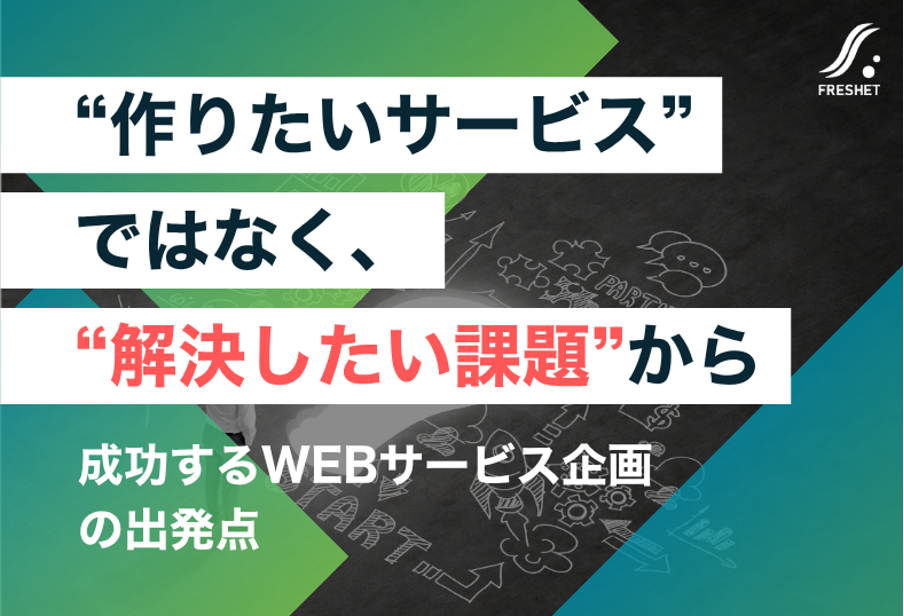
多くのWEBサービス開発が失敗する原因は、アイデアや機能が先行してしまい、「なぜそのサービスを作るのか」という問いが曖昧なまま企画が進むことにあります。開発の目的が“作ること”に置き換わった瞬間、プロジェクトは方向性を失い、期待した成果が得られません。
本コラムでは、“解決したい課題”を出発点としたWEBサービス企画の考え方と、課題定義を中心に据えた開発プロセスの実践方法を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】日本居住経験ベトナム人の再雇用にみる、人材循環の新たな課題と可能性
日本での就労や留学経験を持つベトナム人材を、帰国後に日系企業へ再びつなぐパソナグループの求人アプリ「おかえりジョブ」が注目されている。日本の商習慣や礼儀を理解する人材を確保したい企業と、帰国後のキャリア形成に悩む人材を結びつける仕組みだ。一方で、現地に2,000社以上ある日系企業の多くが、こうした“即戦力”を十分に活用できていなかったことが背景にある。悪質な仲介業者を排除するJICAの公式求人アプリの整備も進む中、課題は「送り出し」から「帰還」までの循環をいかに持続的に設計するかに移っている。
出典:日本経済新聞「日本居住経験のベトナム人、帰国後も日系企業で活躍 礼儀・商慣習に精通 パソナ系が求人アプリ」2025年9月19日付朝刊
ポイントをひとことで
WEBサービス開発の失敗は、技術力の不足よりも“課題定義の甘さ”から生じることが多いです。現場では「機能を増やせば便利になる」と考えがちですが、解決すべき問題が明確でなければ、機能はただの飾りになります。重要なのは、誰のどんな不便を解消したいのかを構造的に整理し、開発の目的を一本化することです。課題を正しく定義すれば、設計や仕様の判断軸が明確になり、結果的にムダのない“使われるサービス”を作ることができます。
“作ること”が目的化したプロジェクトの行き着く先
新しいWEBサービスの構想を立てるとき、最初に浮かびがちなのが「どんな機能を作るか」「どんなデザインにするか」というアイデアの部分です。
しかし、機能や見た目から入ってしまうと、ユーザーが抱えている根本的な問題や、ビジネスとしての目的を見失いがちになります。
たとえば、社内業務の効率化を目的にシステムを作ったのに、「誰も使ってくれない」「運用が定着しない」といったケース。これは珍しくありません。
原因をたどると、「どの業務の何を改善したいのか」という課題設定が不十分なまま、解決策だけが走り出してしまったことが多いのです。
DXの本質は“仕組みで課題を解くこと”にあります。
「どんな課題を、誰のために、どんな方法で解決するのか」。その順序を誤らないことが、成功するWEBサービス企画の出発点になります。
課題定義から始める開発が成果を生む理由
課題を明確にせずに進めると、どれだけ優れた技術を使っても、成果につながらないシステムができてしまいます。
逆に、課題定義がしっかりしているプロジェクトほど、要件の優先順位が明確になり、ムダな開発を減らすことができます。
課題定義の目的は、現象ではなく“原因”を特定することです。
たとえば「顧客対応の時間がかかる」という課題があるとします。
その原因は「情報が一元管理されていない」「担当者ごとの対応履歴が共有されていない」「入力項目が多くて登録が遅い」など、構造的な要因に分解できます。
このように、課題を“症状”ではなく“構造”で捉えることで、開発すべき機能や優先順位が自然と見えてきます。結果として、技術投資が成果に直結するシステム設計が可能になるのです。
問題意識を共有することから始まる要件定義
課題定義を行う際に重要なのが、「問題意識の共有」です。
経営層、現場担当者、システム開発会社の三者がそれぞれ異なる視点を持っています。
経営層は“コスト削減”や“新規事業創出”を重視し、現場は“作業負担の軽減”や“入力のしやすさ”を重視する。
それぞれの視点が交わらないまま企画が進むと、最終的に「誰のためのサービスか」が曖昧になります。
問題意識を共有するためには、まず次の3点を整理することが効果的です。
- 何が“現状の課題”なのか(現象)
- その課題が発生している“構造的な要因”は何か(原因)
- それを解消した先にどんな“理想の状態”を目指すのか(目的)
この3つの問いを明確にし、全員が同じ認識を持つこと。
これが、後の要件定義の精度を大きく左右します。
“顧客課題”を掘り下げることでサービスの方向性が定まる
BtoCやBtoBを問わず、WEBサービスの成功要因は「顧客の課題をどれだけ正確に理解できるか」にあります。
多くの企業がUX調査や市場分析に注力しますが、最も大切なのは“ユーザーが本当に困っていること”を掘り下げることです。
たとえば、ある企業が新しい予約管理サービスを作る際、ユーザーの要望をそのまま取り入れて「カレンダー機能」「通知機能」などを追加したとします。
しかし、実際の利用データを分析すると、予約の“管理”よりも“キャンセル対応の煩雑さ”が最大の課題だった。
この場合、本当に必要なのは「予約を減らす機能」ではなく、「キャンセルを自動処理できる仕組み」だったということになります。
課題を誤ると、いくら機能を追加しても“使われないサービス”になってしまいます。
真の課題を発見するためには、インタビュー・行動観察・データ分析の3点を組み合わせ、表面的な要望の裏にある“行動の理由”を掘り下げることが欠かせません。
解決策は“作る前”に検証する──プロトタイピングの重要性
課題が整理できたら、次に必要なのは“仮説検証”です。
解決策をコードで作る前に、仮説を紙やモックアップの段階で確認することで、方向性のズレを早期に発見できます。
この段階で意識すべきなのは、「解決策の正しさ」ではなく「問題理解の深さ」です。
開発に入る前に、「本当にこの仕組みで課題が解決するのか」を関係者と共有できていれば、後戻りの少ない堅実なプロジェクトが進められます。
また、プロトタイプを通じて現場担当者やユーザーの反応を得ることで、“機能要件”がより明確になります。
これにより、開発フェーズでの仕様変更を最小限に抑えることができ、結果的にコスト削減にもつながります。
成功するWEBサービス開発に共通する3つの要素
課題定義から始めるWEBサービス開発には、成功プロジェクトに共通する3つの特徴があります。
- 目的と成果の一致
「どの課題を解決したいのか」を明確にし、KPIを設定している。
開発の途中でも目的を見失わず、意思決定が一貫している。 - 現場との対話の継続
ヒアリングやレビューを定期的に行い、開発側と運用側の距離を保っている。
現場の知見をリアルタイムで反映できる体制が整っている。 - 改善を前提とした設計
リリース後もデータ分析やユーザーフィードバックを踏まえ、継続的に改善を重ねている。
完成ではなく、“進化し続けるサービス”を前提に設計されている。
これらの3つが揃うことで、WEBサービスは“作って終わり”ではなく、“使われ続ける資産”へと成長していきます。
まとめ
WEBサービス企画の成否は、最初の一歩──すなわち“課題の定義”にかかっています。
作りたい機能や最新の技術を優先するのではなく、解決すべき問題の本質を見極めること。
それが、開発の方向性を決め、成果を最大化する唯一の方法です。
「なぜこのサービスを作るのか」「誰のどんな課題を解決するのか」。
その問いから始まるプロジェクトこそ、ビジネスの成長を支える真のWEBサービス開発といえるでしょう。
課題の定義から始まる開発は、単なるシステム構築ではなく「事業の再設計」に近いプロセスです。
フレシット株式会社では、要件が固まっていない段階から並走し、事業の目的や現場の課題を整理するところから支援します。
パッケージの枠に縛られず、ビジネスの構造に最適化した仕組みをゼロから設計できることが、フルスクラッチ開発の最大の強みです。
「何を作るか」ではなく「なぜ作るのか」から始めたい方は、ぜひフレシットへご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

