カカオトーク刷新に見る“収益化ファースト”の落とし穴──機能追加より「信頼設計」が重要な理由
2025-10-09
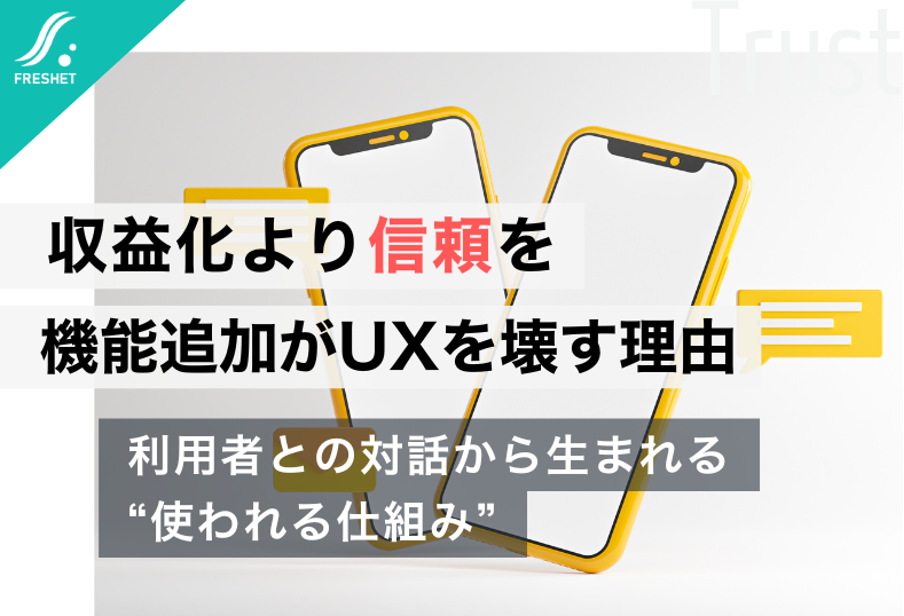
韓国のカカオ社が提供するSNS「カカオトーク」が、AIを活用した大規模刷新を発表した直後に利用者から強い反発を受けました。操作性の変化や課金誘導と受け取られる設計が原因とされ、ネット上では「アップデートを阻止する方法」が拡散するほどの騒動となりました。
この事例は、最新技術や新機能を投入しても「ユーザー体験を損なえば信頼を失う」ことを如実に示しています。本コラムでは、短期的な収益化を優先する“収益化ファースト”がUX(ユーザー体験)を壊す理由と、ビジネスゴールとユーザー体験を両立させるための「信頼設計」という考え方について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】カカオトーク刷新、AI強化で利便性向上狙うも利用者との対話が今後の鍵に
韓国ネット大手カカオは、主力SNS「カカオトーク」を生成AIと連携させて大規模刷新した。自社開発のAI「カナナ」やChatGPTを組み込み、スケジュール管理や予約、検索など日常業務を支援する機能を追加。しかし、操作性の変化や課金誘導と受け取られる設計に利用者の不満が噴出し、一部機能を元に戻す事態となった。専門家はAI活用を高く評価する一方で、技術の進化が利用者体験を損なえば信頼を失うと指摘。利便性と収益化の両立には、技術よりもまず「利用者との対話」を軸にした設計思想が欠かせない。
出典:日本経済新聞「カカオトーク、AIと融合 店予約や予定管理/チャットGPT採用 課金誘導と批判、苦い発進」2025年10月4日付朝刊
ポイントをひとことで
技術革新が加速する中で、多くの企業が「機能の多さ」や「最新技術の導入」を価値と捉えがちですが、真に重要なのは利用者が安心して使える“信頼の設計”です。システムは企業の思惑を押し付ける場ではなく、ユーザーとの関係を育てる接点であるべきです。収益化を優先した機能追加は一時的な数字を生むかもしれませんが、信頼を損ねれば本来の価値は失われます。フルスクラッチ開発こそ、企業の理念と利用者体験を丁寧に一致させるための最も有効な手段と言えます。
技術よりも「使い続けてもらう仕組み」が価値を生む
近年、AIや自動化技術の発展により、システムやアプリの機能は飛躍的に向上しています。しかし、どれだけ高度な機能を実装しても、ユーザーが離れてしまえばビジネスとしての価値は失われます。
多くの企業が新機能の追加やサービス内課金によって収益拡大を狙いますが、こうした“収益化ファースト”のアプローチは、しばしば「操作のしづらさ」や「押しつけがましさ」を生み出します。
利用者は直感的に「この機能は自分のためではなく、企業のためにつくられた」と感じ取ります。この瞬間、信頼が揺らぎ、利用意欲が低下するのです。
ユーザー体験の本質は、「自分の目的を自然に達成できること」にあります。いくら優れた技術を組み合わせても、企業側の都合で押しつけた機能や導線は、UXを壊す最大の要因となります。
システム刷新が失敗する共通点
多くのシステム刷新プロジェクトに共通する失敗要因のひとつが、「開発目的のすり替わり」です。
当初は「利用者の利便性向上」や「業務効率化」を目的としていたはずが、開発が進むにつれて「社内評価指標の改善」や「新規収益源の確保」といった企業側の都合が優先されていきます。
その結果、現場のユーザーが求めていない機能が実装され、日々の運用が複雑化し、定着率が下がるという悪循環が生まれます。
カカオトークの事例もまさにその典型です。AI連携やショート動画広告などの新機能は先進的でありながら、ユーザーが求めていた“快適なコミュニケーション”という本来の価値を後退させてしまいました。刷新とは単なる「新しい技術の導入」ではなく、「既存の信頼関係を再構築する行為」であることを忘れてはなりません。
信頼を設計するという発想
では、どうすれば「使われ続けるシステム」を実現できるのでしょうか。
キーワードは“信頼設計”です。信頼設計とは、ユーザーが「このシステムは自分のために設計されている」と感じられる体験を構築するプロセスです。
その基盤となるのは、以下の3つの設計思想です。
- 透明性の確保
利用者が操作中に「なぜこの機能があるのか」を理解できるようにすること。突然の機能変更や不自然な広告導線は、ユーザーの不信感を高めます。更新の背景や目的を適切に伝えることが、信頼の維持につながります。 - 共感を軸にした機能設計
“どのような状況で利用されるか”を想定した体験設計が重要です。ユーザー調査やヒアリングを通じて「現場での使われ方」を理解し、業務フローや心理的負担を軽減するUI/UXを設計します。 - 長期的な運用視点
初期リリースで完璧を目指すのではなく、運用を通じて改善していく柔軟性が求められます。定期的なアップデートよりも、利用者の声を聞きながら“徐々に馴染ませる”プロセスこそが、結果的に安定した定着につながります。
信頼設計とは、技術をユーザーに押しつけるのではなく、「安心して任せられる仕組みをどう共創するか」という思想そのものなのです。
収益化とユーザー体験を両立させるには
収益化とUXは、しばしば対立するテーマのように語られます。しかし、両者は本来、補完関係にあります。
ユーザー体験が向上すれば利用頻度が増え、結果として収益性も上がります。重要なのは、短期的なKPI(クリック率や滞在時間)ではなく、長期的なロイヤルティを指標とすることです。
そのためには、以下のような考え方が有効です。
- ユーザー行動データの“背景”を読み解く
- クリック率よりも“満足度の変化”を追う
- 利用者からの定性的フィードバックを重視する
- 機能追加よりも“削減”を選択する勇気を持つ
特に、フルスクラッチでシステムを開発する場合、これらを初期段階から設計に反映することが可能です。パッケージや既存ツールでは難しい“信頼を積み上げる設計”が実現できます。
ユーザーとの関係を壊す「アップデート疲れ」
多くのアプリや業務システムが抱える課題に「アップデート疲れ」があります。頻繁な更新や機能追加は、企業側には前向きな改善でも、ユーザーにとっては“慣れた操作の破壊”です。
この疲れを蓄積させると、いずれ離脱や利用放棄につながります。
“アップデート=改善”という思い込みを捨て、ユーザーの操作習慣や心理的安心感を守ることが大切です。変えるべきは機能ではなく、「感じのよさ」です。
開発会社にとっては、技術的な進化以上に、変えない勇気を持つ判断力が求められます。
信頼設計はUXの最上位概念
UXデザインというと、UIの見た目や操作性に注目が集まりがちです。しかし、本質は「このシステムを使っても大丈夫だ」と思ってもらえる心理的安全性の設計にあります。
それが“信頼設計”です。
信頼設計が欠けたシステムは、一見便利でも長続きしません。逆に、信頼が積み重なれば、多少の不便があっても利用者は離れません。
だからこそ、開発において最も重要なのは「どう使わせるか」ではなく、「どう信頼されるか」です。
まとめ
カカオトークの事例は、最新技術やAIを駆使した刷新であっても、ユーザー体験を損ねれば信頼を失うことを示しています。短期的な収益化を優先すると、企業は“使ってもらうための仕組み”ではなく、“使わせるための仕掛け”に偏りがちです。
システム開発において本当に重要なのは、機能の多さや先進性ではなく、「利用者が安心して任せられる設計思想」を持つことです。それが、変化の激しい時代においても使われ続けるシステムを支える、最も強固な基盤となります。
フレシット株式会社では、この「信頼設計」という考え方を開発の中心に据えています。単に機能を実装するのではなく、利用者の行動や心理、業務の流れまで丁寧に読み解き、使い続けられるシステムをゼロから設計します。フルスクラッチだからこそ、既存の枠にとらわれず、御社のビジネスとユーザーの双方に最適化された体験を形にできます。短期的な成果ではなく、長く信頼される仕組みを共に築きたいとお考えの際は、ぜひフレシット株式会社にご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

