カカオトーク刷新に見る“改修の落とし穴”──「使いにくくなった」と言われないために避けるべき3つの誤解
「何を変えるか」より「なぜ変えるか」──リニューアル成功の分かれ道。
2025-10-18
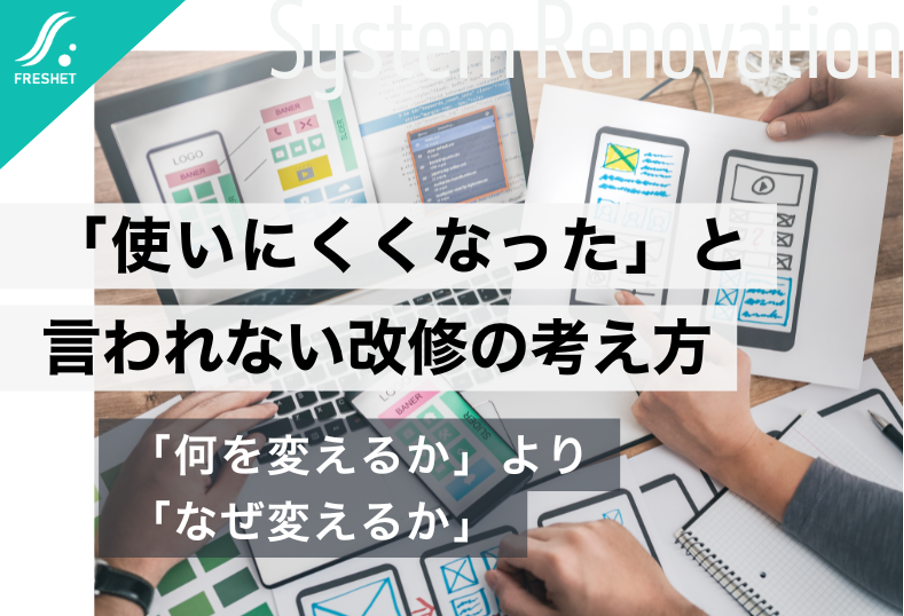
韓国のカカオ社が展開するSNS「カカオトーク」が、生成AIを活用した大規模アップデートを実施した直後、ユーザーから「使いにくくなった」「元に戻したい」といった不満の声が殺到しました。新機能や広告導線を追加したものの、利用者の体験を損ねたことで、同社は一部機能を急きょ元に戻す対応を迫られています。
この事例は、システム改修における“ある誤解”を浮き彫りにしました。それは、「新機能の追加が価値向上につながるとは限らない」ということです。本コラムでは、刷新やリニューアルの際に陥りやすい3つの誤解と、それを防ぐための設計・検証プロセスの要点を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】カカオトーク刷新、AI強化で利便性向上狙うも利用者との対話が今後の鍵に
韓国ネット大手カカオは、主力SNS「カカオトーク」を生成AIと連携させて大規模刷新した。自社開発のAI「カナナ」やChatGPTを組み込み、スケジュール管理や予約、検索など日常業務を支援する機能を追加。しかし、操作性の変化や課金誘導と受け取られる設計に利用者の不満が噴出し、一部機能を元に戻す事態となった。専門家はAI活用を高く評価する一方で、技術の進化が利用者体験を損なえば信頼を失うと指摘。利便性と収益化の両立には、技術よりもまず「利用者との対話」を軸にした設計思想が欠かせない。
出典:日本経済新聞「カカオトーク、AIと融合 店予約や予定管理/チャットGPT採用 課金誘導と批判、苦い発進」2025年10月4日付朝刊
ポイントをひとことで
システム改修の失敗は、多くの場合「技術」ではなく「理解不足」に起因します。現場のユーザーがどのように使っているか、どんな小さな操作に慣れているかを見落とすと、改修後に“使いにくくなった”という声が生まれます。新機能の追加や見た目の刷新は成果に見えますが、実際の価値はユーザーの作業効率と心理的負担の軽減にあります。改修とは進化ではなく再設計であり、「変える勇気」と同時に「変えない判断」を持つことこそ、システムを長く生かす鍵です。
機能を増やすほど価値が上がる、は誤解である
多くのシステム開発において、「機能追加=進化」と捉えられがちです。しかし実際には、機能を増やすたびに操作は複雑化し、ユーザーが目的を達成するまでの導線が長くなる傾向があります。
特に既存ユーザーが慣れ親しんだ操作体系を変更すると、心理的な抵抗が大きくなり、「改悪」と感じられてしまうことも少なくありません。
たとえば、カカオトークではAI機能やショート動画広告などを新たに導入しましたが、利用者が求めていたのは「より便利な機能」ではなく、「これまで通り快適に使える体験」でした。目的が異なれば価値の感じ方も変わります。
システム改修で本当に目指すべきは、“機能の多さ”ではなく“機能の意味づけ”です。つまり、「ユーザーにとって何を解決するのか」を明確にしない限り、追加した機能は“ノイズ”にしかなりません。
ユーザーが慣れている操作を変えるリスクを軽視してはいけない
リニューアルやUI刷新で特に注意すべきは、「慣れ」の破壊です。
既存ユーザーは、日々の業務や生活の中でシステム操作を身体的に覚えています。その「無意識の操作」が崩れると、たとえ改善点があっても不満が先に立ちます。
多くのシステム開発会社が陥るのは、「自分たちが見やすい」「美しいUI」を優先しすぎることです。利用者の実際の使用環境を想定しないまま画面構成を変えると、結果として“学び直し”が必要になり、導入効果が下がります。
特に業務システムでは、わずかな操作変更が生産性の低下やミスの増加に直結します。
UI改修を成功させる鍵は、「変えるべき部分」と「変えてはいけない部分」を明確に線引きすること」です。すべてを刷新するのではなく、既存の安心感を残しながら、課題解決に必要な最小限の改善を行うことが理想的です。
「データが示しているから大丈夫」は危険な思い込み
システム改修において、アクセス解析や行動ログなどのデータは重要な判断材料です。しかし、それを“絶対的な真実”と捉えるのは危険です。
なぜなら、数字は「何が起きたか」は示しても、「なぜ起きたか」は教えてくれないからです。
たとえば、ある機能の利用率が低下しているとき、その理由は「機能が不要」だからとは限りません。操作が分かりにくい、導線が埋もれている、あるいは認知されていない──といった背景があるかもしれません。
このように、データは“表面的な結果”を示すにすぎず、UXを正しく判断するにはユーザーの声や行動観察と組み合わせる必要があります。
改修の前後で実施すべきは、「定量データ+定性フィードバック」を用いた多面的な検証です。
数字だけを根拠に改修を進めると、利用者の“体験上の不快感”を見逃すリスクが高まります。
ユーザーをテストの“被験者”ではなく“共創者”にする
UX後退を防ぐもう一つの重要な要素は、テスト設計のあり方です。
多くのプロジェクトでは、リリース直前に行う操作テストを「確認作業」として捉えがちですが、理想は“共創プロセス”としてのテストです。
ユーザーを被験者として扱うのではなく、「どの操作がわかりづらいか」「どう感じたか」を意見として吸い上げ、UIや機能設計に反映するサイクルを構築することが重要です。
このアプローチを取ることで、ユーザー視点の課題を事前に洗い出し、開発側の思い込みを排除できます。
また、テスト対象者を“想定ユーザー”に限定せず、社内の別部署や初心者層など、異なる立場の人にも触れてもらうことで、新たな発見が得られます。
“専門家の視点”だけでなく、“素人の戸惑い”を設計段階から吸収できることが、フルスクラッチ開発の大きな強みです。
改修の本質は「直す」ことではなく「育てる」こと
システム改修というと、「古くなったものを新しくする」「不具合を修正する」といった“修理的な発想”にとらわれがちです。
しかし、ビジネスにおける改修の本質は、「変化する利用環境に合わせて、システムを育てること」です。
改修の目的は、技術的な刷新ではなく、「ユーザーとの関係性を持続的にアップデートすること」にあります。
そのためには、システム開発会社と発注側の両者が「なぜ変えるのか」「誰のために変えるのか」を共有し、長期的な視点での運用設計を行うことが欠かせません。
フルスクラッチで開発されたシステムであれば、柔軟な改修や段階的な改善が可能です。
一方、パッケージやテンプレート型のシステムでは、仕様制約が多く、ユーザーの声を反映しにくいケースも少なくありません。
“使われ続けるシステム”を目指すなら、最初から「改修しながら育てていく」前提での設計が求められます。
改修プロジェクトを成功させる3つの要点
システム改修を成功に導くには、以下の3点を意識することが重要です。
- ユーザーの不満点を「数字」ではなく「文脈」で捉える
利用率低下の背後にある心理や業務上の制約を理解することが出発点です。 - “変えない設計”を前提に、最小限の改修を積み重ねる
大幅なリニューアルよりも、安心感を残した部分改修が長期的な信頼を生みます。 - テスト段階からユーザーを巻き込み、共創プロセスを設計する
操作性や理解度を検証しながら、利用者視点を定着させることがUX向上の近道です。
これらを徹底することで、機能追加やUI刷新を行っても「使いにくくなった」と感じさせない、持続的なUX向上が実現します。
まとめ
システム改修は、単なる更新作業ではなく、ユーザーとの関係性を再構築する重要なフェーズです。
新機能を追加することが必ずしも価値を高めるとは限らず、むしろ使い勝手を損なうリスクをはらんでいます。
成功する改修プロジェクトの共通点は、「何を変えるか」よりも「なぜ変えるのか」を明確にし、ユーザーを開発プロセスの中心に据えている点です。
“システムを育てる”という長期的な視点を持つことで、企業は利用者の信頼を失うことなく、より強固なUXを築いていくことができます。
フレシット株式会社では、システムを「つくって終わり」にせず、「育て続ける仕組み」として捉えています。フルスクラッチ(オーダーメイド)開発を通じて、御社の業務や利用者の行動を深く理解し、改修や運用保守フェーズでも“使いにくくならない仕組み”を一から設計します。変化に柔軟に対応しながらも、ユーザーが安心して使い続けられる──そんなシステムの在り方を共に考え、長期的な価値を積み重ねていく開発を実現します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

