システム開発でよくあるトラブルの原因・対策・予防法を徹底解説
2025-10-12
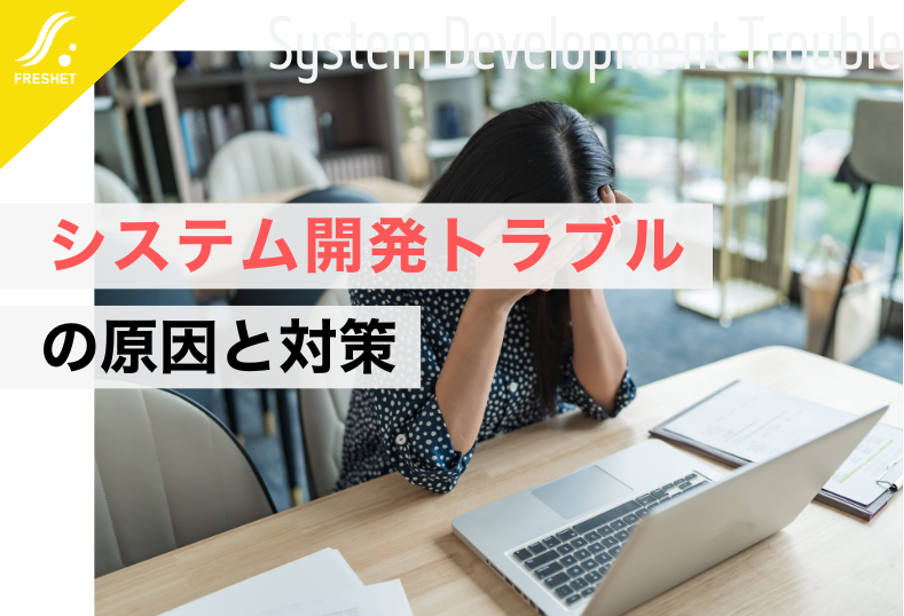
システム開発にトラブルはつきものといわれます。プロジェクトを進めていく上で実際にトラブルに遭遇し、痛い目を見た経験をお持ちの方も多いでしょう。しかしながら、多くのトラブルは、あらかじめ発生の原因を把握し、予防のためのポイントさえ押さえておけば、回避が可能です。
このコラムでは、システム開発で発生するトラブルの原因や、実際に起きたシステム開発のトラブル事例に触れながら、トラブルを未然に防ぐためのポイント、実際にトラブルが発生した際に取るべき初動対応などについて詳しく解説します。システム開発のトラブルに関するよくある質問とその答えも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
システム開発で発生するトラブルの原因
システム開発で発生するよくあるトラブルの原因は、次の通りです。
- 要件定義不足
- マネジメント不足
- 技術力不足
- コミュニケーション不足
- 開発手法がシステム内容と合っていない
以下、それぞれ解説します。
要件定義不足
システム開発で発生するトラブルの原因の1つは、要件定義不足です。あいまいな要件定義のため、本来あるべきシステムの内容が明確になっておらず、重要な機能の欠如や実業務との不適合といったさまざまなトラブルが発生します。
さらにスケジュール遅延、予算超過などの事態に発展する恐れもあるため、関係者間での擦り合わせを丁寧に行い、精度の高い要件定義を実現することが重要です。
>>要件定義の失敗事例から学ぶ成功のポイントはこちら
マネジメント不足
システム開発プロジェクトの進行中におけるマネジメント不足も、トラブルの主要な原因になる恐れがあります。
たとえ前項で触れた精度の高い要件定義が実現できたとしても、時勢に順応するために仕様の見直しが必要となったり、想定よりも開発に手間取ってしまったりすることは少なくありません。そのような状況を大きなトラブルに発展させないためには、的確な視点と判断力によって開発現場を牽引するリーダーシップ力と、広い視野で全体の調整を図るマネジメント力が不可欠です。
技術力不足
要件を満たすシステムを開発するだけの技術力がそもそも不足しているために、トラブルが発生するケースもあります。
本来、システムの重要な意義はさまざまな課題をテクノロジーによって解決するところにあり、それを実現するのが開発エンジニアです。当然、開発エンジニアがテクノロジーを使いこなせなければ要件は満たせず、そのままプロジェクトを進めても、トラブルを呼び起こす品質の低いシステムができあがるだけとなってしまいます。
コミュニケーション不足
システム開発におけるコミュニケーション不足は、上述したあいまいな要件定義など、トラブルの火種となるさまざまな状況を呼び起こします。
普段から関係者間で密なコミュニケーションを図っていれば、想定外の事態が発生した際にも協力し合って迅速に対応できるなど、トラブルを防いでスムーズにプロジェクトを進めることが可能です。また、専門用語を多用せず、十分な知識がない人にも分かりやすい言葉で説明するといった配慮も重要でしょう。
開発手法がシステム内容と合っていない
トラブルを防ぎながら品質の高いシステムを開発するには、システムの内容と開発手法の相性が良いことも重要です。
例えば、ユーザーのフィードバックを受けながら長期に渡って改善を続けていくようなWEBアプリなどでは、アジャイル型の開発手法が向いているといわれます。にもかかわらず、経験が長く実績が豊富だからといってウォーターフォール型での手法にこだわるあまり、スケジュールの遅延や品質の低下を招いてしまっては、本末転倒といえるでしょう。
>>アジャイル開発のメリットとデメリットとは?開発会社へ依頼する際のポイントについても解説
実際に起きたシステム開発のトラブル事例5選
以下、実際に起きたシステム開発のトラブル事例を、厳選して5つ紹介します。
トラブル事例1:現場の意見を何でも取り込もうとした結果…
システム開発の要件を定めるために、実際に使用する現場ユーザーの意見に耳を傾けることは重要です。ただし、現場の声には、自らの立場と役割のみを考慮した、視野の狭い独りよがりな意見も多いことに注意しなければなりません。
とあるシステムの開発を進めていたA社では、現場の意見をすべてシステムに反映させようとしたところ、要件定義が膨大な規模になりました。予算も人的リソースも限られていたため、開発プロセスで大幅なスケジュール遅延が発生し、プロジェクトが頓挫してしまいました。
>>要件定義が失敗する原因は?6つの失敗事例から学ぶ対策を解説
トラブル事例2:とにかく早期のリリースにこだわるあまり…
B社では、これまでにない新規サービスを他社に先駆けて提供するため、システムの早期リリースを最優先課題としていました。そのため、新規サービスに不可欠となる市場検証もままならないまま、仮説と推測を基にした要件定義によってプロジェクトを進めました。
その結果、早期リリースは実現できたものの、全く市場に受け入れられないシステムとなり、多額の投資が無駄になったのです。特に、新規サービスを立ち上げる際には、十分な市場検証と綿密な要件定義が重要といえるでしょう。
>>システム開発の期間の目安は? 作業工程から短縮方法までわかりやすく解説
トラブル事例3:実績豊富なシステム開発会社への丸投げで安心していたが…
C社では、とあるシステムの構築を外部のシステム開発会社D社に依頼しました。D社はその分野で実績豊富な会社であったため、C社の担当者はプロジェクトの初期段階からほとんど介入することなく、いわば丸投げの状態で安心しきっていました。
しかしながら、納期間際に状況を確認したところ、ほぼ完成しているシステムの仕様が当初の思惑とは全く異なるものだったのです。不満を訴えるも、D社の責任者は「すべて任されていたはず」の一点張りで、交渉の余地がありませんでした。
トラブル事例4:非機能要件をなかなか満たせず…
E社では、AI(人工知能)を始めとする最新のテクノロジーを駆使した高度なシステムの構築を検討していました。そこで、技術力が高いと評判の外部システム開発会社F社に開発を依頼。要件定義などの上流工程を丁寧に行い、慎重にプロジェクトを進行しました。
ところが、F社でも初めて扱うテクノロジーが多かった上、メイン担当者の退職なども相まって、非機能要件(処理スピードやユーザビリティなど)の実現に想定外の時間を要してしまったのです。その結果、何度も開発スケジュールの見直しが発生し、納期も大幅に遅延することとなりました。
トラブル事例5:予期せぬエラーに振り回されて…
システム開発では、想定外の事態が発生しがちです。特に複雑な要件が絡み合うシステムでは、熟練エンジニアでも対応に難儀するような予期せぬエラーが頻発したりします。
G社では、H社から請け負ったシステムを開発していました。ところが、OS(オペレーティングシステム)に起因する予期せぬエラーが数多く発生し、その解消のために徐々に開発スケジュールが遅延していきました。納期が迫り、いよいよ間に合わないとなったところで発注元であるH社に相談したところ、「なぜもっと早い段階で情報を共有しなかったのか」と憤慨され、損害賠償を求められる事態にまで発展してしまいました。
>>その他システム開発の失敗事例はこちら
システム開発のトラブルを未然に防ぐためのポイント
システム開発のトラブルを未然に防ぐには、前掲の「システム開発で発生するよくあるトラブルの原因」で紹介したようなトラブルの原因を排除するのが有効です。具体的には、次の通りです。
- 要件定義を明確にする
- 的確なマネジメントを行う
- 十分な技術力があるシステム開発会社に依頼する
- 密なコミュニケーションを図る
- システム内容と合致した開発手法を採用する
以下、順に解説します。
要件定義を明確にする
システム開発の目的を始め、必要となる機能、性能、ユーザビリティなどの要件を可能な限り具体的に定めます。
的確なマネジメントを行う
プロジェクトの進捗管理はもちろん、トラブルなどのリスクに対する管理、システム性能といった品質に関する管理など、マネジメントすべき内容は多岐に渡ります。
十分な技術力があるシステム開発会社に依頼する
開発を外部に依頼する場合、過去の実績や得意分野を十分に確認の上、必ず複数のシステム開発会社を比較検討して依頼先を決定しましょう。システム内容によっては「高度な要件にも対応できるか」「最新のテクノロジーも扱えるか」といった条件も重要です。
密なコミュニケーションを図る
密なコミュニケーションによって、課題や問題の早期把握と迅速な対策を心掛けましょう。また、的確なコミュニケーションは、要件や仕様の認識相違を防ぐことにもつながります。
システム内容と合致した開発手法を採用する
昨今は多くのプロジェクトでアジャイル型の開発手法が採用されていますが、ウォーターフォール型が悪いというわけではありません。重要なのは、開発するシステムの内容に合致しているかどうかです。
システム開発のトラブル発生時に取るべき初動対応
もしも、システム開発においてトラブルが発生した際には、初動対応が重要です。
まずはトラブル事象の全容を把握し、影響範囲を特定しましょう。次に、開発を請け負っているベンダーであれば依頼元へ、社内プロジェクトであれば上層部へエスカレーションするなど、状況に応じてしかるべき関係者と情報を共有します。一定の被害が予想される場合は、その拡大を防ぐために、一時的な対応や回避策を検討することも大切です。
これらの対応は、すべて迅速に実施しなくてはなりません。そのためには、普段からトラブル発生時の体制やフローを確立しておくこともポイントです。
システム開発のトラブルに関するよくある質問
以下、システム開発のトラブルに関するよくある質問とその答えを紹介します。
Q.トラブルにならないための要件定義とはどのようなものか。
A.要件定義は、システムを使用するユーザー側(発注者や現場部門)と、構築を担当する開発側(受注者やシステム部門)が協力して行うべきであるといえます。トラブルを防ぐためには、丁寧なコミュニケーションによって両者の認識を合わせ、システムに必要となる内容を明確かつ具体的に記載した「要件定義書」を作成することが重要です。
また、要件定義書は、「業務要件」「機能要件」「非機能要件」に分けて記載の上、それぞれについてイメージ図なども活用しながら、高度な専門知識がなくても理解できるようなものにする必要があります。
なお、上述の通り要件定義はユーザー側と開発側が協力して行うべきものですが、要件定義に重大な不備があった場合、開発側がユーザー側に対して損害賠償の責任を負うこともあります。
Q.外部のシステム開発会社に開発してもらったシステムの品質があまりにも低いので、費用の支払いを拒否することは可能か。
A.品質が低いなど、システムが合意した仕様を満たしていないことを「瑕疵」といいますが、システム開発会社は迅速な補修や代替措置などによって瑕疵担保責任を回避できる可能性があります。この場合は、費用を支払う必要があるといえるでしょう。
一方で、システム開発会社がユーザー側の指摘に応じず、合意した仕様を満たさない状態が長く続く場合には、瑕疵担保責任が発生し、ユーザー側は費用の支払いを拒否できることもあります。いずれにせよ、まずはITに精通した弁護士に相談し、指示を仰ぐことが重要です。
まとめ
システム開発のトラブルを防ぐには、要件定義不足・マネジメント不足など、どのような状況がトラブルの原因になり得るかをあらかじめ把握し、これらを回避しながらプロジェクトを進めることが重要です。
また、多くのトラブルは、的確なマネジメントの実施とともに、関係者の密なコミュニケーションによって防止できることも意識しておくと良いでしょう。
さらに、外部の専門会社にシステム開発を依頼する場合は、十分な実績と技術力を持つ会社を選定することはもちろん、決して丸投げはせず、定期的に情報を共有し、状況を確認することをおすすめします。システム開発のトラブルを未然に防ぐためには、最初の要件整理から開発・テスト・運用保守までを一貫して伴走できる体制が欠かせません。
当社フレシット株式会社では、要件定義フェーズからエンジニアが直接参画し、業務課題や現場の実情を丁寧に整理したうえで、フルスクラッチ(オーダーメイド)で最適なシステムを構築します。
「伝わっていなかった」「想定していなかった」といった認識のズレを防ぐため、開発過程でも定期的なレビューや成果物の共有を徹底。お客さまと同じ視点で課題を捉え、トラブルの起きにくい堅牢な開発体制を実現しています。
もし、「過去の開発で苦い経験をした」「今のシステム開発会社に不安がある」とお感じでしたら、ぜひ一度フレシット株式会社へご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
監修者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田 順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

