DOWAのアルムナイ採用にみる「自社文化のデジタル化」──SaaSでは描けない内製ポータル・コミュニティ開発の実践論
自社文化を体現するデジタル基盤の構築戦略。
2025-10-13
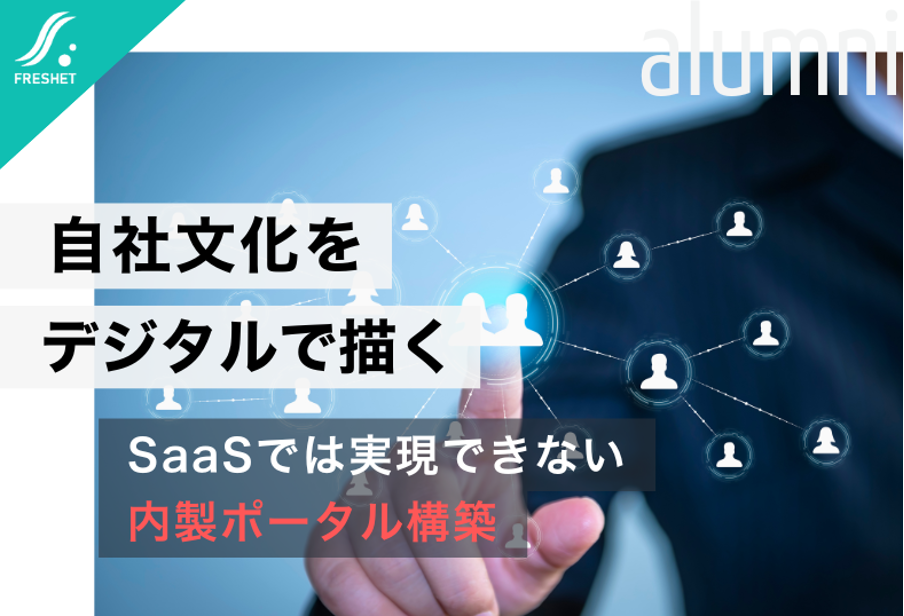
DOWAホールディングスが退職者(アルムナイ)と現役社員をつなぐコミュニティサイトを開設しました。この取り組みの本質は、単なる採用施策ではなく、企業文化そのものをデジタル空間で再構築する試みといえます。
多くの企業がSaaSを導入して業務効率化を進める一方で、「自社らしさ」や「独自の文化」をどうデジタル上で表現するかという課題が浮かび上がっています。
本コラムでは、SaaSでは実現しづらい“文化のデジタル化”をテーマに、内製ポータルやコミュニティサイトの構築戦略をフルスクラッチ開発の観点から解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】DOWA、DXで退職者とのつながり再構築──アルムナイ制度をデジタルで推進
DOWAホールディングスは、退職者(アルムナイ)を対象とした再雇用制度を正式に導入し、現役社員と退職者が交流できるオンラインコミュニティを開設した。DXを活用し、チャット機能や社内ニュース配信を通じて「緩やかなつながり」を維持する仕組みを構築。人手不足への対応に加え、退職者が社外で培った知見を新事業やイノベーション創出に生かす狙いがある。デジタル基盤による継続的な関係構築は、人的資本の循環活用を支えるDX戦略の一環といえる。
出典:日本経済新聞「DOWAが退職者採用現役社員との交流サイトも」2025年10月7日付朝刊
ポイントをひとことで
企業文化を「デジタルで表現する」という視点は、DXの中でも最も難易度が高く、同時に本質的なテーマです。多くの企業が効率化に偏りがちな中で、自社の理念や行動様式を仕組みに落とし込むことこそが、真のデジタルトランスフォーメーションといえます。フルスクラッチ開発は、機能の自由度以上に「思想の再現性」に価値があります。つまり、システムをつくることは“自社らしさを再設計する行為”であり、文化を未来へ継承するための最も実践的な経営手段なのです。
SaaSの限界──文化は「機能」では再現できない
SaaS(クラウド型サービス)は、導入が容易でコストを抑えられる点が魅力です。勤怠管理、社内チャット、プロジェクト管理など、一定の業務プロセスを効率化するには非常に有効な選択肢です。
しかし、SaaSはあくまで「汎用的な仕組み」であり、他社と同じ設計思想・同じUI(ユーザーインターフェース)で動くことが前提となります。そのため、企業が長年培ってきた文化や価値観を反映させようとすると、機能的・構造的な制約に直面します。
たとえば、社内のコミュニケーション文化を重視する企業では、「雑談から生まれるアイデア」をどうデジタルで再現するかが重要です。しかし、既製の社内SNSや掲示板機能では、自由度が低く、運用者が意図する“温度感”を保つことが難しくなります。文化を継承し、社員や退職者を含めた「つながり」を育むためには、システムそのものを“自社の価値観”に合わせて設計する必要があります。
「自社文化のデジタル化」とは何か
「自社文化のデジタル化」とは、単に紙の業務をオンライン化することではありません。
それは、企業が大切にしている行動原則・価値観・判断基準を、デジタルの仕組みの中に埋め込むことを意味します。たとえば、組織の中で「挑戦を歓迎する文化」があるならば、社内ポータルには“挑戦の記録”や“失敗からの学び”を共有できる仕組みを設ける。あるいは「個々の貢献を見える化する文化」であれば、評価制度やナレッジ共有の仕組みに「感謝の可視化」機能を組み込む。
このように、システム設計そのものが文化を体現する場になります。既製のSaaSでは、企業固有の価値観を細部まで反映させることは困難です。したがって、文化をデジタル上で表現しようとする企業ほど、フルスクラッチによるシステム構築を検討する価値があります。
フルスクラッチ開発がもたらす「文化表現の自由度」
フルスクラッチ開発の最大の特徴は、“自由度”にあります。
設計段階からUI、データ構造、アクセス権限、通知の仕組みまで、すべてを自社仕様に合わせて構築できます。たとえば、ある製造業では、現場と管理部門の情報格差が課題となっていました。
既製の社内ポータルを導入したものの、現場の声が反映されず、形骸化していたのです。
そこで、フルスクラッチで「現場が投稿しやすい構造」と「経営層が閲覧したくなるデータビジュアル」を融合した独自ポータルを開発。結果として、日報の投稿率が向上し、現場から経営へのフィードバックループが生まれ、経営判断のスピードが大幅に改善しました。このように、フルスクラッチ開発は単なる業務効率化の手段ではなく、企業文化をシステムに“翻訳”するプロセスなのです。
社内ポータルは「文化の鏡」
社内ポータルは、情報を一元管理するだけの場所ではありません。そこには「何を共有し、どのように伝えるか」という企業の哲学が表れます。たとえば、トップダウン型の企業では「経営メッセージをいかに浸透させるか」が焦点となり、双方向性よりも整然とした構造が求められます。
一方、ボトムアップ型の企業では、社員同士の発信を促進するUIや、リアクションを可視化する仕組みが重要です。このような文化的特性を踏まえて設計するには、既存ツールのカスタマイズでは限界があります。ポータルを単なる情報置き場ではなく、「文化を伝える装置」として再設計することが、DX時代の内製開発の本質です。
コミュニティ開発がもたらす「文化の持続性」
DOWAホールディングスのように、退職者と現役社員をつなぐコミュニティを構築する動きは、企業文化の持続性という観点から極めて重要です。企業の価値は、社員が培ってきた知見や人間関係の中に宿っています。それを「退職=喪失」とせず、デジタルコミュニティによって知の循環を保つことができれば、文化は社内外を越えて広がります。
このようなコミュニティを設計する際には、以下のような点が鍵となります。
- 文化的文脈を理解した設計:単なる情報共有ではなく、「なぜ関わりたいのか」「何を共有したいのか」という動機設計が必要。
- 心理的安全性の確保:社内・退職者・外部パートナーなど、立場の異なる人が安心して交流できる認証・権限設計。
- 更新が続く仕組み:コミュニティが形骸化しないよう、コンテンツ運営やインセンティブ設計をシステム側で支援。
こうした配慮を、業務プロセスやデータ構造の設計段階から組み込めるのが、フルスクラッチ開発の大きな強みです。
「効率化」ではなく「文化の継承」
DXという言葉は、しばしば「業務効率化」や「コスト削減」と同義に語られます。
しかし、DXは、企業が培ってきた価値観や文化を、次の時代にも機能する形に変換する方法でもあります。その意味で、「自社文化をどうデジタル化するか」は、検討に値するテーマであると思います。
デジタルは、文化の“伝達媒体”ともなりえます。組織に根付く信念や行動様式を正しくデジタル上に移植できたとき、DXは“人と文化の進化”の仕組みとして成功します。
まとめ
SaaSの普及によって、企業は容易にデジタル化を進められるようになりました。
しかし、そこに「自社らしさ」をどう残すかという問いは、今なお未解決のままです。
DOWAホールディングスのように、人と文化のつながりを再設計する動きは、DXの本質を突いています。効率化ではなく、「文化をどう残し、どう育てるか」。それをデジタルの力で実現するためには、フルスクラッチによる内製ポータル・コミュニティ開発が有効な選択肢の一つとなるでしょう。
自社の文化や価値観をシステムの中で表現するには、単なる機能の組み合わせではなく、「なぜこの仕組みが必要なのか」を一緒に考え、ゼロから設計する視点が欠かせません。フレシット株式会社では、業務効率化だけでなく、組織の思想や文化を反映した“使われ続ける仕組み”をフルスクラッチで開発しています。汎用ツールでは実現できない「自社らしさ」をデジタルの形にしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の想いを、最適なシステムとして共に描いていきます。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

