システム統合の影響拡大を防ぐ鍵は“分散と制御”──統合基幹システムに潜むリスクとフルスクラッチによる解決法
統合の裏に潜む“リスクのドミノ”をどう断ち切るか
2025-10-19
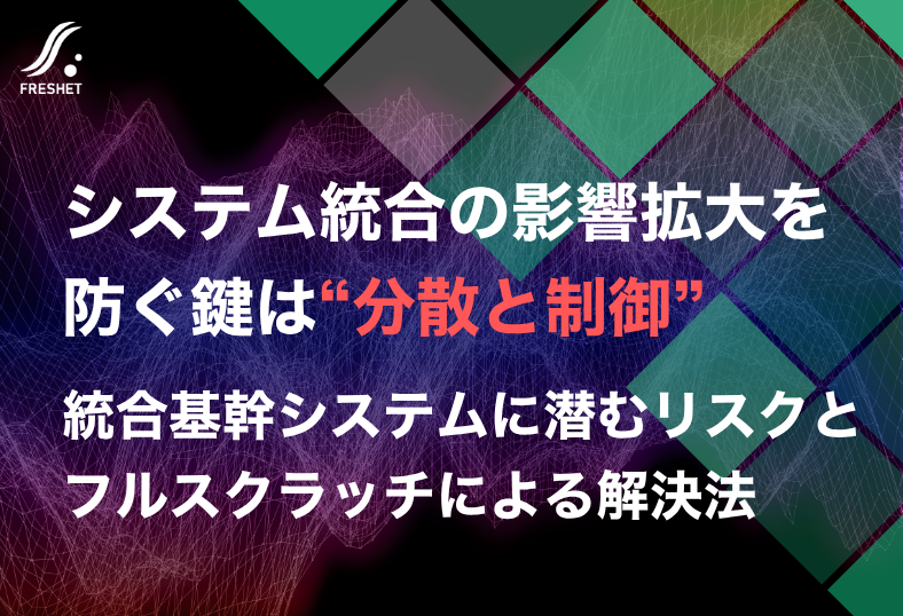
企業の基幹システムをひとつに統合する動きが広がる中で、障害やサイバー攻撃による影響が一気に全社へ波及する事例が相次いでいます。ERP(統合基幹業務システム)は効率化を実現する一方、システムが巨大化すればするほど、ひとつの不具合が事業全体を止めてしまうリスクを孕みます。
本コラムでは、最近のトラブル事例を踏まえながら、被害を最小限に抑えるための「分散と制御」の考え方、そしてフルスクラッチ開発によるリスクマネジメント手法について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】アサヒGHD、システム統合の影響でサイバー被害が拡大
アサヒグループホールディングスはランサムウエア攻撃を受け、国内の受注・出荷やコールセンターが停止した。企業のDX戦略として進む基幹システムの統合は効率化をもたらす一方、一度の攻撃が全社に波及するリスクを高める。食品業界では特に複雑な在庫・流通管理のため大規模システム化が進んでおり、被害拡大の要因となる。グリコの長期障害やHOYA、KADOKAWAの事例も示すように、統合システムは脆弱性を抱えやすく、復旧が長期化すれば巨額の損失につながる。攻撃侵入の早期検知や通信制御、頻繁なバックアップ、予備システムを前提としたBCP策定が不可欠である。
出典:日本経済新聞「サイバー防御DXに死角アサヒGHD、複数部署に被害 システム統合で影響拡大」2025年10月3日付朝刊
ポイントをひとことで
統合基幹システムは効率化の象徴である一方、障害が発生すれば全社停止に直結する構造的リスクを抱えています。システムを一本化することは、経営情報を整理する利点がある反面、「止まる時はすべてが止まる」という弱点を内包します。重要なのは、統合と分離を両立させる設計思想です。分散構造を前提にしたフルスクラッチ開発であれば、影響範囲を限定しながらも業務全体の整合性を保つことができます。効率化よりも“制御性”を重視した設計こそ、安定運用の鍵です。
統合基幹システムがもたらす効率化と脆弱性
多くの企業がERPを導入する理由は、業務全体を一元的に管理できる効率性にあります。販売、在庫、会計、人事といった各領域がリアルタイムで連携し、データの整合性を確保することが可能になります。経営判断を迅速化し、属人的な作業を削減できる点は大きなメリットです。
しかし、同時に「全社がひとつのシステムに依存する」という構造的リスクが生まれます。統合システムは便利である反面、障害が発生すれば全業務が一斉に停止する可能性があります。さらに、ランサムウエアなどのサイバー攻撃を受けた場合、被害が全社に波及する危険性も高まります。効率化とリスクは表裏一体なのです。
実際に起きたシステム障害の波及例
2024年から2025年にかけて、国内外で基幹システム障害による大規模トラブルが相次ぎました。
食品メーカーの例では、老朽化したシステムをERPへ刷新する過程でトラブルが発生し、製造・出荷が数カ月にわたり停止。冷蔵食品や日配品の欠品が相次ぎ、数十億円規模の損失が発生しました。
また、光学機器メーカーや出版関連企業でも、サイバー攻撃を受けて基幹システムが暗号化され、出荷や受注が長期間止まる事態となりました。
これらの共通点は「統合システムの集中化」です。ひとつの障害が全体の停止につながり、復旧にも時間とコストが膨大にかかる。まさに「効率化が裏目に出る」構造といえます。
なぜ障害が“全社規模”に広がるのか
システム統合の本質的な課題は、「すべてをひとつの基盤で動かす」という設計思想にあります。ERPを中核に据える場合、販売管理・生産管理・在庫管理・会計といった複数機能が密接に結合します。
そのため、どこか一つのモジュールで障害が起きると、他の機能が連鎖的に動作不能になります。さらに、データベースや通信基盤が共通化されているため、障害がシステム全体に波及しやすい構造となっているのです。
たとえハードウェアの冗長化やクラウド環境を導入していても、論理的な構造が単一化されていれば「障害の伝播」は避けられません。効率的な統合ほど、同時にリスクの集中を生むというジレンマが存在します。
分散設計という“リスク回避の哲学”
障害の波及を防ぐためには、「分散」と「制御」を意識したシステム設計が欠かせません。
分散設計とは、システム全体をひとつの巨大な仕組みとして構築するのではなく、業務領域ごとに独立性を持たせながら連携させるアプローチです。たとえば「販売」「会計」「在庫」を独立したモジュールとして設計し、APIや専用インターフェースで必要なデータだけをやり取りする構造にすることで、障害発生時の影響範囲を限定できます。
こうした考え方は、単なる冗長化とは異なります。冗長化が「同じ機能を二重に持つこと」であるのに対し、分散設計は「異なるシステム同士の依存度を下げること」です。これにより、障害時の切り離しや復旧が容易になり、業務停止の範囲を最小限に抑えられます。
フルスクラッチ開発が“分散と制御”を実現できる理由
フルスクラッチ開発の最大の強みは、システムを“目的から逆算して設計できる”点にあります。既製のERPパッケージは汎用性を重視するため、機能同士の結合度が高く、柔軟な分離が難しい構造です。一方、フルスクラッチ開発では業務フローやデータ構造をゼロから設計できるため、「どの機能をつなぎ、どこを独立させるか」を戦略的に決めることが可能です。
例えば、在庫管理システムをフルスクラッチで構築し、販売システムとはAPI連携のみで接続する形にすれば、販売側の障害が在庫側に波及するリスクを防げます。また、個別の業務に合わせたセキュリティレベルを設定できるため、重要データの保護も強化されます。
つまり、フルスクラッチ開発は「システムの自由度」そのものを確保する手段であり、分散設計と制御構造を実現する最適解といえます。
【関連記事】
在庫管理システム開発 完全ガイド|開発費用や成功のポイントなどを解説
統合と分離の“バランス設計”が鍵
分散型アーキテクチャの導入は、単にシステムを分ければ良いという話ではありません。過度な分離は情報の断絶を生み、業務効率を損ないます。重要なのは、どこを統合し、どこを独立させるかを見極める「バランス設計」です。
経営判断に必要な情報は一元管理しつつ、現場業務においては独立性を保つ。このように「統合と分離を使い分ける設計思想」こそが、安定稼働と柔軟性を両立させる鍵です。フルスクラッチ開発であれば、このバランスを事業構造や組織体制に合わせて最適化できます。
まとめ
基幹システムの統合は企業の成長を支える一方で、障害や攻撃による全社停止リスクを高める側面を持ちます。効率化を追求するだけではなく、分散と制御の視点からリスクを抑える設計が求められます。
フルスクラッチ開発は、統合の恩恵を活かしながらも影響範囲をコントロールできる柔軟な設計を可能にします。システムを単なる道具ではなく、事業継続性を支える“戦略的インフラ”として位置づける視点こそが、DX時代の安定した成長を実現する鍵となるでしょう。
統合と分散の最適なバランスを見極めるには、業務理解とシステム設計の双方に精通した開発パートナーが欠かせません。フレシット株式会社では、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発により、事業特性やリスク許容度に応じた柔軟なアーキテクチャを設計します。既存パッケージでは実現しづらい「分散と制御」を両立させ、将来の拡張性や安定稼働を見据えたシステム構築をご支援いたします。効率化と安全性の両立を目指す際は、ぜひ当社にご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

