スズキに学ぶ“第三者の視点”の力──外部システム開発会社が見抜く、社内では気づけない課題
社内常識を相対化することで、システムを本質から磨き直す。
2025-10-15
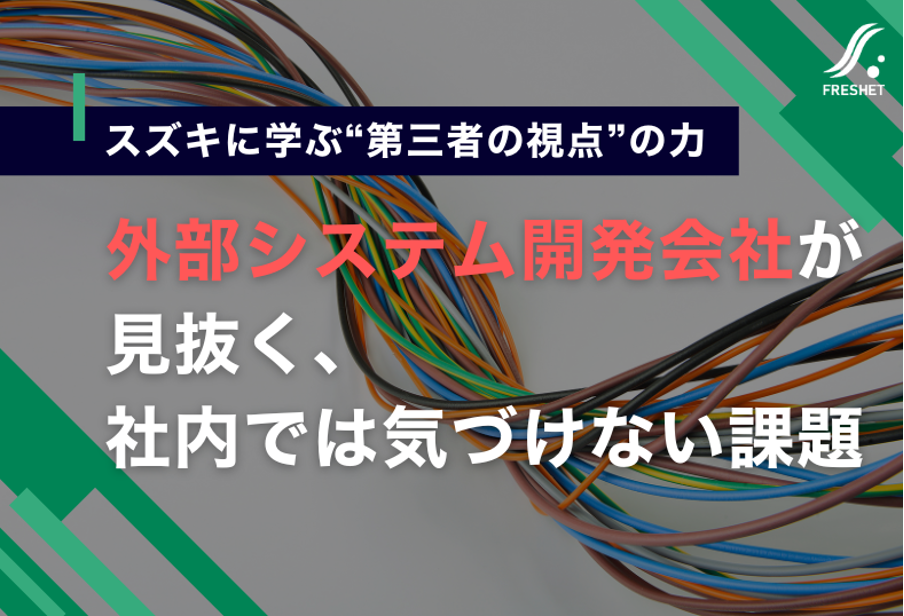
長年使ってきたシステムや業務フローは、“慣れ”によって非効率を見過ごしてしまうことがあります。
しかし、外部のシステム開発会社が関わることで、社内の前提や思い込みを客観的に見直し、業務全体を根本から改善できるケースがあります。
本コラムでは、第三者の視点がもたらす「気づきの力」に焦点を当て、外部開発パートナーが果たす役割や、社内では見落としがちな課題を浮き彫りにします。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
【関連記事】
システム開発は外注 or 内製?担当者が知るべきメリットやデメリット、外注先の選び方を解説
目次
【記事要約】異業種の視点が生んだ「気づき」──スズキが家電メーカーから得た新たな発見
スズキは軽量化プロジェクト「Sライト」で、異業種との交流を通じた技術革新を進めている。家電メーカーを訪問し軽自動車「アルト」を見せた際、「電線が多くないか」という指摘を受け、同社技術陣は驚いた。自動車業界では当たり前とされていた設計も、他分野の専門家には異質に映る。所属する業界や企業が異なれば、視点や「許容範囲」の基準が違うのは当然であり、そうした多様な視点からの率直な意見は、企業の“常識”を見直す契機となる。スズキは今後も異業種との対話を継続し、新たな気づきを技術進化へとつなげていく考えだ。
出典:日経クロステック/日経Automotive「スズキが驚いた異業種からの指摘、アルト『電線多くないか』」2025年9月17日
ポイントをひとことで
システム開発において、社内の慣習や思い込みは最も厄介な“見えない制約”です。長年の運用で築かれた前提は、時に非効率を正当化し、改善の芽を摘み取ります。第三者である外部のシステム開発会社が入ることで、業務フローを客観的に再定義でき、構造的な課題を発見できます。つまり、外部の視点は単なる監修ではなく、組織が見落としてきた「思考のアップデート装置」。慣れの壁を越えた時、システムも組織も一段進化します。
社内システムに潜む「慣れ」という落とし穴
多くの企業で長年使われている業務システムには、利用者の「慣れ」が深く根付いています。業務担当者が毎日同じ操作を繰り返すうちに、「使いづらいけれど仕方ない」「本当はもっと効率化できるが、手順が決まっているから」という意識が定着してしまうのです。
この“慣れ”は、見方を変えれば組織の文化でもあります。しかし、システムを刷新しようとするとき、それが最大の障壁になります。既存の仕組みを前提に考えると、根本的な改善案が出てこないからです。
外部のシステム開発会社が入ることで、この固定観念を一度リセットできます。第三者の目線は「なぜこの手順なのか」「このデータの流れは必要なのか」といった、社内では“当たり前”と思われていた部分に疑問を投げかけます。そこから、新しい業務設計や効率化の糸口が見えてくるのです。
「仕様」が組織の思い込みを映す
システム開発の現場では、「仕様」という言葉が頻繁に使われます。しかし、その仕様は必ずしも“最適”ではありません。むしろ、「過去のやり方を踏襲しただけ」というケースも多いのです。
社内でシステムを作る場合、担当者は既存業務に詳しい一方で、その業務が「本当に今の時代に合っているか」を客観的に検証するのは難しいものです。結果として、現場の声をそのまま反映した“属人的な仕様”が増え、複雑でメンテナンスしにくいシステムができあがります。
外部のシステム開発会社は、複数業界のプロジェクトを通じて多様な仕様や運用フローを見てきた経験があります。そのため、他社ではどのように同じ課題を解決しているのか、どんな技術設計が主流かといった知見を持っています。この「比較の視点」こそが、社内だけでは得られない強みです。
第三者によるレビューを受けることで、自社の仕様がどれほど特殊なのか、どこに改善の余地があるのかが明確になります。
外部のシステム開発会社がもたらす“構造的な気づき”
外部のシステム開発会社が介入する最大の価値は、単なる「設計・開発スキル」ではありません。本質は、“構造的な気づき”を与えてくれる点にあります。
たとえば、システムを刷新するときに「なぜこのデータを二重で入力しているのか」と問われて初めて、部門間でデータが連携されていないことに気づく。あるいは、「なぜこの処理は手動なのか」と問われて、既存ルールが自動化を妨げていたことが明らかになる。社内メンバーだけでは見過ごしてしまう非効率やリスクを、第三者の視点が浮き彫りにするのです。
また、システム開発会社は問題を技術的な構造に置き換えて捉える力を持っています。業務上の違和感を「データ設計」や「UI/UXの導線」といった形に翻訳し、解決策として提示できる。これが、単なる外注ではなく“開発パートナー”としての価値です。
「社内の声」と「外部の知見」をどう融合させるか
第三者の視点を最大限に活かすためには、社内の現場の声と外部の知見をバランスよく融合させることが重要です。現場の担当者は、自社の業務に関するリアルな課題を最も理解しています。
一方で、外部のシステム開発会社は、多業種にまたがる開発経験をもとに“他社ではどうしているか”を知っています。この2つの視点を対話によって掛け合わせることで、「本当に使えるシステム」が生まれます。
要件定義フェーズで、外部のシステム開発会社が積極的に現場ヒアリングを行うと、業務の流れやボトルネックが可視化され、社内だけでは整理しきれなかった課題が浮き上がります。その上で、現場の声をベースにしたシステム設計を行うと、納得感の高い開発が実現します。
つまり、第三者の関与とは“社内を否定すること”ではなく、「自社の強みを正しく引き出すための鏡」として機能するのです。
内製化では得られない“改善の再現性”
近年では、内製化を進める企業も増えています。確かに、スピードやコントロールの観点ではメリットがありますが、リスクも存在します。
内製チームは自社業務に特化しているため、同じメンバー・同じ思考の枠組みの中で議論が進みがちです。その結果、改善のアイデアが“過去の延長線上”に留まり、抜本的な改革にはつながりにくいことがあります。
一方、外部のシステム開発会社は、さまざまな業界・技術領域での成功・失敗事例を蓄積しています。
その知見をもとに、業界特有の常識を相対化し、別業種のアプローチを応用することができます。
この「再現性のある改善サイクル」を取り込むことで、システム開発は単なる刷新ではなく、継続的な最適化へと進化します。
外部レビューを取り入れることが“リスク回避”につながる
第三者の視点は、品質保証やリスク管理の観点でも非常に有効です。
開発が進む中で、仕様の肥大化や要件の曖昧化が起きるのはよくあることです。社内メンバーだけでは、どこまでが必要でどこからが過剰なのか判断が難しい場合もあります。
外部のシステム開発会社が関わると、客観的な立場から「それは本当に必要か」「別の方法で解決できないか」と建設的な議論を行うことができます。これにより、不要な機能追加やスケジュール遅延、コスト膨張といったトラブルを未然に防げます。
さらに、第三者によるレビューやセカンドオピニオンを仕組み化しておくことで、システム開発の品質は安定し、プロジェクト全体の透明性も高まります。
>>システム開発のセカンドオピニオンをお考えの方へ!第三者視点の重要性を解説
まとめ:外部の目がシステムを成長させる
第三者の視点は、単に「外部からのチェック」ではなく、自社の課題を客観的に再定義し、業務全体の構造を磨くための“触媒”です。長年の慣習や業務の癖は、内部の人だけではなかなか気づけません。
しかし、外部のシステム開発会社が関わることで、当たり前と思っていた前提が見直され、システムはよりシンプルで、本質的な形へと進化していきます。社内で積み上げてきた経験に、第三者の視点を加える。それは、システムだけでなく、組織の思考をアップデートする第一歩でもあります。
フルスクラッチ開発の価値は、「既存をなぞる」ことではなく、「自社の強みを最大限に引き出す」ことにあります。当社フレシット株式会社は、業務整理や課題抽出の段階から伴走し、外部の視点で“気づきを設計に変える”ことを得意としています。業界横断の開発実績と提案力をもとに、業務の本質を見極め、柔軟かつ拡張性のあるシステムをゼロから構築します。
自社の仕組みを改めて見直し、「今の業務に最も合う形」を実現したいとお考えの方は、ぜひ一度フルスクラッチ開発の可能性をご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

