IT子会社再編の動きに学ぶ──“夢物語”を現実に変える外部チームの力とは
外部なのに社内みたいに動く。そんな開発チーム、ありますか?
2025-10-16
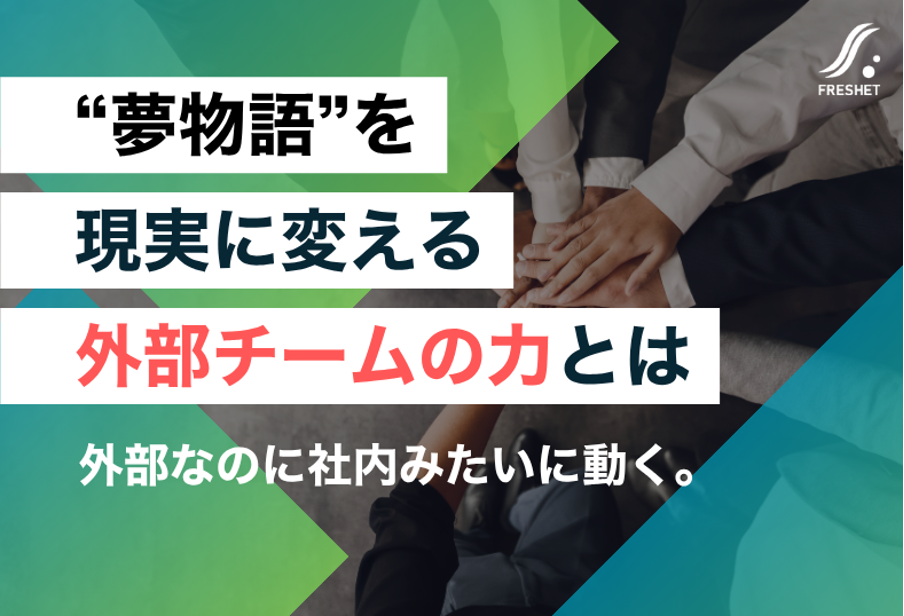
三井住友信託銀行や東洋紡など、多くの大手企業がIT子会社を本体に吸収する再編を進めています。その背景には、「ビジネスとITの分断では変化に追いつけない」という危機感があります。
ただし、現場に技術とビジネスの両方を理解する人材を揃えることは容易ではありません。社内だけで完結しようとすると、人的リソースや専門性に偏りが生まれ、スピードや柔軟性を損ねてしまうケースも少なくありません。
本コラムでは、企業が内製化を進める中で直面する課題と、それを補う外部のフルスクラッチ開発チームの役割について解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
【関連記事】
システム開発は外注 or 内製?担当者が知るべきメリットやデメリット、外注先の選び方を解説
目次
【記事要約】IT子会社の吸収合併が進む理由──三井住友信託銀行・みずほFG・東洋紡の共通点
企業のデジタル戦略を加速するため、大手企業がIT子会社を本体に吸収する動きが広がっている。三井住友信託銀行は約1000人規模のIT子会社を統合し、ビジネスとITを一体化。スピードと実行力の両立を狙う。みずほフィナンシャルグループも2026年にIT子会社を吸収予定で、開発内製化と迅速な意思決定体制の構築を進めている。東洋紡も2023年にIT子会社を統合し、無駄な外注を削減。社員の意識変化やコスト削減など効果が表れている。共通するのは「ITを経営の中枢に据える」方針であり、外部委託型から自前体制への転換が加速している。
出典:日経クロステック/日経コンピュータ「IT子会社を着々と本体に『取り込む』大手、三井住友信託銀行や東洋紡の決断理由」2025年10月6日
ポイントをひとことで
多くの企業がIT子会社を吸収する動きの背景には、ITを「外部委託の対象」から「経営の中枢」に戻す流れがあります。しかし、内製化を進めても技術とビジネスの両方を理解する人材が不足すれば、理想と現実の乖離が起こります。その隙間を埋めるのが、ビジネス理解を持つ外部フルスクラッチ開発チームの存在です。彼らは実現可能なシステム設計を通じて、夢物語ではなく“動く仕組み”に変える力を持つ。内製と協働のバランスが、これからの開発の鍵になるでしょう。
内製化の限界──「技術とビジネスをつなぐ人」が不足している
多くの企業が「IT子会社の吸収」を選ぶ理由のひとつは、技術と業務が切り離された体制への反省です。かつてのように、事業部門が企画を立て、IT部門が指示を受けて開発する“分業型モデル”では、スピードも柔軟性も確保できません。
しかし、組織を統合したとしても、すぐに理想的な一体化が実現するわけではありません。三井住友信託銀行のように、「技術とビジネスの両方を理解する人材」を増やすには、長期的な育成が必要です。
実際には、現場で意思決定を担う担当者の多くが、「技術的に実現可能かどうか」を判断できないままプロジェクトを進めてしまうことがあります。その結果、要件が曖昧なまま開発が進行し、実装段階で手戻りが発生する――こうした構造的な問題が、いまだ多くの企業で繰り返されています。
内製化は理想的な方向性である一方、「即戦力として技術知見を持つ人材を確保できない」という現実的な壁が存在するのです。
外部チームを“協働パートナー”として組み込むという選択肢
このような状況で注目されているのが、外部のシステム開発会社を“外注”ではなく“協働パートナー”として迎え入れるアプローチです。単なる発注関係ではなく、ビジネス側の戦略を理解しながら技術的な選択肢を共に検討できるチームを持つことが、内製化とスピードの両立を実現します。
特にフルスクラッチ(オーダーメイド)開発を得意とする開発会社は、パッケージや既存SaaSに依存せず、業務フローやデータ構造を一から設計できます。これにより、企業固有の業務や意思決定プロセスを損なわずにシステム化でき、組織全体の柔軟性を高めることができます。
外部チームを“社内の一部”として巻き込み、コミュニケーション・ツールなどを通じて同じプロジェクト環境で議論を重ねることで、実質的な一体運営が可能になります。内製化を進めながらも、経験豊富な外部メンバーの知見を組み合わせることで、最小限のリソースで最大の成果を生むことができるのです。
「翻訳者」としての外部チームの価値
ビジネスと技術の間には、しばしば“翻訳の壁”が存在します。経営層や事業部門が描く構想を、技術的に落とし込む過程で誤解や曖昧さが生まれ、開発現場ではそれを実装レベルに変換できずに手戻りが発生する――そんな状況は珍しくありません。
フルスクラッチ型の開発会社は、こうした「翻訳者」の役割を担います。業務要件を聞き取りながら、技術的制約やリスクを明確に伝え、「どこまで実現でき、どんなリスクがあるか」を論理的に説明する。その上で、現実的な実装プランを提示できるのが、最大の強みです。
つまり、外部チームがプロジェクトに参加することで、ビジネスの“夢物語”が現実的なシステム仕様へと変換されるのです。内製チームが見落としがちなリスクや技術的な制約を早期に可視化し、プロジェクト全体の再現性と成功確率を高める役割を果たします。
属人化を防ぎ、ナレッジを残す仕組み
外部の開発会社を活用する際に懸念されるのが「ノウハウが社外に流出する」リスクです。しかし、フルスクラッチ開発に強い企業では、開発ドキュメントや仕様書、コード規約などを整備し、プロジェクトの知見を形式知化する仕組みを備えています。これにより、外部チームが離れた後も社内メンバーが保守や改修を続けられる状態を維持できます。
属人化を防ぎ、知識を社内に残す設計思想こそが、“本質的な内製化”の第一歩です。外部の力を借りながらも、自社の中にスキルと仕組みを根付かせることができるのです。
スピードと柔軟性を両立する“ハイブリッド型”体制
みずほフィナンシャルグループが語るように、もはや「3年かけて構築するシステム」では時代に合いません。市場や顧客の要望は常に変化し、業務プロセスも半年単位で見直しが求められます。
フルスクラッチ型の外部チームを取り入れることで、要件定義から開発・改修までを短いスパンで回し、反復的に改善できる体制を構築できます。スピード感を持ちながらも、自社独自の仕様や品質基準を守る――それがハイブリッド型体制の最大のメリットです。
特に、クラウド環境やマイクロサービス構成のような現代的なアーキテクチャに対応するには、こうした柔軟性の高い開発パートナーとの協働が不可欠です。
「ノー」と言える開発チームが品質を支える
東洋紡の事例にも見られるように、システム開発の世界では“依頼されたものをすべて引き受ける”姿勢がかえってコストを増やす場合があります。外部チームが単なる受託者ではなく、「その仕様で本当に効果があるのか」「投資に見合う成果が出るのか」を冷静に判断できる存在であることが、長期的な信頼関係を築くうえで重要です。
システム開発会社が、依頼された内容をただ実装するのではなく、時には“ノー”を提示しながらより良い代替案を提案できる関係。それこそが、共創型の開発パートナーとしての理想形です。
まとめ
IT子会社を本体に統合する企業が増える背景には、「ITを経営の中枢に取り戻す」という共通の目的があります。しかし、内製化を進めるだけでは「技術とビジネスの両方を理解する人材」の不足という課題は解消できません。だからこそ、外部のフルスクラッチ開発チームを“外注先”ではなく“協働パートナー”として組み込むことが、現実的かつ効果的な選択肢となります。
フルスクラッチ開発は、単にオーダーメイドであるというだけでなく、企業独自の思考やスピードをシステムに反映できる唯一の手段です。ビジネスを理解し、技術を使って現実に変える外部チームの存在が、これからのDXを支える大きな力となるでしょう。
フルスクラッチ開発は、単なる受託ではなく、企業の思想や現場のリアルを形にする共創のプロセスです。既存システムやパッケージに合わせるのではなく、「自社らしい仕組み」を一から設計することで、ビジネスの変化に即応できる柔軟な体制が生まれます。
フレシット株式会社では、業務理解と技術設計の両面から伴走し、要件整理から実装・運用まで一貫して支援します。貴社チームと日々の対話を重ね、単なる外注ではなく“同じチームの一員”として課題を解決していく。そうした「現場と一体で動く開発」を通じて、理想を現実に変えるシステムづくりをお手伝いします。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

