鴻池運輸のクラウド移行に学ぶ──「止まらないDX」を実現する現実的な経営判断とは
止めないDX、動かしながら変えていく――“クラウドリフト”という現実解
2025-10-17
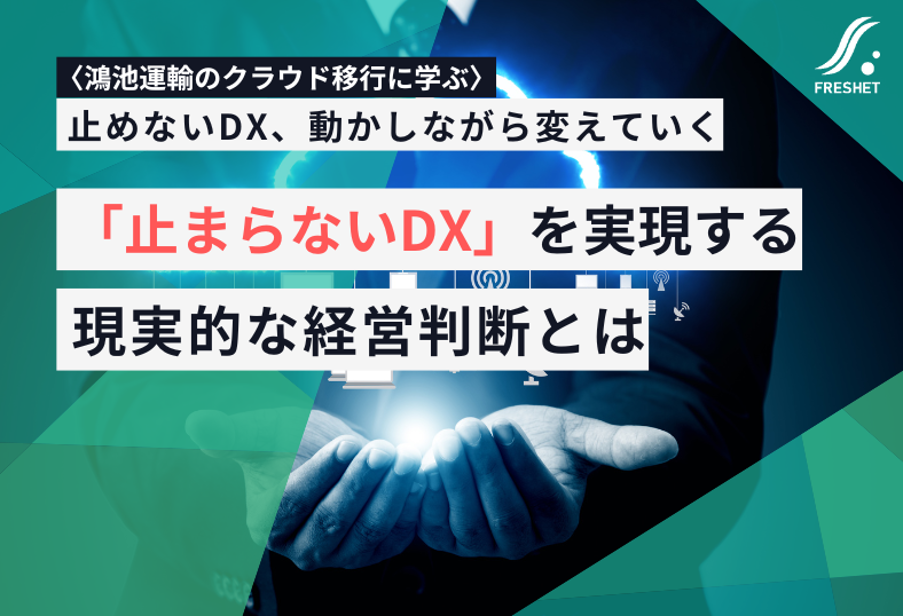
デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するうえで、避けて通れないのが「クラウド移行」です。ただし、理想を追いすぎてプロジェクトが長期化したり、システムが止まってしまったりするケースも少なくありません。
鴻池運輸は、4年をかけて業務システムの約9割をクラウド化しました。その際に採用したのは「クラウドシフト」ではなく「クラウドリフト」という現実的な選択でした。なぜその判断が成功につながったのか、その背景と、企業が見習うべきDXの進め方を考察します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】鴻池運輸、4年で業務システムの9割をAWSへ移行──「虎の穴」で人材育成とゼロトラスト基盤を整備
鴻池運輸は2018年から4年間で業務システムの約9割をAWSに移行し、クラウドファーストを実現した。サイロ化したIT基盤やベンダー依存を解消するため、クラウドリフト方式で段階的に移行。並行してゼロトラスト型のセキュリティーを導入し、ZscalerやOktaなどを活用してリモート環境でも安全に業務ができる仕組みを整備した。さらに、ITベンダーNSDと共同設立した「コウノイケITソリューションズ」で社員を実務教育し、専門人材を育成。経営層の理解を得ながら、コスト削減よりもガバナンス強化とIT人材育成を重視し、内製開発への基盤を築いた。
出典:日経クロステック/日経コンピュータ「鴻池運輸が業務システムの9割をクラウド移行、4年をかけた成果」2023年5月24日公開
ポイントをひとことで
クラウドリフトを単なる「延命策」と捉えるか、「持続的DXへの第一歩」と捉えるかで、企業の未来は大きく変わります。鴻池運輸の判断は、理想論よりも現実を見据えた賢明な選択でした。DXの本質は、完璧なシステムを作ることではなく、止めずに改善を続けること。クラウドリフトは、そのための“動かしながら進化させる”戦略です。重要なのは、移行後にどれだけ柔軟に改良できる設計を組めるか。そこにこそ、真のDXを実現するための設計思想と意思決定力が問われます。
DXを止めないための選択、「クラウドリフト」とは何か
クラウドリフトとは、既存のシステム構成を大きく変えずに、そのままクラウド環境に移行する手法を指します。システム全体を作り直す「クラウドシフト」とは異なり、再設計や再構築にかかる時間やコストを抑えながら、早期にクラウド基盤の恩恵を受けられる点が特徴です。
クラウド移行の目的が「最新の技術に置き換えること」ではなく、「業務を止めないこと」「継続的に改善できる環境をつくること」であれば、クラウドリフトは極めて現実的な第一歩です。理想を追いすぎるあまり、再構築プロジェクトが頓挫するよりも、まずはクラウド上でシステムを安定稼働させ、そこから段階的に最適化を進める方が、経営的にも合理的といえます。
「理想より持続」を選んだ鴻池運輸の判断
鴻池運輸は、2018年から4年間かけて業務システムの9割をクラウド化しました。採用したのは、既存アプリケーションを構成を変えずに移行するクラウドリフトの方針。「スキルも予算も時間もない」という現実的な制約の中で、同社は理想を追うのではなく、“DXを止めない”ことを優先しました。
>>システムをクラウド化するメリット・デメリットや注意点を解説
この判断は、単なる「妥協」ではなく「戦略的な一歩」です。再構築を選んでシステム刷新が長期化すれば、その間に既存環境の保守切れやセキュリティリスクが高まり、DXの機運そのものが失われてしまいます。鴻池運輸は、「今できる最善」を積み上げながら、将来的なシステム最適化への道を開いたのです。
システムを止めないことが最大のリスク回避
DX推進の現場でしばしば見落とされがちなのは、「変化の途中でも業務を止めない設計ができているか」という観点です。クラウドリフトは、クラウドシフトのような大掛かりな再設計を必要としないため、業務を止めずに移行を進めることができます。
特に、物流や製造、医療など、日々のオペレーションを止められない業界では、「安全に段階的に進める」ことこそが最重要の要件になります。クラウドリフトは、クラウド化への“通過点”であると同時に、業務を中断しないための堅実なリスク回避策としても有効なのです。
IT人材不足の中での“時間戦略”
鴻池運輸がクラウドリフトを選んだ背景には、人材不足という明確な課題がありました。専門的なITスキルを持つ人材が社内に少ない中で、いきなりクラウドシフトを実現するのは現実的ではありません。クラウドリフトによってまずは既存システムをクラウド上に載せ、同時に社内のITリテラシーを高める時間を確保する──。
この「時間の確保」こそが、DXの成功に欠かせない重要な経営判断です。クラウド化によって保守やインフラ管理の負荷が軽減されれば、次のステップとしてアプリケーション開発や業務改善にリソースを回すことができます。
クラウドリフトがもたらす“可視化”の効果
もう一つ、クラウドリフトには見逃せない副次的効果があります。
それは「自社のシステム全体が可視化される」ということです。
オンプレミス環境では、システムごとに管理方法やセキュリティツールが異なり、担当者以外には全体像が見えにくくなることがあります。クラウドに移行することで、利用しているリソースやデータ構造、アクセス権限などを一元的に把握できるようになります。この「見える化」が、次のステップであるクラウドシフト(再構築)や内製化への土台となるのです。
クラウドリフトは“延命”ではなく“進化”の序章
クラウドリフトは一見、「とりあえずクラウドに載せただけ」と捉えられることもあります。しかし実際には、既存システムの“延命策”ではなく、次の成長に向けた“進化の序章”です。
鴻池運輸はクラウドリフトを終えた後、IT子会社を通じてクラウドスキルの育成を行い、将来的なアプリケーションの内製化を見据えています。これは、クラウドリフトを単なる「移行」ではなく、「組織変革のための段階戦略」として捉えている証拠です。クラウドリフトの価値は、「今のシステムを動かすこと」と同時に、「次の一手を打てる組織を育てること」にあります。
理想を追うDXが失敗する理由
多くの企業がDXでつまずくのは、理想を先に描きすぎることにあります。“クラウドネイティブ”“ゼロトラスト”“マイクロサービス”といったキーワードを並べても、現場が追いつかなければ机上の空論に終わります。
経営層が「時間・コスト・スキル」という現実的な制約を理解し、持続可能なロードマップを描けるかどうかが成否を分けます。鴻池運輸の事例は、まさに理想を後回しにしてでも「まず動かす」ことを選んだ勇気のある経営判断でした。
DXを成功させる本質は、「何を導入するか」ではなく「どう継続するか」にあります。
クラウドリフトから始まる段階的DX戦略
クラウド移行を段階的に進めることは、企業の成長に合わせた柔軟なDXを実現するうえで有効です。
クラウドリフトで既存環境を移し、クラウド環境上で運用を安定させながら、次のフェーズでクラウドシフト(最適化・再構築)へ進む──。
この二段構えのアプローチが、現場の混乱を最小限に抑えながら、確実にDXを定着させる道です。
また、この段階的アプローチを採用することで、各フェーズでの学びを蓄積し、社内にノウハウを残すことができます。最初から完成を目指さず、「試して、改善して、積み上げる」という考え方こそ、クラウド時代の経営戦略にふさわしい姿勢です。
まとめ
クラウド移行において「クラウドシフトではなくクラウドリフトを選んだ」鴻池運輸の判断は、理想を諦めたのではなく、DXを止めないための現実的な経営判断でした。限られたスキル・予算・時間の中でも、「まず動かす」「止めない」「育てる」という三つの軸を優先したことが、結果的に持続可能なDXの実現へとつながりました。
クラウドリフトは、目的ではなく出発点。
システムを止めないという現実的な選択こそが、真のDXを実現する企業に共通する思考なのです。
クラウドリフトを出発点として、次のフェーズで本格的な最適化や業務再設計を進めていくには、現場を深く理解し、要件を一から整理できる開発パートナーの存在が欠かせません。
フレシット株式会社は、業務プロセスに合わせたフルスクラッチ(オーダーメイド)開発を得意とし、クラウド環境を前提とした柔軟なシステム設計や段階的なリプレイスにも対応しています。
既存資産を活かしながら“止まらないDX”を実現したい企業にとって、理想と現実をつなぐ伴走型の開発パートナーとしてお力になれるはずです。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

