スズキ流に学ぶ「外部の目」の効用──“指摘される力”が開発を強くする仕組みとは
「指摘は成長のサイン」──外部の目がシステムを一段上の品質へ導く。
2025-10-20
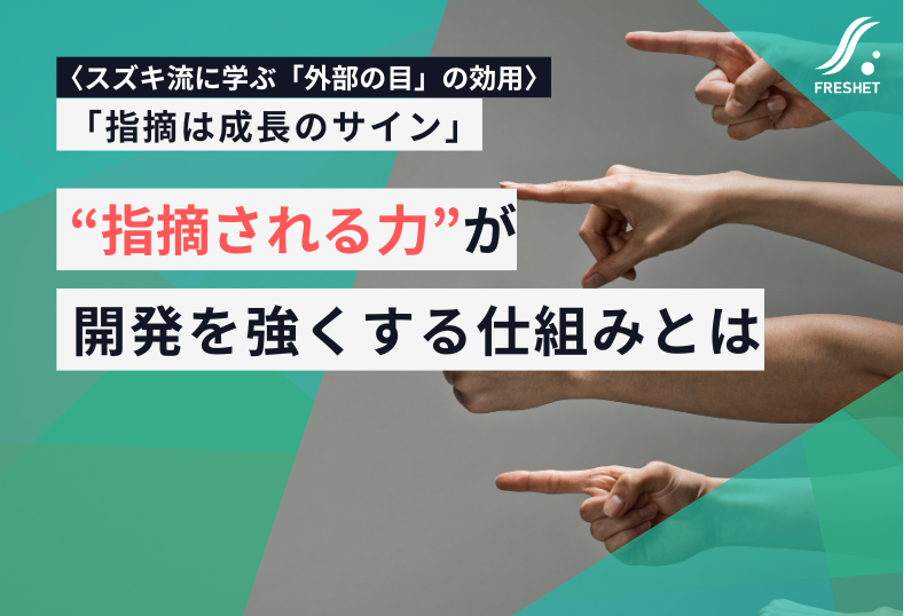
システム開発プロジェクトでは、内部だけで完結すると気づかないリスクが積み重なりやすくなります。一方で、外部のシステム開発会社や専門家によるレビューを定期的に取り入れることで、仕様の妥当性・品質・コストを客観的に見直し、プロジェクト全体の精度を高めることができます。
本コラムでは、「指摘される力」を組織の成長エンジンとして捉え、外部レビューを活用した開発体制の作り方を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】異業種の視点が生んだ「気づき」──スズキが家電メーカーから得た新たな発見
スズキは軽量化プロジェクト「Sライト」で、異業種との交流を通じた技術革新を進めている。家電メーカーを訪問し軽自動車「アルト」を見せた際、「電線が多くないか」という指摘を受け、同社技術陣は驚いた。自動車業界では当たり前とされていた設計も、他分野の専門家には異質に映る。所属する業界や企業が異なれば、視点や「許容範囲」の基準が違うのは当然であり、そうした多様な視点からの率直な意見は、企業の“常識”を見直す契機となる。スズキは今後も異業種との対話を継続し、新たな気づきを技術進化へとつなげていく考えだ。
出典:日経クロステック/日経Automotive「スズキが驚いた異業種からの指摘、アルト『電線多くないか』」2025年9月17日
ポイントをひとことで
外部レビューを取り入れるという発想は、単なる品質保証の手段ではなく、組織の“思考の固定化”を防ぐ構造改革です。社内だけで完結する開発は、効率的に見えても思考の多様性を失いやすく、結果としてリスクを内包します。第三者の視点を継続的に受け入れることで、プロジェクトは透明性を増し、判断の質が高まります。つまり、指摘を恐れず仕組みに変えることこそが、強い開発体制への最短ルートなのです。
外部の意見が「痛い」と感じるのは、成熟の入り口
開発現場では、外部からの指摘に対して「今さらそんなことを」「うちの事情をわかっていない」と反発が起きることがあります。しかし、これはどの組織にも起こりうる自然な反応です。長年同じ体制で開発を進めていると、メンバーの間に共通認識が生まれすぎてしまい、思考の幅が狭くなります。
実際、プロジェクトの失敗要因を分析すると、問題そのものよりも「誰も指摘しなかったこと」に原因があるケースが少なくありません。仕様の曖昧さ、スケジュールの甘さ、レビュー不足──こうしたリスクは、内部の論理で完結している環境ほど見落とされやすいのです。
外部のシステム開発会社が加わることで、異なる業界・文化の視点から改善の提案がなされます。
その“外の視点”を受け止めることができたとき、組織は初めて本当の意味で成熟に向かい始めます。
「第三者のレビュー」がプロジェクトを整流化する
外部レビューの最大の価値は、プロジェクト全体の流れを“整流化”できる点にあります。開発が進むにつれて、社内では「誰が判断すべきか」「どこが責任を持つか」が曖昧になり、議論が属人的になって意思決定が遅れるケースが少なくありません。
第三者のレビューは、こうした構造的な歪みを是正します。客観的な立場から仕様書や設計書を精査し、「本当に必要か」「より合理的な方法はないか」を明確化することで、プロジェクトの方向性が整理され、意思決定の精度が高まります。
さらに、外部のシステム開発会社は他業界のプロジェクトにも携わっており、異なる業種の成功モデルや開発手法を横断的に知っています。その知見を持ち込むことで、業界固有の常識に縛られない、より柔軟なシステム設計が可能になります。
「品質」「納期」「コスト」を両立する仕組みとしての外部レビュー
システム開発において最も難しい課題が、「品質・納期・コスト」のバランスです。多くのプロジェクトで、この3つのうちどれかを犠牲にせざるを得ない場面が生じます。
しかし、外部レビューを取り入れることで、このバランスを保ちやすくなります。第三者が初期段階から仕様や進捗をチェックすることで、後戻りを防ぎ、結果として無駄なコストや遅延リスクを抑えることができます。
品質面でも、外部の視点は強力です。
テスト設計や運用フェーズで「想定外の利用パターン」や「例外処理の抜け」が指摘されることがあり、内部チームでは気づかなかった欠陥が明らかになることもあります。
第三者の関与が、システムの信頼性と安全性を底上げするのです。
セカンドオピニオンがもたらす透明性と安心感
医療の世界に「セカンドオピニオン」という概念があるように、システム開発でも第三者の見解を得ることは重要です。
特定の開発体制やパートナーに依存していると、設計思想や技術選定が偏ることがあります。また、進行中のプロジェクトでは「もう引き返せない」と思い込み、問題を認識しながらも修正を先送りにしてしまうケースも少なくありません。
外部のシステム開発会社がセカンドオピニオンとして入ることで、現在の設計方針や進行体制を客観的に再評価できます。結果として、経営層・現場・開発チームのあいだでの透明性が高まり、「この判断は正しかったのか」という振り返りの機会が生まれます。
特に大規模プロジェクトやマルチベンダー体制では、外部レビューが“第三の安全弁”として機能します。利害関係に左右されない客観的な視点を持つことで、組織は健全な意思決定を保つことができるのです。
>>システム開発のセカンドオピニオンをお考えの方へ!第三者視点の重要性を解説
「指摘を受け入れる文化」が開発組織を育てる
外部レビューを活かすためには、指摘を受け入れる文化が欠かせません。レビューで出た意見を「批判」と捉えるか、「改善のチャンス」と見るかで、組織の成長速度は大きく変わります。
重要なのは、指摘を“個人の否定”ではなく“仕組みへの提案”と位置づけることです。誰かの責任を追及するのではなく、構造的に何が問題だったのかを冷静に議論する。これにより、メンバーは防御的ではなく建設的な姿勢で意見を交換できるようになります。
外部のシステム開発会社が行うレビュー内容は、自社の開発力や品質保証体制の成熟度を測る鏡でもあります。その指摘を次の改善に活かしていくことが、結果的に組織全体を強くしていくのです。
外部レビューを“仕組み”として組み込む
外部レビューは単発のイベントではなく、開発プロセスの一部として継続的に取り入れることが理想です。
たとえば以下のような段階的レビュー体制を構築すると、安定した品質向上につながります。
- 要件定義段階:仕様の整合性・業務要件の妥当性を外部視点で検証
- 設計段階:冗長な構造や依存関係の偏りを早期に指摘
- 実装段階:セキュリティやパフォーマンス面のリスクを洗い出し
- 運用前レビュー:障害対応や運用保守体制の適切性を確認
このようにフェーズごとに第三者の意見を入れることで、社内レビューの質が高まり、再現性のある品質向上サイクルが生まれます。さらに、レビュー結果をドキュメント化することで、ナレッジが組織に蓄積され、次の開発にも活かせるようになります。
まとめ:指摘を受け入れることが、開発の“強さ”を生む
外部レビューの目的は、単にミスを見つけることではありません。異なる視点を受け入れ、組織の「思考の型」を進化させることにあります。
社内だけでは見落としがちな課題を、外部の専門家が指摘してくれる。そのプロセスを恐れずに活かすことができる企業こそ、変化の激しい時代においても強くしなやかな開発体制を築いていけます。
“指摘される力”とは、謙虚さと柔軟さを備えた組織に宿る力。
外部の目を味方に変えることが、真に成長する開発文化への第一歩となるのです。
外部の目を受け入れるという姿勢は、システム開発における最も重要な成長の鍵です。
当社フレシット株式会社は、まさにその「第三者の視点」を提供するシステム開発会社です。
業務整理や要件定義の段階から深く伴走し、社内だけでは気づきにくい課題を掘り起こし、最適な形に設計していきます。既存の枠にとらわれない発想と確かな技術力で、貴社の業務に真にフィットするフルスクラッチ(オーダーメイド)開発をご提案します。
システムの見直しや刷新をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

