ルールを守るシステムから、ルールを育てるシステムへ
現場が変わるたびに、システムも成長する──“進化する標準化”という発想
2025-10-22
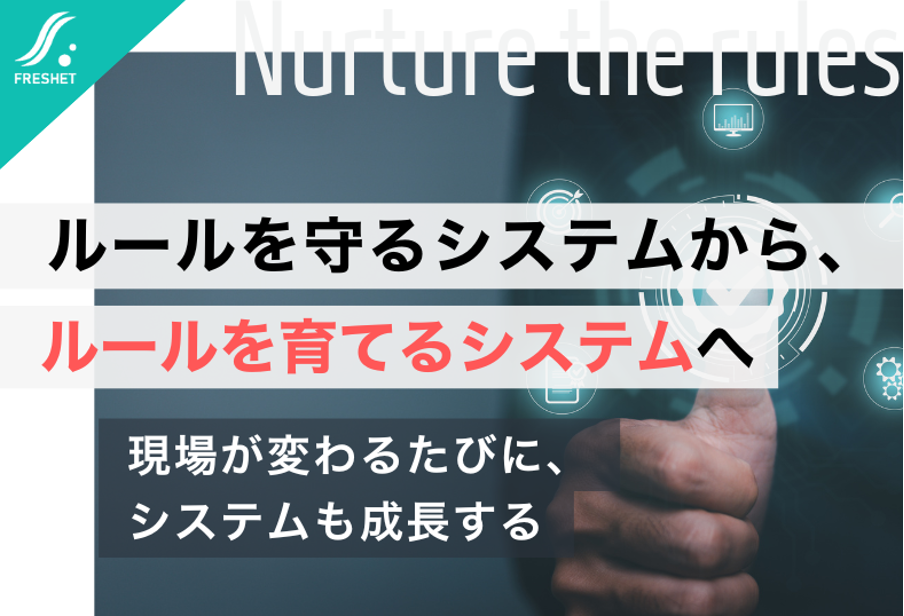
近年、製造業を中心に「図面のデジタル管理」や「ノウハウ共有」を通じて、業務の標準化を進める動きが広がっています。しかし、標準化は一度つくれば完成するものではありません。市場環境、組織体制、現場のオペレーションは常に変化しており、システムもそれに合わせて“進化し続ける仕組み”でなければなりません。
本コラムでは、システムを「共通ルールを育てる入れ物」として捉え、標準化を持続的に支えるアーキテクチャ設計の考え方を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】図面の共有・活用で工場間連携を強化、AIが製造ノウハウを可視化
製造現場で図面管理の効率化が進んでいる。仲精機(大阪府)はAIで図面を分析・管理するキャディのシステムを導入し、約6万枚の図面を共有化。従来は工場ごとに異なるルールでデジタル化が進み情報が分断されていたが、共通のフォーマットで作業手順や加工条件を記録し、工場間の仕事の融通や技能伝承が可能となった。熟練社員の図面メモも検索可能となり、暗黙知の継承や生産効率の向上に寄与。図面を核としたデータ共有は中小製造業の競争力を高め、供給網全体の安定にも貢献する。
出典:日本経済新聞「〈小さくても勝てる〉図面から生産・調達改革工場間の垣根なくし仕事融通 AIで職人メモ見える化」2025年10月15日付朝刊
ポイントをひとことで
標準化の本質は「統一」ではなく「更新し続けられる仕組み」にあります。現場は常に変化し、例外や新たな要件が生まれる中で、システムがその変化を受け止められるかが競争力を左右します。固定化された業務フローを守るだけの仕組みは、やがて現場の足かせになります。重要なのは、ルールをデータとして管理し、必要に応じて柔軟に改訂できるアーキテクチャを備えることです。システムは完成品ではなく、組織とともに成長する“設計思想”そのものだといえます。
標準化とは「固定化」ではなく「変化への適応」
多くの企業がDXの一環として「業務標準化」を掲げていますが、現場では往々にして“ルールの固定化”として進められてしまいます。確かに標準化の目的は、属人的な判断や手順を減らし、業務を再現性のある形に整えることにあります。
しかし、実際の現場では市場の要求や顧客仕様、技術トレンドが日々変化します。固定化された標準は、やがて現場と乖離し、形骸化してしまうのです。真に意味のある標準化とは、「変化を前提に更新できる仕組みを持つこと」です。つまり、標準を“生きたルール”として育てるアーキテクチャが求められます。
システムが「共通ルール」を内包する
標準化が進むと、業務ルールや手順書が整備されます。しかし、それらが紙やExcelのままでは、共有や更新が追いつきません。一方、システム内に業務ロジックとして組み込まれると、日々の業務運用の中で自然と「ルールが実行される」状態を生み出せます。
例えば、製造業における工程管理システムであれば、「図面ごとに作業時間を登録する」「加工条件を共通フォーマットで入力する」など、操作の流れそのものが標準ルールの実装となります。
このように、システムが業務ルールの“実体”を持つことで、標準化が定着します。しかし、ここで重要なのは「ルールを組み込んだら終わり」ではないという点です。現場での改善や例外対応が発生した際に、そのルールを素早く見直し、再構築できるアーキテクチャが必要です。
固定化の落とし穴──更新できないシステムは、やがて“負債”になる
システムを導入して標準化を進めたつもりが、数年後には「現場の実態に合わない」「ルール変更が反映できない」といった課題に直面するケースは少なくありません。
この原因は、設計段階で“変化を許容する構造”が考慮されていないことにあります。
たとえば、
- 業務ロジックが画面やコードに埋め込まれており、修正コストが高い
- 設計段階で例外処理や追加項目を想定していない
- 標準化のルールがドキュメントではなく個人の判断に依存している
このような状況では、システムが標準化を“固定化”してしまい、むしろ柔軟な運用を妨げる存在となってしまいます。
柔軟に変化できるアーキテクチャ設計とは
標準化を進化させるためには、システムに「柔軟性」と「継続的な変更容易性」を持たせる必要があります。そのための設計思想には、次のようなポイントが挙げられます。
1.業務ルールをデータ化する
業務ルールをソースコードではなく設定やマスタとして管理することで、現場主導で変更できるようにします。ルールを構造化データとして保持すれば、再利用・比較・差分管理も容易になります。
2.フローを“固定”ではなく“テンプレート化”する
プロセス管理のフローを一つの型に固定するのではなく、「テンプレート」として持ち、現場や案件に応じて調整可能な設計にします。テンプレート更新が全体に反映される構造をつくれば、標準の維持と柔軟性を両立できます。
3.データ連携を前提としたモジュール構造
工程・購買・品質などの機能を密結合で設計すると、どこかの変更が全体に影響してしまいます。APIやマイクロサービス的なモジュール設計により、部分的な改善や標準更新を可能にします。
4.更新の責任を明確にする
標準ルールを維持する責任者を定義し、システム上で変更の履歴と承認フローを可視化します。誰が、いつ、どのルールを変えたかを追えることが、標準の信頼性を保ちます。
標準化は“設計のプロセス”で成熟する
多くの企業では「まずツールを導入し、その後にルールを整備する」アプローチをとりますが、本来、標準化とは設計段階から始まるプロセスです。
フルスクラッチ開発では、要件定義やプロトタイプ設計の段階で、業務ルール・例外処理・承認フローなどを一つひとつ整理しながら“共通言語”を作っていきます。この過程そのものが、組織の標準化を進める第一歩です。
さらに、設計・開発・運用保守のサイクルを通じて現場の改善点を取り込み、標準を更新し続ける文化を定着させることが重要です。つまり、標準化とは完成形ではなく「成長する仕組み」なのです。
システムが「育つ」ことで組織も育つ
システムが現場に根づくとは、「現場が自ら改善できる構造を持つ」ことを意味します。
属人的な判断や手作業を排除するだけでなく、“例外対応を仕組みに取り込める”柔軟性があって初めて、標準は進化します。
結果として、現場の改善提案がデータとして蓄積され、次の設計に活かされる──この循環が、企業全体の学習サイクル(ナレッジ・ループ)を形成します。
このように、標準化を支えるシステムは、単なるツールではなく「共通ルールを育てる入れ物」であり、それ自体が組織の知を更新し続けるプラットフォームとなります。
まとめ
標準化とは、業務ルールを一度定義して終わるものではなく、現場の変化に合わせて更新され続ける“生きた仕組み”です。そのためには、変化を許容し、部分的な改善を容易にする柔軟なアーキテクチャ設計が不可欠です。システムが組織のルールを内包し、現場の改善を取り込みながら成長していくとき、企業は初めて「進化し続ける標準化」を実現できます。
フレシット株式会社では、こうした「変化に適応する標準化」を前提としたシステム設計を重視しています。現場の業務ルールや判断基準を丁寧に整理し、それを柔軟に更新できる構造として実装することで、企業の成長に合わせて進化する“生きたシステム”を実現します。汎用パッケージに合わせるのではなく、自社の業務を基点に設計する。その考え方こそ、フルスクラッチ(オーダーメイド)開発の真価です。業務の標準化を「固定化」ではなく「進化」として捉える企業にとって、当社の開発アプローチは最適な選択肢となるはずです。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

