図面管理DXが示す次の一手──ノウハウを“引き継げる形”にする属人化解消の設計論
ノウハウを資産化する──属人化を防ぐ情報設計とシステム構築の新基準
2025-10-25
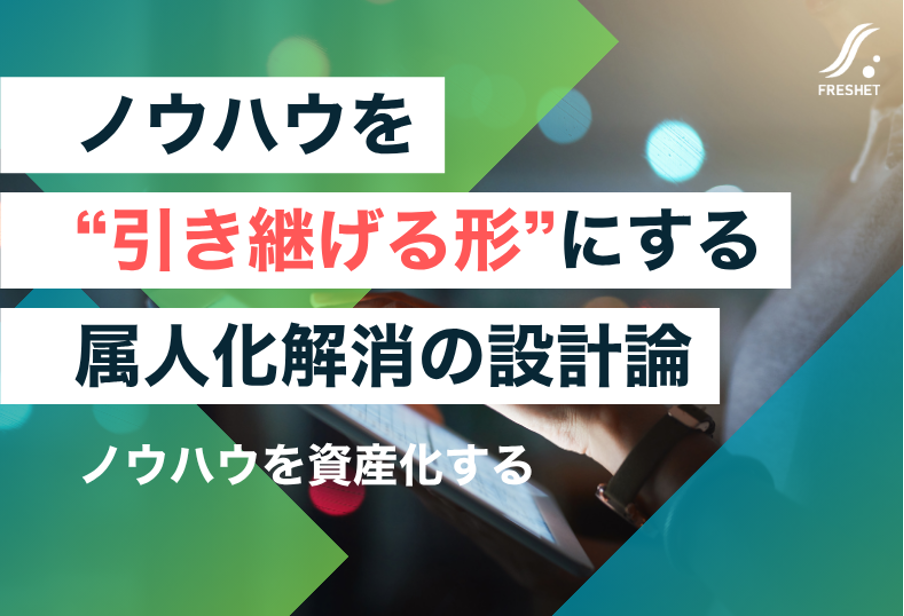
製造現場やバックオフィスなど、あらゆる業務の現場で「属人化」が課題となっています。特定の担当者しか分からない判断や手順、経験に基づくコツ。これらが文書化されても、検索できなかったり、探し出せなかったりすれば共有されたとは言えません。
本コラムでは、こうした“知識の分断”を解消するために、データ構造・検索設計・タグ設計をゼロから描くフルスクラッチ開発のアプローチを解説します。ノウハウを「引き継げる形」にするために、システムが果たすべき役割とは何かを考えます。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】図面の共有・活用で工場間連携を強化、AIが製造ノウハウを可視化
製造現場で図面管理の効率化が進んでいる。仲精機(大阪府)はAIで図面を分析・管理するキャディのシステムを導入し、約6万枚の図面を共有化。従来は工場ごとに異なるルールでデジタル化が進み情報が分断されていたが、共通のフォーマットで作業手順や加工条件を記録し、工場間の仕事の融通や技能伝承が可能となった。熟練社員の図面メモも検索可能となり、暗黙知の継承や生産効率の向上に寄与。図面を核としたデータ共有は中小製造業の競争力を高め、供給網全体の安定にも貢献する。
出典:日本経済新聞「〈小さくても勝てる〉図面から生産・調達改革工場間の垣根なくし仕事融通 AIで職人メモ見える化」2025年10月15日付朝刊
ポイントをひとことで
属人化の解消は、単なるマニュアル化や情報共有の問題ではなく、「知識の構造化」ができているかどうかにかかっています。経験やコツを残しても、検索できず、再利用できなければ意味がありません。重要なのは、情報を“探せる形”に設計することです。データ構造・検索設計・タグ設計を業務に合わせて最適化することで、組織の中に知識が循環し、個人の経験が企業の力へと転換されます。システム設計とは、知識を流通させるための“企業の血流設計”でもあるのです。
属人化は“個人の問題”ではなく“構造の問題”
属人化は、特定の社員が有能すぎるから起こるのではありません。むしろ、業務ルールや判断基準がシステムや仕組みに落とし込まれていないことに起因します。業務マニュアルが存在しても、現場で起きる小さな判断や例外対応は文書に残りにくく、暗黙知のまま個人に蓄積されていきます。
さらに、こうした暗黙知は共有フォルダやチャットのログの中に埋もれ、「どこにあるか分からない」「誰が持っているか分からない」といった状態を生み出します。このように、情報の構造が整っていないことこそが属人化の本質です。
したがって、解決の鍵は「情報を探せる・引き継げる構造を設計すること」にあります。
文書化だけでは“共有”にならない理由
多くの企業が属人化対策としてマニュアル化や文書化を進めていますが、その多くが「形式的な共有」にとどまっています。
たとえば、ドキュメントをPDFにまとめて共有サーバーに保存する。
一見整っているように見えても、必要な情報にすぐアクセスできなければ意味がありません。
問題は、文書化ではなく検索性と再利用性です。情報を登録する仕組みだけでなく、後から探す・引き出すための構造がなければ、せっかく蓄積されたノウハウも“死蔵データ”になります。
属人化の解消には、単に「書き残す」ことではなく、“見つけやすく・活かしやすい形で残す”ことが求められます。そのためには、業務特性に合わせた情報設計が不可欠です。
データ構造設計が「知識の流通」を左右する
ノウハウを再利用できるかどうかは、システムの“データ構造”にかかっています。
どんな情報を、どの単位で、どの関係性で保存するか。
これを安易にパッケージソフトの仕様に合わせてしまうと、本来業務に即した整理ができず、情報が断片化してしまいます。
たとえば製造業では、「図面」や「工程情報」などがノウハウの核になります。これらを単なる添付ファイルとして保存するか、それとも「加工条件」「使用機材」「担当者コメント」といった関連データとして構造化するかで、後の活用可能性は大きく変わります。
さらに、属人化を防ぐには「情報の関係性」を明示する設計が必要です。部品Aの工程が部品Bとどう関係しているのか、ある作業手順がどの製品群で共通しているのかを可視化できれば、現場に新しい担当者が入っても、ノウハウを横断的に引き継げる仕組みになります。
検索設計が“引き継ぎ”の質を決める
情報を構造化しても、それを“見つけられなければ”意味がありません。検索機能は単なる利便性ではなく、組織の記憶を引き出すためのインターフェースです。
優れた検索設計では、単語検索だけでなく、工程・製品・担当者・日付・タグなど複数の切り口から横断的に絞り込みができるようにします。これにより、「似たような案件」「同じ条件で過去に対応した事例」などを即座に再利用できるようになります。
また、検索履歴やアクセス頻度を解析すれば「どの情報が現場でよく参照されているか」を把握し、
マニュアルやルールの改善にも役立てることができます。つまり、検索設計は単なる“探すための機能”ではなく、知識が循環する仕組みそのものなのです。
>>システム開発の引き継ぎ方法は?必須項目や依頼会社の選び方についても詳しく解説
タグ設計が「現場の思考」を可視化する
タグは、情報を探すための補助機能というよりも、現場の思考パターンを可視化する“設計要素”です。
属人化が進んだ現場では、同じ内容でも人によって表現や分類の仕方が異なります。たとえば「不具合」「トラブル」「異常対応」といった言葉がバラバラに使われると、検索で漏れが生じ、ノウハウの共有が滞ります。
そこで、システム設計段階で「共通タグの設計」を行い、現場で自然に使われる用語と公式分類の両方を紐づけることが重要です。さらに、タグを固定せず“進化できる構造”にしておくことで、新しい業務や製品にも柔軟に対応できます。
タグは単なるラベルではなく、人の思考を整理し、組織の言語を統一する仕組みなのです。
フルスクラッチ設計がもたらす“流通する知”
パッケージソフトでは、データ構造・検索設計・タグ設計があらかじめ固定されています。そのため、自社特有のノウハウを格納・検索・活用するには制約が多く、属人化の根本解決には至りません。
一方、フルスクラッチ開発では、業務フローや情報の流れをゼロベースで整理し、「現場の知識がどのように生まれ、どこに残るのか」を構造的に設計できます。このプロセスこそが、属人化を解消し、知識を“流通させる仕組み”を生むのです。
具体的には、以下のようなステップで進めます。
- 現場ヒアリングにより、暗黙知の発生ポイントを可視化
- 知識の単位・関係性・利用場面を定義
- データベース構造を設計(マスタ/履歴/添付情報など)
- 検索・タグ・通知設計を業務シーン別に最適化
- 運用後に利用ログを分析し、継続的に構造をチューニング
こうして、システムが「知識の通り道」として機能するようになります。
ノウハウを個人が持つのではなく、組織全体で再利用できる“共有知”へと昇華させる設計思想が、フルスクラッチ開発の最大の価値といえるでしょう。
ノウハウを“探せる・使える・更新できる”組織へ
属人化の解消は、単に情報を整理するだけではなく、「探せる」「使える」「更新できる」仕組みを組み合わせることです。
業務は常に変化し、ルールも手順もアップデートされ続けます。その変化を前提に、データ構造や検索・タグを柔軟に進化させる仕組みがあれば、知識は自然に組織全体へと循環します。
ノウハウを引き継ぐとは、情報を保管することではなく、次の人が迷わず使える“形”にすること。属人化を防ぐ最良の方法は、システムそのものに“知識の流通構造”を組み込むことにあります。
まとめ
属人化の課題は、個人の能力や情報量ではなく、情報設計の問題です。経験やコツを文章に残しても、探せなければ意味がありません。データ構造・検索設計・タグ設計を業務に合わせて設計することで、ノウハウは「引き継げる形」に生まれ変わります。
システムが知識の循環を支える仕組みとして機能することで、組織は個人依存から脱し、“知が流通する企業文化”を築くことができます。
フレシット株式会社では、業務の中に埋もれたノウハウや暗黙知を“再利用できる知識”へと変換する仕組みづくりを重視しています。現場の業務構造や判断基準を丁寧に分解し、それらをデータとして扱えるように設計することで、属人化を解消しながら知識が循環するシステムを構築します。既存パッケージに業務を合わせるのではなく、自社の強みや文化を活かした「フルスクラッチ(オーダーメイド)開発」で、変化に強く、次の世代へ確実にノウハウを引き継げる仕組みを実現します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

