他社システムの引き継ぎについて | 失敗しないためのポイントを解説
2025-10-30
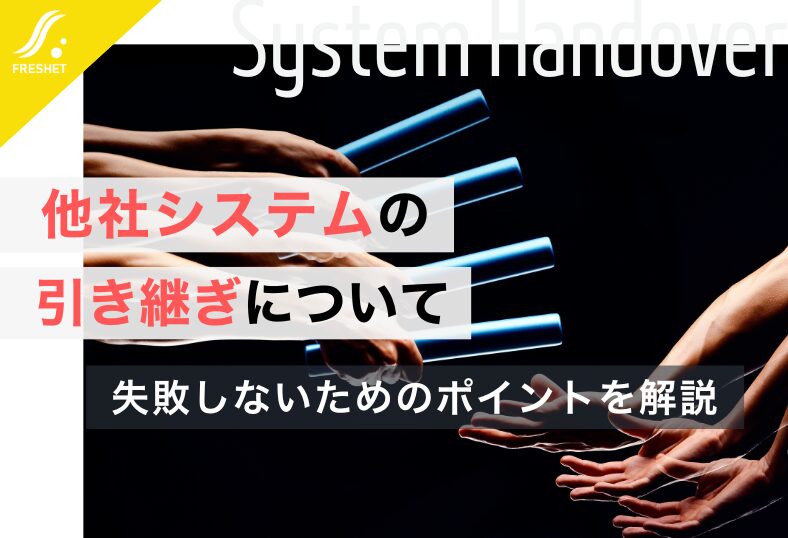
他社が開発したシステムの引き継ぎは、単なる移管作業ではなく、リスクを最小限に抑えるための入念な調査と計画が欠かせません。
そこで本コラムでは、
- 他社システムの引き継ぎのために必要な事前準備
- 他社システムの引き継ぎ手順 5STEP
- 他社システム引き継ぎ時のリスクと対策
について解説します。
他社システムの引き継ぎは、新規開発以上に経験と技術力が問われる領域です。現状の体制に不安や課題を感じている方は、ぜひ参考になさってください。
【関連記事】
システム開発の引き継ぎ方法は?必須項目や依頼会社の選び方についても詳しく解説
システム開発の巻き取りについて | プロが徹底解説します
システム開発のセカンドオピニオンをお考えの方へ!第三者視点の重要性を解説
目次
他社システムは引き継ぎできるのか?
他社が開発したシステムを別会社に引き継ぐことは、結論として可能です。しかし、簡単ではないという事実も知っておきましょう。ここでは、どのような場合にシステムの引き継ぎが必要なのか、なぜ引き継ぎが難しいのかについて解説します。
引き継ぎが必要になる主なケース
担当システム開発会社のリソース枯渇
運用保守は突発対応が多く、一定の人的リソースの確保が必須となります。担当システム開発会社の人的リソース確保が難しくなると、以下のような状況が見受けられるようになります。
- 問い合わせや障害対応が遅い
- 対応品質や納期が安定しない
- システム開発会社側で人員削減や方針変更が発生する
これらは、システムの安定稼働に対する脅威です。他社へのシステム引き継ぎ検討のシグナルだといえます。
担当システム開発会社の廃業
担当システム開発会社が廃業する場合も同様です。突然の廃業では、引き継ぎのための事前準備も難しくなります。いざとなればいつでも引き継ぐことができるという備えは、日常的にしておくべきでしょう。
運用保守費用および内容の見直し
いざ運用保守が始まると、担当システム開発会社の費用や対応内容に不満を感じることもありえます。「この金額でこれだけしかしてくれないの?」「システム障害への対応が遅すぎる」などの不満を抱えたままにするのは危険です。運用保守は一度始めて終わりではなく、これから先も長く続くプロセスです。違和感を感じる場合には、別のシステム開発会社への引き継ぎを検討するべきです。
>>運用保守とは?それぞれの違いや外部に依頼する際の注意点についても解説
他社システムの引き継ぎが難しい理由
システムのブラックボックス化
システムは仕様書を元に開発されることが理想的です。しかし、長く運用すればするほど、仕様書だけでは全てが説明されず、システムがブラックボックス化していることも多いです。仕様書には書かれていない例外処理や運用上の暗黙の了解などは、システム引き継ぎの障壁となるのです。操作ログの解析や旧システム開発会社や業務担当者へのヒアリングが必要になります。
開発ルールの違い
システム開発では設計書の書き方や、独自の開発ルールがシステム開発会社ごとにあるものです。同じ仕組みの場合でも、ルールが異なるとプログラムの読み方や修正の手順が変わり、思わぬトラブルにつながることもあります。
他社システムの引き継ぎ時には、旧システム開発会社の開発ルールを確認し、新システム開発会社にも共有しておくことが重要です。
業務理解度の低さ
旧システム開発会社に比べると新システム開発会社は業務への理解度がどうしても低くなります。「前のシステム開発会社なら言わなくてもわかってくれていたのに」と、引き継ぎ直後に不満が出るケースも考えられます。引き継ぎ後のフォロー体制を発注者側でも整えると、スムーズな引き継ぎができるでしょう。
他社システム引き継ぎに必要な事前準備
難易度が高いとはいえ、システムの引き継ぎは不可能なものではありません。他社システムの引き継ぎの成否は、事前準備で決まります。
ドキュメントの確認
契約書
一番重要なことは現システム開発会社と結んでいる契約書です。契約書には、システムの著作権の帰属先、運用保守の対象、引き継ぎ支援の可否など、引き継ぎに関わる重要な内容がすべて記載されています。これらの取り決めによって、システムを別会社に引き継ぐことができるか、どこまで引き渡してもらえるかが変わります。まず初めに契約書の内容を確認しましょう。
仕様書
システム開発は、基本的に仕様書を元に進められます。仕様書は開発内容を正確に把握するうえでの基礎資料であり、引き継ぎ時に重要な役割を果たします。ただし、実際の運用の中で追加・変更された部分が仕様書に反映されていないケースも少なくありません。そのため引き継ぎ前には、最新の仕様書が存在するか、そして実際のシステムと内容が一致しているかを確認する必要があります。
運用保守マニュアル
担当システム開発会社のメンバーは、常に固定されているわけではありません。プロジェクトの状況に応じて、人員の入れ替えや増員が行われることもあります。このようなメンバーの変更に対応するため、担当システム開発会社には運用保守マニュアルが必ず存在するはずです。もし用意されていない場合には、引き継ぎ前に必ず作成を依頼し、今後の運用に支障がないようにしておきましょう。
システムの確認
開発言語
システム開発では、開発言語と呼ばれる言語を使います。Java、C言語などさまざまな言語がありますが、何の開発言語を使っているのかということは、担当システム開発会社にとって非常に重要です。システム開発会社によって開発言語の得意・不得意がありますので、システム開発会社選定のタイミングで伝えられるように事前に調べておきましょう。
システムのバージョン
運用保守においてはバージョン管理が重要です。通常、改修や障害対応を行う度に、システムのバージョンが更新され、その履歴は運用記録として残されます。他社システムの引き継ぎの際には、最新のバージョンがいくつか、そのバージョンに適応した仕様書が存在しているかを確認しておきましょう。
サーバのバージョン
システムを運用保守するには、サーバなどの環境情報の確認も欠かせません。バージョンによっては同じサーバでも出来ること、出来ないことなどが変わる場合があるからです。現行のサーバのバージョン情報を正確に把握しておくことが、引き継ぎ後のトラブルを防ぐことにつながるのです。
ソースコードの洗い出し
システムには、開発言語を使ってシステムを動かすための命令文が書かれています。これを「ソースコード」と呼びます。ソースコードが引き継がれない場合、システムの改修などがスムーズにできません。必ずすべてのソースコードを洗い出しておきましょう。
他社システムの引き継ぎ手順 5STEP
次に、具体的なシステムの引き継ぎ手順を解説します。
STEP1 現状調査と課題整理
前述の「システム引き継ぎに必要な事前準備」を元に情報を整理し、システムの引き継ぎを行うことで改善したい課題を洗い出します。
STEP2 引き継ぎの目標設定
システムを引き継ぐことで達成したい目標を具体的に設定します。
例えば、システムへの問い合わせに対する回答を、3日以内から24時間にするといったことです。このようなサービスの質に関わる取り決めを「サービスレベル」と呼びます。必ず明文化しておきましょう。
STEP3 システム開発会社選定
引き継ぎ先のシステム開発会社を選定します。選定する際には複数の候補システム開発会社に対して相見積もりを必ず取り、体制や対応、費用など多角的に踏まえて検討しましょう。
STEP4 引き継ぎ計画書とバックアップ
引き継ぎ先のシステム開発会社が決まったら、引き継ぎ計画を立て、計画書に落とし込みましょう。計画を立てるポイントは作業の細分化とスケジュールの逆算です。まず、いつまでに引き継ぎを完了しておきたいのか設定します。引き継ぎに必要な作業を洗い出し、引き継ぎ完了日から逆算してどのようなスケジュールで動くべきかが見えるはずです。計画書策定には担当システム開発会社に協力してもらうとよいでしょう。
また、実際に引き継ぎを行う前にシステムやデータのバックアップを取っておくことも忘れないようにしましょう。
STEP5 運用開始・フォローアップ
引き継ぎ計画書の全工程が完了して初めて、新システム開発会社による運用保守が始まります。しかし、いくら万全に引き継ぎ準備をしたとしても、実際に始めてみると予想外の問題にぶつかることもあります。最初は特に、新システム開発会社に丸投げせず、発注側もフォローをする意識を持つとよいでしょう。
他社システム引き継ぎ時の注意点と対策方法
次に、システムを引き継ぎする際の注意点と対策について解説します。
1.データ破損やシステム停止のリスク
他社システムの引き継ぎにあたり、プログラムやデータベースをサーバーごと移す可能性もあります。そういった移行が発生する場合、データの破損やシステム停止のリスクは避けては通れません。
対策として、システムやデータのバックアップを取得しておくことや、引き継ぎ作業を中断し元に戻す判断基準などを設定しておくと効果的です。
2.契約・権利トラブルのリスク
旧システム開発会社との間に契約や権利のトラブルが発生するケースもあります。契約書を事前によく確認し、引き渡し対象を明確にしておきましょう。
>>システム開発における準委任契約とは?請負契約との違いなども徹底解説
3.仕様やノウハウが引き継げないリスク
システムやドキュメントは引き継げたとしても、明文化されていない仕様やノウハウを引き継げない可能性があります。既存ドキュメントは可能な限り集め、引き継ぐ前に旧システム開発会社や社内担当者と打ち合わせを重ねるなどして対策が必要です。
4.関係者間の認識ずれによるリスク
引き継ぎ対象の範囲を誤っていたり、スケジュールの認識がずれていたりということは起こり得ます。引き継ぎ計画書で対象範囲とスケジュールを明確にした上で、定例会による進捗管理を行うなど対策をしましょう。
5.セキュリティ上のリスク
引き継ぎを行うと旧システム開発会社から新システム開発会社へシステムの管理者が移ることになります。旧システム開発会社はもちろん、関係者以外がアクセスできる状態を残さないような対応が必須です。
全アカウント分のパスワードの再設定、不要な権限や接続の削除、システムにアクセスした記録の確認などの対策を行っておきましょう。
他社システムの引き継ぎに関するよくある質問
最後に、他社システムの引き継ぎでよくある質問をまとめて回答します。
Q1.ソースコードがないと引き継ぎできない?
A.不可能ではないが工数・コストが増えます。
リバースエンジニアリングという手法を用いることで、既存プログラムから仕様書を作成し、運用保守を行うことは可能です。しかし作業量の増加に伴い、費用も増加します。場合によっては、一からシステムを作り直したほうが早く、安く済むこともあるため、状況に応じた判断が必要です。
Q2.契約書で確認するべきポイントは?
A.納品物、著作権の帰属、保守範囲、秘密保持条項、引き継ぎ支援の有無などを確認するとよいでしょう。
旧システム開発会社が何を納品し、その著作権は誰が持ち、どの範囲で保守を行うのか、ということがすべて書かれているはずです。引き継ぎ時の支援についても明記されている場合もあります。
Q3.旧システム開発会社が協力しない場合どうする?
A.まずは契約確認、ログの取得を行いましょう。しかし最悪の場合、引き継ぎではなく再実装の方針検討をすることになります。
契約書に引き継ぎ支援について書かれている場合、その通りに進めましょう。記載がない、あるいは協力しない旨が書かれている場合は、実際に動いているシステムの記録(ログ)を集めておくと、役に立つ場合もあります。
それでも引き継ぎ情報が揃わない場合は、再実装の方向でも検討が必要です。
Q4.引き継ぎにかかる期間の目安は?
A.規模・ドキュメント次第です。
小規模なシステムであれば期間は数週間〜、中〜大規模は数か月みておきましょう。費用も同様で、期間だけでなく難易度によっても大きく変動します。
見積り時に予算を伝えておくと、システム開発会社も見積りを出しやすくなるのでおすすめです。
他社システムの引き継ぎはできる!徹底した事前準備を
他社システムの引き継ぎは、トラブルや情報不足などのリスクを伴うものの、しっかりとした事前準備と計画があれば、スムーズに進めることが可能です。契約内容やドキュメントの整理、システムの現状把握など、地道な確認が引き継ぎ成功のカギになります。
しかし、システムの引き継ぎの際には、旧システム開発会社の協力やシステムの現在の状態と整合の取れた仕様書など、理想的な条件がそろわないことも少なくありません。ですが、当社フレシット株式会社では、そうした“情報が限られた状態”からでも現行システムを解析し、引き継ぎ・運用保守・機能追加までを行うノウハウを蓄積しています。
「今の会社ではもう限界かもしれない」「資料がないから引き継ぎは無理だろう」と感じている場合も、まずは一度ご相談ください。当社は、現行環境の分析から最適な引き継ぎ・再構築プランまで、確実に伴走いたします。
監修者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田 順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

