“見えないデータ”を動かす、横断的データ活用のアーキテクチャ設計
バラバラのデータを「意味のある動き」に変える仕組みとは。
2025-11-09
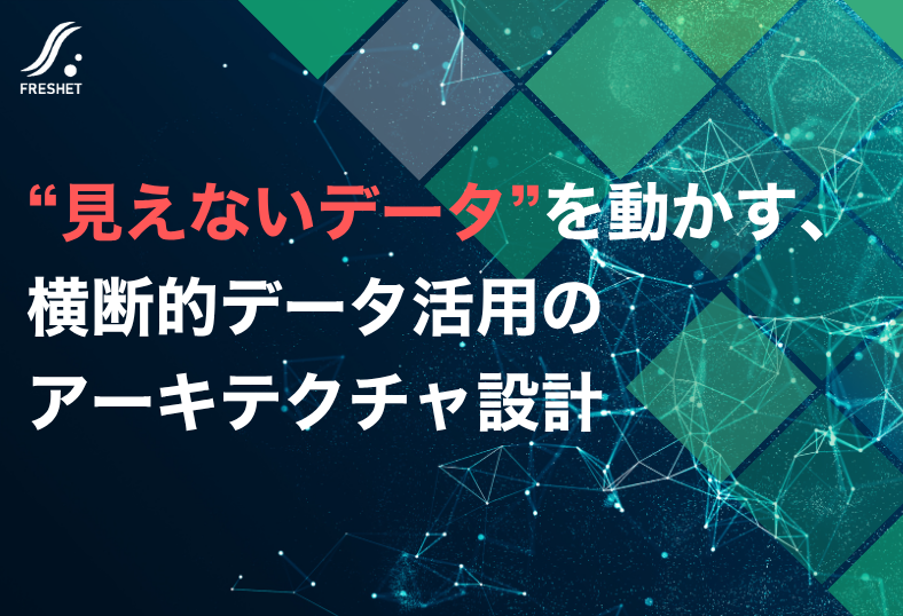
NTTデータが新会社を設立し、介護者支援のためのクラウド型データ連携基盤を構築する──この動きは、介護業界に限らず、多くの企業が直面している「データの分断」という課題に対して示唆を与えています。
社内外に点在するデータをどのように整理し、横断的に利活用できる環境を整えるのか。その鍵を握るのは、アプリケーションではなく“データアーキテクチャの設計思想”です。
本コラムでは、データ活用を支える裏側の構造──API設計・権限管理・メタデータ設計──の3つの観点から、業務効率化とデータガバナンスの両立を実現するための要諦を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】NTTデータ×東京海上、介護分野のDX推進へ──クラウド型データ連携基盤で支援強化
NTTデータは東京海上日動火災保険と共同で新会社「NTTデータライフデザイン」を設立し、働く介護者(ビジネスケアラー)を支援するサービスを開始する。企業には介護実態の把握や研修、相談体制構築を支援し、これらを効率化するクラウドシステムを提供。個人には専門家によるオンライン相談窓口を設け、最適な民間サービス選定をサポートする。特徴は、介護者・企業・介護サービス業者をつなぐクラウド上のデータ連携基盤を構築し、個人情報保護に配慮しながら介護関連データを横断的に活用できる点にある。介護分野でのデータ共有とDXを推進する取り組みとして注目される。
出典:日本経済新聞「ビジネスケアラー支援NTTデータ、東京海上と新会社」2025年10月23日付朝刊
ポイントをひとことで
横断的なデータ活用を支えるアーキテクチャ設計は、単なる技術論ではなく“組織構造の再設計”でもあります。データが部門単位で閉じている限り、どれほど高度なツールを導入しても全体最適は実現しません。重要なのは、業務・データ・権限を一体で設計し、現場の更新がそのまま経営判断に反映される仕組みをつくることです。APIやメタデータの整備は目的ではなく手段。データが流れることで組織が動き、組織が変化を生む──それが真のDXの姿だといえます。
分断されたデータの課題──“動かない情報”が経営を鈍らせる
企業の中には、部門やシステムごとに異なる形式・粒度のデータが散在しています。営業部門の顧客管理システム、製造部門の生産管理、経理部門の会計システム──それぞれが最適化された状態で存在する一方、全体としての整合性が取れていないケースは少なくありません。
このような状況では、以下のような問題が発生します。
- 必要なデータを探すのに時間がかかる
- 同じ情報が複数箇所で管理され、更新漏れや矛盾が生じる
- 経営判断のための分析に時間がかかり、タイムリーな意思決定ができない
つまり、データは“存在している”にもかかわらず、“使えていない”状態です。
この「見えないデータ」を動かすために求められるのが、横断的なデータ利活用を支えるアーキテクチャ設計です。
データアーキテクチャ設計の核心──「つなぐ」と「制御する」を両立させる
データを活かすための設計とは、単にシステム間を連携させることではありません。
真に重要なのは、「つなぐ」と同時に「制御する」ことです。無秩序にデータを流通させれば、セキュリティリスクや整合性の問題を引き起こす可能性があります。
ここで求められるのが、以下の3要素を明確に整理したアーキテクチャです。
- データの出入り口を定義するAPI設計
- アクセス権限を制御する認証・認可の仕組み
- データの意味や関係性を定義するメタデータ設計
これらを有機的に組み合わせることで、単一システムでは実現できない「横断的なデータの可視化・統合・利活用」が可能になります。
API設計──データを安全に“流す道”をつくる
データ連携の起点となるのがAPI(Application Programming Interface)です。
APIは、異なるシステム同士を安全に接続し、必要なデータだけをやり取りするための“通信規約”のような存在です。
たとえば、介護サービスのデータ連携基盤であれば、
- 介護者のプロフィール情報
- サービス提供業者のスケジュール情報
- 利用実績データ
といった多様な情報を、権限に応じて交換できる仕組みを整備する必要があります。
ポイントは、「共通で使える仕組み」と「自社専用の仕組み」をうまく使い分けることです。
たとえば、異なるシステム同士がデータをやり取りする際には、一般的なルールや形式に沿って設計すれば、他システムとの連携や将来の拡張が容易になります。一方で、独自の承認フローなど、業務ごとに特殊な処理が必要な部分は、自社専用の仕組みを用意することで柔軟に対応できます。
フルスクラッチ開発では、この2つの仕組みを自社の業務内容に合わせて設計できるため、現場にフィットしたスムーズなデータ連携が可能になります。
権限管理──データ活用の自由と安全を両立する
データがつながるほど、求められるのが「誰が、どのデータに、どの範囲でアクセスできるのか」という厳密な制御です。
介護や医療など個人情報を扱う分野では、アクセス権限の設計がデータ連携の成否を左右します。
権限管理には主に次の3層構造が有効です。
- ユーザー層:利用者や担当者を識別する仕組み(例:SSO、OAuth2.0)
- ロール層:職種や立場に応じてアクセス範囲を定義(例:管理者、相談員、一般職)
- データ層:フィールド単位でのアクセス制御(例:氏名は閲覧可、要介護度は不可)
この3層設計をクラウド環境で実装することで、セキュリティと利便性を両立したデータ活用が可能になります。特にフルスクラッチ開発では、既存の権限モデルに制約されず、業務フローに合わせた柔軟なロール設計が実現できます。
メタデータ設計──“意味の統一”がデータ利活用を支える
データが共有されても、意味が揃っていなければ活用はできません。
ここで重要になるのが、メタデータ(データの定義や属性情報)です。
たとえば「利用者ID」「顧客コード」「会員番号」など、異なるシステムで同一人物を表していても、命名規則や桁数、属性がバラバラであれば統合は困難です。このような問題を避けるためには、データ項目ごとに以下を明確に定義しておく必要があります。
- データの意味・単位・型
- 更新頻度・出所・責任者
- 他システムとの関係性
メタデータを共通言語として整備することで、組織をまたいだデータ分析やAI活用の精度が向上します。
さらに、メタデータ管理を自動化できる設計にしておくことで、将来的なシステム拡張にも柔軟に対応できます。
横断的データ活用を実現するための“段階的アプローチ”
横断的なデータ利活用基盤を整備するには、一気通貫の大規模開発ではなく、段階的に進めるアプローチが有効です。
- 現状のデータ構造と課題を可視化する
まずは、各システムのデータ項目やフォーマットを棚卸しし、重複や欠損を洗い出します。
この段階で、業務フローや運用体制も合わせて整理することが重要です。 - 最小単位での連携から始める
全システムの統合を目指すのではなく、優先度の高い業務領域(例:顧客・請求・在庫など)から小さく連携を試みます。
これにより、データ流通の“筋道”を検証しながらリスクを最小化できます。 - 共通データモデルを確立する
各システム間で共通して扱うデータ項目について、形式や意味を統一します。
これがメタデータ設計の基盤となり、将来的な拡張性を担保します。 - APIを介したデータ流通を自動化する
一度整備したAPIを中心に、データの取得・更新・分析を自動化。
この仕組みが定着することで、システムをまたいだ横断的なデータ活用が可能になります。
DXの本質は“データが動くこと”
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるシステム刷新ではありません。
真の目的は「データが動く」ことで業務が変わり、人の判断や創造が生まれる仕組みをつくることにあります。
データ連携基盤を設計するという行為は、裏側のアーキテクチャを整備する地味な作業に見えるかもしれません。
しかし、それは企業全体のデータを“使える状態”に変えるための最も本質的な投資です。
業務を横断してデータを利活用できる環境を持つ企業こそ、変化の激しい時代において柔軟に進化できるのです。
まとめ
横断的なデータ活用を実現するには、アプリケーションの導入よりも前に、データをどう扱うかという“構造的な設計”が必要です。
API設計でデータを安全につなぎ、権限管理で流通を制御し、メタデータ設計で意味を統一する。
この3つの視点が揃って初めて、見えなかったデータが動き出します。
企業内外のデータが点ではなく線でつながるとき、業務の効率化だけでなく、新たな価値創出の可能性が広がるのです。
フルスクラッチ開発の最大の価値は、業務の実態とデータ構造を「最初から正しく設計できる」ことにあります。フレシット株式会社では、既製のSaaSやテンプレートでは実現できない“横断的にデータが動く仕組み”を、業務プロセスの理解から共に設計します。APIやメタデータの構造、運用現場での使いやすさまで含めて一貫して開発することで、システムが企業に合わせて成長していく環境を実現します。現場を理解し、未来の拡張性まで見据えたフルスクラッチ開発をお求めの方は、ぜひフレシットにご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

