図面共有が変える製造業の生産効率──“情報の壁”を超えるデータ設計の条件とは
共有できるデータ設計──現場の多様性を保ちながら整合性を築く方法
2025-11-10
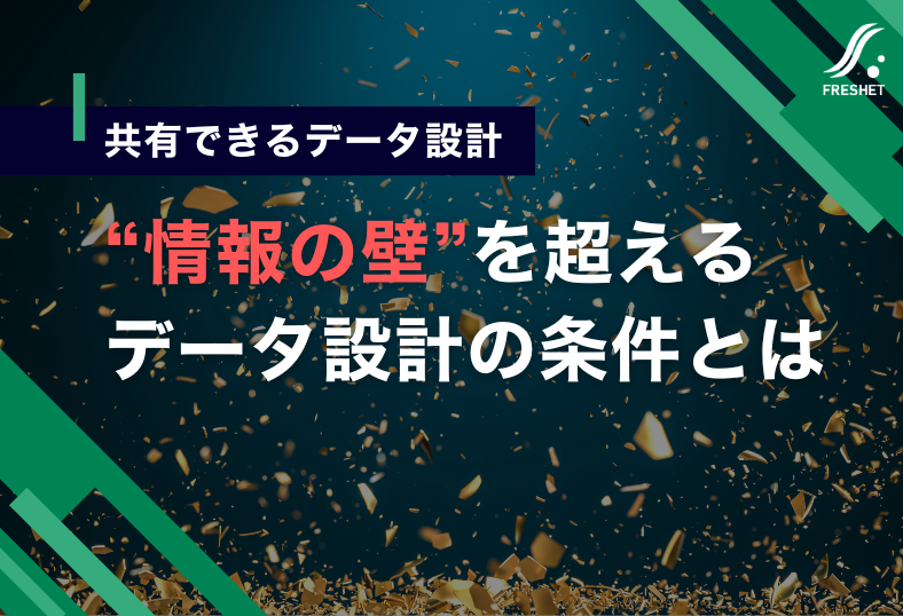
工場や拠点、部署ごとに異なるルールでデータを管理していると、同じ情報を扱っているはずなのに、共有できないという現象が起こります。
「図面」「工程」「顧客」「在庫」──どれも業務の根幹を支える情報ですが、入力ルールや命名規則がバラバラなままでは、システムが分断され、正確な情報活用ができません。
本コラムでは、バラバラな仕組みが生む“情報の壁”を解消し、現場全体でデータを共有・活用できる仕組みをどう設計すべきかを、フルスクラッチ開発の観点から解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】図面の共有・活用で工場間連携を強化、AIが製造ノウハウを可視化
製造現場で図面管理の効率化が進んでいる。仲精機(大阪府)はAIで図面を分析・管理するキャディのシステムを導入し、約6万枚の図面を共有化。従来は工場ごとに異なるルールでデジタル化が進み情報が分断されていたが、共通のフォーマットで作業手順や加工条件を記録し、工場間の仕事の融通や技能伝承が可能となった。熟練社員の図面メモも検索可能となり、暗黙知の継承や生産効率の向上に寄与。図面を核としたデータ共有は中小製造業の競争力を高め、供給網全体の安定にも貢献する。
出典:日本経済新聞「〈小さくても勝てる〉図面から生産・調達改革工場間の垣根なくし仕事融通 AIで職人メモ見える化」2025年10月15日付朝刊
ポイントをひとことで
多くの企業では「データ共有」が目的化し、構造設計の不整合が見過ごされています。入力ルールや命名規則が部門ごとに異なれば、同じ情報でも意味がずれ、分析や連携は成り立ちません。重要なのは統一ではなく整合性です。つまり、異なるシステム同士でも共通の構造と理解で接続できる状態をつくることです。フルスクラッチ開発は、この「整合性の設計」を業務起点で描ける点に強みがあり、現場と経営の情報をなめらかに結ぶための最適な手段といえます。
“同じデータ”でも共有できない現実
多くの企業では、デジタル化が進んでいるにもかかわらず、部門ごとに異なるシステムやツールを使っているため、同じ情報が複数の場所で管理されています。
例えば、営業部ではExcelで顧客情報を管理し、製造部では専用システムに入力し、経理部では別の形式で再入力している。そんな状況が珍しくありません。
それぞれの部門では最適化されているように見えても、全体としては情報がつながらず、手戻りや二重入力が発生し、共有コストが増大します。これは単にツールの違いではなく、「データ構造と運用ルールの不一致」が引き起こす問題です。
情報の壁を生む「構造のズレ」
データが共有できない原因は、システム間で「構造のズレ」が発生していることにあります。
たとえば、顧客情報を例に取ると、Aシステムでは「顧客名」だけを文字列で管理しているのに対し、Bシステムでは「顧客名」「部署名」「担当者」「取引区分」と分かれている場合、統合するときに整合性が取れません。
また、製造現場では「図面番号」や「部品ID」の命名ルールが統一されていないことも多く、拠点ごとに微妙に異なるルールで登録されているため、同じ製品を指しているのにシステム上は“別物”として扱われてしまうことがあります。
こうした小さな違いが積み重なることで、システム間のデータ連携や自動処理が難しくなり、結果として“情報の壁”が生まれるのです。
統一よりも“整合性”を重視する発想へ
では、どうすればこの情報の壁を解消できるのでしょうか。よくある誤解は、「すべてのシステムを統一すればよい」という考え方です。確かに統一すれば見た目はシンプルですが、業務ごとの特性や例外処理を無視してしまうと、現場での運用が破綻します。
重要なのは、「統一」ではなく「整合性」です。すべてを同じ仕組みにするのではなく、共通ルールのもとに“整合性を保てる構造”を設計することがポイントです。
たとえば、
- データ項目の定義(名称・型・桁数・必須/任意)を明確にする
- 共通IDやキー項目を全システムで採用する
- 命名規則やコード体系を統一する
- 更新タイミングや優先システムをルール化する
これらを実現するためには、システム開発会社がデータ設計の段階で「業務間の接点」を丁寧に洗い出し、部門横断で共有できる最小公倍数を見つけ出す必要があります。
データ構造設計の基本は「共通語化」
情報を共有するための第一歩は、“データを共通言語に変えること”です。
人間の会話でも、同じ言葉を使っていても意味が違えば誤解が生じます。
システムにおいてもそれは同じです。たとえば「納期」という言葉一つを取っても、営業では「お客様への約束日」、製造では「出荷完了予定日」、購買では「仕入先からの納入日」と定義が異なる場合があります。
この状態では、データを連携しても正しく分析できません。したがって、全社共通のデータ定義を整備し、誰が見ても同じ意味で理解できる状態をつくることが不可欠です。
フルスクラッチ開発では、この共通語化のプロセスを要件定義の初期段階で行うことができ、「現場での運用ルールを設計に反映する」ことが可能です。これが、既存システムの制約を受けないオーダーメイド開発の大きな強みです。
運用設計が“データの質”を決める
データ構造を整えても、運用が乱れればすぐに品質は落ちます。
情報共有を定着させるためには、日々の運用の中で「正しいデータが、正しい手順で入力される」仕組みが必要です。
たとえば、
- 入力時にフォーマットを自動チェックする
- 必須項目を未入力のまま保存できないようにする
- 更新履歴を残して変更理由を追跡できるようにする
- ロール(役割)ごとに編集権限を制御する
といったルールをシステムに組み込むことで、入力者の意識に頼らずデータ品質を保つことができます。
特にフルスクラッチ開発では、企業の業務フローや責任分解構造に合わせて運用設計を細かく定義できるため、「ルールを運用で徹底する」ことが可能です。これはパッケージソフトや既製品にはない強みです。
分散を恐れず、連携で全体最適を目指す
情報の壁をなくすには、「すべてを一つにまとめる」発想ではなく、「バラバラなまま、つながる構造をつくる」発想が有効です。
たとえば、販売管理・在庫管理・生産管理が別システムであっても、共通のマスタ構造とAPI連携を持たせることで、全体として統一的なデータ活用が可能になります。
このように、分散したシステムを連携で結ぶ設計こそが、現場に負担をかけずに全社最適を実現する鍵です。フルスクラッチ開発は、部分最適と全体最適の両立を目指す企業にとって、柔軟かつ持続的なアプローチを提供します。
データ共有の最終目的は「判断の質を高めること」
データを共有すること自体が目的ではありません。最終的なゴールは、組織全体で意思決定の質を高めることにあります。
経営層がリアルタイムで状況を把握し、現場がデータをもとに自律的に判断できるようになる。そのためには、正確で整合性のある情報基盤が不可欠です。
もし、データが重複・矛盾・欠落していれば、AIやBIツールを導入しても期待した成果は得られません。したがって、システム設計の根幹に「情報共有の思想」を組み込むことが重要なのです。
まとめ
バラバラな仕組みは、業務の多様性を支えてきた一方で、情報の断絶という新たな壁を生み出しています。この壁を壊すには、単なる統一化ではなく、整合性を保ちながら全体をつなぐデータ構造と運用設計が必要です。
フルスクラッチ開発なら、業務特性に合わせて情報の“通り道”を描き、現場の柔軟性を失わずに共有基盤を築くことができます。共有できるデータ設計とは、単にシステムをつなぐことではなく、組織全体が同じ情報で動ける“共通の思考構造”を設計することに他なりません。
フレシット株式会社では、部門や拠点ごとに異なる業務ルールを丁寧に分析し、全体で整合性を保ちながら“つながるデータ構造”を一から設計します。現場の運用を犠牲にするのではなく、実際の業務フローを基点にシステムを構築することで、分断された情報を有機的に連携させることが可能です。既存パッケージでは届かない領域まで踏み込み、企業の実態に合わせたフルスクラッチ(オーダーメイド)開発で、組織全体が同じ情報で動く“仕組みの再設計”を実現します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

