トライアル×NECの流通DXに見る──「発注先」ではなく「共創パートナー」へ、進化するシステム開発の関係性
DXを成功に導くのは、発注関係を越えた“共創”という選択。
2025-11-12
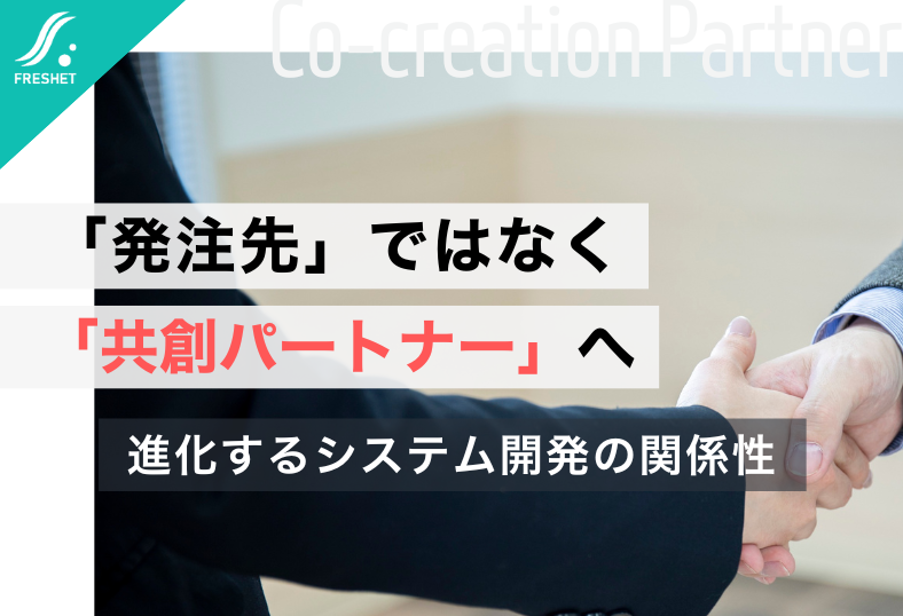
従来のシステム開発は、「依頼して作ってもらう」「納品して終わり」という発注関係が一般的でした。しかし、DX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せる現在、その関係は大きく変わりつつあります。
トライアルホールディングスとNECが協働して構築を進める流通データ連携の取り組みでは、複数企業が共通の基盤を共有し、業界全体の効率化を図る「共創型DX」が進行しています。この潮流は、システム開発会社を“発注先”ではなく“事業の共創パートナー”として捉える考え方の広がりを象徴しています。
本コラムでは、DX時代における新しい開発関係のあり方と、フルスクラッチ開発が果たす役割について考察します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】トライアル×NEC、流通業DXで40兆円のムダ削減へ──業界横断のデータ連携で最適化を加速
ディスカウント大手トライアルホールディングスはNECと協働し、流通各社が在庫・出荷・POSなどのデータを共有する新たな基盤づくりを進める。サントリーやスギHDなど60社超が参画し、異なる規格のデータを統一してサプライチェーン全体を可視化。AI分析により需要予測や発注量を最適化し、欠品や過剰在庫などの非効率を削減する。個社単位から業界全体の最適化を図る「横割りDX」により、流通業界の構造的なムダ・ムラ・ムリの是正を目指す。NECは複数企業に共通基盤を提供する新事業モデルへの転換を進め、業界のDX推進を支える。
出典:日本経済新聞「〈ビジネスTODAY〉トライアル、60社とムダ削減流通データ共有、NECと組む サントリーなど参画」2025年11月1日付朝刊
ポイントをひとことで
DXを単なるシステム導入と捉えるか、事業変革のプロセスと捉えるかで成果は大きく異なります。前者は一度の納品で終わりますが、後者は継続的な改善を前提に、企業の成長とともに進化していきます。共創型の開発とは、発注先を“外部業者”ではなく“思考と実行を共に担うパートナー”と位置づけることです。経営課題を共有し、変化を吸収できる仕組みを育てていく。そこにこそ、DXの持続的な成果を生み出す真の価値が存在します。
共創型DXが示す「発注関係の再定義」
DXの本質は、単なる業務効率化ではなく、事業構造そのものの再設計にあります。
これまでのように、システムを依頼して納品してもらうだけでは、変化の早い市場に対応することが難しくなっています。
トライアルとNECの事例では、60社以上の企業が共通のプラットフォーム上でデータを共有し、在庫や物流の最適化を図る仕組みを構築しています。これは、単独企業の課題解決を超え、業界全体の生産性を底上げする取り組みです。
このようなスキームを実現するには、「どこかに発注して作ってもらう」関係ではなく、事業やデータ構造を共に理解し、長期的に育てていく“共創関係”が欠かせません。
共創型の開発では、システム開発会社が単なる実装担当ではなく、「経営の視点」と「現場のリアリティ」の両方を踏まえた設計パートナーとして機能します。
DXの実現には、技術力だけでなく「どのように業務を変えていくか」を共に考える姿勢が求められているのです。
DX時代に求められるのは「継続的に育てる開発」
従来のシステム開発は、明確な要件を定義し、それを納期までに完成させることがゴールでした。
しかし、DXにおいては、開発の完了が終わりではなく“始まり”です。
市場環境や顧客ニーズの変化が激しい中で、システムもそれに合わせて柔軟に成長していく必要があります。一度納品したシステムを放置してしまえば、数年後には現場の実態と合わず、再び改修コストが膨らむという悪循環に陥ります。
そのため、DX時代のシステム開発は「作って終わり」ではなく、「使いながら育てていく」ことが前提となります。
この考え方において重要なのが、システム開発会社と企業が対等な立場で協議を重ね、事業の変化に応じてシステムを成長させていく“パートナーシップ型”の関係です。
フルスクラッチ開発は、そのための柔軟な基盤を提供します。既存パッケージの制約を受けず、自社の成長ステージや戦略に合わせて機能を拡張できるため、「育てる開発」が可能になります。
共創パートナーに求められる3つの視点
発注型の開発から共創型開発へと移行するためには、システム開発会社にも新たな姿勢が求められます。特に重要なのは次の3つの視点です。
1.事業理解を前提にした設計
共創の第一歩は、クライアントの業務を正確に理解することです。
単に要件を整理するのではなく、「なぜその業務が存在するのか」「どんな指標で成果を測るのか」まで踏み込んで設計する必要があります。これにより、システムが単なるツールではなく、経営を支える仕組みとして機能します。
2.データを軸とした構造的な発想
トライアルの事例のように、複数の企業や部署を横断してデータを共有するには、データ構造の設計力が鍵となります。
DXでは、データの収集・加工・共有・分析の一連の流れを見通した設計が求められます。フルスクラッチ開発では、この流れを自社の業務構造に合わせて最適化できるため、将来的な拡張にも強い基盤をつくることが可能です。
3.継続的改善を前提とした開発体制
DX推進は「導入して終わり」ではありません。
利用者のフィードバックをもとに改善を重ねる体制こそが、成果を左右します。開発後もシステム開発会社と定期的に対話し、改修・追加開発を通じてアップデートしていくことで、システムが“生きた経営資産”になります。
「単発取引」から「共通基盤の共創」へ
NECがトライアルと構築を進める共通プラットフォームは、従来の“個別開発”の枠を越えています。
複数の企業が同じ基盤を利用し、それぞれのデータや業務を持ち寄ることで、業界全体の生産性を底上げするという考え方です。
このような取り組みは、単なるシステム開発ではなく、「共通言語を作る」プロジェクトともいえます。
各社が異なるフォーマットや運用ルールで業務を進めてきた中で、それを統合・再設計するには、システム開発会社に高い理解力と調整力が求められます。
ここでも、フルスクラッチ開発の柔軟性が生きます。既製のシステムでは対応できない“企業ごとのデータ構造”を吸収しながら、共通化・最適化を進めることができるからです。共通基盤を持ちながら、個社ごとの特性を活かす。これこそが、DX時代における理想的な「共創の形」といえるでしょう。
DX成功の鍵は「関係性のデザイン」にある
DXを成功させるうえで見落とされがちなのが、「システムよりも、関係性の設計が重要である」という点です。どれだけ優れた技術を導入しても、事業会社と開発会社の間に認識のズレがあれば、現場に根付かず形骸化します。
共創型のプロジェクトでは、目的や指標、改善サイクルを両者が共有することで、はじめて持続的な成果が生まれます。そのためには、「開発を依頼する側」と「開発を受ける側」という上下関係ではなく、対等な立場での協働体制を築くことが不可欠です。
フルスクラッチ開発は、まさにこの関係性デザインを支える手段でもあります。自社の業務・データ・現場に合わせた柔軟な開発が可能だからこそ、双方が納得感を持ってプロジェクトを進めることができるのです。
まとめ
DX時代のシステム開発は、もはや「発注して終わる」ものではありません。変化の激しい環境に対応し続けるためには、開発会社と事業会社が“共に育てる”関係を築く必要があります。
トライアルとNECが示したように、共通基盤を共有しながら業界全体を変えていく取り組みは、今後のDXの方向性を象徴しています。
発注先から共創パートナーへ。
この転換こそが、企業の持続的な成長を支えるDXの核心といえるでしょう。
フレシット株式会社では、こうした「共創パートナー」としての開発体制を何よりも重視しています。業務の流れやデータ構造を深く理解したうえで、長期的な視点から事業とともに成長するシステムをフルスクラッチで構築します。単なるシステム導入ではなく、「現場が動き、経営が変わる」開発を伴走型で支援することで、クライアント企業が自らの強みを最大限に発揮できる環境を整えます。DXを“発注”ではなく“共創”として実現したい方は、ぜひフレシットにご相談ください。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

