トライアルHDに学ぶ ー 最先端より“最適解”を導く『オペレーションドリブン思考』
最新よりも最適を。現場から始まるシステム開発。
2025-11-14
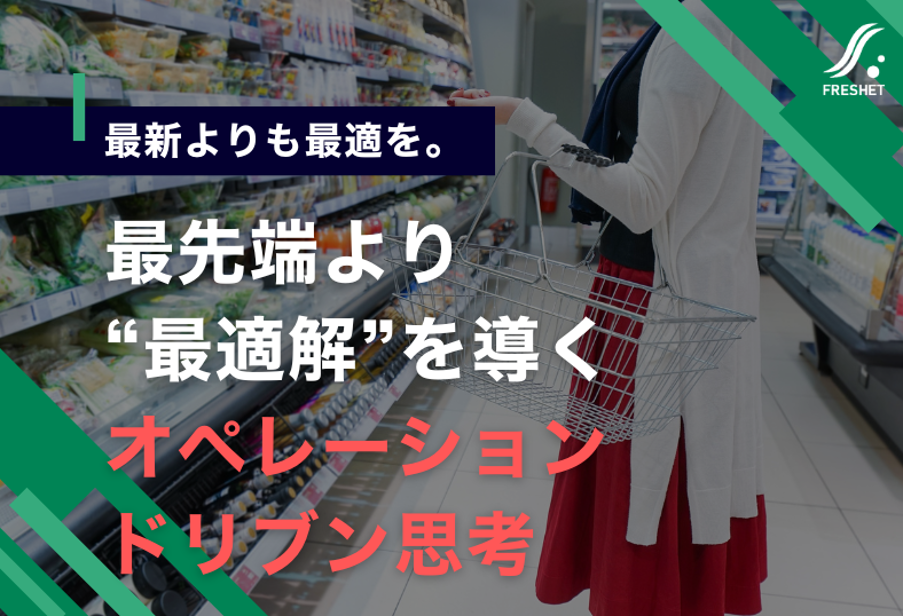
デジタル化やDXの波が加速するなかで、「どんな技術を導入すべきか」という判断に迷う企業は少なくありません。AI、IoT、RPA、生成AI――次々と登場する新しいテクノロジーに対し、「取り残されてはいけない」という焦りから導入を急ぐケースも見られます。しかし、最先端技術の導入が必ずしも業務効率化やコスト最適化につながるとは限りません。
本コラムでは、小売業のトライアルホールディングスが掲げる「オペレーションドリブン」という考え方を手がかりに、企業が陥りがちな“技術ありきのDX”を見直し、現場から成果を生み出すためのシステム開発アプローチを解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】トライアルHD、オペレーションドリブンで挑む都心型小型店戦略
小売大手トライアルホールディングスが都内に小型スーパー「トライアルGO」を展開する。西友の買収で首都圏進出を果たし、母店から総菜供給する新モデルを構築。顔認証による無人レジや自動値下げシステム、カメラによる在庫管理などを導入し、省人化と低価格を両立する。だが同社が重視するのは「技術導入」ではなく「オペレーションドリブン」——現場の業務効率やコスト削減に直結しない技術は採用しない姿勢だ。電子棚札も使用頻度に応じ限定運用。アマゾンの失敗を教訓に、実務起点のDXで競争優位を築こうとしている。
出典:日本経済新聞「トライアル、小型店で都内進出デジタル化、アマゾン教訓」2025年11月3日付朝刊
ポイントをひとことで
オペレーションドリブン思考が示しているのは、「技術が主役ではなく、業務こそが主役」という当たり前のようで難しい原則です。多くのDX失敗は、ツール導入が目的化し、現場の運用や課題構造を深く理解しないまま進むことに起因します。本来システムは業務フローの延長線上にあるべきで、先端技術も“運用をより良く動かすための部品”にすぎません。フルスクラッチ開発は、この考え方を最も忠実に実現できるアプローチであり、企業ごとの固有業務に寄り添った最適解を構築できる点に真価があります。
オペレーションドリブンとは何か
「オペレーションドリブン」とは、現場のオペレーション(運用・業務)を起点に技術を選び、設計・実装していく考え方です。
トライアルホールディングスの永田洋幸社長は「運営の効率化とコスト低減につながらない技術は採用しない」と明言しています。つまり、どれほど先進的な仕組みであっても、現場が動かせなければ意味がないということです。
この考え方は、小売業に限らず、製造業・物流業・サービス業などあらゆる分野に通じます。企業のDXが失敗する多くの要因は、導入する技術が「現場の課題」と結びついていないことにあります。
オペレーションドリブンは、“技術を動かす側”の視点を中心に据えたアプローチなのです。
技術導入の目的を「運用効果」から定義する
多くの企業がDX推進の初期段階でつまずく理由の一つが、「導入目的の不明確さ」です。
AIやRPAを導入しても、「何を改善したいのか」「どうすれば定着するのか」が明確でないままプロジェクトが進行してしまうことがあります。
オペレーションドリブン思考では、最初に“運用効果”を定義することから始まります。
たとえば、以下のような問いを立てます。
- どの業務フローのどの部分が最もボトルネックになっているのか
- その業務を効率化することで、どんな成果が得られるのか
- 改善効果を測定する指標(KPI)は何か
これらを明確にすることで、単なる「ツール導入」ではなく、現場の生産性向上を目的としたシステム開発へと方向性が定まります。
「何を入れるか」ではなく「何を動かすか」
多くの企業が新技術を選定する際、「どのツールを導入するか」から検討を始めがちです。
しかし、オペレーションドリブンの発想では順序が逆です。まず“動かしたい業務”を定義し、そこに最も適した技術を選びます。
例えば、店舗オペレーションを効率化したい場合、AIカメラを導入するよりも、
まず「在庫確認・補充・発注」の流れをどう改善できるかを整理します。
業務フローの可視化を通じて、必要なデータがどこにあり、誰が操作し、どのタイミングで共有すべきかを把握する。
その上で初めて、画像認識AIや自動発注システムの導入可否を判断するのです。
つまり、オペレーションドリブンとは「技術主導ではなく、業務主導でシステムを組み立てる思考法」と言えます。
「最先端」よりも「最適解」を見極める選球眼
トライアルHDが採用した電子棚札の例は象徴的です。価格変更を自動化する先進技術として多くの企業が導入を進めるなか、同社は「毎日安売り(EDLP)」という方針から値札の更新頻度が低く、導入メリットが限定的と判断。青果など必要な範囲に限定して運用しています。
このように、オペレーションドリブンでは“技術を使いこなすための現実的な選択”が重視されます。
無理にすべての工程を自動化するのではなく、「どの部分をデジタル化すれば現場の手間が確実に減るか」を見極めることが、真のDX推進につながります。
企業が取り入れるべきは“最新技術のカタログ”ではなく、“自社の現場課題リスト”です。
システムは業務の延長線上にあるべきであり、目的は常に「現場の運用をより良く動かすこと」にあります。
フルスクラッチ開発がもたらす柔軟性
このような“現場起点の設計思想”を実現するうえで、フルスクラッチ開発は有効な手段となります。
既製パッケージやSaaSは導入スピードが早い反面、業務特有のフローに合わせた細やかな調整が難しく、「運用に合わせた設計」よりも「システムに業務を合わせる」状態になりがちです。
フルスクラッチであれば、既存の業務手順を活かしつつ、
- 入力負担を減らすUI設計
- データの一元化と自動連携
- 属人化を防ぐ権限・承認フローの仕組みなど、オペレーションドリブンの思想を体現できます。
重要なのは、システムを導入することではなく、現場が自然に使い続けられる仕組みを作ること。
そのためには、開発段階で現場担当者を巻き込み、実際の運用シーンを想定しながらプロトタイプを検証していく姿勢が欠かせません。
“デジタル化”と“効率化”を混同しない
DXという言葉が広がるにつれ、「紙からシステムに置き換えた=デジタル化できた」と誤解されるケースもあります。
しかし、単なる置き換えではオペレーションの効率化にはつながりません。
たとえば、Excel管理をクラウドツールに移行しても、承認フローや集計手順がそのままであれば、効果は限定的です。
オペレーションドリブン思考では、まず「業務フローの見直し」から始めます。
デジタル化はその結果として行うものであり、効率化の手段に過ぎません。
ツール導入を目的化せず、現場がどう動くかを中心に考えることが、本質的なDXへの第一歩です。
成功するDXは“身の丈設計”から生まれる
生成AIやIoTなど、企業を取り巻く技術は進化し続けています。
しかし、どんな技術も「使いこなせなければ意味がない」という原則は変わりません。
オペレーションドリブンの発想は、企業が身の丈に合ったDXを設計するための指針といえます。
それは「最新を追わないこと」ではなく、「現場の最適解を追うこと」。
大企業でも中小企業でも、現場の課題は一つひとつ異なります。
現場を理解し、データとオペレーションの関係性を正しく設計することが、
長期的な運用コストの削減と、現場の生産性向上につながります。
まとめ
オペレーションドリブン思考とは、華やかな最新技術を追うことではなく、現場を支える地に足のついたシステムづくりの姿勢です。「何を入れるか」ではなく「何を動かすか」を基準に技術を選ぶことで、システムは“現場の道具”として機能しはじめます。
フルスクラッチ開発は、その思想を最も柔軟に実現できる手法です。
DXの本質は技術導入ではなく、現場が動きやすくなる仕組みをどう設計するかにあります。
最先端よりも最適解。それが、これからのシステム開発に求められる視点です。
フレシット株式会社では、この「オペレーションドリブン」の思想を実践の中心に据えています。
私たちが提供するフルスクラッチ開発は、最新技術を“目的”ではなく“手段”として扱い、現場で本当に機能する仕組みを共に設計していくことを重視しています。
業務フローの棚卸しからプロトタイプ検証、運用保守フェーズでの改善まで一貫して伴走し、システムを「導入して終わり」にしない。
貴社のオペレーションを深く理解し、最適解を導き出す。それが、フレシットの考えるフルスクラッチ開発です。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

