“言われた通りにつくる開発”から脱却──事業課題に踏み込むシステム開発会社の選び方
要望を“そのまま”作るだけなら、いつまでも課題は解けない
2025-11-17
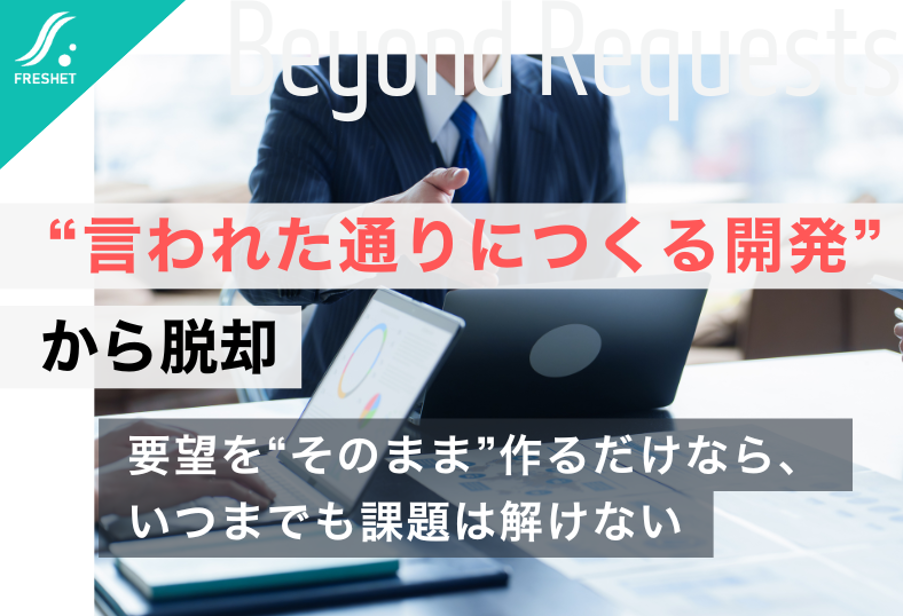
多くの企業がシステム開発で直面するのは、「要望は伝えたのに、業務課題が解決されていない」という根深い問題です。これは、要件を表面的に実装するだけの開発体制が生む典型例です。本来、システム開発会社に求められるのは、要望をそのまま再現することではなく、事業の背景や課題の構造を理解し、必要であれば逆提案を行いながら、最適な解決策へと導くことです。
本コラムでは、単なる“言われた通りの開発”から脱却し、本質的に価値のあるシステムをつくるための開発パートナーの選び方を解説します。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
目次
【記事要約】富士フイルムの「クローン工場」戦略が示す、混沌期に勝ち残る企業の条件
富士フイルムは地政学リスクを見据え、設備やシステムを統一した「クローン工場」を英・日・米・デンマークに短期間で展開。米国での大型受注(約4500億円)につなげ、バイオ医薬版TSMCをめざす体制を築いた。環境変化を逆手に取った迅速な投資判断が勝因とされる。一方、日本企業では保守性が根強く、設備投資が伸び悩む。トライアルは購買データを共有する独自経済圏で小売大手に挑戦。フコクは非ケイレツの立場を活かし、EV向け部品で中国BYDに採用されるなど、混沌を機に変革した企業が成果を上げている。変化の波が速まるなか、既存の枠組みを超えた成長投資の決断が企業の存続を左右する。
出典:日本経済新聞「〈THESTRATEGY〉勝ち筋をつくる(1)巨人の牙城崩す『クローン工場』富士フイルム、混沌逆手に4500億円受注 10年後の存亡かけ現状打破」2025年11月5日付朝刊
ポイントをひとことで
システム開発がうまくいかない最大の理由は、要望をそのまま実装する“作業”に終始してしまう点にあります。要望はあくまで表層であり、その裏には業務の非効率や意思決定の歪みなど、もっと深い構造的な課題が潜んでいます。本来求められるのは、要望を鵜呑みにせず、その背景にある業務ロジックや運用の前提を丁寧に読み解き、必要に応じて逆提案できる開発パートナーです。技術力以上に「課題を定義し直す力」が、長期的に機能し続けるシステムを生む鍵になります。
なぜ「言われた通りにつくる開発」では成果が出ないのか
システム開発プロジェクトの多くは、発注側が要求を伝え、開発側がそれを形にするという流れで進みます。しかし、この構造には大きな落とし穴があります。
発注者自身が課題を正確に把握できているとは限らないためです。
発注者は日々の業務で課題を感じていても、それが“症状”に過ぎないのか、“構造課題”なのかを切り分けることは容易ではありません。
たとえば「操作画面を増やしたい」「この項目を追加したい」といった要望は、一見明確に見えますが、その裏には業務フローの不整合、権限管理の不備、データ構造のズレなど、別の本質課題が潜んでいるケースも多いのです。
システム開発会社が要望をただ実装するだけでは、これらの構造課題に踏み込めません。結果として、
・機能は増えたのに業務が改善されない
・運用負荷が増える
・次々と追加開発が必要になる
といった“終わりのない改修”につながります。
本当に必要なのは、要望に従うだけの開発ではなく、課題の本質に迫る姿勢です。
“もの言うパートナー”が提供する価値
新聞コラムで紹介されたフコクの例では、顧客の課題を「持ち帰らず」現場で解決し、必要であれば逆提案まで行う“もの言うサプライヤー”の姿勢が信頼を生みました。システム開発でも同じ構造が成り立ちます。
顧客の課題を理解するためには、業務の流れ・判断基準・顧客体験・現場の制約まで踏み込む必要があります。この理解が欠けると、システムは単なる作業の電子化に留まり、企業価値を高める構造改革の道具になりません。
逆に、課題を深く理解し、以下のような視点で逆提案できるシステム開発会社はプロジェクトの成功確率を大きく高めます。
・その要望の背景にある本当の課題は何か
・既存プロセスを見直した方が良いのではないか
・データ構造を変えた方が将来的に拡張性が高いのではないか
・業務負荷を減らすために別のアプローチが採れるのではないか
・機能追加ではなく業務ルールの改善が先ではないか
このような視点を持つ開発会社は、単なる“作業者”ではなく、プロジェクトの成功を共に担う“パートナー”になります。
課題に踏み込める開発会社は何が違うのか
課題に踏み込めるシステム開発会社と、言われた通りにしかつくれないシステム開発会社の違いは、技術力だけではありません。プロジェクトの上流から関与し、事業側の判断基準を理解する力が重要です。
業務理解力が高い
業務フローを図面ではなく“動き”で捉えることができるシステム開発会社は、課題の構造を正確に掴めます。現場の制約や人的オペレーションも含めて理解できるため、解決策の精度が高まります。
要件定義力が強い
発注者が説明しきれていない前提条件を整理し、必要であれば質問や検討事項を提示し、曖昧さを排除します。曖昧な要件ほどプロジェクトの失敗要因になるため、この能力は不可欠です。
逆提案ができる
「言われた通り」ではなく、「もっと良い選択肢」を提示できるシステム開発会社は、業務改善とシステム構築を両輪で考えています。顧客の業務に踏み込んで考えるからこそ可能な姿勢です。
技術と業務を往復しながら考えられる
技術だけではなく業務、業務だけではなく技術。この往復がスムーズにできるシステム開発会社は、システムの“仕様を満たすための開発”ではなく“成果を出すための開発”ができます。
“要望ベース”から“課題ベース”への転換が必要
現代のシステム開発では、企業側も発注スタイルを変える必要があります。
特に、要望リストだけを渡して「この通りに作ってください」という発注方法は、複雑化するデータ構造・高度化する業務要件に対応できません。
企業が求めるべきは、
「この要望は、どの課題とつながっていますか?」
と問い返してくれるシステム開発会社です。
この問いがあるだけで、プロジェクトの方向性は大きく変わります。
・本当に必要な機能だけが残る
・不要な開発コストを削減できる
・業務プロセスそのものが改善される
・運用フェーズの負荷が減る
言い換えれば、“課題を正しく定義できるシステム開発会社”こそ、最終的なコストパフォーマンスが最も高いのです。
システム開発会社を選ぶ際に見るべきポイント
では実際に、どのような観点でシステム開発会社を選べば良いのでしょうか。以下は特に重要な基準です。
ヒアリング時に「質問の質」が高い
本質的な課題を見抜くため、現場の動きや判断基準に関する質問が多いシステム開発会社は信頼できます。
業務の“前後”まで踏み込んで聞いてくれる
システムが触れる範囲の外側まで把握しようとする姿勢は、結果として開発の正確性と汎用性を高めます。
「その要望は本当に必要ですか?」と言ってくれる
これが言えるシステム開発会社は、成果にコミットする覚悟がある証拠です。
代替案・改善案を提示してくれる
選択肢を提示できるシステム開発会社は、理解が深く経験値が高いシステム開発会社です。
開発中にも柔軟に軌道修正できる
課題が見えた段階で方向転換できるのは、フルスクラッチの強みを理解し、“設計しながら考える”姿勢がある証です。
まとめ
システム開発は「言われた通りにつくる」だけでは、企業の課題解決にはつながりません。要望の背景にある本質的な課題に踏み込み、必要であれば逆提案を行う“もの言うパートナー”こそ、長期的に企業価値を支えるシステムを生み出します。課題を理解し、業務の前後を含めた構造的な視点で提案できる開発会社を選ぶことが、プロジェクト成功の最も重要な要素になります。
“言われた通りにつくる開発”では、本質的な課題解決にはたどり着けません。システムが本来果たすべき役割は、業務の矛盾や非効率を解消し、事業そのものの生産性と再現性を高めることです。だからこそ、課題の構造を深く理解し、必要であれば要望を再定義しながら最適解へ導く姿勢が欠かせません。
フレシット株式会社では、この「課題に踏み込む」スタンスを最も大切にしています。要件を鵜呑みにするのではなく、業務の流れ・制約・判断プロセスまで踏まえて本当に必要なシステム像を共に描きます。フルスクラッチの柔軟性を活かし、既存のやり方に縛られない逆提案や改善提案を行うことで、長く使える“動く資産”としてのシステムを構築します。
要望通りに作るだけでは物足りない、課題の核心から整理し直したい。そのような思いがあれば、ぜひ一度ご相談ください。貴社の事業の未来を見据えた、本質的なシステム開発をご一緒いたします。
>>フルスクラッチ(オーダーメイド)のシステム開発について詳細はこちら
著者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

