システムリプレイスの進め方とは?流れや失敗しないためのポイントなどを解説
2025-04-14
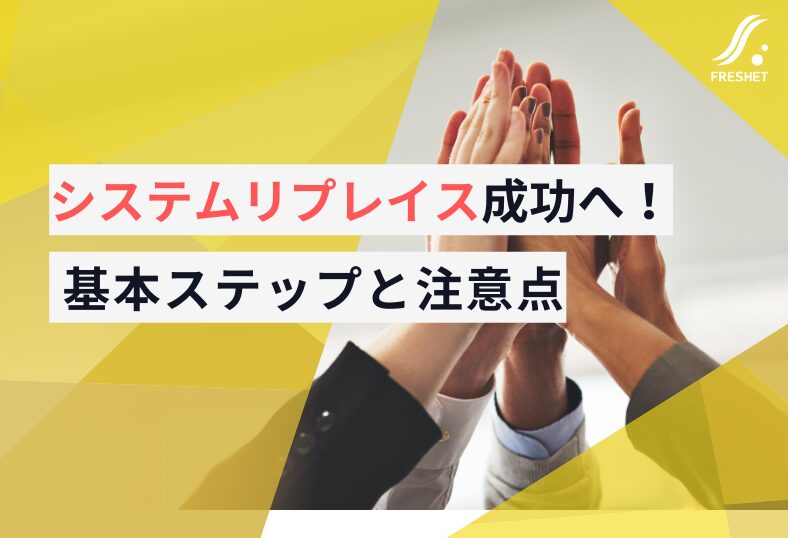
IT技術の発展が目覚ましい現代において、企業が運用するシステムにも日々変革が求められています。
企業の成長や市場の変化に対応するためには、古いシステムから新しいシステムへの刷新するシステムリプレイスが不可欠です。
しかし、システムリプレイスは適切な計画や手順を踏まずに進めると、想定外のコストや業務への影響が出てしまうリスクがあります。
この記事では
- システムリプレイスとは
- システムリプレイスの進め方 6つのSTEP
- システムリプレイスで失敗しないための5つのポイント
について解説します。
自社の目的にあったシステムリプレイスを実施し、業務運用をより効率化させるため、ぜひ参考にしてください。
目次
システムリプレイスとは
システムリプレイスとは、古くなったシステムを新しいシステムに置き換えることを指します。
類似した言葉にシステムマイグレーションがありますが、これは現行のシステムやデータを新しい環境に移すことを指し、システム自体は同じものを使います。一方、システムリプレイスは環境だけでなく、システムそのものを全く別のシステムに置き換えます。既存の契約管理システムを外部のクラウドサービスに移行することもシステムリプレイスのひとつです。
システムリプレイスの目的
システムリプレイスには5つの目的があります。順に解説します。
- システムの老朽化防止と故障予防
- 業務の効率化や生産性向上
- セキュリティ強化とコンプライアンス遵守
- 維持費・運用保守コストの削減
- 事業成長に対応するシステム構築
01.システムの老朽化防止と故障予防
システムは長年使用すると老朽化し、故障の原因につながります。
国税庁が定める自社利用目的のソフトウエアの耐用年数(原価償却)は5年です。この5年を目安に企業はシステムリプレイスを検討する傾向にあります。
しかし、必ずしも5年でシステムリプレイスをしなければいけないということではありません。システムリプレイスの必要性は企業や業務によってさまざまです。リプレイスの時期は企業の戦略などにあわせて検討しましょう。
02.業務の効率化や生産性向上
システムリプレイスではシステムを最新のものに置き換えるため、業務の多様化に伴うビジネスや、市場そのものの変化に対応することが可能です。
また、システムリプレイスはDX(デジタルトランスフォーメーション)につながります。DXとは、業務プロセスやサービスなどを、デジタル技術を活用して変革することです。
今まで手入力で行っていた勤怠管理の出勤記録をパソコンのログインと連動させて自動化したり、部署によってバラバラに管理していたデータを新システムで一括管理したりすることなどがシステムリプレイスにおけるDXとして挙げられます。
新システムによって業務を効率化し、生産性を向上することがシステムリプレイスには期待されるのです。
>>DXを推進するためのシステム開発についてプロが解説
>>DXとIT化の違いとは?DXが求められている理由についても解説
>>アナログ業務をデジタル化したい方へ!重要なポイントやよくある失敗についても解説
03.セキュリティ強化とコンプライアンス遵守
システムリプレイスによって既存システムでは対応が困難だった最新のセキュリティ対策を導入し、コンプライアンスを守ることが可能です。
企業やビジネスにおいて、ITサービスやそれを支えるシステムが脅威にさらされることは、業務停止を引き起こしかねません。古いシステムを使い続ければそのリスクは高まる一方です。安定した業務運営のためにも、システムリプレイスは不可欠です。
04.維持費・運用保守コストの削減
システムは古ければ古いほど維持費や運用保守コストがかかる傾向にあります。
例えば、自社にサーバーを持つオンプレミス運用の場合だと、修理や部品交換に莫大な手間とコストがかかります。オンプレミス運用からクラウドサービスにシステムを置き換えることで、運用保守担当の作業負担を軽減し、運用保守コストの削減が可能となります。
>>運用保守とは?それぞれの違いや外部に依頼する際の注意点についても解説
05.事業成長に対応するシステム構築
システムリプレイスでは、数年後の事業成長を見据えた新システムの導入も可能です。拡張性を持たせたり、AIやビッグデータの活用も行えます。将来性を見据えた検討が重要です。
システムリプレイスの4つの方式
システムリプレイスの方式について、順に解説していきます。
| 方式 | 特徴 | メリット | デメリット | 適したパターン例 |
|---|---|---|---|---|
| 一括移行 | 新システムへ一気に移行 | ・移行期間が短い ・互換性を気にしなくていい | ・システム停止時間が必ず発生 ・問題発生時の影響が大きい | ・既存システムが古すぎて一括で変えたい場合 ・停止時間のあるサービス |
| 段階移行 | 新旧システムを共存させ、段階を踏んで移行 | ・システムを完全停止しなくてよい ・1つずつの段階ごとは移行作業が短時間で済む | ・移行完了までに時間がかかる ・互換性の問題が出る可能性が高い | ・大規模なシステム ・複雑なシステム |
| 並行移行 | 新旧システムを並行稼働し、検証完了後に移行 | ・運用結果を新旧システムで比較可能 | ・新旧システムの管理コストが増える ・移行完了まで時間がかかり移行コストも増える | ・官公庁 ・金融機関 ・医療機関 |
| パイロット移行 | 先行部門のみ移行。検証完了後に他の部門へ展開 | ・先行部門のノウハウを活かせる | ・移行完了までに時間がかかる ・先行部門で成功しても、他部門では問題がでることも | ・新しいビジネスモデルをシステム化する ・既存システムと全く異なるシステム |
一括移行
一括移行方式とは、既存システムから新システムへ一気に切り替える方法です。
既存システムが非常に古く、システムを一気に刷新したい場合に有効といえます。また、夜中にシステムを使用しない時間があるなど、システムを一定時間止めても問題ない場合にもおすすめです。
切り替えが一度で済むため、移行作業が比較的簡単です。移行そのものの手間やコストを抑えることができます。また、切り替え後に旧システムとの互換性を気にせず移行できることも特徴です。しかし、移行作業中はシステムを完全停止するので業務影響が出やすく、移行中に問題が発生した場合は影響範囲が大きくなってしまう傾向にあります。
段階移行
段階移行方式とは、既存システムから新システムへ機能や段階に分けて少しずつ移行する方法です。
複雑な機能をもった、一括で移行できない大きなシステムなどに適した方法になります。例えば、利用者が多くシステムが複雑な場合は、機能ごとにシステムを置き換える段階移行がおすすめです。
システムを完全停止させずに移行でき、1つ1つの切り替え作業時間は短くできます。しかし、最終的な移行完了までには段階を踏むので時間がかかるという問題があります。また、新旧システムが一時的に共存するので管理が複雑になったり、新旧システムの互換性で問題が出たりする可能性があります。
並行移行
並行移行方式とは、新旧システムを並行稼働させ、新システムの検証が完了してから完全に移行する方法です。
システムリプレイスのリスクを最小限にしたい場合に効果的だといえます。官公庁や金融機関、医療機関など、特にミスが許されない業界で採用されることが多いです。
移行中に旧システムを止めないため、新システムと運用状況を比較することができ、より安全に移行することができます。しかし、新旧2つのシステムが稼働するのでその分システムの管理コストが増えるのと、移行完了まで長い期間を要するため移行コストが増えることは覚悟しておきましょう。
パイロット移行
パイロット移行方式は、一部の部門をパイロット(=先行)部門とし、新システムを試験的に導入する方式です。パイロット部門で運用が安定するまで確認してから、他部門へ展開できます。
新しいビジネスモデルをシステムに導入する場合や、新たな技術を試験的に導入する意味合いが強いです。
試験運用でノウハウを得ることができ、問題が発生しても影響を受けるのはパイロット部門だけなので影響が少なくすむことがメリットです。
しかし、部門ごとに移行を行っていくため、移行の完全完了までに時間がかかります。また、パイロット部門で成功した場合でも他の部門独自の原因で移行がうまく行かない可能性は否定できません。
システムリプレイスの進め方
ここではシステムリプレイスの進め方を6つのSTEPに分けて解説します。
- 現状分析と課題の整理
- 新システムの要件定義
- ベンダー選定・システム設計
- 開発・テスト
- 移行計画の策定と実施
- 本番運用・改善
STEP1:現状分析と課題の整理
システムリプレイスの目的は企業やシステムによって異なります。
現状を分析し、何が課題なのか把握することで、システムリプレイスの目的を明確にしておくことが重要です。なぜなら、目的があやふやなままリプレイス計画を立ててしまうと、期待した効果が得られず、コストが重なっても効果が出ない、という結果を招きかねません。
STEP2:新システムの要件定義
現状の課題を把握したうえで、新システムに対する要件定義を行います。要件定義とは、「何を実現したいのか」を明確にすることです。
要件定義では洗い出した課題に対して、
- 何をどこまで改善したいのか
- どの課題の対応が優先順位が高いのか
- いつまでに移行を完了したいのか
などを整理していきます。
要件定義が不十分な状態でリプレイスを進めてしまうと、実現したかったことが達成できず、業務にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
>>要件定義が失敗する原因は?6つの失敗事例から学ぶ対策を解説
STEP3:ベンダー選定・システム設計
要件定義の次は、ベンダー選定に入ります。ベンダーとは、システム開発においてシステムの開発や構築を担う委託先のことです。
ベンダーと契約した後は、要件定義に従ってシステムの具体的な設計を行います。ベンダー主導の工程ですが、企業担当者はシステム設計について要件漏れや認識齟齬がないか注意深く確認することが重要です。要件定義からベンダーに入ってもらうことも、認識齟齬がなくなるので有効な手段といえます。
STEP4:開発・テスト
設計が完了すると、次はシステム開発です。システム開発はベンダーが進め、個別の機能についてのテストもベンダー内で行われます。
しかし、機能を連結し、システム全体のテストを実施する際には、企業担当者もテスト結果の確認が必要です。ベンダーはシステムのプロではありますが、業務のプロではありません。業務要件を満たしているか、最終的には企業担当者が責任をもって確認しましょう。
STEP5:移行計画の策定と実施
開発とテストの次は、移行計画を考えます。移行計画とは、旧システムから新システムへの切り替え作業の計画のことです。
何月何日の何時から切り替えを始めて、という具体的な手順を明確にします。移行中にトラブルが発生していないか確認するチェックポイントを計画に設けることも重要です。
計画を策定した後、その移行手順で問題ないか確認するため、移行リハーサルを行います。問題点が解消されるまでリハーサルを繰り返し、はじめて移行が可能な状態になるのです。
STEP6:本番運用・改善
システムリプレイスは移行が終われば完了というわけではありません。実際に新システムが問題なく稼働しているか、監視も必要です。
システム上の問題が起こっていないことはもちろん重要ですが、要件以外の改善点がある場合なども記録しておきましょう。それが、将来的にシステム改修をする場合の新たな要件となります。
システムリプレイスで失敗しないためのポイント
ここからはシステムリプレイスで失敗しないための5つのポイントを解説します。
- 目的と要件の明確化
- 既存業務の最適化
- 適切な移行方式の選択
- リプレイス後のサポート
- 根拠のあるベンダー選定
01.目的と要件の明確化
システムリプレイスにおいて、何が課題で何を解決しなければいけないのか、どうしたいのか、優先度などをベンダー頼りにせず企業側が主体となって具体的に決めることが重要となります。
具体的には、RFP(Request for Proposal:提案依頼書)を用意するのが効果的です。RFPとは、システムベンダーに具体的な提案を依頼するために使用する書類です。
02.既存業務の最適化
システムリプレイスのタイミングで、業務プロセスの見直しも行いましょう。プロセスを最適化することで、新システムにあったサービスを検討することができます。業務フローの整理、自動化できる業務の洗い出しなどを行うことが重要です。
03.適切な移行方式の選択
どの移行方式が企業や対象のシステム、業務に適しているか、コストや時間軸も考慮したうえで、検討しておきましょう。
例えば、24時間対応が必須となるカスタマーサービスのシステムで一括移行方式を選択してしまうと、業務停止期間が発生してしまいます。
逆に、段階移行方式や並行移行方式などを選択すると、移行完了の全体的な期間は延びるため、移行コストも増加します。業務を優先するのか、移行コストの削減を優先するのか、業務影響とコストのバランスを考えて適切な移行方式を選択しましょう。
04.リプレイス後のサポート
システムリプレイス後は、新システムに利用者が慣れるまで時間がかかります。
新システムを早く定着させるためには、十分なアフターフォローが必須です。
新システムの使い方レクチャー、問い合わせ窓口の設定など、どういったフォローを行うかリプレイスの前に具体的に決めておきましょう。
05.根拠のあるベンダー選定
選定理由について誰が聞いても納得できるようにしましょう。ベンダー選定のポイントについて順に解説します。以下のポイントを参考に比較してみてください。
- 導入事例の詳細な評価
- 開発後のサポート体制
- コストと導入効果のバランス
01.導入事例の詳細な評価
多くのベンダーでは、導入事例や評価をHPなどに記載していますので、選定の際にはよく確認をしましょう。特に自社と同業種の導入実績や、業界特化型のサービスを持っているかなどが重要です。
02.開発後のサポート体制
ベンダーやプランによって開発後のサポートが異なります。
運用保守対応があるか、いつまで運用保守対応してくれるか、問い合わせ対応が可能か、などがポイントです。また、企業側もどこまでサポートしてほしいか明確にしておきましょう。
03.コストと導入効果のバランス
コストは安ければ安いほどよいというわけではありません。しかし、削減できるコストは削減すべきです。
- ベンダーはコストに見合った対応をしてくれるか
- 過剰なサービスが原因でコストが膨らんでいないか
- 提案内容に過不足がないか
など、十分にチェックしましょう。
目的にあったシステムリプレイスを
システムリプレイスは、これが絶対に正解だというものはありません。
企業がもつ既存システムはそれぞれ異なります。また、どんなシステムに変えたいのかもさまざまです。システムリプレイスで何をいつまでに実現したいのか。そもそも今抱えている課題は何か。しっかりと検討した上で取り組みましょう。
ぜひ、自社の目的にあったシステムリプレイスを成功させ、業務の生産性向上や、企業の成長につなげてください。
さいごに
システムリプレイスは、単なるシステムの入れ替えではなく、企業の未来を左右する重要な経営判断の一つです。だからこそ、自社の課題や目的に深く寄り添い、最適な形で伴走してくれるパートナーの存在が不可欠です。
フレシット株式会社は、フルスクラッチ開発に特化し、企業ごとの業務プロセスや成長戦略に最適化されたオーダーメイドのシステム構築を得意としています。豊富な実績と、丁寧なヒアリング・提案力で、お客様にとって「本当に必要なシステム」をゼロから共に作り上げます。
「汎用的なサービスでは物足りない」「業務にぴったり合った仕組みを作りたい」そんな想いをお持ちの方は、ぜひ一度、フレシット株式会社にご相談ください。確かな技術力と柔軟な対応力で、理想のシステムリプレイスを実現します。
監修者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田 順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

