社内システムの構築方法とは?3つの手法を徹底比較!
2025-08-06
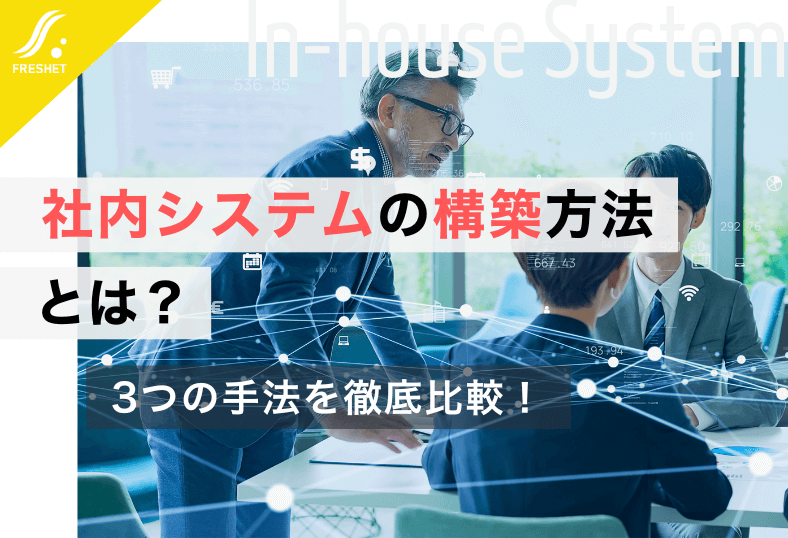
業務が属人化している、Excel管理に限界を感じている。こんなとき、検討したいのが社内システムの構築です。
社内システムとは、企業内で利用するシステムのことで、業務効率化や生産性向上を目的として構築します。とはいえ、「ノーコードで作るべき?」「システム開発会社に頼む?」「そもそも何から始める?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、
- 社内システム構築のメリット・デメリット
- 社内システム構築の3手法の徹底比較
- 社内システム構築の手順7STEP
について解説します。
目的にあった社内システムを構築し、より効率的で生産的な業務運営を目指しましょう。
【関連記事】
Excel管理に限界を感じていませんか?脱Excelの方法を解説します。
目次
社内システムを構築する5つのメリット
社内システムを構築することで、多くのメリットを得ることができます。まずは、その代表的な利点を把握しておきましょう。
業務の効率化・自動化
社内システムの構築によって、手作業やExcelなどで対応していた業務をシステム化することができます。結果として、定型的な業務の負荷が減り、より創造的な仕事に人員リソースをあてがうことが可能になります。
>>アナログ業務をデジタル化したい方へ!重要なポイントやよくある失敗についても解説
情報の一元管理と見える化
社内システムを活用することで、業務に必要な情報を一元管理することが可能になります。さらに、社員が必要なときに、必要な情報へアクセスできるようになることもメリットでしょう。
属人化の解消
社内システムを構築することで、業務の属人化を防ぐことができます。「Aさんしかこの業務を知らない」という状況がなくなるため、チーム全体で業務にあたることができます。
業務プロセスの見直し
社内システムを構築するには、既存の業務プロセスの洗い出しが欠かせません。この過程を通じて、無駄な工程を省いたり、手順を最適化したりすることで業務全体の効率化やプロセスの見直しにもつながります。
将来的な拡張性
業務を社内システムに落とし込むことで、拡張性を持たせることができます。
例えば、導入当初は勤怠管理のみの運用だったとしても、後から給与計算や申請ワークフローなどの周辺機能を追加することも可能です。結果、自社の成長やニーズに合わせたシステムを構築できるのです。
社内システムを構築する3つのデメリット
ここまでメリットをご紹介してきましたが、一方で社内システムを構築する上でのデメリットも存在します。メリット・デメリットの両面を把握した上で、判断することが重要です。
要件定義の失敗により、開発そのものがうまくいかない
社内システムの構築が失敗する原因は、実は要件定義の段階にあります。逆にいえば、ここで課題や目的を正しく整理できれば、社内システムの構築は成功に近づくといえるでしょう。
要件定義の失敗をはじめ、システム開発が失敗する原因は以下のコラムをご確認ください。
3つのコスト(初期/開発/運用保守)がかかる
社内システムの構築には、当然ですがコストがかかりますので、費用と効果のバランスを見極めることが重要です。
- 初期コスト
社内システムを構築するにあたって必要となるコストです。サーバや製品といったリソースのコストも含まれます。 - 開発コスト
システム開発会社への委託費や自社の人的リソースにかかるコストです。 - 運用保守コスト
社内システムを運用していくために必要なコストです。
>>システム開発の費用相場は?費用を抑えるコツや依頼先選びのポイントについても解説
>>システムのランニングコストの相場はいくら?コスト削減方法についても解説
運用までに時間がかかる
社内システム構築には短くとも数か月、大規模のものでは数年かかることもあります。すぐに運用できないため、既存業務と並行した開発が必要です。どの程度の期間、既存の方法で業務が耐えうるのか、予め想定しておかなければなりません。
社内システムの構築における3つの手法
社内システム構築には、主に3つの手法があります。それぞれの手法のメリット・デメリット、目安となる期間や費用を解説します。
| ノーコード開発 | システム開発会社への委託 | 内製(自社開発) | |
|---|---|---|---|
| メリット | ・開発スピードが早い ・非エンジニアでも対応可能 ・比較的コストが安い ・改修・追加が柔軟 | ・要件定義から運用まで一括対応可能 ・技術的に高度な開発にも対応 ・品質・保守性が高い ・自社の負担が少ない ・大規模システムを計画しやすい | ・自社でノウハウを蓄積できる ・カスタマイズ性が高い ・社内の業務に密着した開発が可能 |
| デメリット | ・複雑な要件には不向き ・セキュリティや拡張性に限界あり ・サービス依存のリスクあり | ・コストが比較的高め ・企業側でシステム開発会社の管理が必要 | ・開発リソースの確保が困難 ・専門知識が求められる ・立ち上がりまでに時間がかかる |
| 期間目安 | 1〜3か月 | 3~9か月 (規模・業務範囲により大幅変動) | 6〜12か月以上 (規模・企業の状況により大幅変動) |
| 費用目安 | ・自社での場合、数千円~数万円(サービスの月額利用料) ・開発支援を受ける場合は50万〜300万円程度 | 100万〜3,000万円程度 (規模・業務範囲により大幅変動) | 人件費+初期コスト |
| 総評 | ・速度重視 ・お手軽さ重視 ・複雑な開発は不向き | ・品質重視 ・大規模開発可能 ・複雑な開発にも対応 | ・ノウハウ蓄積重視 ・IT人材の確保が必須 ・開発を急ぐ場合には不向き |
ノーコード開発
ノーコード開発とは、プログラミングの知識やスキルがなくても開発できる手法です。主に専用のアプリケーションやWEBサービスを利用し、図形をパワーポイントに貼り付けるような感覚で開発できるのが特徴です。
最大のメリットは、エンジニア人材を確保せずに開発が進められることです。スモールスタートにも向いており、初期コストを抑えやすいのもメリットでしょう。しかし、既存の部品で構築するため、複雑な要件には対応できない点には注意が必要です。
シンプルなシステムであれば1か月程度で構築可能で、費用は月額数千~数万円で済む場合もあります。ただしランニングコストには留意してください。
なお、ノーコード開発をシステム開発会社に委託することも可能ですが、その場合は50万~300万円程度の費用がかかるため、コストが安くなるというノーコード開発の利点はあまり感じられないでしょう。
システム開発会社への委託
社内システム構築は、システム開発会社に委託するケースが現在の主流です。外部に委託することで、要件定義から運用保守まで一括して対応してもらうことが可能です。技術的に高度な要件や複雑なシステムにも対応できる点が大きな強みといえます。
開発期間はシステムの規模に比例して長くなる傾向にありますが、短くとも3か月、一般的には9か月前後での完了が目安となります。費用も比較的高くなりますが、プロに任せられるという点において、最も信頼できる手法といえます。
システム開発に慣れていない場合や、人的リソースに余裕がない場合は、システム開発会社への委託をおすすめします。
内製(自社開発)
システム開発会社に委託せず、自社でシステム開発を行うことを、内製と呼びます。
メリットとしては、自社にシステム開発のノウハウが残せること、社内の業務により密着した開発がしやすいことなどが挙げられます。
一方で、内製の場合はIT人材を常に確保しておくことが必要があるため、一定の体制・予算が求められます。特に中小企業では、専門人材の採用や育成が難しいケースも多いため、ハードルの高い手法といえます。
既にITチームが社内に常駐している企業の場合、開発期間は6~12か月が目安となりますが、一からIT人材を確保する場合には数年単位の期間がかかります。通常業務の合間で対応しようとすれば、さらに長期化することでしょう。
なお、費用については社内の人件費が主なコストとなりますが、使用するツールやガブサービスの導入費用などの初期コストがかかる点に注意が必要です。
社内システム構築の進め方
ここでは社内システム構築の進め方の手順を7つのSTEPで解説します。
STEP1:業務課題の洗い出し
社内システムを構築するためには、業務の洗い出しが必須です。
どの業務をどのようにシステム化するのか検討するために、自社がどういった業務課題を抱えているのか把握しましょう。
STEP2:目的と要件の明確化
社内システム構築の目的と要件を明確にします。
この工程では洗い出した業務課題に対し優先度を決めることが重要です。1つの社内システムで、企業が抱える業務課題をすべて解消することは基本的にできませんので、どの課題を優先的に解決すべきか判断が必要になります。
優先度の設定に失敗すると、本当に解決したかった課題がそのままにされたり、役に立たないシステムが出来上がったりすることもあるため、慎重に検討しましょう。
>>要件定義が失敗する原因は?6つの失敗事例から学ぶ対策を解説
STEP3:構築方法の検討
要件定義に対し、どの手法で構築を行うのかを検討します。それぞれの手法の特徴をよく理解した上で決定しましょう。要件だけでなく、自社の人的リソースをどれだけ割けるかも、重要な判断材料となります。
STEP4:予算・スケジュール決定
予算やスケジュールは予め決まっている場合が多く、提示された見積りが必ずしもその範囲内に収まるとは限りません。
何を重視するのかは企業によって異なりますが、「予算内での実現」を重視するのであれば、機能の見送りや開発範囲の調整といった判断も必要になることもあります。
STEP5:パートナー選定(委託の場合)
システム開発会社に社内システム構築を委託する場合、このタイミングで正式に開発の依頼をします。システム化の要件や予算、スケジュールは必ず認識を合わせておきましょう。また、準委任契約と受託契約、どちらの形態で契約するのかも重要であるため、以下のコラムを参考になさってください。
STEP6:開発(詳細設計/開発/テスト/導入)
ここからは開発工程に入ります。
システムを具体的にどのように組むかを決める詳細設計書の作成、実際のプログラミング作業にあたる開発、開発したシステムが要件通り動いているか確認するテスト、実際に使えるようにするための導入といった工程です。
委託の場合、開発をメインで担当するのはシステム開発会社です。しかし、この開発工程をシステム開発会社にすべて丸投げすることは非常に危険です。企業の担当者がしっかりと状況を把握・管理し、要件に沿ったシステムが構築されているかをチェックしてください。
STEP7:運用開始と運用保守
システムは導入して終わりではありません。運用開始後には、運用保守が必要です。保守とは開発したシステムが持続的・効果的に使えるように維持・改善することで、運用後に気づいた課題や要望などをくみ上げ、改善していくことでシステムはより有用なものになります。
また、社内システムの使い方を社員にレクチャーすることも重要です。新しいものを利用し始めることは、社員からすると大きな負担となります。使い方がわからないとなれば、その社内システムは利用されませんので、丁寧なレクチャーを行うことでシステムの形骸化を防ぐことができます。
補足:システム開発会社にいつ相談する?
システム開発会社に相談するのはSTEP2のタイミングがおすすめです。
なお、ノーコード開発を選択した場合でも、要件定義はシステム開発会社に入ってもらうことをおすすめします。ノーコード開発はIT人材がいないまま開発をするケースが多いため、つまずくことも珍しくありません。開発自体に知識やスキルはいらないとはいえ、要件定義に関しては有識者のアドバイスをもらった方が良いでしょう。
社内システム構築が得意な会社の見つけ方
最後に、システム開発会社への委託を検討することになったが、どう選べばよいかわからないとお悩みの方へ、社内システム構築が得意な会社の見つけ方をご紹介します。
導入事例を確認する
システム開発会社のホームページには導入事例やお客さまの声が紹介されています。導入事例の企業が自社の業種や業態、規模にあっていることを確認しましょう。
フルスクラッチ開発に対応しているか
フルスクラッチ開発とは既存のサービスや製品に頼らず、独自に開発する手法で、オーダーメイド開発と理解するとよいでしょう。フルスクラッチ開発ができるということは、相応の技術力があるという判断基準にもなるため、覚えておきましょう。
>>パッケージ開発とスクラッチ開発の違いとは?それぞれの特徴と適切な選び方について解説
要件定義前から相談に乗ってくれるか
システム開発に慣れていない企業では、業務課題の洗い出しから苦戦することも少なくありません。
システム開発会社によっては要件定義前の課題整理の段階からサポートしてくれる会社もあります。業務内容や現場の状況を丁寧にヒアリングした上での提案となるため、安心して任せられるでしょう。親身になって相談に乗ってくれるシステム開発会社かどうかも判断基準の一つです。
社内システム構築はフレシット株式会社におまかせ
社内システム構築は、これをすれば絶対に間違いないという正解はありません。企業ごとに抱えている課題も、業務も、規模も異なるためです。
フレシット株式会社は今まで数多くの企業さまを支援して参りました。要件定義前の課題整理のご相談から、フルスクラッチ開発、既存製品を利用した開発など幅広くご対応し、企業ごとにぴったりの社内システム開発をご提案いたします。
ぜひ一度フレシット株式会社にご相談ください。
監修者プロフィール
フレシット株式会社 代表取締役 増田 順一
柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら

